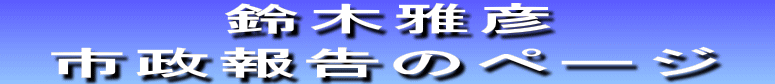 |
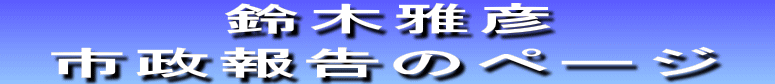 |
| �g�b�v�y�[�W�ɖ߂��@�@�@���[���@�@ |
| �s����c���̕�V�Ȃ� |
| ���ʐE�̕�V���z�̕ϑJ | |||||
| �s�� | ���s�� | �c�� | ���c�� | �c�� | |
| ���� | 1,130,000�@ �i1,017,500�j |
870,000 �i809,100�j |
670,000 | 610,000 | 550,000 |
| 04�N | 1,130,000�@ �i1,117,500�j |
870,000 �i860,400�j |
670,000 �i662,600�j |
610,000 �i603,200�j |
550,000 �i543,900�j |
| 96�N | 1,130,000�@ | 870,000 | 670,000 | 610,000 | 550,000 |
| 94�N | 1,090,000�@ | 845,000 | 640,000 | 585,000 | 530,000 |
| 92�N | 1,040,000�@ | 810,000 | 610,000 | 555,000 | 500,000 |
| 90�N | 960,000 | 750,000 | 560,000 | 505,000 | 450,000 |
| 89�N | 900,000 | 700,000 | 520,000 | 465,000 | 410,000 |
| 88�N | 880,000 | 680,000 | 500,000 | 445,000 | 390,000 |
| 86�N | 830,000 | 630,000 | 470,000 | 415,000 | 360,000 |
| 84�N | 770,000 | 577,000 | 440,000 | 385,000 | 330,000 |
| 81�N | 700,000 | 525,000 | 400,000 | 350,000 | 300,000 |
| �@����1999�N�ɋc���ɂȂ�܂������A��̕\������ƁA����ȑO�̋c��͂Q�N�ɂP��A���ɂ͖��N�A�s����c���̕�V�z���Ă������Ƃ�������܂��B �@�i�j���̐����͏��̕t���ňꎞ�I�Ɍ��z���Ă�����z�ł��B �@�Ȃ��A��L�͌��z�ŁA�P�ʂ͉~�ł��B |
|||||
| �s�E�����ے����̋����ɂ��� | |||
| ���� | �Ǘ��E�蓖 | ���v | |
| �������ō����z | 490,000 | 94,252 | 584,252 |
| ���������ό��z | 467,923 | 89,830 | 557,753 |
| �ے����ō����z | 456,800 | 60,462 | 517,262 |
| �ے������ό��z | 421,159 | 62,128 | 483,287 |
| �����̎x�����z |
| �@�����̂ɂ���ċ����̊z�͈Ⴂ�܂����A�Îs�̏ꍇ�����z�T�T���~�ł��B���K�͎����̂̒��ł͂��Ȃ�Ⴂ���ł��B�����Ă��̋��z�́A�����c���ɂȂ����P�X�X�X�N�ȑO����ς���Ă��܂���B���Ȃ݂ɕ��c���͂U�P���~�A�c���͂U�V���~�ł��B �@���m�ɂ͕�V�ƌ����܂��B�����Ⴄ���ƌ����A�����̂��߂̋����ł͂Ȃ��A�c���Ƃ����E���ɑ����V�ƌ������ƂŁA�]�������ƕی��̑Ώۂł͂���܂��A�ސE��������܂���B�܂��A�����̏ꍇ�͐�����ۏႷ�邽�߂ɁA�������������Q�T���܂ł����ł��܂��A�c����V�͂P�O�O�������������邱�Ƃ��ł��܂��B |
| �V�������z�Ǝ���z�@�O�W�N�P�Q���̏ꍇ |
| �@�Ƒ��\���ɂ���Ĉ������Ŋz������Ă��܂��̂ŁA�c�����ꗥ�����ł͂���܂���B���̍����̖����Ō����ƁA�����ł��Q�Q�C�X�U�O�~�ł��B�����ďZ���ł��S�Q�C�X�O�O�~�ł��B����ɋ��ς̊|����������܂��B���ꂪ���ƂW�W�C�O�O�O�~��������܂��B �@���̑��ɋc��W�҂̊������Ղ�ψ���ʂɍs���Y�N���p�ȂǂɎg�����߂ɁA�����T�C�O�O�O�~���V��������܂��B���������͕��ψ����������N�ɎQ����������ŁA�Y�N��͌��Ȃ��Ă��܂��B �@���ꂪ�ʏ�V�����������z�ŁA���v�P�T���W�W�U�O�~�ɂȂ�܂����A�P�Q���͂���ɔN�������������A�S�C�O�P�U�~�̐ŋ���������܂����B����ɂ��A�V�����̑��z�͂P�U���Q�W�V�U�~�A�x���z�̂R�O��������ŏ����Ă����܂��B �@�T�T���~����V�������z�������������܂��ƁA�R�W���V�P�Q�S�~�A���ꂪ����z�ł��B�c���ɂȂ������́A�m���A�S�Q���~���炢�̎���ł����B |
| �������獑�ۗ��Ȃǂ��x�����܂� |
| �@���̂R�W���~�]�肪�c���̐����Ɏg����킯�ł͂���܂���B�T�����[�}���ł��ƁA���肪��{�I�ɐ����Ɏg����킯�ł����A�c���̏ꍇ�́A���c�Ƃ̕���^�C�A���ꂽ���Ɠ��l�ŁA�������N�ی�����[�߂Ȃ���Ȃ�܂���B�ܘ_�A���ی���������܂��B����ɍ����N���̊|�������[�߂܂��B �@�����̍��v�͖�P�O���~�ɂȂ�܂��B��������z��������܂��ƁA�c��̂͂Q�W���~�ƌ������ƂɂȂ�܂��B �@�������Q�W���~����Ƃ��Ďg���킯�ɂ͂����܂���B�c���ɂ͕t�����̑I��������P�o���Ȃ���Ȃ�܂��A�c�������ނ��Ă��A�I���ŗ��I���Ă����ƕی����o�܂���A���������Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A�s���ɂ͂P�����ƂɂR�O�O�O���~�̑ސE�����o�܂����A�c���ɂ͑ސE���͂���܂���B�]���āA���̂��Ƃ��l���Đ������Ȃ���Ȃ�܂���B |
| ����������͋c�������Ɏg���� |
| �@�c���̑�Q�̋����̂悤�Ɍ�����u����������v�Ƃ�������������܂��B����͈ȑO�A�̎����̓Y�t�`�����Ȃ��������߁A���Ɏg���Ă�������܂���ł����B�Ƃ������Ƃ͋c���Ƃ��Ă̊����Ɏg���Ă������A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��B �@�Â����c���ɕ����ƁA���_�̎�O�A�c����V�͏グ�ɂ����̂Ő���������i�ȑO�͈Ⴄ���O�ł������j�̐��x��������A�ƌ����l������܂��B�����c���ɂȂ��Ă���ł��A�T�����ŏo�O�����R�[�q�[�オ���܂�ɂ����z�ŁA����������̎g�����Ƃ��Ă������Ȃ��̂��ƁA�V���Ɏw�E���ꂽ��h������܂����B �@���ɉߋ��̐���������̎g�����ɋ^�₪�������Ƃ��Ă��A���݂͕s���N�Ȏg�����͕s�\�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B �@���͂ƌ����A�̎����̓Y�t�`���̂Ȃ����ォ��A������Ɨ̎����i�ʂ��ł͂���܂���j��Y�t���A�g�����𖾂炩�ɂ��Ă��܂����B���݁A�Îs�c��ł́A���ׂẲ�h�̐���������̗̎������Y�t���ꂽ���ނ��쐬����Ă���A�N�ł����ł��{���ł���悤�ɂ��Ă���܂��̂ŁA�S��������̕��͎����ǂ����K�ˉ������B �@���ۂ̎g�����́A��i�n�̎��@�A���Ƃɂ��肢���ĕ�������鎞�̍u�t���A�T�����Ŏg�p���鎖���p�i�A�����E�����̂��߂̏��ЁE������A�c��̃R�s�[�g�p���Ȃǂ������Ǝv���܂��B �@�Îs�c��̐���������͈�l������T���~�ł��B����͑S���̌������ݒn�̒��ŁA������R�Ԗڂ��炢�ɏ��Ȃ����z�ł����A����ɖ��N�S���~�ɉ����āA�P���~�͂��̎��X�̏d�v�ۑ�A���Ƃ��Εۈ牀�E�c�t���̑��K���X�̑ϐk�⋭�ȂǂɎg���A�Ƃ����悤�ȓ���[�u�𑱂��Ă��܂��B�]���Đ���������͂S���~�A�g�����͋c���Ƃ��Ă̊����Ɍ��肳��A�������̍������̂ɂȂ��Ă��܂��B �@�Ȃ��A���̌��S���~�i�N�ԂS�W���~�j�͋c�������炦����̂ł͂Ȃ��A�g��Ȃ��������͕Ԋ҂���`��������A���ۂɂ͔������g��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�O�X�N�P������c�������̍L���ɂ��g����悤�ɂȂ�܂����̂Łi���̋c��ł͈ȑO����F�߂Ă��鏊�����������j�A�����̋c�����c�������悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |
| �Îs�c��́u��p�ُ��v�͌�ʔ� |
| �@�����i09.06.23�j�[���̃e���r�ԑg�Ŏs�c��́u��p�ُ��v�Ɓu��ʔ�v�����グ���Ă��܂����B���ˎs�c��̗Ⴊ����Ă����̂ł����A�S���������ݒn�̓��A�ǂꂾ���Ɂu��p�ُ��v�̐��x������A����ɂ��̒��łP���P���~�ȏオ��ȂǂƕĂ��܂����B�܂��A�u��p�ُ��v�ȊO�Ɍ�ʔ���x�����Ă���c�������悤�ȕ��ł����B �@���̔ԑg�������ɂȂ����Îs������������������ł��傤�B�Îs�̎s��c������������Ă���낤�Ǝv����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������ԑg�͌ʂ̐������o���Ȃ����Ƃ������̂ŁA������������Ƃ������̂ł��B������͎s��c���ɑސE��������ƁA���S�ɊԈ�����L�����ڂ����V�������������炢�ł��B �@�����ŒÎs�́u��p�ُ��v�ɂ��Ċm�F���܂����B���Îs����A�{��c�ƈψ���ɏo�Ȃ���ƂP����3000�~���u��p�ُ��v�Ƃ��Ďx������Ă��܂����B���́u��p�ُ��v�p�~�������Ă��܂������A���Ȃ����Ƃ͌��E�I���@�Ŋ�t�s�ׂƌ��Ȃ���܂��̂ŁA�����Ȃ��������Ă͂��܂����B�������ۂł��Ȃ����߁A�S���I�ɂ́A��������ƂŁu�����v����c��������悤�ł����A�������Ă��A�����̍s���悪����܂���B���ǂ͈��ނ̎��ɋ������������đS�z��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@������A��ʔ�Ƃ��Ă̐��i�𖾗Ăɂ��悤�ƁA�����c��܂ł̌o�H���Г��W�q�܂ł�1500�~�A����ȉ��͋K��ɏ]���đ��z�A�Ƃ����`�ŁA�S�̂Ƃ��āu��p�ُ��v�̑��z���팸���܂����B�����Ă���ɉ������s���A���݂ł����S�Ɍ�ʔ�̈Ӗ������Ɍ��肵�A�P�q37�~�Ƃ����������̗���K���i�ٔ����ɂ����ꂪ�K�p����܂��j�Ɠ������z�ɂ��܂����B �@���̏ꍇ������12�q�i�O�̉����̎��Ɏ����l����o���Ă���܂��j�ł��B12�~37�ł�����A444�~�ɂȂ�܂��B���̓o�X�ŋc��ɍs���悤�ɂ��Ă��܂����A�����̃o�X���440�~�ł��B�܂莄�̏ꍇ�͌�ʔ�Ƃ��Ă̎�|�ɍ��v�������z�ɂȂ��Ă���킯�ł��B �@�����������ꂩ�炷��ƁA������u��p�ُ��v�Ƃ������x�́A�Îs�ł��p�~��������ň�v�ł���̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B |
| �{�[�i�X�ɂ��� |
| �@�c���ɂ��{�[�i�X�i�����Ε蓖�j������܂��B�ސE�������ƕی����Ȃ��c���ɂƂ��ẮA���ꂪ�V��̐������x����d�v�Ȍ����ƂȂ�܂��B���邢�͂����I�������Ƃ����������ł��傤�B09�N�̉Ẵ{�[�i�X�͎x���z��115���~�ŁA�V������25���~�]��A���������̎��肪89���~���ł��B �@���̃{�[�i�X�́A���͈ȑO�͂����ƍ������̂ł����B�����c���ɂȂ�O����ԍ��������̂ł����A�����c���ɂȂ������ɁA�����i���̐����[�u�Ƃ��āA�l���@�����ƌ������ɑ��Č��z�̊������s���܂����B����Ȍ�����z�����������A�ŋ߂ł�09�N�T���ɂ�����������A���v�Ō��z�������S��قǂ������Ǝv���܂��B����ɏ����Ēn�����������c�������z���s���܂����i���Ԉ���Ă��炲�߂�Ȃ����j�B �@����ɂ���ĈȑO���{�[�i�X�͔N�ԂT�O���~�]�艺�����Ă��܂��B�茳�Ɏ������c���Ă��Ȃ��̂Ő��m�ɂ͕�����܂��A���l�Ō����A�T�����[�}������̉Ẵ{�[�i�X��100���~�قǂ������Ǝv���܂��i��{�{�x�X�̉c�Ɛ��с{�l�̉c�Ɛ��сj�B |
| ��Ƌc���̐��� |
| �@���ꂪ�c���̕�V���������̎���ł��B�]���ċc�������ɐ�O���Ă���c���̐����͎��f�ɂȂ炴��܂���B �@�����s��������܂��̂ŁA�X�[�c���K���i�Ƃ��Ĕ���˂Ȃ�܂��A�������͈̔͂��L����܂��̂ŁA�����ɏo��@��������܂��B����ƌ��X�̍��T�オ�Ȃ��Ȃ��̋��z�ɂȂ��Ă���̂ł��B�o���s�s����K��c������A�p�[�e�B�Q���������܂��B���H��c�����J�Â��鐳���̉ꎌ������Ȃǂ�����܂��B��������l�X�Ȓc�̂̉�������܂��B�؉ƏZ�܂��ł�����ƒ�������܂��B �@���̂悤�ɒ���E�s����̏o��N�Ԃ�ʂ��ƁA�P�O�O���~�ɂ��Ȃ�܂��̂ŁA���퐶���͎��f�ŁA���ň��ނƂ������Ƃ�����܂���B�̂̐E��̓��������۔V���ŐH�����J���Ă���̂ŁA���܂ɂ����֊���o�����炢�ł��B �@�ܘ_�A�c�������ɐ�O�����A�{�Ƃ�ʂɎ����Ă�����������X������܂��B�����������X�͖{�ƂŐ������ێ��ł��鏊��������܂�����A���̂悤�Ȑ����ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����ɏ������̂́A�����܂Ŏ��l�̌o�ϐ����ł��B |
| �c���N�����x�͕��O |
| �@���āA�c�������ށA���邢�͗��I��̐����͂ǂ��Ȃ�ł��傤���B�{�Ƃ̂�����́A���̌o�c�ɐ�O���邾���̂��Ƃł����A�c�������ɐ�O���Ă����ꍇ�́A�N��ɒB���Ă���ΔN���Ő������邱�ƂɂȂ�܂��B �@�S�O��A�T�O��̏ꍇ�A�������͂R���ȏ�c�������Ă��Ȃ��ꍇ�A�N��������܂��瓭������܂���B�����Ȃ�ƔߎS�ł��B���ƕی����Ȃ����N�̎��Ǝ҂ɂȂ�̂ł�����A�z��҂̎����ɗ����������ɂȂ�܂��B���������I�E���ނ̗��N�̏Z���ł⌒�N�ی����Ȃǂ́A�O�N�̏����Ɋ�Â��ĉۂ����܂��̂ŁA�������̏�ԂŕS���\���~���x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B �@���N�ł�����d����������܂���B���ǁA�����ی����P�[�X���o�Ă��܂��B �@�N�����ł���ꍇ���]�T������Ƃ͌����܂���B�Ȃ��Ȃ�A�c���萔�팸�̗��s�ƕ����̑升���ŋc����������������ł��B�܂�A�|�������l������A�N������l���������̂ł��B�Îs�̏ꍇ�A�����O�̂P�O�s�����ɂP�U�U�l�̋c�������܂������A���͂R�W���ł��B2010�N�̑I������͂R�U���ɂȂ�܂��B �@���̂��߁A�����V�`�W�N�̊Ԃɉ��́u�����v�������āA�|�������オ��A���z�������������܂����B�����c���ɂȂ������͂R�����߂�����P�W���~�قǂ̔N�����ł��܂����B���ꂪ���͂P�R���~�ق��ɂȂ��Ă��܂��B �@�Ƃ��낪�A��q�̗��R�����x���̂��̂��j�]���O�ɂȂ��Ă��܂��B�|�������������N���̕������|�I�ɑ����̂ł�����A�c�����ς͖��N�Ԏ��ŁA�Q�O�P�Q�N�ɂ͐ϗ������[���ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B�Ƃ������Ƃ́A���ꂩ��͋c�����N�����ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�ސE���͂Ȃ��A���ƕی��͂Ȃ��A�N�����Ȃ��A�ł͋c���̐����͐��藧���܂���B �@�Ƃ������ƂɂȂ�̂Ȃ�A���O���̈ꕔ�ɗႪ����悤�ȁA����V�̃{�����e�B�A�ɂ��c��x�ɂ��邵���Ȃ��Ȃ�ł��傤�B�����A�����̂̎d�g�ݎ��̂��Ⴂ�܂�����A�P���Ƀ{�����e�B�A�c���͍��̎d�g�݂̒��ł͕s�\�ł��B�܂��A���x��@���̒m����K�v�Ƃ��܂����A�l�X�Ȍ�������ɍs���K�v������܂�����A����I�ɂ����������Ԃ̗]�T���ۏႳ��Ȃ��{�����e�B�A�ł́A�s���^�c�ɑ���`�F�b�N�@�\���ێ��ł��邩�ǂ����A�^�₪�c��܂��̂ŁA�d�g�ݎ��̂�ς���K�v������ł��傤�B |
| �g�b�v�y�[�W�ɖ߂� |
| ���T�P�S�|�O�P�P�S�@�Îs��g�c���Q�V�X�O�@�s�����D�e�����@�O�T�X�|�Q�P�P�|�O�P�Q�U ���[���@hpvqg2qv@zc.ztv.ne.jp |