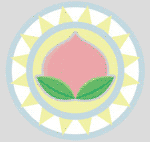|
昔話
昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました...。 これは桃太郎の話の最初の行(くだり)で、昔話を語るときにはよく使われるが、何故かお父さんお母さんでなく、おじいさんとおばあさんで始まっている。 私も2・30年前にお年寄りの住む家を訪問して、5年間ほど昔話を聞き回った経験があるが、物語になっていない昔の話はずいぶんと聞かせてもらった。
「あそこにキツネがよう出て化かした」 こんなひとくちの話が多いが、中にはもう少しまとまった話に出会うこともある。大げさかも知れないが、昔話から歴史を塗り替えることもあるもんだ。
一の坂の観音さまという話をまとめたときに、「昔この付近に住んでいた木地屋(ろくろを使って木のお椀などを作っている人)が、暗闇の坂道を上っていると谷間から『きじよ、きじよ』と呼ぶ声がする...」。こんな書き出しだったのが、この話を知り合いの歴史家の先生に送ったら、榊原に木地屋がいたのかとおどろかれて調査にこられた。
聞いたままをまとめたのがよかったもので、もし「この付近に住んでいたお年寄りが、暗闇の坂道を上っていると谷間から『じいよ、じいよ』と呼ぶ声がする...」とでも書き換えていたら、過去の事実も判らないまま済んでいたことだろう。 またこれよりも、もっともっと以前に聞いた話で、田圃に水を引くための水路のであい(みんなが出会っての共同作業)のとき、一緒にいたお年寄りから「この水路を造るときにあの向こうの山に提灯を置いて、ここからその灯りを見ながら高低を決めていったのじゃ」と自分が見ていたように話してくれた。このお年寄りの若い頃には水路があったはずだから、おじいさんから聞いたのかな、明治の始め頃に作られたのだろうと思っていた。
その後、400年余り前に出来ている湯治場の絵地図から知ることになった。その水路は湯治場の中を横切っている。400年前は地元の豪族榊原氏の元で湯治場を開き管理されていたようだし、江戸時代になると藤堂藩が湯治場を管理している。湯治場がすでに出来ていたならば、その中に水路を通すことは許されなかっただろうし、もともと水路があったに違いない。 たかが昔話ではない。知り得た昔話は必ずそのまま次の世代に語り継いでいくべきで、後に必ず役に立つ地元の貴重な資料でもある。
(2005.1.6)
|