|
牛あれこれ
私らの若いころは、肉といえばかしわ(鶏肉)だった。牛の肉ならせいぜいコマギレ肉。牛肉はほとんど食べなかった。 それよりも牛といえば家族の一員。大戸を入ると大きな目をした牛が、よだれを垂らして迎えてくれる。人もよく働いたが、牛も実によく働いた。
草刈りは牛を養うため、毎日の日課になっていた。 それは今でも年寄りの語りぐさになっている。 「昔は朝早うから草刈りに行って、草刈らんと一日寝てしもたこともあった。のんびりしてたなあ」 そんなのんびり者も、この歳になって今でも、現職として働いて老人会の行事にも出れないというから、世の中どうなっているのだろう。 牛は農家の宝だった。
こって(雄牛)はあかんけど、めんた(雌牛)はええ。かけぼ(種付け)に連れてって、ええベコを産んでくれたら儲けもん。 出産もまた、それぞれの家で見ることが出来、今ではテレビでも見ることが出来ないものを間近に見ることが出来た。
生まれたベコが大きくなると、農業協同組合の広場でベコ市があり、競りに掛けられる。
ベコ繋ぎの柵はあったが、収まりきれず桜の木にもベコは繋がれていた。
今でも榊原の農協の前に、あまり大きくもなれずに、ごつごつの幹を持つ桜の古木が残っている。 「ご苦労さんだったね、よく頑張ってきたね」 と声を掛けてしまう。
(2004.7.1)
|

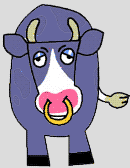 牛というと焼き肉、牛丼、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキなど、肉といえば牛を思い浮かべる今日この頃ではあるが、昔は違った。
牛というと焼き肉、牛丼、しゃぶしゃぶ、すき焼き、ステーキなど、肉といえば牛を思い浮かべる今日この頃ではあるが、昔は違った。