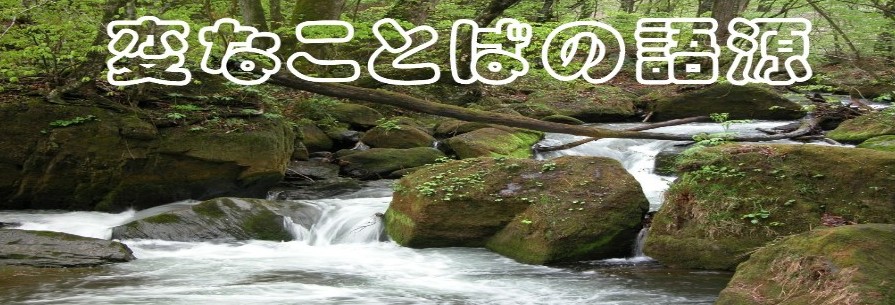
◆圧巻
中国の故事「諸巻を圧倒す」からきたことばで、書物、催し物、物事などの中で最も優れている部分のことを意味する。
「巻」は試験の答案のことで、唐から清朝時代にかけて行われた科挙(かきょ)(官史登用試験) の最優秀の答案を一番上に乗せたことから、他を圧して最も優れたものを「圧巻」というようになった。
◆ 油を売る
江戸時代の「油売り」からでた言葉で、仕事を途中でなまけ、むだ話などをして時間をつぶすこと。
当時、行灯(あんどん)の油は升で量り売りをしていたので、油売りは油のしずくが切れるまで、
客と世間話をしながら待っていた。
その様子が怠けているように見えたことからきた。
また、小間物屋が女性を相手に髪の油を売る時も同様で、世間話をしながら商売をした。
[い]
◆いかさま
江戸時代 武士があいづちを打つ時は「如何様、左様でござる」と言った。その武士が 失業すると、威厳を保ちつつ陰で相手をだますような人物が現れたので、だまされた相手は そうした武士のことを「如何様野郎」と言った。
そこから詐欺的な行為やいんちきをすることを「いかさま」と言うようになった。
◆ 一目おく
囲碁用語から出た言葉で、自分より優れた人物として、相手に敬意を払うことを意味する。
囲碁の世界では、対局時に自分が一目先に置くことは、相手を強い者として一歩譲ることを意味した。
そこから「彼には一目も二目もおいている」などと言うようになった。
[う]
◆上前をはねる
上米とは、江戸時代年貢の中から一定量に米を納めることで、容器に入った米の上の部分を取ることを「上米取り」と言った。
大阪地方では「お前」を「オマイ」と言うように、「米」のマイが「前」のマイと混同し、また「取る」がいつの間にか「はねる」 に変わって、「上前をはねる」という言葉が出来て、人に取り次ぐべき代金の中から、一部をごまかして自分のものにすることに使われるようになった。
◆うだつがあがらない
家を建てて棟上げすることを「うだちが上がる」というが、「うだち」は木造の家の梁の上に立てて、
棟木を支える短い柱のこと。
「うだつ」は「うだち」のなまったもので、「うだつが上がらない」は、棟上げができないことを意味した。
「うだち」というものは、下に梁があり、上からは棟木に頭を押さえつけられている状態なので、そこから地位や生活程度が低いままで、
少しもよくならないことの例えに使われている。
◆ 内股膏薬 』(うちまたこうやく)
内股に付けた膏薬は、両もものどちら側にもべたべたついて、薬としての効果がないということから、信念がないため、
その時々の都合であちらについたり、こちらについたりすること。
また、そのような人をさす。
これに似た言葉に「理屈と膏薬はどこへでも付く」ということわざもある。
◆うんともすんとも
江戸時代、ポルトガル人が伝えた「ウン・スン・かるた」というゲームでは、「ウン」は一の意味「スン」は
最高の意味で「ウン・スン」という言葉がよく使われたが、やがて天正かるたが大流行するようになると、
「ウン・スン・かるた」はすたれ、「ウン」とも「スン」とも言わなくなってしまった。という
ことから、全然返事をしないことを意味するようになった。
[お]
◆おおわらわ
「大童」と書きます。戦国時代の武士の髪型からきたことばです。
力の限りに奮闘、活躍すること。
「童」(わらわ)は子供の散らし髪のことで、武士も戦場で奮闘する時は兜を脱ぎ、髪をふり乱して、 「童髪」になるところから、非常に忙しく働くことを「おおわらわ」(大童)と言ったのです。
◆おかぶ
江戸時代、特定の人だけが独占した職業上、営業上の特権「株」からきたことばで、その人の得意中の得意という意味。
この独占、特権と言う意味が転じて、一般的に得意とするものの意味になった。
職業上の特権を意味する「株」には今でも相撲社会における「年寄株」がある。また、ある人が得意とする技などを、
ほかの人がもっと上手にやることを「お株を奪う」という。
◆おけらになる
虫の「ケラ」が前足を広げている格好が、勝負に負けてお手上げになった状態と似ているところから、
有り金を使い果たし、無一文になってしまうこと。
◆おしゃか
鋳物職人が火力が強すぎて不良品ができると、「火が強かった」と言った。これを東京の人は、
「ヒ」を「シ」と発音したので、「シガツヨカッタ」になり、いつの間にか「四月八日」に
変わった。この日はお釈迦様の誕生日なので「おしゃか」になってしまった。
◆おせっかい
匙(さじ)の一種の「切匙」(せっかい)とは、すり鉢の内側や容器のすみについたものを取るときに
使う道具のことで、細かいところに入り込んで、ものをかき出すことを意味することから、
他人のやっていることによけいな手出しをすること。
◆おやつ
時刻の「八つ」(2時)からきたことばで、間食をすること。またその食べ物の両方を指す。
昔から午後のこの時刻に、お菓子や果物などの間食をする習慣があったことから、間食を「お八つ」と呼ぶようになった。
現在は時刻にかかわらず、三回の食事以外に食べることをいうようになっている。
[か]
◆気質(かたぎ)
職人が使った「形木」(かたぎ)からきたことばで、身分、職業、年齢などに特有の類型的気風、性質のこと。
「形木」は、布地の染付けなどに使った模様を彫り抜いた木のことです。
平安時代にこの形木を使う染め物職人に独特の気質があって、それを一般の人が「気質」(かたぎ)と呼ぶようになったとされる。
江戸時代になると、人物の類型的性質を面白く描いた「世間息子気質」、「世間娘容質(かたぎ)」「浮世親仁(おやじ)形気(かたぎ)」などの“気質物”という浮世草子が流行した。
明治時代になると、坪内逍遥(しょうよう)が当時の学生気質をテーマに書いた小説「当世書生気質」を発表して、世間から注目を集めた。
◆かしましい
女は一人でいれば静かだが、二人三人と集まっておしゃべりに夢中になると、まことにやかましい。
そこから女三人集まった「姦」という字がつくられ、「かしまし」と読むようになった。
◆かも
鴨はつかまえやすく、数も多いため手に入れやすい鳥だったことから、利用しやすい人、
特に勝負事などで楽に負かすことの出来る相手のことを言う。
◆かまとと
「かま」は蒲鉾で「とと」は幼児語で魚を意味する。「かまぼこ」を、これは「とと」かと聞いたということからきている。
知っているのに、上品ぶって知らないふりをすること、また、そのような人をさす。
江戸時代末期に上方(大阪)の遊里で使われたのが最初で、やがて、一般に広まり、特に性的な面で知らないふりをする、
という意味で使われた。
近頃では、この言葉は、「ととかま」(かまととの反対)とかかまゴジラ(ひどいかまとと)とかの形にひねって使われている。
なお、若者の間では、上品ぶったり、いい子ぶったりする人を「ぶりっ子」と呼んでいる。
◆皮切り
鍼灸(しんきゅう)療法から出たことばで、物事の始め、最初のことを意味する。
最初に打つ針や最初にすえる灸は大変痛く、まるで身の皮を切られるようだ、ということから使われた言葉で、
何事も最初は苦しいとの例えとして「皮切りの一灸」と言うことわざがある。
なお、灸をすえて効果があがるところを「ツボ」と呼び、そこから「ツボを抑える」「ツボを心得る」などの言葉が出来た。
[き]
◆きざ
「気障」と書き気にさわる、気にかかるの意味の「気障り」(きざわり)の下の略。 江戸時代、服装、動作、言語などが気取っていて嫌みなことをさした。その後気にかかるだけでなく、 もっと不愉快な感じを意味するようになった。
◆几帳面
建築用語から来たことばで、折り目正しくきちんとしていること。
「几帳」は、室内の仕切りに立てた家具のことで、「面」は、柱の角のことをいい、この角をきちんと仕上げる
ことを面をとるという。
几帳の柱にこの面のとり方がが多く用いられたことから、大変きちんとしていることを「几帳面」と言うようになった。
[く]
◆くだらない
「へりくだる」(謙遜する)ことをしない、相手を敬う心得のない人を「くだらないやつ」 と呼んだことから、つまらないこと、値打ちがないことに使われている。
◆くだを巻く
糸車の管(くだ)は、錘(つむ)に差して糸を巻き付ける軸のことで、糸車を廻すと管がブーブーと
音をたてる。その音が耳ざわりなので、そのことから、酔っぱらいがくどくどと言うことをさすようになった。
[け]
◆毛嫌い
この語源には、二つの説があり、「博労ことば」説と「闘鶏用語」説がある。
意味は、何の理由もなく、感情的に嫌うこと。
「博労ことば」説は、博労(馬喰)が馬を交配させようとした時、牝馬(ひんば)が牡馬(ぼば)を 嫌って寄せ付けなかったことから、馬も相手の毛並み(毛色)で、好みを決める事があるのだろうと、推測した博労が言い出したことばとするもの。
「闘鶏用語」説も同じようなもので、闘鶏場で、ある鶏が相手の姿を見ただけで、退いてしまった、ということから、 一瞬にして嫌う事を「毛嫌い」と言ったもの。
◆けりをつける
助動詞の「けり」は、過去(~た)を表したり、詠嘆(~たなあ、~だったなあ)を表したりする。
そのため和歌や俳句で「~ありけり」「~なりけり」などと「けり」で終わる文章が多かったことから、
物事の決着をつけることを意味するようになった。
◆けんもほろろ
「けん」も「ほろろ」も共にきじの鳴き声で、無愛想に聞こえたことから、人の頼みや
相談を全く取り合わず、はねつけることの意味に使われている。
[こ]
◆ごたごたする
鎌倉時代に北条時頼に招かれて、中国から来日した兀庵普寧(ごったんふねい)という禅僧は、 理屈っぽく単純な話をしても、話がこんがらがってしまった。そのことを「兀庵兀庵する」と 言ったのが転訛して「ごたごたする」になり、混雑すること、もめることに使われるようになった。
◆ごまかす
江戸時代に作られた「胡麻胴乱」と言う「胡麻の菓子」は、見かけはおいしそうだが、
食べてみると中に何も入っていないのでおいしくなかった。そこから、表面だけをとりつくろう
ことを「胡麻菓子」と呼んだのが動詞化し「ごまかす」となって、人目を紛らわすことや、
あざむくことに使われるようになった。
[さ]
◆さげすむ
建築用語の「下墨」(さげすみ)からきたことばで、見下げること。軽蔑することの意味。
大工が柱などの傾きを見る為に、おもりをつけた墨縄(すみなわ)を下げて調べた。 そこから、人を見下げる意味にも使われるようになった。
後に「下墨」(さげすみ)を動詞化した「下墨む」に「蔑む」(さげすむ)という字が使用された。
◆さじを投げる
薬を調剤する「匙」(さじ)を「投げる」とは、医者が患者を診て治る見込みがないと診断したことを意味する。
そこから、これ以上やってもしょうがないと断念する意味に使われるようになった。
江戸時代、大名の侍医は「おさじ」と呼ばれ、患者を生かすも殺すも、この侍医の「さじ加減」一つで決まったという。
◆さびしい
金属の「錆」からでたことばで、静かで心細い、物悲しいことを意味する。
錆が生じると、ザラザラと荒れてくることから、平安時代景色が荒れているというときに、「さびし」ということばが
使われた。また、貴族が没落すると、その境遇についてもいうようになった。
◆さばを読む
語源には、「さばの数え方」説と、「魚市場の名称」説とがあり、意味は、数量をごまかすこと。
「さばの数え方」説では、さばは腐りやすい魚なので、早口で数えたため、数を飛ばすことが多かったことからとされる。
「魚市場の名称」説では、江戸時代、魚市場のことを「いさば」と言い、そこでの魚の数え方を、「いさば読み」と
言ったのが略されて、「さば読み」となったとされる。
[し]
◆じだんだを踏む
足で踏むふいごの「地踏鞴」(じたたら)が転じて出来た言葉で、くやしがって、足を踏む姿が地踏鞴(じたたら)を 踏む様子に似ているところからきた言葉で「地団駄」と書く。
◆しのぎを削る
刃物の「鎬」(しのぎ)とは、刀の刃と脊との境い目の線状に小高く盛り上がっている部分のことで、
刀と刀で激しく切り合うときは、鎬を削り取ってしまったということから、激しく戦うことを意味する。
[す]
◆すっぱ抜く
忍者、闇者の別名からきたことばで、秘密をあばくこと、出し抜くことをいう。
戦国時代、忍者の別名を「透波」(すっぱ)といい、彼らは敵方の様子をさぐり、その秘密を暴露した。V そこから、公表されていない、隠された部分をあばいて明るみに出す事を「すっぱ抜く」というようになった。
[そ]
◆そそっかしい
「そ」は馬を追うかけ声で、それを重ねて「そそ」と言った。「そそ」は江戸時代、人を 追い立てる意味にも使われ、転訛して「そくさく」となった。それがさらに、形容詞の 「そそかしい」になり、促音がついて「そそっかしい」となった。追い立てられてあわてるところから、 落ち着きがない、軽率で不注意な様子を指すようになった。
促音が加わった江戸ことばとしては、「あさっぱら」「むかっぱら」「はったおす」などがある。
◆そりが合わない
「そり」は「反り」と書き、刀身の曲がり具合のこと。刀を鞘(さや)に納めるとき、刀と鞘は同じ曲がり具合で
なければいけない。そこから気が合わない、うまくいかない、仲がしっくりいかないことなどの例えに
使われるようになった。
その反対に、気が合うことは「うまが合う」といい、乗り手と馬との呼吸が合うことを言う。
[た]
◆高飛車(たかびしゃ)
将棋用語から出たことばで、上から押しつけるような態度に出ること、頭ごなしに威圧すること。
飛車が守りの位置にいる「居飛車」(いびしゃ)に対して、中央に進出して攻撃の構えを することを「高飛車」と言った。
そこから、人が高圧的な態度に出ることを意味するようになった。
◆だらしない
「しだらない」からきた言葉で、「しだら」とは自堕落の転訛したもので、それを倒置した「だらし」に、強調の「ない」がついたもの。
そこから、身を持ちくずした格好、しまりがないこと、きちんとしていないこと等に使われるようになった。
◆だめを押す
囲碁用語で「だめ」とは、むだな目のことで、白、黒双方の石の境にあって、どちらの所有にもならない所。
そこへ終局後、石をならべていくことを「だめを押す」という。そのことから、大丈夫だとわかっていても、
念にために・・・という意味に使われるようになった。
[ち]
◆ちょっかいを出す
「ちょっかい」は、猫がじゃれて前足で物をかき寄せるしぐさのことで、そこから 横合いからよけいなことをしたり、口や手を出すことに使われるようになった。
◆ちゃらんぽらん
ポルトガルからきた「チャルメラ」は「チャラメラ」「チャンメラ」「チャルメロ」などさまざまな呼び方をされていたが、
そこから、「チャルメラ」という言葉と「チャランポラン」という言葉が生まれたとされている。
そのチャルメラのおかしげな音を聞いて、何のことだかさっぱり解らなかったことから「わけがわからない」
「いいかげんな」「でまかせ」などの意味に使うようになった。
◆ちょうちん持ち
江戸時代の「提灯(ちょうちん)持ち」から出たことばで、他人の手先として、その人に有利になるように働くこと、
また、必要以上に人をほめあげること。
提灯持ちは、身分の高い人の夜の外出や婚礼などのときに、提灯を持って先導する人のこと。
そこから、えらい人にへつらう者を指すようになり、冒頭の意味合いが生まれた。
◆ちんぷんかん
「陳分漢」と書き、「陳分」は中国人によくある姓名で、「漢」は熱血漢のように男性を
意味する語。江戸時代、中国人の名前は読みにくく、解りにくかった。そこから世間の
人が「ちんぷんかん」を「なにがなんだかわからない」という意味で使ったと言う。
もう一説に、中国には「チンプトン、カンプトン」という言葉があり、チンプトンは、聞いても解らない。
カンプトンは、見ても解らないという意味から、見ても聞いても訳が解らない事に使われるようになったという説もある。
また「珍糞漢」「陳粉漢」「陳奮漢」などとも書き、儒学生が漢語をしゃべっているのを、
ひやかしていったもの。と言う説もある。
なお、同じような語源を持つ言葉に「頓珍漢」(とんちんかん)があるが、これは鍛冶屋が
交互に打つ槌(つち)の音がうまくそろわないところからきたと言う語源説もある。
[つ]
◆つつがない
「つつが虫病」からきたことばで、無事でいること、異常がないこと。
この病気の原因は、ダニの一種の「つつが虫」で、人間がこの虫に刺されると、高熱や発疹などを伴い、死亡することが多かった。
ここから、「つつが虫病にかからないでいる」ということが無事でいることの意味になった。
無事で生活していることを、便りで知らせる時によく使われる手紙用語でもある。
つつが虫(恙虫):
ダニ類の一種で、1㎜ばかりのごく微小な体で、うす赤く、無色の毛が生え、幼虫は真っ赤でもっと小さい。成虫は植物質を食べるが、
幼虫は野ねずみの耳に付着し、体液を吸う。この幼虫時代に川べりの田などで働く人を襲い、つつが虫病を冒す。
◆月なみ
「月例」という意味の「月並」からきたことばで、平凡、ありきたり、陳腐などを意味する。
「月並(月次とも書く)は、本来は、月ごとの意味で、ある物事が毎月決まって行われることをさす言葉だった。
これが、現在のような意味になったのは、明治時代、革新的な俳人の正岡子規が、月例句会を開いていた旧派の俳句を「月並俳句」
「月並調」と言って批判して以後のこと。
ありきたりで進歩がなく、陳腐な俳句という意味から、あらゆる陳腐なことをさすようになった。
[て]
◆ていねい
「丁寧」と書き、中国の軍隊で警戒の合図に使った鐘からきた言葉。
親切で礼儀正しいこと。また、物事を念入りにやることをいう。
鐘は右に振ると「丁」、左にふると「寧」と鳴り、この鐘を何度も振って合図した。ここから、同じことを繰り返す、つまり 念入りにやることを「丁寧」というようになったのです。
◆てくだ
語源には「手段」(てだん)がなまったもの。
《てだん→てくだ》
機織(はたおり)の道具「管」(くだ)に手がついたもの。
《て+くだ》などの説もあるが、曲芸の一種の水芸から出た言葉と言う説が有力で、意味は、人をだます手段、人をあしらう方法を言う。
水芸の手管(てくだ) は水を出す管で、芸人はそれを客に見えないように手に隠し持って演じていた。
そこから、「人をだます」意味に使われるようになった。
また、「てくだ」は、「手練手管」(しゅれんてくだ)ともいい、「てれん」は、「手練」と同じく熟練した鮮やかな腕前と
いう意味。
なお、同じような意味を持つ言葉に「手玉に取る」がある。これは、子供が遊ぶ「お手玉」から出たことば。
◆手ぐすねを引く
「手に薬煉(くすね)を引く」の意味から来た言葉で、充分に用意して、相手を待ち受けること。
「薬煉」とは、松脂(まつやに)を油で煮て煉り合わせた一種の補強材で、兵士は合戦の前に薬煉を弓の弦に塗り、
敵の攻撃を待ちかまえたのである。
そこから、準備を整えて相手を待ち構える状態をいうようになった。
◆でたらめ
さいころを振ってよい目がでるか、悪い目がでるか、どちらでもかまわない、出た目にまかせる。
後はなにがあっても知ったことではない。というでまかせで、筋の通らないことを言ったり、行ったり
すること。
[と]
◆とどのつまり
魚のトドはボラの成長したもので、成長するにつれて名前が変わる魚を「出世魚」と呼ぶ。 トドの場合は、幼魚から成魚になる間に、オボコ→イナッコ→スバシリ→イナ→ボラ→トドなどと 名称を変える。最後にトドと呼ばれるところから、最後のところ、つまるところという意味になった。
世間知らずの娘を「おぼこ娘」と呼ぶには、ボラの幼魚時代のオボコからきたもの。
◆土左衛門(どざえもん)
実在の人物の名前からとった言葉で、水死者のことを言う。
享保のころ(1720年代)の相撲界に、成瀬川土左衛門という力士がいた。この男が色白でぶくぶく太っていたので、
水にふやけた溺死人(できしにん)のように見えた。
そこで水死人を見た人が、「土左衛門のようだ」と言い始めたことから広まった。
なお、「八百長」という言葉も八百屋の長造という実際の人物から来た言葉である。
◆どさくさまぎれ
江戸時代末期に禁止されていた博打(ばくち)の現行犯は、佐渡へ島送りにされ、金山で
働かされた。そこで博徒は、賭場の手入れのことを佐渡を逆にして「どさを食う」と言った。
ここから手入れの際に起こる騒動や混乱を「どさ」と言い、それが現在の「どさくさ」に
なり。その混乱している状態を利用して、自分の目的を果たすことを「どさくさまぎれ」
と言うようになった。
◆どたんば
江戸時代の犯罪者が、刑場で首を切られる時は、土で築いた壇の土壇場(切場)に引き出されて刑の執行を受けた。
そこから物事の最後のせっぱつまった場面を意味するようになった。
◆どじをふむ
「鈍遅」説と「土地」説がある。
「鈍遅」説は、動作が鈍くて遅れている人をさしたことばが、後に失敗することを表すようになった。
「土地」説は、江戸時代、相撲で土俵外に足を出して負けることを「土地を踏む」と言ったことから、
失敗すること、間抜けなことを意味するようになった。
[な]
◆縄張り
本来は敷地に縄を張って、建物の位置を定めることであった。それが江戸時代に博徒の間で使われ、 親分の勢力範囲をさすようになった。現代では、一般の人々の間でも、自分の受け持ちと他人の 受け持ちの区別を表すのに用いられている。
◆成金
将棋で「歩」が敵陣に入って「金将」と同じ資格を得ることから、歩のような身分の低い者が、急に金のような力を
持つことを指すようになった。そのようなことから今日では、土地を売ったり、事業に成功して急に金持ちになった
人のことを、土地成金、新興成金などと呼んでいる。
[に]
◆にっちもさっちも
「二進三進も」と書き、ソロバンの割り算の九九に今は使われていないが、「二進一十」(にっしんいんじゅう) 「三進一十」(さんしんいんじゅう)という教え方があり、ソロバン用語での「二進も三進も」は、 金銭の融通がきかないさまを言った。そこから、商売や家計が苦しい事を指すようになり、 やがて、一般的に行き詰まって動きがとれないこと、どうにもこうにも少しも進展しないことを 意味するようになった。
◆にやける
「若気」(にやけ)を動詞化したことばで、男が女のように弱々しく、変にしゃれていることを意味する。
「若気」(にやけ)とは、鎌倉・室町時代に諸大名のそばに仕えていた小姓(こしょう)や
衆道(しゅうどう)(男娼=男色)のことで、これらの男性は化粧などをしていて、美しく装っていた。
そこから、女のように弱々しい男を意味するようになった。
一般的には、ニヤニヤ笑って、態度をはっきりさせない人などにも使っている。
[ぬ]
◆抜き差しならない
「抜き差し」は刀を「抜く」ことと「差す」ことで、「処置」「処理」を意味する。そこから 、刀を抜くことも差す事もできない窮地に追い込まれ、どうにもこうにも進展しないことを 言うようになった。
◆濡れ衣
「実のない」を「蓑(みの)ない」にかけてできたことばで、蓑がないと雨に降られて衣(着物)が濡れる。
そこから蓑ないこと→実のないこと、真実でないこと、根拠のない浮き名、無実の罪、事実無根の
ことを「濡れ衣を着せる」というようになった。
[ね]
◆ねこばば
「猫糞」(ねこばば)説と「猫婆」説とがある。
「猫糞」説は、猫は糞をすると砂をかけて隠す習性があることからきた説と
「猫婆」説は、猫好きの老婆が、他人のものを借りても借りっぱなしで返さなかった、 ということからきた説とがある。きたないことを「ばばっちい」というのも「ばば」(糞) からきたもの。
[は]
◆破天荒
ある村で科挙(かきょ)(官史登用試験)の不合格者を「天荒」と呼んでいたのが、 村に始めて合格者が出たので、「天荒」を破ったという意味から「破天荒」ということばができたのである。
◆はったり
喧嘩の時、いきなり相手をはり倒すなどして、乱暴な行動に出て、自分を実際の力より
強くみせることからきたもので、「はったりをかける」「はったりを利かす」などと、
自分の力を誇示することに使われる。
◆ばてる
「果てる」からきたことばで、これ以上できないところまでいって、疲れきってぐったりしてしまうさまを言うようになった。
◆はなむけ
「馬のはなむけ」が略された言葉で、旅立つ人に贈る金品、詩歌などをいう。
漢字では「餞」「贐」と書く。
平安時代、旅立つ人の行く方向に馬の鼻を向けて、道中の安全を祈った風習からきたもの。
なお、贈答用の物品を「引出物」というのは、平安時代、祝宴の終わりに主人側が馬を庭に引き出してその馬を客に
贈ったことから生まれたことば。
◆羽目をはずす
板を縦または横に平らにはることで、その羽目板をはずすということは、常識からはずれる。
即ち調子に乗って度を過ごした人の様子をさすようになった。
[ひ]
◆左利き
鉱夫が使った金山(鉱山)用語からきたもので、酒の好きな人のこと。「左党」ともいう。
江戸時代、金山で働く人々が左手に鑿(のみ)を、右手に鎚(つち)を 持って金鉱を掘ったので、左手を鑿手(のみて)、右手を鎚手(つちて)と呼んだ。
そこから、左手の「鑿手」を「飲手」にかけて、酒飲みのことを意味するようになった。
◆ひやかし
紙すき職人から来た言葉で、品物を見たり値段を聞いたりするだけで、何も買わないことや、からかうことを意味する。
江戸時代、浅草紙を作っていた職人たちが、紙の原料を水に浸して「冷やかし」ている間、近くにあった吉原遊郭に出かけて、
張り見世の遊女を見て回った。
仕事中なので、からかったり品定めするだけで、決して遊女を買わなかった、ということからきたものです。
漢字では「素見」「素通」などと書く。
◆ピンからキリまで
ポルトガル語からきたことばで、始めから終わりまで、最上の物から最低の物までという意味。
「ピン」は、ポルトガル語のピンタ(=点)を略した語で、かるたやさいころの目の1のこと、「キリ」は、クルス(=十字架)の転訛した語で、
10のこと、つまり、「1から10まで全部」の意味である。
「キリ」は、日本語の「切り」で、区切り、切れ目である、とする説もある。
また、利益の一部を取ることを、「ピンはね」というのも、「ピンタ」の下の略からきていて、「一」が転じて「一部分」の意味になり、
「一部分をはねる」という意味である。
[ふ]
◆ぶきっちょ
「無器用」(「不器用」とも書く)がなまってできたことばで、手先をうまく動かすことができないこと、物事の要領が悪いこと。
「無器用」の「器」は、うつわ、入れ物などの日用器具のことで、役に立つ器具という意味。
そこから働きのある人、才能のある人などを「器用」というようになった。
この反対語が「無器用」で、本来「ぶきっちょう」と読んだのが、江戸では詰まって「ぶきっちょ」になった。
また、左ききの人のことを「左ぎっちょ」というのも「左器用」がなまってできたもの。
[へ]
◆へそくり
「ひそかなる金」が転訛して「へそかる金」となり、さらに「へそくり金」となり略して 「へそくり」と呼ばれるようになった。一般的には、妻などが内密にためた金のことに 使われている。
同じような意味を持つ言葉に「虎の子」がある。これは、虎は自分の子供を非常に可愛がり
大事にすることからきている。
◆べらぼう
人名からきたという説と竹の「へら」からきたという説がある。
まぬけ、のろま、愚か者など、人をののしることば。
人名説では、江戸時代の寛文年間に、大坂の見世物小屋に出ていた人物の名前からきたという。
この人物は「可坊」(べらぼう)「便乱坊」(べらぼう)と
呼ばれ、全身が真っ黒で、頭がとがり、目は赤く、あごは猿に似ていた。
そこから醜い人を「べらぼう」というようになり、さらに人をののしる時に使うようになった。
「へら」説では、米をつぶす竹製のへらを「箆棒」(べらぼう)とよび、そこから、
飯を食べるだけで何の役にも立たない人(ごくつぶし)のことを「べらぼう」といった。
[ほ]
◆ぼんくら
博打用語の「盆暗」の「盆」は、盆ござのことで、さいころを伏せた盆に暗いこと、つまり 勝負に対する読みが下手な人のことで、それが一般に広まって、物事に見通しのきかない ぼんやりした人、少し抜けた所のある人の意味に使われるようになった。
[ま]
◆孫の手
中国の伝説に出てくる「麻姑の手」(まこのて)からきたことばで、 木の端を手の指の形に彫った背中をかく道具のこと。
漢の時代、麻姑(まこ)という名前の仙女がいた。
彼女の爪は長く、それでかゆい所をかいてもらうと、良い気持ちになった。そこからかゆい所をかく棒のことを 「麻姑の手」と言った。
日本では、形が孫の手のように可愛らしい事から、「まご」と濁り、「孫の手」と書くようになった。
◆卍巴(まんじともえ)
二つの渦巻きという意味からきている。敵と見方が追いつ追われつ、上下左右に変転し、入り乱れることをいう。
「卍」は、右旋回の渦巻きの意味で、ヒンズー教の太陽神ビシュヌの胸毛が右旋回であったところからきている。
「巴」は、字の形が示しているように、左旋回の渦巻きの意味。
このそれぞれ正反対の方向に旋回する渦と渦がぶつかり合うことを「卍巴」(まんじともえ)と言ったもの。
なお、三者が互いに争って入り乱れることを「三つ巴」という。
[み]
◆みっともない
「見たくもない」の音便形で「見たうもない」の転じたもので「みともない」に、促音 が加わってできたもので、人が見たくもないと思う格好を指すようになって、見苦しいこと、 外聞が悪いことの意味に使われている。
◆みえ
動詞の「見える」の連用形が名詞化したもの。
他人によく見られるように、自分を飾ることをいう。
「見栄」と書くのはあて字である。
本来は単に見える様子を意味したが、それが外観、外見を飾ることの意味になり、
「みえを張る」「みえをつくろう」などと使うようになった。
なお、歌舞伎役者が目立つ表情やしぐさをすることを、「見得を切る」というのも、同じ語源からきたものです。
[む]
◆むてっぽうな
「無手法」と書いて、即ち手に何も持たない、何の考えもなく行う、ものの前後を考えないで、 一気にやってしまうことことを言うようになった。「無鉄砲」と書くのはあて字で、鉄砲玉のように 一気に突き進むという意味合いを付け加えたもの。
[め]
◆目白押し
「めじろ」という鳥は、木の枝にくっつき合うようにして止まる性質がある。本来は、 子供がこれを真似て、「押しくらまんじゅう、押されて泣くな」と言って遊ぶことを 「目白押し」と呼んだのだが、いつしか一般的にも使われ、大勢の人々がすき間なく並んでいることを いうようになった。
◆目安がつく
江戸城の評定所におかれた「目安箱」から生まれた言葉で、見当がつく事と言う意味。
「目安箱」は、八代将軍の徳川吉宗が大衆の意見を聞き、それを政治に生かすために設けた投書箱。
そこからおおよその見当がつくことの意味になった。
なた、同じような意味の言葉に「めどがつく」がある。
これは、目でみることのできる所の意味からきたもの。
◆メリヤス
この語源には、スペイン語の「medias」(メディアス)説とポルトガル語の「meds」(メイアス)説とがある。
両語とも、伸縮するように作った、機会編みの綿織物のこと。
両語とも、本来の意味は「靴下」である。
この靴下に使われた生地を日本では「莫大小」(メリヤス)と書いた。
「莫」は「無」という意味で、大きい人でも、小さい人でもぴったり合うという意味から使われた漢字。
これは明治初期、大阪で開かれた第一回全国勧業博覧会に出品されたメリヤス製品を見て、
政治家の三条実美(さねとみ)が命名したものと言われている。
[も]
◆もとのもくあみ
木に加工して美しく仕上げた朱塗の椀が、使っている内に朱がはげて、「元の木椀」(もとのもくわん)に なってしまった。これがなまって「もとのもくあみ」になってしまった。という ことから、苦労してやったことことがだめになり、以前の悪い状態に戻ることを言う。
◆もどき
「擬き」(もどき)と書き、「擬く」の連用形が名詞化したもので、意味はある物に似ていることをいう。
「擬く」は、似せて作ることで、そこから偽物を作って、本物に見せかけることを言うようになった。
味が雁の肉に似ている「がんもどき」。
葉が梅の葉に似ている「梅もどき」などの例がある。
[や]
◆焼きが回る
「焼き」は、刀の切れ味をよくするため、刀を熱することで、強く焼きすぎると逆に切れ味が悪くなることから、 「焼きが回る」という言葉が出来た。そこから年をとって能力が衰えたり、腕前が鈍ったりすることに使われるようになった。
同様の言葉に「焼きを入れる」がある。これも刀の刃を焼いて切れ味を増すように「人に制裁を加えて、鍛える」という
ことからできたことば。
◆やじ馬
「おやじ馬」が略されたもので、おやじ馬、つまり老馬は常に若い馬に後について歩いた。
そこから人間の場合にも、人の後について、面白半分で騒ぎ立てる人のことをいうようになった。
◆やにわに
「矢庭に」と書き、矢を射る場所、矢の飛んでくる場所からきている。いきなり、だしぬけに、という意味。
矢庭にいるときは、すばやい動作で事を運ぶことが必要であった。
そこから「矢庭に」は、「たちどころに」「すぐに」などの意味に使われるようになった。
◆山の神
古来山の神は女性と考えられていて、この神は機嫌が悪い、嫉妬心が強い、醜い姿をしている、
などの特徴をもっていたため、妻を卑しんでいう場合の例えになった。
◆宿六
「宿」は家のことで、「六」は役立たずの意味の「ろくでなし」を擬人化したもので、「宿のろくでなし」の略。即ち
亭主のことで、妻が夫を卑しめ、又親しんで使う呼称のこと。
◆やけ
「焼ける」が転じてできた言葉で、自爆自棄になることを意味する。
本来は動詞「焼ける」の連用形が名詞化した「焼け」である。
大切な物を焼いてしまった時に起こる捨てばちな気持ちを現している。
「自棄」と書くのはあて字。
なお「やけ」を強めた言い方が「やけのやん八」「やけの勘八」などで、略して「やけっぱち」という。
[ゆ]
◆ゆすり
遊女が相手の気持ちを動揺させ、相手の心を試す意味から転じて、相手を揺り動かして、 金品を奪い取ることの意味になった。漢字では「強請」と書く。
似た言葉に「たかり」があるが、これは蟻や蜂が一カ所に集まって、物を取る様子からきている。
[よ]
◆横紙破り
和紙は縦にすき目があるので縦に破りやすいが、横には破りにくいことから、無理を知りながら、 自分の考えを押し通そうとすること。
同じような意味の言葉に「横車を押す」がある。荷車も前後には動くが横に押しても進まないことからきている。
◆夜なべ
「夜並」(よなべ)からという説と、「夜鍋」(よなべ)からという説とがあり、
夜まで仕事をすること、夜業すること。
「夜並」説は、夜を昼に並べることからきたとするもの。
「夜鍋」説は、夜仕事をする時、鍋で物を煮て食べながらしたということからきている。
◆より
「縒り」「撚り」などと書き、糸や縄の「より」からきたことば。
ねじり合わせること、ねじり合わせたもの。
糸を強くする為に何本かの糸をねじり合わせて、一本の糸にすることを「よりをかける」いう。
また、かけたよりがゆるんだのを元通りにすることを「よりを戻す」という。
ここから、技能を発揮しようと一心にそのことに取り組むことを「よりをかける」といい、別れた男女がまたもとの仲に戻ることを、
「よりを戻す」と言うようになった。
[ら]
◆烙印
刑罰に使う罪人の印として、犯罪者が額に焼き印をつけられ、消すことの出来ない汚名を 「烙印を押される」といった。
[る]
◆るす
「留守」と書き、「留まり守る」の略。
意味は、家に居ないこと。
本来の意味は、主(あるじ)不在の家を守ることであったが、不在の主の方に重点が移り、 単に「不在」の意味に使われるようになった。
また、もとの意味の「守り」は、「留守番」「留守居」と呼ぶようになった。
なお、家に居ても居ないふりをすることを「居留守を使う」という。
[れ]
◆れっきとした
「れき(歴)とした」に促音「っ」が入って出来た言葉。
身分、家柄などが立派なことをいう。
「歴」は、明らかな、はっきりした、の意味。
そこから、祖先がはっきりした由緒ある家柄を「歴とした」と形容するようになった。
また、社会的に名高い人を「お歴歴」と呼ぶ。
[ろ]
◆ロハ
「只」(ただ)の字をロとハのカタカナ二文字に分解したもので、無料のこと。
このことばは、明治時代、西欧の風習が入ってきてから使われるようになった。
従来、茶店で休むと茶代をとられたが、公園にあるベンチは無料で休むことができたので、「ロハ台」と呼ばれた。
◆ろくでなし
「ろく」は「陸」と書き、大工道具で水平を測る器具のことで、陸地のように平らである、
という意味。そこから「物の状態が正しい」「完全だ」「まじめだ」などを意味するようになった。
その否定語が「ろくでなし」で平らでないこと、曲がった者、役に立たない者、のらくら者の意味になった。
「ろく」はその他「ろくに・・・・ない」のように打ち消しの意味でも使われている。
[わ]
◆わりかん
「割前勘定」が略されたもので、各自が平等に勘定を払うこと。
江戸時代。戯作者(げきさくしゃ)の三東京伝が、勘定の支払いを必ず頭割りにしたので、 それを「京伝勘定」といった。
また、戦争中は、軍隊でよく使われた方法なので「兵隊勘定」ともいった。
近頃では、「わりかん」は各自がそれぞれ自分の飲食した分について払うこと、とする若い人が多い。
