
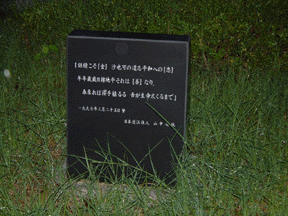
友鹿洞(ウロクドン。旧名・慕夏洞)

友鹿洞(ウロクドン。旧名・慕夏洞)
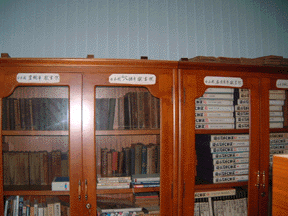
友鹿洞(ウロクドン。旧名・慕夏洞)
韓国大邱(テグ)広域市「沙也可の里」を訪問する
「沙也可」という名前は「女性」のようだが、そうではありません。念のため。
前回の「闇の日本史」で、韓国の降倭の子孫が住む「沙也可の里」(友鹿洞)を少し紹介したが、2002年8月に私も訪問したことがある。(仲尾宏先生と「朝鮮通信使の足跡」を旅した時で、ある。私のHP「朝鮮通信使」にも写真を掲載しているのでご覧ください。)
「沙也可」についての歴史研究は、これからの日韓親善交流に、朝鮮通信使とあわせて、必要なツールとなろう。
説明文・・・・「沙也可の里」とは・・・(私が説明するより、次を見ていただきたい)
(引用:統一日報 2003,3,5号) http://www.onekoreanews.net/index.htm
韓国・慶尚北道は大邱(テグ)広域市郊外の友鹿洞(ウロクドン。旧名・慕夏洞)に降倭・沙也可を訪ねる日本人観光客が増えている。今から四〇〇年前、豊臣秀吉が三〇万の大軍を出兵し朝鮮半島を侵攻した。韓国でいう壬辰倭乱(イムジンウェラン)、日本でいわゆる文禄・慶長の役である。この時、鉄砲の技術を備えた若い軍事集団が朝鮮への侵攻を正道にあらずと拒否、朝鮮王朝側に降伏した。彼らは鉄砲製造の技術を敵方である朝鮮軍に伝え、降倭領将として朝鮮側とともに豊臣軍と戦った。そのリーダーが沙也可(一五七一〜一六四二)である。沙也可、時に二二歳。彼は朝鮮王朝の臣下としてその後もいく度か功労を立て、金海金氏の名字を受け、金忠善(キム・チュンソン)将軍として称えられた。友鹿里には沙也可一四代金在徳さんを頭とする沙也可の子孫およそ三〇〇人が住み、ひとつの村をなす。慕夏堂(沙也可の号)を奉安祭享する鹿洞(ノクドン)書院が朝鮮朝正祖一八年=一七九四年=創建され、今日に至っている。友鹿里と鹿洞書院に日本人観光客が来るようになったのは九〇年代に沙也可の物語が徐々に広まってから。「降倭」と紹介された当時の二文字が新鮮に映った。四〇〇年も昔の個性的な日本人の足跡をたどり友鹿里を訪ねる日本人観光客は〇〇年約一五〇〇人、〇一年二〇〇〇人と毎年二〇〜三〇%の増加ぶりを見せている。今年も近江八幡市職員が立ち寄る予定。
沙也可(金忠善)は、どんな人物?
壬辰倭乱で豊軍に反旗。 一五九二年四月、豊臣秀吉が朝鮮に侵攻した際、加藤清正軍の右先鋒として三〇〇〇人の兵を率いて同月十三日、釜山に上陸した。上陸のその日に直ちに略奪を禁じる軍令を下し、同二十日、反旗をひるがえして朝鮮軍に投降した。後の『慕夏堂記』には「釜山に上陸して殺戮を犯した」と記され、豊臣軍の侵攻を批判。「捨生取義」を叫んで礼と義の国・朝鮮に部下二四人ともに身を委ねた。三〇歳の時、晋州(チンジュ)牧使の娘を娶(めと)った。沙也可は火縄銃(鳥銃)の製造と火薬の製法に明るい雑賀衆と言われ、その出身は瀬戸内海とも九州ともいわれる。火薬の製法伝授と火縄銃の製造によって戦局を好転させる功を立て、宣祖から金海金氏・金忠善(日本名・沙也可)の賜姓賜名を受けた。沙也可の投降の背景には雑賀衆は鉄砲が上手く「陣借り」して戦をした傭兵集団であったため、「自分たちを必要とするところなら秀吉でも家康でもよく、日本でも朝鮮でもよかった。一族の活路を求めて居着いた」という見方をする人もいる。
沙也可は弱冠二二歳で壬辰乱に参戦、秀吉の二度目の侵攻・丁酉再乱に対抗して二六歳で再び参戦。北防一〇年の戦闘、李の反乱、丁卯胡乱、丙子胡乱に志願し戦ったので「三乱の功臣」と称えられる。七二歳で死没。望郷の七言絶句を残し、故郷を懐かしんだ。
この文中に出てくる近江八幡市職員とは私たちのことである。残念ながら2003年は私ではなかったが。なぜ「統一日報」の記事に、近江八幡市のことが載っているのかというと、近江八幡市国際(交流)協会が、この旅行を後援しているためであり、毎回、友鹿洞のすぐ近くの「密陽市」と近江八幡市が、朝鮮通信使を通じて姉妹都市提携しており、市長の親書を持って行っているためである。
なぜ「密陽市」と朝鮮通信使と「近江八幡市」なのかというと、密陽出身の義僧といわれた「松雲大師」(韓国では四溟大師=サンミョンテッサ)が、朝鮮通信使(最初は探賊使できた)のきっかけをつくり、近江八幡市には、朝鮮通信使が通った街道「朝鮮人街道」が残されており、昼食休憩を八幡別院(本願寺派)で行なったという記録があることから、韓国・密陽市と近江八幡市は1994(平成6)年12月に姉妹都市提携を結んでいる。
なお「朝鮮通信使」や「松雲大師」のことは「仲尾宏先生(京都造形芸術大学)=滋賀県大津市のお住まい」の著作物を読むことをお勧めします。なんせ先生は第一人者だと私は思っています。こんなことを私は実際に目撃しました。仲尾先生と「朝鮮通信使の足跡」の旅で、韓国釜山から船で対馬に渡るときの船中で、韓国の学生グループ(もちろん私たちのグループではない)の一人が、先生に話しかけ、先生に対馬での講演(ゼミ)を依頼したのです。私はそのとき先生の横の座席でした。その夜、対馬で一泊したとき、夕食のあと、先生は、例の韓国学生グループが泊まっている旅館へ、出かけていかれましたので、ああ、講演にいったのだなあ、と思いましたが、そのとき、韓国の学生にも知られている高名な先生(こちらは友達みたいに親しくさせていただいていたので、)なのだと改めて認識した次第である。滋賀には地元のものを評価しないという風潮があるが、私もそれに染まっていたのだろうか。
2002年には近江八幡市で、「朝鮮通信使ゆかりのまち」全国大会を開催した。国内からは、仲尾先生はもちろん、雨森芳洲の縁で高月町や対馬市(厳原)、福岡市、広島市、大垣市、静岡市などから参加され、韓国の領事館や、朝鮮総連、韓国居留民団、さらには、韓国密陽市からは市長一行と中学生、釜山市からも参加された。そして、非公式だが、「沙也可の里」からも、私が友鹿洞に行ったとき、サムゲタン(鳥料理)で迎えてくださった「金」氏(=沙也可の子孫=名前を失念した)も近江八幡市に見えられていた。当然、再会を喜んだのは言うまでもない。
下記は、私が「沙也可の里」=友鹿洞を訪れたときの写真である。韓国に「近江八幡」という名前があったのには感激した。記念碑にある「近江国住人 山中 靖城」という方は、近江八幡市加茂町にお住まいの郷土史家で、密陽市との中学生交流についても協力をいただいている方である。
密陽市にある松雲大師像
 |
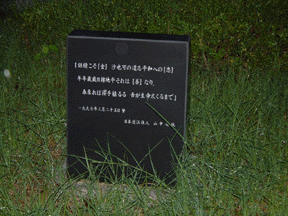 友鹿洞(ウロクドン。旧名・慕夏洞) |
 友鹿洞(ウロクドン。旧名・慕夏洞) |
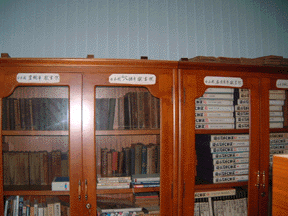 友鹿洞(ウロクドン。旧名・慕夏洞) |