
1,出る杭になってやる
これは、私のPCの壁紙(背景)用として作ったものである。

出る杭は、もっと出てやろまいか
「出る杭は打たれる」というが、まさに、私の市役所での人生は「出る杭は打たれる」の連続であった。出なくてもよいのだが、あえて、わたしの前を走る人がいなかったというのもあろうが、いつのまにか、私の性分として、人が手をつけていない分野を開拓していくのが楽しみとなっていた。やはり仕事は楽しんでするものであると私は思っている。親しい職員に言わせると、私は10年ほど他の職員より前を走っているそうである。いまは時代の流れが速く、それでも3〜5年は先を見ているそうである。それは私のせいではなく、他の職員が私に合わせるように(=私と同じように)、スキルアップをしなければならないところを、努力を怠っているということらしい。ずいぶんと持ち上げてくれるものである。その友人は私のことをよく分かっていてくれるからこその発言だと思う。県から出向されていたM職員からも「あなたは、県庁とか、もっと大きな規模の市役所にいれば能力を発揮できるタイプだ」といわれたことがある。どういう意味にとったらよいのか聞き忘れたが、カツオやマグロが小池では泳げないという意味だろうと理解した。実際、今の市役所内では私の知っている2〜3の職員を除いて他の職員は私の発想や企画についてこようともしないし、その半分は抵抗勢力と化すのである。まさに農村集落に根強い(いや日本社会全体にはびこる)「足引っ張り」という悪しき共同体規制に伴う意識の壁と化すのである。それを行政文化という人もいるが、やはり人=職員の意識の問題であろう。
市民課にいたとき、住民票等の自動交付機を導入しようとしたら、JRでは自動券売機を導入して、人情味がなくなった。やはり対面販売がよいではないか。というような屁理屈で反対された経緯がある。私は窓口が混むということもあるが、市民には対面方式の交付システムだけでなく自動交付機という選択肢を増やすほうがよいのではないか。対面が苦手な人もいる。ATMなどが拡大している理由はそこにある。と反論したが、結局、認めてもらえなかった。
それから6年後にIT化の進展に併せて自動交付機は、市民課に導入された。一時が万事この調子である。私がパートナーシップ推進課にいた時にも机の配置の件で2回ほどあった。1回目は、新たな課としてスタートするときの事、新規の課であるから、既存の事務机を廃止して、三重県庁みたいにフリーアドレス制(固定した机を持たずに、空いてある場所に座る)にしようと課内で合意して、大きなフリー机をもらえるように財政課と交渉したが、そんな形は認められない。貸し出す事務机を使ってくれの一点張りであった。もうすこし柔軟な頭で対応してほしいものである。事務机6個よりもフリー机1個のほうが安くつくと思うのだが。2回目は総合窓口の設置に併せてパートナーシップ推進課と環境課が、西別館に移動したときのこと。床をOAフロアーにしてくれたので、室内は土禁としたが、そのとき、既存の事務机(前回にそのように財政課に言われていたので)を利用して、民間等の事務所が行なっているようなパネルで仕切り個室風(下図)にして合理的に配置しようとしたのだが、それも、今の市役所内でそんなことをしている課はどこにもない。他との均衡がとれない。という理由で反対された。
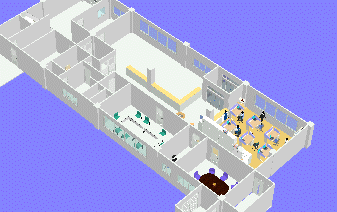
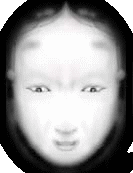
この配置についても、いづれかの未来には、どこかの課で実現されることだろう。
いづれにせよ、私の現役時代にはどうか分からないが、頭を何回もたたかれようが、挑戦だけは続けていきたい。
