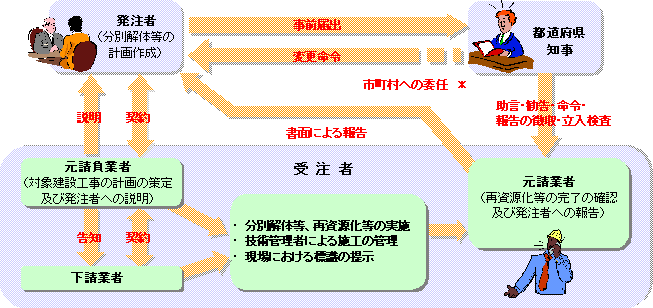
平成14年5月30日より、建設(解体)工事は分別解体・再資源化が義務づけられています。
大量生産・大量消費社会による廃棄物の排出量増大に伴い、最終処分場の不足や不法投棄の多発などの問題が深刻化している中で、特に問題となっている建築解体廃棄物を中心に、土木系も含めた建設廃棄物全体のリサイクルを推進するため、平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が公布され、平成14年5月30日より完全施行されました。
特定の建設資材を用いた現場では分別解体を行い再資源化することなどが義務づけられました。この分別解体・再資源化を徹底させるために以下の義務が課せられています。
| 発注者(民間・公共・個人問わず)および受注者に課せられている義務 | |
|---|---|
| 発注者 | 建物解体工事を発注する場合、工事着手の7日前までに届出等が必要 |
| 受注者 | 解体工事における分別解体 |
| 分別解体により発生した特定の建設資材廃棄物の再資源化等 | |
| 分別解体計画等についての発注者への説明 | |
| 届出事項を告知したうえでの下請負契約 | |
| 再資源化等の完了を発注者に書面報告 | |
| 解体工事業の登録が必要 ただし、建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係るものに限る)を受けているものは除く | |
| 対象建設工事の種類 | ||
|---|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積の合計 | 80m2 |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 | 500m2 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円(税込) |
| 建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円(税込) |
上記の規模における工事により発生した建設資材廃棄物のうち、コンクリート、木材等その再資源化が資源の有効な利用および廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものであり、以下のものが政令で定められています。
ただし、指定建設資材廃棄物(木材)については、再資源化施設までの距離が遠いなど、経済性等の制約が大きい場合には、再資源化に代えて縮減(焼却)を行えば足りることとしています。
→工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを越える場合等
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手日の7日前までに分別解体等の計画等について、都道府県知事(又は建築主事を置く市町村・特別区の区長。以下同じ。)に届出なければいけません。また、都道府県知事は、その計画が施工方法に関する基準に適合しないと認めるときは、発注者に対し分別解体等の計画の変更等を命ずることができます。
なお、国や地方公共団体については、対象建設工事の届出に代えて、都道府県知事に対してあらかじめその旨を通知すれば足りることとしています。
元請業者は、対象建設工事を請負うにあたり、発注しようとする者に対して分別解体等の計画等の必要事項を書面で説明しなければいけません。また、元請業者・下請負人にかかわらず対象建設工事を請負うものは、下請負人に対して発注者が都道府県知事に届出した事項を告知しなければいけません。
また、元請業者は再資源化等が完了した際、その旨を発注者に書面で報告し、あわせて再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければいけません。
発注者と元請業者の契約に際し、契約書の中に建設業法に定められた事項のほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を明記することで、両者が解体に関して適正な費用を負担する意識をしっかりと共有することを求めています。
都道府県知事は、分別解体等の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該対象建設工事受注者又は自主施工者に対して、分別解体等の実施に関し、必要な助言・勧告又は命令をすることができます。
また、再資源化に関しても都道府県知事(又は地域保健法の保健所を設置する市・特別区の区長)は、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該対象建設工事受注者に対して、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関し、必要な助言・勧告又は命令をすることができます。
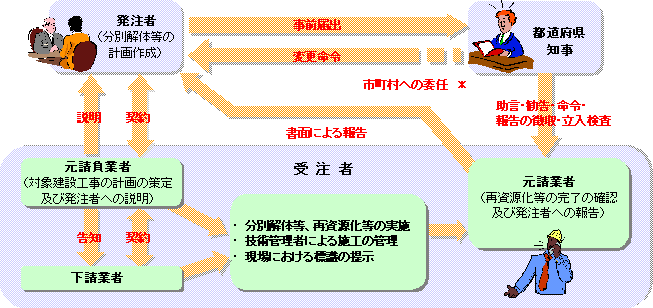
| 分別解体等および再資源化等の実施義務は平成14年5月30日以降に契約した一定規模以上の建設工事に適用 契約によらず自ら施工される場合には平成14年5月30日以降に着手した一定規模以上の建設工事に適用 |