�m���Ĕ[���I�p���������@�̎��ۂƎ��̎v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Q�N���[���Z���^�[���@�@����@�G�v
�P�A�͂��߂�
�@�p�����̏����́A�s���E�����̐����ƌ��N�A��Ƃ̌o�ϊ����A����ɂ͒n�����ɒ������Ă��邱�Ƃ���A���̎��X�Ŏ���̗v�����āA�x�X��������Ă��܂����B�ȉ�������ݖ���s�@�����A�n�����̔j��A�����̊��p�Eػ��ق̐��i�Ƃ������e�ϓ_���牽�x����������A�K���͋�������Ă��܂����B�܂��A�z�^�Љ�`�����i�@��Ɠdػ��ٖ@�Ȃǔp���������@�̓��ʖ@�Ƃ������ׂ��e��̐V�@�����肳��Ă����Ƃ���ł��B
�@���������v�����āA�{�s�̂��ݏ����{�݂���W���@���N�X�ω��i�����P�j�����Ă����Ƃ���ł��B
�@�������A�܂��s����r�o���Ǝ҂̔F���s������������悤�Ɏv���܂��B�����œ�����p�����s���Ɋւ���Ă��鑤����A���̒��Ŋ����Ă��邱�Ƃ̈�[���ȉ��ɏq�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B
�Q�A��Q�N���[���Z���^�[�́u��ʔp�����v�́u���ԏ����{�݁v�ł�
�@���a�T�V�N�ɉғ����������́A�T�O���F���Q�F�łP�U���ԉғ����ĂP�O�O��/���̏����\�͂ōŐV�����ւ��Ă����̂ł����A���łɂQ�S�N���o�߂��A�{�݂̘V�������ڗ����Ă��܂����B����4�N�ɂ͑e�傲�ݔj�Ӌ@�i�T�^�[���j�����A�����P�O�N�ɂ�ػ��پ����u��߂�����v�����������݂��ғ����Ă��܂��B�܂������P�S�N�ɂ̓_�C�I�L�V�������̂��߂̔r�K�X���x�����i���u�j�{�݂����݂��A�����P�U�N�x����5���N�v��ŁA�V�����ɑΉ����邽�߂̋@�\�̍H����i�߂Ă��܂��B���̍H���͘F���߂邱�Ƃ���3�T�Ԃ����x�i����ȏ��~����Ɩ�����������邲�ݗʂŃs�b�g�����݂��ꎞ�I�ɒ�������Ƃ��낪���邽�߁j�ŔN2��ɕ�����5�N�ԂŐ����H�������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�܂��A�F�̉^�]�ғ����Ԃ������P�V�N�x����Q�S���ԉғ��i���`�y�܂ŁB���j���͋x�F�j�ɕύX���܂����B
�@���W�ɂ��Ă��A���a58�N�x����A�r���E�ʂ�s�R���݂���敪���A�����X�N�x�ɂ̓y�b�g�{�g���Ǝ��p�b�N���R���݂���敪���A�������݂Ƃ���ػ��قɉĂ��܂��B�܂������P�T�N�x�ɂ͐V���E�G�����A����18�N�x����̓_���{�[�����������݂Ƃ��ĉ�����Ă��܂��B
�@���̂悤�ɏ����ł����݂̔r�o�ʁ��ċp�ʂ�}���A�K���ȏ����ɓw�߂Ă���Ƃ���ł����A�܂��܂����ݏo�����[���̕s�O���r�o�ʂ̑����ȂǑ����̉ۑ肪����A�s���E���Ɣr�o�҂̈�w�̗����Ƌ��͂��d�v�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�N�X���ݏ����o����������Ă���A����Ȃ�O�ꂵ�������ʑK�v�ƍl���Ă��܂��B
�@���ɁA���{�݂ɔ�������Ă��鎖�ƌn���݂̔����҂̕��́A�����A���{�݂ł́A�����Y�p����ʔp�����ƕ����ď����ł���Y�Ɣp�����i�����A�������A�j������Ă��܂������A����6�N�ɔp������������S�ʉ��������ہA�u�����Y�p�̏����v�̍��͍폜����܂����B���̂��߁A���݂́A�������݁i���ƒ�n��ʔp�����j�Ǝ��ƌn��ʔp������������ꂵ�Ă��܂���B�������A�����Y�p�������Ă��鎖�ƎҁE���Ə��̕����A���܂��ɁA�����܂��̂ŁA���d�ɂ��f��\�������Ă���܂��B�E�E�E
�����u���킹�Y�p�v�Ƃ́A�s�������Y�p�̏�����������ꍇ�ɂ����p��ł��B���t�̎g�����̖��ł����A���̏ꍇ�́u���������p�����v�Ƃ����ق����������Ǝv���܂��B�r�o�҂̔p�����̔��o�ߒ��ɂ����ĕ��ʂ���Ă��Ȃ��p�������s�����������邱�Ƃ����ۂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B�s�������u�����Y�p�v�������p�����Ƃ������ƂŁA��ʔp�����̏����{�݂ŎY�Ɣp�������������邱�Ƃ��A�Ȃ��i�܂Ȃ����Ƃ������Ƃɂ́A�������̗��R������܂��B�@����́A���肬��Ō����Ε⏕���K���@�ᔽ�ɂȂ肤��Ƃ������Ƃł��B�i�{���p���������{�݂̕⏕�͈�ʔp�����̏����ɌW�镔���ɂ����⏕�����o�Ă��Ȃ��̂ŁA�Y�p�ɂ��Ă͌������Ǝҏ����ӔC�����O�Ƃ��Ă���A�͂��߂���Y�p����������v��Ȃ�A���̊��������⏕���͂ł܂���B�j�܂��A�Y�p�ɂ��Ă͏����̎萔�����邱�ƂɂȂ邽�߁A�c���ʂ��Ď萔�����߂�����K�v�ɂȂ�܂��B�����ĂȂɂ��A���f�{�݂ł���p���������{�݂́A�s���������ݏ����{�݂�ݒu����ꍇ�ł������N����قǁA�n����������ςł���A���v��̒i�K�ŁA�n���̗����邽�߂Ɉ�ʔp������������Ȃ��Ɩ��Ă��邱�Ƃ��唼�ł���܂��B�Y�p�̏ꍇ�ɂ͍L��I�Ɉړ����Ă���A���̎s�����⌧����̎Y�p���Ȃ����̎s�����Ŏ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�Ƃ������ƂŁA�����i�K�����ʔp������������Ȃ��ƒn���̖����邽�߁A�r��������Y�p������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂����Ԃł��B�E�E�E�E���������u�p�����v�ɂ́A�Y�Ɣp�����A���ƌn��ʔp�����A�ƒ�n��ʔp�����Ƃ����R�̑傫�Ȃ����肪����܂��B���̂������Ɍ������Ǘ����ׂ����̂���ʊǗ��Y�Ɓi���邢�͈�ʁj�p�����Ƃ����܂��B��̓I�ȗ�����Ă݂�ƁA�Y�Ɣp�����ɂ͓��ނ���܂��B�u�p�v���X�`�b�N�v�u�K���X�����v�u���������v�Ƃ������A�ǂ�ȋƎ�ł��Y�Ɣp�����ɂȂ���́B�����āu�������v�u�����v�u�@�ۂ����v�̂悤�ɋƎ�ɂ���āi�Ⴆ�A���{�Ƃ̎������j�͎Y�Ɣp�����ƂȂ�A����ȊO�͎��ƌn�̈�ʔp�����ƂȂ���̂�����܂��B�t�ɂ����Ί�ƁE���Ə�����o�邲�݂́u�Y�Ɣp�����v���u���ƌn��ʔp�����v�̂����ꂩ�ɂȂ�킯�ł��B�p���������@�ł͏�������ӔC�͖��m�Ɍ��܂��Ă��܂��B���Ȃ킿�A�ƒ�n��ʔp�����͎����̂���������B�Y�Ɣp�����E���ƌn��ʔp�����͊�ƁE���Ə�������̐ӔC�ł����Ȃ��A�Ƃ������̂ł��B�u�s�@�����v����Ζׂ���S�~��������ƊǗ����邵���݂��u�����Ǝ҂̋����v�Ɓu�Ǘ��[�i�}�j�t�F�X�g�j�v�ł��B�܂������x�ł����A���ƌn��ʔp�����͎s�����̋����ƎҁA�Y�Ɣp�����͓s���{���̋����Ǝ҂��S�����ƂɂȂ��Ă��܂��B�����P�T�N�̔p���������@�̉����Ō��i�����E����̋`��������������ᔽ�����ꍇ�̏����͂�茵�����Ȃ��Ă��܂��B�����āA������͊Ǘ��[���x�i�}�j�t�F�X�g�j�Ō����ɏ����n�܂ł̗�����Ǘ����܂��B�Ǘ��[�͔r�o�҂�������ҁA���ԏ����{�݁A���o�ҁA�ŏI������Ɨ���A���ꂼ�ꂪ�ʂ����Ǘ����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�ŏI������ɉ^�ꂽ�S�~�͊Ǘ��[�Ń`�F�b�N����A�r�o�҂܂ŏ����߂���܂��B������T�N�ԕۑ����A�����̍ۂɂ͒��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�E�E�E�E���̏����̎d���̗�O���u���킹�Y�p�v�Ƃ������x�ł��B��ʔp�����ƈꏏ�ɔR�₹����̂������܂��B�{���A�Y�Ɣp�����ɕ��ނ������̂́u�p�v���X�`�b�N�v�u�����v�u�������v�u�@�ۂ����v�Ȃljƒ납��o��S�~�Ɠ����̂��̂ł������Ƃ��Ă��A��ƁE���Ə��͐ӔC�������ď��������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���ƌn��ʔp��������Ƃɏ����ӔC������܂��B�i���Ȃ݂ɁA���Ǝ҂�����I�ɉ������邲�݃X�e�[�V�����Ɏ̂Ă遁�o���̂͊��S�Ȉ�@�s�ׂł��B�j�����ŁA���ƌn��ʔp�����Ɠ����悤�ɎY�Ɣp�����Ŏ����̂̏ċp�{�݂Ɏ����߂�悤�ɁA��O�K�肪�݂���ꂽ�̂ł��B�u���킹�Y�p�v���x�́u��ƁE���Ə��͐ӔC�������ĎY�Ɣp��������������v�Ƃ������Ƃ̗�O���x�Ƃ����܂��B�E�E�E�E�E�������A���̐��x�́A�O�q�̂Ƃ���{�s�ł͓K�p���Ă���܂���̂ŁA�������{�݂Ɏ����߂鎖�ƌn���݂͎��ƌn��ʔp���������̎�����ƂȂ��Ă���A�Y�Ɣp��������������ŏ���������s�ׂ͈�@�s�ׂƂȂ�܂��B�܂��A���ƌn��ʔp�������邢�͎Y�Ɣp�������ƒ�n��ʔp�����ƋU���Ď���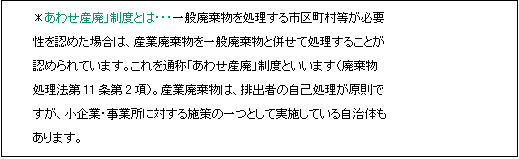 �ނ��Ƃ��֎~����Ă��܂��̂ŁA��ƁE���Ǝ҂̕��́A�����ӂ����肢���܂��B
�ނ��Ƃ��֎~����Ă��܂��̂ŁA��ƁE���Ǝ҂̕��́A�����ӂ����肢���܂��B
�R�A���݂ɌːЂ��Ȃ��E�E�E���ꂪ��肾
�@�p�����͔����ꏊ�ɂ���ĉƒ�n��ʔp�����A�Y�Ɣp�����A���ƌn��ʔp�����Ɩ@���ł͖��m�ɕ�����Ă���̂ł����A���������A�S�~�ɌːЂ��Ȃ�����A���ۂ̌���ł́A�u�������ꂽ���݂���ʂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ����̂��������E���̎����ł��B���Ǝ҂̂��݂��ƒ납��̂��݂��ƋU���Ď����Ă���ꂽ��A�����j�~�ł��Ȃ����Ԃ�����܂��B�Ⴆ�A�������Ŏg���Ă����|���@�i�ƒ�p�j�͋敪�ł́A�Y�Ɣp�����i���������A�p�v���X�`�b�N�j�Ɩ����ł����Ă��A�������Ǝ҂��A�ƒ�Ŏg���Ă����|���@���Ƃ����Ď����ꍇ�ɂ́A�����M�p���邵������܂���B��t���ł̐��ۂł̖h�~��͂���قǏd�v�ł���A�������A���U�̎�����������A���̎��Ǝ҂͔�������̂ł����A�����I�Ɏ��X�Ɣ�������邲�݂����������������Ă���킯�ɂ͂����܂���B���������A�����̒��o�����Ȃ�A�������Ƃ��������P�[�X�����̒����ɂȂ�܂��B�ƒ�n��ʔp�����̉�������Ă��邲�݃X�e�[�V�����̒��ɂ��A���邢�͋��Ǝ҂����W�������݂̒��ɂ���@���݂͍��݂��Ă��邩��������܂���B�������A��������Ă��܂�����A�S�~���敪���邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł��B���̂��ߐ��ۂŃ_���Ȃ��̂̓_���ƌ�����B�R�Ƃ����ԓx��A�s���̖@������ɑ���[���E�����ƃ���������͌������܂���B���ɕ����P�W�N�S������萔�����l�グ����Ă���܂����A���Ƃ��݂��ƒ낲�݂��ƋU���Ĕ�������鎖�Ə��̕��������Ȃ��Ă��܂��B���Ƃ��݂Ȃ̂��ƒ낲�݂Ȃ̂��͎����Ă������݂̒����ׂ�Δ��邱�ƂȂ̂ł����A�������������Ǝ҂�����Ƃ������Ƃł��B
�@����ɖ��Ȃ̂́A�����P�U�N�x�ɂ����Ȃ�����ƁE���Ə����v�����ł́A�ߍ]�����s���ɂ͂Q�C�W�O�O�̎��Ə�������܂��B�Ƃ��낪�A���{�݂ɒ��ڂ��݂��������Ă��鎖�Ə��i���Ƃ��݂Ƃ��ė�����������Ă��鎖�Ə����j�͂R�O�O���Ə��A�i���j���g��X�R�Y�ƂȂǂ̈�ʔp�������W�^�����Ǝ҂W�Ђ��_��Ȃǂ��Ď��W���Ă��鎖�Ə��͂S�O�O���Ə��ŁA�v�V�O�O���Ə��ł����Ȃ��B���Ƃ̂Q�P�O�O���Ə��́A�ǂ��ɂ��݂������Ă����ď������Ă���̂ł��낤���B�����炭�A���s���ɂ��݂������Ă����ď���������A���ȏ��������Ă���Ƃ͍l�����Ȃ��B�����炭�X�e�[�V�����ɏo����Ă��邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B���N�ƒ�ɔz�z����u���݃J�����_�[�v�ɂͽð��݂ɏo���Ȃ����݂Ƃ��āu���ƌn���݁i���ƌn��ʔp�����A�Y�Ɣp�����j�v�����Ԃɋ����Ă���̂����A���Ă����Ȃ��̂ł��낤���H
�s���ɂ́u���݃X�e�[�V�����v�̐��͂P�R�O�O�ӏ�����Ƃ���Ă��邪�A���ۂɂ͂R�P�S�P�ӏ��ł���B�iH17�A�R�������݂ŁE�E�E���̓���́A�R���݃R�[�X���P�Q�S�V�ӏ��A�s�R���݃R�[�X���P�Q�S�S�ӏ��A�������݃R�[�X���U�T�O�ӏ�����B�j�R���݂ƕs�R���݁A�������݂̂R�̃X�e�[�V���������܂��ܓ����ꏊ�ɂ���A������P�ӏ��Ƃ��ăJ�E���g����ƂP�R�O�O�ӏ��ɂȂ邪�A���ꂼ����W�����قȂ�W�łR�ӏ��Ƃ��ăJ�E���g����Ɓu�R�P�S�P�ӏ����ð��݁v�ƂȂ�̂ł���B
���Ƃ��݂��A�X�e�[�V�����ɏo����Ă���ƁA�ƒ낲�݂Ƃ��Ď��W���J�E���g����̂ŁA���{�݂ւ̔����ʂ���W�ʂ̃f�[�^�[�ɂ��傫�Ȍ덷���łĂ���̂ŁA���݂̃f�[�^�[�͐M���ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�܂��A���ۖ��Ƃ��āA�����珬�K�͏��X�ȂǂɁA�u�ƒ낲�݂ƈꏏ�Ɏ��Ƃ��݂��o���Ȃ��ł��������v�ƌ[�����Ă��A�o���l�����Ǝ҂͏o�����낤���A�����܂ł̔�����i�̂Ȃ��l�⋖�Ǝ҂Ɉ˗�����̂����Ԃ�l�́A�X�e�[�V�����ɏo���̂ł͂Ȃ����낤���B
�����̈ᔽ���݂��Ȃ�����i�Ƃ��āA�Č��s�E���l�s��F���s�́A�L���łȂ玖�Ƃ��݂��X�e�[�V�����ɏo���Ă��悢�Ƃ����悤�ɕ��@��ς��Ă���B���Ȃ킿���ꂪ�A�u���ƃS�~��p�w��܁v�̔̔��ł���B���̎��ƃS�~��p�w��܂ŁA�X�e�[�V�����ɏo���ꂽ���݂́A�s�����W���Ă���B�u�ߍ]�����s�����̕��@���܂˂�ׂ��ł���B�v�ƂP�V�N�x�Ɋ��ۂ̔p�����S���ɒ�Ă�����A�V�����{�݂��ł�����l����B�Ƃ������Ƃň�R���ꂽ�B
�܂��������b�ɂȂ�Ȃ��B��R���ꂽ�̂́A���ꂾ���ł͂Ȃ��B���ɂ����Ắu�ƒ낲�݂̗L�����K�C�h���C���v���P�W�N�x���ɂ��o�����Ƃ����̂ɁA�{�s�ł͂Ȃ�̏��������Ă��Ȃ����Ƃł���B���̂��߂̑Ԑ����ƒ��O�ɗ����グ�邱�Ƃ��Ă����̂����A������A�V�{�݂̉ғ��ɂ��킹�Č�������Ƃ������Ƃł������B�i���̒��ł͖{���ɂ��C������̂����ȁA���̒S���A���͂Ǝv�����B�]�k�����Ă̒�A�����P�W�N4���̒���ٓ��ŁA���̊��ۂ̒S���A���͑�����ւ��ƂȂ����B�j�{�s�́u�p����������{�v��v�i����11�N3������j�ł́A�V�����{���݂͕���20�N�ғ��ƂȂ��Ă��邪�A���܂��ɏꏊ�E�p�n��{�݂̓��e�E�K�͂��������܂��Ă��Ȃ���Ԃł���A�ނ�i���ۂ̔p�����S���j�͕���23�N�ғ���ڕW�ɂ��Ă���ƁA��������������Ɍ��ݎ����̉��������ďq�ׂ��܂���Ă������A���K�̌v��͂����܂ł�����20�N�S���̉ғ��ł���B��{�v��ł́A�w��ܐ�������16�N�x�ɂ͎��{���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂����A���ꂳ��������Ă��Ȃ������B�Ӗ��ɂ���������B�i�ٓ��������Ă����R�ł������B�j���Ȃ݂ɁA�w��ܐ����̗p���Ă��Ȃ��̂͌����ł͋ߍ]�����s�Ƃ��ƂP�ӏ��ł���B�O�q�̔p����������{�v��ł͕���16�N�x�ɁA�w��ܐ������邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A���������ɕ����Q�R�N�x���炷��ɕς��Ă���B����������̖������Ɓi�ނ�͐V�{�݂̌`�Ԃɕ�����K�v������Ƃ��������͂��Ă��邪�E�E�E�j
�V�{�݂̌��݂ɂ��Ă��A���Z���^�[�ł́A������x�̗v�]�������Ă���B����͌��݂̎�@�Ƃ��Ă�PFI�����p����Ƃ������Ƃł���A���s�̘F����̂���̂ɍ��̕⏕���ΏۂƂ��邽�߂ɂ́A�RR���i�̎{�݂ꏊ�ɍ�邱�Ƃ��K�v�ŁA���̂��߂ɂ́A�V�{�݂����݈ʒu�ɋ߂��ꏊ�Ɍ��݂���B�F�ɂ��Ă��K�X�n�Z�F�������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����T�C�N���Z���^�[�ɂ́A���L�̊ʁAPET�{�g�������łȂ��A���̑��v����؍ނ̃`�b�v�����}���{�݂����B���邢�͒�d���ɂ��^�]���\�Ȃ悤�Ɏ��Ɣ��d�i�ł���Γd�C�������Ȃ��悢���j�������A�ċp�M�𗘗p�������c�̗���≷���v�[�����אڂ��Č��݂��邮�炢�̂��̂��ق����B�ȂǂȂǁA�ƂĂ������Ȋ�]�ł���B�E�E�E�E�����̊�]�Ɗ��҂�����ɕ����Q�R�N�܂ʼn������Ƃ́A�ƂĂ������ł�����̂ł͂���܂���B
������ɂ��Ă��A���Ƃ��ݑ�́A�K�v�ł���A���̂��ߓ����ōl���Ė{�s�̔p�����������Ɋ�Â����Ə��ł́u�p�����Ǘ��ӔC�ҁv�̑I�C�����Ă��炤�K�v������Ƃ̌��_�ɂȂ�B�u�p�����Ǘ��ӔC�ҁv�̐ݒu�����肢���邱�ƂɂȂ����B������A�����ł͂Ȃ����ۂł��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂����A���܂܂ʼn������Ă��Ȃ������B�Ƃ������Ƃ����ł���B���L�́A�������l�������ʂł��邪�A���ۂɒ�Ă�����A�����ɏC�����������ĕԂ��Ă����B������ŏo���Ƃ����̂ł��낤���B����ł͖{�����t�ł���B���{�݂ɒ��ڔ������Ă��鎖�Ǝ҂ɂ͓n���邾�낤���A���Ǝ҂����W���Ă��鎖�Ǝ҂�A���̎��Ə��Ɍ[������̂́A�I�^�N�炾�낤���B�E�E�Ƃ̎v��������A���ۂɍĒ�N������A���܂��ɉ����Ȃ��ł���B�ȉ��Q�l�ɁA�����ōl�������ʂ��f�ڂ��Ă����B
���ݔ����@���ƎҁE���Ə��̊F�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߍ]�����s�@��Q�N���[���Z���^�[���@
�@���ƌn���݂̓K���r�o�y�ь��ʉ��ɔ����u�p�����Ǘ��ӔC�ҁv�̑I�C�ɂ��āi�˗��j
�@�����A�v�X�����˂̂��ƂƂ���ѐ\���グ�܂��B
���f�͓��N���[���Z���^�[�������p�����������肪�Ƃ��������܂��B
���āA����Q�N���[���Z���^�[�ł́A�ŋ߁A���ƌn��ʔp�����Ə̂��ĎY�Ɣp��������������A���ƌn��ʔp�����ɍ����ĎY�Ɣp�������������ގ��Ǝ҂��ڗ��悤�ɂȂ������߁A��t�ł́A����̃g���u�����₦�܂���B
�@���{�݂͈�ʔp�����̏����{�݂ł���A�Y�Ɣp�������������邱�Ƃ́A���s�@�ł͂ł��܂���B���݂��p�����ɌW��͎Y�Ɣp������s�@�������A���邢�̓o�[�[�����ȂǍ��ۓI�Ȗ��܂Ŋւ���āA�V���������킵�Ă��邱�Ƃ͂����m�̂��ƂƑ����܂��B����قnj������ɂ��邱�Ƃ��������肢�܂��āA���{�݂ɏ������ϑ������ꍇ�ɂ́A��ʔp�����i�ƒ납��̐������݂ƁA�Y�Ɣp�����Q�O��ނ��������Ɗ����ɔ����Ĕr�o����鎖�ƌn���݁j�݂̂̔����ƒ��ԏ����Ɍ��点�Ă��������Ă���܂��B
�܂��A���ݎ���`��͓����ł��A��ʂ̉ƒ납��o����鐶�����݁i�ƒ�n��ʔp�����j�Ƌ�ʂ��āA���Ɗ����ɔ����Đ������p�����i���݁j�̂��Ƃ����ƌn���݂Ƃ����܂����A���ƌn���݂͂���ɁA�Y�Ɣp�����Ǝ��ƌn��ʔp�����i�Y�Ɣp�����ɊY�����Ȃ����݂������B�j�̂Q�ɕ�����邱�Ƃ́A�悭�����m�̂��ƂƑ����܂��B�i���ʎ��Q�Ɓj�����I�ɂ���玖�ƌn���݂́A���Ǝ҂��ӔC�������ēK�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɓu�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v�ɒ�߂��Ă��܂��B���ȏ������ł��Ȃ��ꍇ�Ɍ����āA���̏������Y�Ɣp���������{�݁i�Ǝҁj�Ȃ�A���͈�ʔp���������{�݁i�����ł���͎̂��ƌn��ʔp�����̂݁j�ɏ������ϑ����邱�Ƃ��ł��܂��B
���������ۂ́A�ƒ낲�݂ƌ����������Ȃ��ꍇ������A�Y�Ɣp�����Ȃ̂Ɉ�ʔp�����Ƃ��Ď����݂������i�����Ə��A���Ǝҁj������A�����ȏꍇ�ɂ͂��݃X�e�[�V�����ɉƒ낲�݂ƈꏏ�ɔr�o�������������܂��B
�]���āA�����������ݖ����������邽�߂ƁA�����Ď��ƌn���݂̌��ʉ��E�r�o�}���𐄐i���邽�߂ɁA���ʁu�ߍ]�����s�p�����̌��ʉ��A�������y�ѓK�������Ɋւ�����v�Ɋ�Â��u�p�����Ǘ��ӔC�ҁv���e���Ə��A���Ǝҁi���Ɗ����̑召���킸�j�őI�C���������A���݂̌��ʁE�K���r�o�ɓw�߂Ă��������悤�ɂ��肢������̂ł��B���łɁA�ƒ낲�݂Ɋւ��Ă͒n�掩����Łu����₩�����i���v��I�o���A���݂̌��ʉ��E�������y�ѓK���r�o�ɓw�߂Ă��������Ă���Ƃ���ł�����A���K���ł͂P������50kg�ȏ�̎��Ə��ƂȂ��Ă��܂����A����ȉ��̎��Ə��ɂ����Ă��������`���ł͂���܂��A���Ɗ�����n��ōs�Ȃ���Ƃ̎Љ�I�ӔC�Ƃ��āu�p�����Ǘ��ӔC�ҁv�����I�C���������A���ƌn���݂̓K���r�o�y�ь��ʉ��E�������v��̍���ɓw�߂Ă��������悤�ɂ��肢������̂ł��B
��
�u�p�����Ǘ��ӔC�ґI�C�́v�͎s�������ۖ��͑�Q�N���[���Z���^�[�֒�o���������B
�Ȃ��A��o���ꂽ�l���́A���̋Ɩ��ɂ͗��p�������܂���B
�R�A�z�^�Љ�`���̂��߂̎{����ǂ����i���Ă�����
�V�{���݂̂��߂̑�P�̃n�[�h���Ƃ��āA�u�z�^�Љ�`�����i�n��v��v�̍�������Ċ��Ȃ�OK��Ƃ����葱��������܂��B����́A�P�Ɏ{�ݐ��������邽�߂̎�i�ł͂Ȃ��A���R���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɩ��ł���܂��B�����P�Q�N6���Ɂu�z�^�Љ�`�����i��{�@�v���������A�ʖ@�Ƃ��āA�]���́u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���i�p���������@�j�v�̉�����A�u�����L�����p���i�@�i�p�\�R�����T�C�N���j�v�u�e�����T�C�N���@�v�u�Ɠd���T�C�N���@�v�u���݃��T�C�N���@�v�u�H�i���T�C�N���@�v��C�u�O���[���w���@�v����ɂ́u�����琄�i�@�v�u�n�����g�������i�@�v��u�����ԁi��ցj���T�C�N���@�v�Ȃǂ��V���ɐ��肳��܂����B���̂��߃e���r��p�\�R�����͂��߁A���ݕ��ʂƏo�����͂���ɂ��ߍׂ����Ȃ�C�s���̕��́A���܂��܂Ȃ��݂̕��ʕ��@�Əo�����Ɍ˘f����ʂ������Ǝv���܂��B�����������֘A�@�͂܂����X�Ɨ\�肳��Ă���ƕ����Ă��܂��B���ꂪ�Q�O���I�㔼���琢�E�̕��j�Ƃ��đł��o���ꂽ�z�^�Љ�Ƃ����l�����ł��B���̎Љ�̑��ړI�͌������₷���̂ł����A�����āu���T�C�N�������鎖�v�ł͂Ȃ��A�z�^�Љ�ڎw���Ă���̂́u���ւ̕��S�����Ȃ����鎖�v�ł��B�z�^�Љ�̃e�[�}�́A��������炵�āA���炵����Ȃ����������T�C�N���ŕ₨���Ƃ������̂ł��B
�@�܂��A���̐ӔC���̂́u�Љ�̍\�����v�����ׂĂ̍����i�L�`�̓��{�ɏZ�ސl�j�ł���A��Ƃ����ł��Ȃ���A����҂����ł�����܂���B�O�q�̏z�^�Љ�ւ̓]�������邽�߂̖@���u�z�^�Љ�`�����i��{�@�i���́E�z�@�j�v�𐧒肷�鎖�ɂ���āA�u���E�n�������c�́A���ƎҁA�����v�������ӔC�ɂ��Ė@���Ŗ��L���Ă��܂��B�܂��A���̖@���̐���Ǝ����������āu���T�C�N���֘A�@�v�ƈ�ʂɌĂ�Ă���U�̖@�����V���ɐ���A�Q�̖@������������܂����B���̏z�@��93�N�Ɋ��Ȃ����肵���u����{�@�v�̒��̂��݂Ɋւ��镪����o���ăx�[�X�Ƃ��@�����������̂ł��B�p���������@���̌ʖ@�����Ǝ҂ȂNJW�҂̌����⌠���𐧌�����̂ɑ��āA���̊�{�@�͗��O��g�g�݂������A�W�҂̈�ʓI�ȐӖ����߂��@���ƂȂ��Ă��܂��B�Ƃ�����A��ʐ��Y�E��ʏ���̎Љ��z�^�̊����ׂ̏��Ȃ��Љ��ڎw���āA���ݏ������[�Ŏҕ��S���琶�Y�ҁE����ҕ��S�ɓ]�����Ă��������ɂ��Ă��܂��B���ݖ��ɂ́A�s���̊S�������Ȃ��Ă��Ă��܂����A���݂�ŋ��ŕ��S��������A���v�����Y�҂ƕ։v������҂��A���ꂼ��ӔC�S����u�z�^�Љ�v�̓����́A�܂��܂��n�܂�������ł��B
�@����ɁA���s�c�菑�Ɋ�Â��u�n�����g�������i�@�v���������ꉷ�g���K�X�i��_���Y�f�j�����炷���߂̓w�͂��`���Â����A�ċp�ɂ���ď��������Ă����u���݁v�̌��ʉ���uMOTTAINAI�v(���������Ȃ�)���_���A���܈�x�A�����E���Ǝ҂ɋ��߂��Ă��܂��B
���̏z�^�Љ���`�����邽�߂Ɏs�����͉�������悢���B��������߂邽�߂̌v�悪�u�n��v��v�Ȃ̂ł��B���������Ă���s�����肷��u�n��v��v�i�K�C�h���C���j�ɂ́A���낢��Ȏ{�ԗ�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�s�@�����p�g���[��������A�ЊQ�p��������ł��B�ؓ��̃`�b�v�������R�A��ɋ������Ă��܂��B�����́A���R�A���{��O��ɃN���A���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł���A�n��v�悪���邩����A�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�s�̎{��Ƃ��āA���܂łɂ����g��ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������̂���ł��B���ݎ{��Ɋւ��ẮA�ߍ]�����s�́A�����o�x��Ă��܂��B�i�����������ۂɂ��Ĕp���������Ă������͌����ł��g�b�v�𑖂��Ă����Ǝ������Ă����̂����A����ɂ��Ă���ԂɁA�����A�x��Ă��܂��Ă��邱�Ƃɂ́A���R�Ƃ����B�j��P�ɁA���N���[���Z���^�[�ɕ��C�����Ƃ��A�u����₩�����v�̂Ȃ��ŋʉ���̓͏o��������������ɂ��ւ�炸�A���ԂƂ��āA���̋Ɩ�������Ă��Ȃ������̂ŁA�폜����Ȃ��������Ȃ�\�����ꂽ�̂ɂ��ւ�炸�A���܂��ɉ������̓������Ȃ��̂������Ēm��ׂ��ł���B
���āA�����ŁA����A�L��p�ɍ쐬�����A���݂Ɋւ��邱�Ƃ��A���ꂼ��e�[�}���Ƃɂ܂Ƃ߂��̂ŁA�ǂ�łق����Ǝv���f�ڂ��邱�Ƃɂ��܂����B
�i�u�m���Ĕ[���I���݃V���[�Y�v�j�����P�W�N�x�L��p
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P
��Q�N���[���Z���^�[�͈�ʔp�����̏����{�݂ł��I
�@�@�@�Y�Ɣp�����ɕ��ނ����u���݁v�̔����E�����݂́A�֎~���܂��I
�@�p���������@��m�낤
�s���⎖�Ǝ҂̂Ȃ��ɂ́A�Y�Ɣp�����ƈ�ʔp�����̋敪���悭��������Ă��Ȃ����������܂��B�Y�Ɣp������������ŁA�u���������^��ł����̂₩��v�Ɩ����������������Ȃ�����܂���B�����ō���́A������ʔp�����ŁA�����Y�Ɣp�����Ȃ̂�������������Ǝv���܂��B
�p���������@�͉���Â炢�Ƃ��������悭�����܂��B�m���ɖ@����ǂ�ł������ɂ킩��Ȃ����Ƃ������̂��p���������@�Ȃ̂ł����A�W�҂ł�������Ă��邱�Ƃ������悤�ł��B�u���݁v�Ƃ����p�ꂩ�炵�Ă����ł���B���ꂪ�u��ʔp�����v���Ӗ����邱�Ƃ��A��ʂ̐l�͂ǂꂾ���m���Ă��邾�낤���B�u�p�����̒�`�v�́u��ʔp�����v�Ɓu�Y�Ɣp�����v�̋敪���炵�ē���B
�p���������@�ł́A�S�Ă̎��Ɗ����ɔ����Đ��������ƌn���݂̂����u�Y�Ɣp�����v�Ƃ��Ă����ނ́A�ΒY�����R�[�N�X�D�̇@�u�R���k�v�A�H��r�����̉��D��R���c�Ԃ̇A�u���D�v�A�p�n�܁E�p�H�p���E�p�R�����̇B�u�p���v�A�p���_���̑��_���p�t�̇C�u�p�_�v�A�ʐ^�����t��p�\�[�_�[�Ȃǂ̇D�u�p�A���J���v�A���������A�����@�ۂ����A�����S�����܂އE�u�p������v�A���ƂɌW����̂�����H�ƁA����o�ŋƂ���̇F�u�������v�A���ƂɌW����̂�p���v�E�Ƌ�����H�ƁE�؍މ��ƂȂǂ���o��G�u�����v�A���ƂɌW����̂�����H�Ƃ���̇H�u�@�ۂ����v�A�H�������Ƃ���o�邨����A�p�������A���y�����A�R�[�q�[�������̑����������̇I�u���A�����c�ԁv�A�V�R�S�������̇J�u�S�������v�i�����S���͔p�v���ɕ��ށj�A�؍킭���C���������C��ʁC�X�N���b�v�̇K�u���������v�A�K���X�����C�ω����K�����C�����킭���C�Z�����g���������Ȃǂ̇L�u�K���X�����E�R���N���[�g�����y�ѓ����킭���v�A�F�Ŏg���M�u�z�����v�A������K�Ȃǂ̇N�u�H�앨�̐V�z�C���z���͏����ɔ����Đ������R���N���[�g�̔j�Ђ��̑�����ɗނ���s�v���v�A�{�Y�_�ƂɌW��O�u�����̂ӂ�A�v�ƇP������̎��́v�A�b�{��H������̂�����̇Q�u�����n�Ō`�s�v���v�A�W�o�@�ŕߑ������R�u������i�_�X�g�ށj�v�A����Ə�L�̇@����R�̎Y�Ɣp�������������邽�߂ɏ����������̂��Y�Ɣp�����Ƃ����A����ȊO�͈�ʔp�����Ƃ���Ă���B����ł͑�Q�N���[���Z���^�[�ɔ����ł��鎖�ƌn��ʔp�����Ƃ͉����ƌ����܂��ƁA�S�Ă̎��Ɗ����Ő������u�p�����v����Y�Ɣp���������������̂����ƌn��ʔp�����ł���A��̓I�ɂ͎���������̎����p�n�`���A�i�{�[���A��������H���Ȃǂ���̎c�т�~�H�ށA����}�Ȃǂ́u�����i���Ƃ���ƂȂǂ̓���Ǝ�E���Ƃ��甭���������̂������j�v���炢�ł��B���������A�����ꂩ��o�������͎Y�Ɣp���������A�A���p�̔p�p���b�g�⎖��������o���ؐ��̊��E�{�I�͈�ʔp�����i�����Nj����E�v���X�`�b�N���̊��E�{�I�͎Y�Ɣp�����ɂȂ�܂��j�B�����Ђ�V���Ђ���o���������͎Y�Ɣp���������A��Ђ̎���������o���������͈�ʔp�����B�����X����o��������͎Y�Ɣp���������A���[����������o��������͈�ʔp�����ȂǂȂǂł��B
�@�悭�A�₢���킹������̂́A�_�Ɨp�̌l�V�[�g��_�Ɨp�̃r�j�[���ł��B���R�A�_�Ƃ����Ƃł�����A�����͎Y�Ɣp�����́u�p�v���X�`�b�N�v�ɊY�����܂��B���ƌn���݂͑S�Ď��Ǝ҂̎��ȏ����ӔC�ŏ��������Ȃ���Ȃ�܂���B���ɎY�Ɣp��������������ꍇ�ɂ͏����}�j���A���i�Ǘ��[�j���K�v�ł��B
�@���̂ق��A��Q�N���[���Z���^�[�ŏ����ł��Ȃ����̂Ƃ��āA�p�\�R���A�①�ɁA�G�A�R���Ȃǂ̖@���Ń��T�C�N�����`���Â����Ă���Ɠd���i��A�s���Ŏw�肵�Ă��鎩���ԁE���A���[�^�[�A�_�@��A���ɁA�s�A�m�E�G���N�g�[���A���Ί�A�댯���i�K�X�{���x�E�_��E�Ζ�ށj�Ȃǂ̓K���������������܂��B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�Q
���ƃS�~�̂Ȃ��ŎY�Ɣp�����͂���Ȃɂ���́H
Q�G�s���ɂ���^�H�i�����Ƃ̍H��ɋ߂�҂ł��B���H��ł͐H�i���T�C�N���@��p���������@�Ɋ�Â������H���łł�p�������Y�p�Ǝ҂Ɉ����Ƃ菈�������肢���Ă��܂����A�������̓`�[�ނ����łɏ������˗�������A�u����͎��ƌn��ʔp����������v�A�Ɖ]���܂����B����4������H����́u�p�����Ǘ��ӔC�ҁv�ɂȂ�������ŁA�Y�Ɣp�����ƈ�ʔp�����̋敪���܂��悭������܂���B��C�҂���́A�������̎����݂Ȃǂ͈ȑO�͎��Г��ɐݒu�����ȈՏ��^�ċp�F�ŔR�₵�Ă����̂ł����A�@���ł��݂̖�Ă���ȈՏċp�F�ł̏ċp�͋֎~�ɂȂ����ƕ����Ă��܂��B���Ă͏����̕��@�������������Ǝv���܂��̂Ŏ���������o�邲�݂Ŏ��Ɏ����P�`�P�R�ɂ��Đ������敪���������Ă��������B���͂����̂��݂͎��ƌn��ʔp�������Ǝv���̂ł����B
�@
A�G��̓I�Ɏs���ɂ���^�u�H���i�����Ƃ̍H����v�Ƃ������ƂŁA�ȉ��Ɏ����ꂽ1~13�̔p�����ɂ��Ă��ꂪ�Y�Ɣp�����Ȃ̂��A���ƌn��ʔp�����Ȃ̂��A�����������Ǝv���܂��B�悭�A����Ȏv�����݂Ő����H���ŏo��̂��Y�Ɣp�����ŁA����ȊO�̎���������̎����p�i���͎��ƌn��ʔp�����Ƃ�����������߂��������������܂����A����͊ԈႢ�ł��B
�P�A�i�{�[��
�Q�A���ꎖ�����̃p�\�R�����
�R�A�ٓ��̐H�c��
�S�A�p���b�g
�T�A�����d���p���d�r
�U�A�u����
�V�A�W���[�X�̋�ʁE�r��
�W�A�n�`���A
�X�A�t���b�s�[�f�B�X�N�A�b�c
�P�O�A�͂��ݓ��̋������[��A��K�Ȃǂ̃v�����[��A�R�s�[�@
�P�P�A���K���X
�P�Q�A�H����ɐA���Ă��陒��}�
�P�R�A�������Ŏg���Ă����e���r�Ɨ①��
���Ԃɐ������܂��B
>�P�A�i�{�[��
���ԈႢ�Ȃ���ʔp�����ł��i�������A�v���X�`�b�N���ł���ΎY�Ɣp�����j
�s�ł́A�_���{�[���A�V���E�G���̂ق��ʁE�т�E�y�b�g�{�g���Ȃ�ػ��قł��鎑�����݂Ƃ��Ď��W���Ă�����̂Ɍ���A���ƌn���݂��L���Ŏ��ꂵ�܂��B
>�Q�A���ꎖ�����̃p�\�R�����
������������v���X�`�b�N�ނŎY�Ɣp�����A�̊��͏��Ȃ��Ȃ�܂������S�Ėؐ��i�̊��Ȃ��ʔp�����ł��B�������p�\�R���́A�@���Ń��T�C�N�����`���Â����Ă��܂��B
>�R�A�ٓ��̐H�c��
���]�ƈ��̐H���i�c�їށj�́A������Ɠ�������ʔp�����Ƃ��Ă��܂��B�������H�c�����v���X�`�b�N�e��Ȃǂɓ����Ĉꏏ�ɏo����Ă���A����͎Y�Ɣp�����Ƃ��Ĉ����܂��B
>�S�A�p���b�g
���ގ��ɂ���ʁB�⎆�ł���Έ�ʔp�����A�v���X�`�b�N���ł���ΎY�Ɣp����
>�T�A�����d���p���d�r
���Y�Ɣp����
>�U�A�u����
���Y�Ɣp�����i�K���X�����j
>�V�A�W���[�X�̋�ʁE�r��
�������H���Ɏg�p������ԈႢ�Ȃ��Y�Ɣp�����ł��B
�@�܂��A�]�ƈ����������e��̋ʁE�r�͕��ނł͎Y�Ɣp�����Ƃ��������ŁA�s�ł͎Y�Ɣp�����̈����ł��B
>�W�A�n�`���A
����ʔp���������A�����Ƃ��ă��T�C�N�������Ă��������B�i�Ǝ퓙�̌��肪��������A�������Ȃǂ͎Y�Ɣp�����ɔ�Y���j
>�X�A�t���b�s�[�f�B�X�N�A�b�c
���Y�Ɣp�����i�p�v���X�`�b�N�ɊY�����܂��j
>�P�O�A�͂��ݓ��̋������[��A��K�Ȃǂ̃v�����[��A�R�s�[�@
�����ׂĎY�Ɣp�����i���������A�p�v���X�`�b�N�ɊY�����܂��j
>�P�P�A���K���X
���Y�Ɣp�����i�K���X�����ɊY�����܂��j
>�P�Q�A�H����̙���}�E��
���]�ƈ�����Ƃ�������}�E�����́A�H��̎��ƌn��ʔp�����ł��B�����Ǝғ��ɗ��ꍇ�́A�����Ǝғ��̎��ƌn��ʔp�����ƂȂ�܂��B
>�P�R�A�������Ŏg���Ă����e���r�Ɨ①��
���e���r�A�①�ɁA����@�Ȃǂ̉Ɠd���i����уp�\�R���͉ƒ�A���Ə����킸���T�C�N���@�Ώې��i�ł��B���ꂼ�ꃊ�T�C�N�������x�����ă��[�J�[���ɕԋp���������B�s�̏����{�݂ł��L���ŗa����܂��B�Ȃ��A���Č`�����ꂽ���̓��T�C�N���ł��܂���̂Łu���������v�A�u�p�v���X�`�b�N�v�̎Y�Ɣp�����Ƃ��ď������Ă��������B
�i�⑫�j
�H���i�����Ƃ̏ꍇ�A���Ɗ������甭�������p�����́u���A�A�@�ہv�ȊO�͑S�ĎY�p�ł��i�u���A�A�@�ہv�͈�p�j�B�������A�u���A�����c���v�ɂ��Ă͐����H�����甭���������͎Y�p�A����ȊO�͈�p�ł��B
�@�܂��A�����p��̂悤�ɖƃv������������A���ʂł��Ȃ��悤�ȕ��ɂ��Ă͑��̂Ƃ��ĎY�p�i�Y�Ɣp�����Ƃ݂܂��j�ł��B�Ȃ��A��p�̒�`�́u�Y�p�ȊO�̔p�����v�ł��B�p���������@�́A���݂̌`�����ŋ敪����Ă���̂ł͂Ȃ��A�����ꏊ�ɂ���ċ敪����Ă��܂��B�����ӂ��������B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�R
���Ə��⏤�X�̃S�~�̓X�e�[�V�����ɏo���܂���I
Q�G�w�O�́��������̎������̎҂ł����A������̖����̕��ɁA�����Ȃ莖�Ə��̕��͂��̂��݃X�e�[�V�����ɂ��݂��o���Ă͍���܂��B�Ƃ����܂����B���܂ŏo���Ă������A�ߏ��̎��Ə��E�������̕����o���Ă��܂��B���������[�߂Ă���̂ɁA�Ȃ��_���Ȃ̂ł��傤���H
A�G�s��1300�ӏ��ɂ��邲�݃X�e�[�V�����́A�ƒ납��o����邲�ݐ�p�̏W�Ϗ��ł��B������ɋ��^���i���ł͂Ȃ��Ǝv�����j�����߂Ă��悤���A���܂����A�����鎖�Ɗ����ɔ����Đ������p�����i���݁j�́A���Ƃ��݂Ƃ����u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v��R���1���ł́u���Ǝ҂́A���̎��Ɗ����ɔ����Đ������p����������̐ӔC�ɂ����ēK���ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ǝ��ȏ����ӔC�����m�ɒ�߂��Ă��܂��B���Ƃ��݂͂���ɁA��ʔp�����ƎY�Ɣp�����̂Q�ɕ�����܂����A������ɂ���A���Ƃ��݂́A�ƒ낲�݂ƈꏏ�ɔr�o���邱�Ƃ͋֎~����Ă��܂��B���܂ŃX�e�[�V�����ɏo���Ă������Ǝ��̂���@�����Ƃ����܂��B����͎�������[�߂Ă��邩��A���邢�͓��Y�X�e�[�V�����ݒu�҂̎�����F�߂Ă��邩��A�Ƃ����������i���فj�̂��̂���Ȃ��A�@���I�Ɉ�@�Ȃ̂ł��B�����A���Ƃ��݂̕s�@�����ɑ��Ă͑�ό��i�ɂȂ��Ă��܂����A������Y������������Ă��܂��̂ŁA�K�@�œK���ȏ����ɓw�߂Ă��������B���Ƃ��݂́A���ƌn��ʔp�����Ȃ�A��Q�N���[���Z���^�[�֒��ڔ������邩�A���͎s�������Ă�����W�^���Ǝ҂Ɉ˗����ėL���ŏ��������Ă��������B���̂��݂��Y�Ɣp�����ɋ敪�������̂Ȃ�u�Y�Ɣp���������Ǝҁv�ɏ������˗����������B�Y�Ɣp���������Ǝ҂́A�����ł���p�����ɂ��قȂ�܂��̂ŁA�i�Ёj���ꌧ�Y�Ɣp��������i077-521-2550�j�ɂ��⍇���������邩�A������http://shiga.sanpai.com/�̃z�[���y�[�W�����ď����ł���Ƃ����T���Ă��������B
�@�Ȃ��A���������̘b���ł����A�o������m�炸�Ɏ��Ƃ��݂��X�e�[�V�����ɏo���Ă���̂́A�M�i���Ȃ��́j���Ə������ł͂���܂���B������@�Ȕr�o�s�ׂ͔��莟��A�s���w�������Ă����܂��i�����ȏꍇ�͔p���������@�ɂ��Y���K�p������܂��j���A����ł��s���召��ƍ��킹��2800���Ə����邤���A���ݓ��s�̏����{�݂ɔ�������Ă��鎖�Ə��ł킩���Ă���̂�25���ł�������܂���B�c���75���́A�����炭����̃P�[�X�̂悤�ɃX�e�[�V�����ɏo����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������Ӗ��ł͖{�s�̂��ݍs���͎s���ɑ��Č��i�ł��Ȃ��A�{���Ή����x��Ă���Ǝ��o���Ă��܂��B���̂��ߕ����P�W�N�x����́A���W�Ɩ��͑S�ʈϑ�����ƂƂ��ɕs�@������X�e�[�V�����̃p�g���[���������������A��ƁE���Ə��E�������E���Ǝғ��̊F����ɑ��Ă��A���Ƃ��݂̏o�����ɂ��Ă̌[�����̋����O���}���g�݂����Ă����܂��̂ŁA���߂��ŁA�X�e�[�V�����Ɏ��Ǝ҂����݂��o���Ă���Ƃ��������������A���ӂ����������A�s�����܂Œʕ������B�܂��A���Ǝ҂̕����A����̓X�e�[�V�����ւ̈�@�ȃ^�_�o���͎~�߂Ă��������B���̂��Ƃ͂��Ȃ��̎��Ə������łȂ��A���ߏ��œ����悤�ɏo���Ă��鎖�Ə�����ɂ����`�����������悤�ɂ��肢���܂��B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�S
�Y�Ɣp�����̏����̎d���́H
Q;�������Ŏg�p�������������̂Ă����̂ł����A�Y�Ɣp�����ɂȂ�܂����H�܂��Y�Ɣp�����̏����Ǝ҂͂ǂ��ɖ₢���킹��悢�ł����B
A;���R�u�Y�Ɣp�����v�ƂȂ�܂��i�ؐ��̊��͈�ʔp�����j�B����������p�v���X�`�b�N�ނ̍������Ƃ��āA�����̋��i�ڂ����Y�Ɣp���������Ǝ҂Ɉϑ����܂��B��������ɂ͏����[�i�}�j�t�F�X�g�j���K�v�ł��B
�@�������A���ۂɊ�����Ȃ������ł��邩(�ߋ��ɏ����������т����邩��)�m���߂Ă���˗����܂��傤�B
�u�Y�Ɣp�����̎�ނƋ�̗�v��������x�݂Ă��������B���������ςł�������ɂ��Ă͂܂���̈ȊO�͈�p�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�E�E�E�ʎ�
�@�܂��A�Y�Ɣp�����̏����Ǝ҂͂ǂ�����ĒT������悢�̂��Ƃ̖₢���킹�ł����A
���@��Ɉȉ��̂悤�ȕ��@������܂��B�����ȊO�̕��@���l�����܂��B
�@�s���{�����̋��ƎҖ��납��T���B������ꌧ�̊e�n��U���ǂ̔p�����S���ہi���ہj�ŋ����Ă���܂��B���̋��ƎҖ���͎s���ۂɂ�����܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�A�C���^�[�l�b�g�Ō�������B�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@(��)�Y�Ɣp�����������ƐU�����c�@�������́A�s���̕��ł����
�@�@�@�@�@�@�@���ꌧ�Y�Ɣp��������̃z�[���y�[�W�ƘA����ł�
http://shiga.sanpai.com/
�Вc�@�l����Y�Ɣp�����������
��520-0051�@���ꌧ��Îs�~�ш꒚��3-30�i���g�r��2F�j
TEL.�@077-521-2550
FAX.�@077-521-6999
���[���@shiga@sanpai.com
���@�ŏI�I�ɂ́A�r�o���Ǝ҂ł���݂Ȃ����f���[���̏�A���W�^���Ǝҋy�я����Ǝ҂ƈϑ��_��葱�������邱�ƂɂȂ�܂��B�}�j�t�F�X�g���K�v�ł��B
���@�Y�Ɣp�����Ɋւ���@�ߓ����Q�Ƃ������ꍇ�ɂ́A���Ȃ̃z�[���y�[�W�̢���@�߁v�̃R�[�i�[�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���Ɗ����ɔ����Y�Ɣp�����ɂ͎��̂��̂�����܂��B�E�E�E�E�E�E�Y�Ɣp�����̎�ނƋ�̗�
|
��@�@�� |
��@�@�́@�@�� |
||
|
�P |
�R���k |
�ΒY����C�ċp�D�C�F���|�r�o���C�p�����Y�@�� |
|
|
�Q |
���@�D |
�r���������D�C���b�L���D�C���������C���n���D�C���R���c���C�����H������o��D�@�� |
|
|
�R |
�p�@�� |
�p�������C�p�؍���C�A���R�[�����̔p�n�܁C�p�^�[���s�b�`�C�Ō`�Ό��@�� |
|
|
�S |
�p�_ |
�p���_�C�p���_�C�p�蒅�t�@�p���o�b�e���[�t�@�� |
|
|
�T |
�p�A���J�� |
�p�\�[�_�t�C�p�A�����j�A�t�C�p�����t�C�����Ό��p�t�C�����ԕs���t�@�� |
|
|
�U |
�p�v���X�`�b�N�� |
�������������C�����@�ۂ����C���A�X�`���[�������C�p�^�C���@�� |
|
|
�V |
�S������ |
�S���`���[�u���̓V�R�S�������Ɍ���i�p�^�C���͔p�v���X�`�b�N�ށj |
|
|
�W |
�������� |
�ʁC�S�����C��S���������C���c�����@�؍킭���@�� |
|
|
�X |
�K���X�����C�R���N���[�g�������y�ѓ����킭�� |
�r�C�K���X�����C�����킭���i�y�ǁC�����K�C�����j�@�� |
|
|
10 |
�z���� |
���F�C���F�C�]�F�C�d�C�F���̎c���C�����p���C�s�Ǎz�C�{�^�C�L���[�|���̃m���@�� |
|
|
11 |
���ꂫ�� |
�H�앨�̐V�z�C���z���͏����ɔ����Đ�����R���N���[�g�̔j�ЁC�����K�̔j�ЁC���̑�����ɗނ���s�v���i�]���C���ݔp�ނƏ̂��Ă������́j |
|
|
12 |
������ |
��C�����h�~�@�ŋK�肷����������{�y�юY�Ɣp�����̏ċp�{�݂̏W����{�݂ŏW�߂�ꂽ���́i�d�C�W�����ߏW�_�X�g�C�W�����ߏW�_�X�g�j |
|
|
13 |
������ |
���C���̂����@�� |
���E�����H�i�����ƁC����o�ŋƓ� |
|
�V�z�C���z�C���z�C�������ɔ��������� |
���� |
||
|
14 |
���� |
�؍ޕЁC���������@�o�[�N�ށ@�� |
�؍ށC�ؐ��i�����ƁC�p���v�����Ɠ� |
|
�V�z�C���z�C���z�C�������ɔ������� |
���� |
||
|
15 |
�@�ۂ��� |
�ؖȁE�r�ѓ��̓V�R�@�ۂ��� |
�@�ۍH�Ɓi�D���������j |
|
�V�z�C���z�C���z�C�������ɔ����@�ۂ��� |
���� |
||
|
16 |
���A�����c�� |
�̂肩���C���������@�� |
�H���i�C���i�����Ɓ@�� |
|
17 |
�����n�Ō`�s�v�� |
���C�E�H�����̕s�H�������̕s�v�� |
�ƒ{��C�H�������� |
|
18 |
�����̂ӂ�A |
���C�n�C�C�ɂ�Ƃ蓙�̂ӂ�A |
�{�Y�_�ƁC�{�Y�ގ��� |
|
19 |
�����̎��� |
���C�n�C�C�ɂ�Ƃ蓙�̎��� |
�{�Y�_�ƁC�{�Y�ގ��� |
|
20 |
���ߑ�P�R���p���� |
��L�P�`19�Ɍf����Y�Ɣp�������������邽�߂ɏ����������̂ł����āC�����ɊY�����Ȃ����́i�R���N���[�g�Ō^�������j |
|
���j�P�R�`�P�X�܂ł̔p�����́C���肳�ꂽ�Ǝ�����r�o�����p�����̂݁u�Y�Ɣp�����v�ƂȂ�܂��B
���Y�Ɣp�����̏����́A�Y�Ɣp���������Ǝ҂ɂ��˗����������B�i���ꌧ�Y�Ɣp�������077-521-2550�j
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�T
���Ƃ��݂̌��ʉ��Ǝ������ɋ��͂��I��Q�N���[���Z���^�[�͈�ʔp�����̏����{�݂ł��B
Q; ��p�̃��T�C�N���@���������̂́A�Y�p�̏��������邵���Ȃ��̂ł����H
A; �s�̏����{�݂Ɏ����߂邲�݂́u��ʔp�����v�ł��B�Y�Ɣp�����͊�ƁE���Ǝ҂̐ӔC�ŏ��������Ă��������B
�܂������z�^�Љ���`�����i���邽�߂ɁA�p���������@�Ƃ͕ʂɁA�Ɠd�̃e���r�A����@�A�①�ɁE�Ⓚ�ɁA�G�A�R���̉Ɠd���T�C�N���@�⌚�ݎ��ނ̃��T�C�N�������݃��T�C�N���@�A�p�\�R���̃��T�C�N���������L�����p���i�@����H�X���̐H�i�c�ԁ��H�i���T�C�N���@�A�����ԓ������T�C�N�����邽�߂̖@�������ԃ��T�C�N���@�Ȃǂ̃��T�C�N���@���ߔN���X�ƒ�߂��Ă��܂��B�@�������A���T�C�N���̓��e����@�͊e�X�ňقȂ�܂��B�e���ł��m�F���������B
���@���T�C�N���@�̑ΏۂƂȂ�Ȃ��p�����́A�Y�Ɣp�����Ƃ��Ĕp���������@�ɏ]����������K�v������܂��B���̏ꍇ�ł��A�Y�Ɣp���������̌��ʂ����T�C�N���Ɍq���郋�[�g��T���Ă݂Ă��������B�܂��A�����݂Ȃǂ͈�ʔp�����Ƃ��ďċp������������A�Î��Ƃ��ă��T�C�N������A��ƁE���Ə��̃C���[�W�A�b�v�ɂȂ�����肩�A�����̗��v�������܂�܂��̂ŁA�ł��邾�����T�C�N���ɉĂ��������B
���@�L�����łȂ��ꍇ�ɂ́A���T�C�N���ł����Ă��p���������@�̓K�p���܂��̂ŁA����T�C�N������Ƃ����\���ł̈�@�s�ׂɂ����ӂ��������B
�Ȃ��p���������@�̋敪��T�C�N���@�����ł͂Ȃ��A�]�܂����Ƃ����ϓ_�ł����A�i�{�[���A�n�`���Ȃǎ����Ƃ��ė��p���\�Ȃ��͎̂����Ƃ��ďo�����ق����悢�Ǝv���܂��B
�܂���ʁE�r���͗e�����T�C�N���@�Ń��T�C�N�����₷���悤���ʔr�o���邱�Ƃ�����҂ɋ`���Â����Ă��܂��B���Ə��Ɋւ��Ă��A�������݃X�e�[�V�����ɂ͏o���܂��A�������݂Ƃ��ē��{�݂ɔ������Ă���������A�萔����Ə����鐧�x������܂��B
�Ɠd���T�C�N���@�Ώەi�����́A���Ə�����r�o���ꂽ�ꍇ�͑�Q�N���[���Z���^�[�ł��t���܂��B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�U
���ɂ₳�������Ə���ڎw����
Q;���݂�r�o���鎖�Ə����ƁA���X�ɂ́u�p�����Ǘ��ӔC�ҁv��u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɖ]���܂������A�{���ł����B�傫�Ȋ�Ƃł͂��������S����u���Ă���Ƃ����b�͕����܂������A�������̂悤�ȏ����ȗ���X�ł��u���Ȃ�������Ȃ��̂ł����H
A;�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���i�ȉ��u�p���������@�v�Ƃ����B�j�ɂ́A���Ǝ҂��o�����ƌn��ʔp�����̏����ɂ��āA���̂悤�ɒ�߂��Ă��܂��B
��
�s�������́A���̋����ɂ����Ď��Ɗ����ɔ������ʂ̈�ʔp�������鎖�Ǝ҂ɑ����Y�p�����̌��ʁA�^�����ׂ��ꏊ�A���̉^���̕��@���̑��K�v�Ȏ������w�����邱�Ƃ��ł���B�E�E�E�E�p���������@��6���̂Q�@��5��
��
���Ǝ҂́i�s�������̒�߂�j��ʔp���������v��ɏ]���āA���̈�ʔp�����̉^�����͏����𑼐l�Ɉϑ�����ꍇ�ɂ͖@��V���12���ŋK�肷����ȗ߂ɒ�߂�҂Ɉϑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E�E�E�E�p���������@��6���̂Q�@��6��
��L�̔p���������@�Ɋ�Â��{�s�̏��i�u�ߍ]�����s�p�����̌��ʉ��A�������y�ѓK�������Ɋւ�����v���ȉ��u�s���v�Ƃ����B�j�ł́A
��9���@(���ƌn�p�����̏���)�@�s�������ł��鎖�ƌn�p�����́A���ƌn�p�����̂����A�ƒ�p�����ƕ����ď������邱�Ƃ��ł���p�����ŁA�s���s����ʔp�����̏����Ɏx�Ⴊ�Ȃ��ƔF�߂�ꍇ�Ɍ��菈�����邱�Ƃ��ł���B
2�@�O���ɋK�肷�鎖�ƌn�p�����ɂ��ẮA�O���3���ɒ�߂��ɏ]���A���Ǝ҂�����^�����A����̏ꏊ�ɔ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
3�@���Ǝ҂�����^���ł��Ȃ��ꍇ�́A��16���1���ɋK�肷��p���������Ƃ̋������Ǝ҂ɂ�����������̂Ƃ���B
��13���@�i���Ǝ҂ɑ��錸�ʌv��̎w��)�@�s���́A��9���ɋK�肷�鎖�ƌn�p�������ʂɋK���Œ�߂�ʂ��鎖�Ǝ҂ɑ��A���ʌv��̍쐬���w�����A���ʉ��A�������ɂ��ĕK�v�Ȏw�������邱�Ƃ��ł���B
2�@�O���̋K��ɂ��w�����ꂽ���Ǝ҂́A���ʌv��̗��ċy�єp�����̋Ɩ���S�����邽�߂̔p�����Ǘ��ӔC�҂�I�C���A�s���ɓ͂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̂��Ƃ���A�s���ł�50kg/���ȏ�̂��ݔr�o���Ǝ҂𑽗ʔr�o���Ǝ҂ƋK�肵�āA����玖�Ə��ɂ́u�p�����Ǘ��ӔC�ҁv�̐ݒu���`���Â����A���ʉ��v��̍�����w�����Ă��܂��B�܂�50kg/���ȉ��̂��ݔr�o���Ǝ҂ɑ��Ă��z�^�Љ�`���̎�|�◝�O�����������������A�C�ӂɁi�����͂����̂ł͂Ȃ����j����I�Ɂu�p�����Ǘ��ӔC�ҁv�̑I�C�����肢���āA�e���Ə��E��Ƃ̂����ʉ��A�������v��̍����A�K�������ɓw�߂Ă��������悤�ɂ��肢���Ă���Ƃ���ł��B�p�����Ǘ��ӔC�҂͎��Ǝ�ł����Ă����܂��܂���B�{�s�̈�ʔp�����̎匴�������Ƃ��݂̑����ł��邱�Ƃ̓f�[�^�[�ɂ�薾�炩�ł��B�s���ɑ��Ắu����₩�����i���v�ɂ�育���ʉ������������߂Ă������A���܂ł͎��ƌn���݂ɑ��Ė��m�ȑ��ł��o���Ȃ��܂ܐ扄���ɂ��Ă������Ƃ̔��Ȃ���A����͎��ƌn���݂ւ̎�g������}���Ă����܂��̂ł����͂����肢���܂��B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�V
�s�w��̂��ݑ܂͂Ȃ��̂ł����H
Q;���́����Ɉ����z���Ă�������ł����A�ߍ]�����s�́A���݂̎w��܂͂Ȃ��̂ł����H
�@�O�ɏZ��ł��������̂ł͔R���邲�ݗp�A�R���Ȃ����ݗp�A�v���X�`�b�N�p�̎w��܂�e�傲�ݗp�͏��������̔�����A�����ɓ���Ȃ��Ǝ��W���Ă���܂��A�R���邲�ݗp�܂Ȃ�1�ƒ�W�O���܂ł�1��80�~��80�����z������1��200�~�ōw������V�X�e���ł����B�K�R�I�Ɋe�ƒ�ł̂����ʉ����}��܂����A���݂̕�������o�������[���������ƌ��i�ł����B�e�탊�T�C�N���@���{�s����n�����ی��z�^�Љ�̐��i��}��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ȃ̂ɁA�ߍ]�����s�̂��ݎ{��͒x��Ă���Ǝv���܂��B�s���͂����ƃV�r�A���^���ɍl���Ă���̂ł��B�L���̎w��܂ł����܂�Ȃ��̂Ŕ̔����l���Ă��������B
A;��ό��������ӌ������肠�肪�Ƃ��������܂��B���āA�ƒ낲�ݔr�o���̎w��܂̌��ł����A���s�A�{�s�ł́A�R���݁A�s�R���݂Ƃ��ɓ����������͒����̌�����܂ŏo���Ă��������悤�ɂ��肢���Ă��邾���ŁA�������̂̂悤�ɓ��ʂɎw�肵���܂͂���܂���B
���������܂�엿�܁A�_���{�[�����ł̔r�o�ɂ��Ă͋֎~�̎w�������Ă���܂��B���ɂ��肢���Ă��邱�Ƃ͔N�ɂQ�`�R��s�R���ݎ��W�p�b�J�[�Ԃ��Ђ��N�������Ƃ���ȈՃK�X�ʁE�X�v���[�ʂ͕K�������J���ĕs�R���݂ł͂Ȃ��āA�������݂ŏo���悤�Ɍ[�����Ă��܂��B�܂��g���̂ă��C�^�[�͉ăK�X�̉t�̂��o���Ă���s�R���݂ŏo���悤�ɁA�R�����Ȃǂ͓d�r���Ă���o���悤�ɂ��肢���Ă��܂��B�Ȃ�ŕs�R���݂Ȃ̂ɉЂ��N�����̂��Ƌ^�����������������ł��傤���A�s�R���݂������̂Ƀ_���{�[���Ȃǂ̉R���̗e����g���Ă�����������邩��A�����̉R���ɉ����̔��q�ň�����̂��ƍl�����܂��B����18�N�x����̓_���{�[���͎������݂Ƃ��ĕ��ʎ��W���n�߂܂����̂ŁA�R���݂�s�R���݂Ń_���{�[�����o���Ă����ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̏�i�ð��݁j�ɒu���Ēu���������݂ŏo���Ȃ�������悤�ɂ��肢���Ă��܂��B
�@�Ȃ��ƒ낲�݂̎w��܂ɂ��ẮA���݁A���Ȃ���ƒ낲�݂̗L�����K�C�h���C�����w������܂����̂ŁA�L���w��܂̓����ɂ��Č������Ă���Ƃ���ł��B�s�����������R�c��Ŏs�Ƃ��Ă̋�̓I�ȈĂ��܂Ƃ܂�܂�����A������Ȃ�p�u���b�N�R�����g�����{���Ă��ӌ������f������\��ł��̂ŁA�����炭���҂����������B
�@�܂��A�ƒ낲�݂̗ʂƕς��Ȃ����K�͂ȏ��X�ɂ��Ă��A�X�e�[�V�������W���ł���悤�ȕ֗��Ȏ��Ƃ��ݐ�p�̎w��܂̓������l���Ă��܂����A���킹�ăX�e�[�V�����܂ŏo���ɍs���Ȃ����N���ƒ�ɑ��Ă̌˕ʎ��W�i���́G�ӂꂠ�����W�j�����������Ă��܂��̂ŁA�����������҂����������B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�W
�傫�Ȃ��̂͐��Ă��������B�V���o�[�ɗ��߂ΈϔC����܂�
Q;��̙�����V���o�[�l�ރZ���^�[�Ɉ˗����A����}���Q�N���[���Z���^�[�ɔ������悤�Ƃ�����A30����`50�a�̒����ɐ��Ă���ƌ����܂����B�Ȃ��ċp������̂Ȃ̂ɐ�Ȃ�������Ȃ��̂ł����B�܂��A�V���o�[�̕��ɑ�Q�N���[���Z���^�[�܂ʼn^��ł��炤�悤�ɗ���A�ϔC�����������܂����B����͂ǂ����ĂȂ̂ł����B
A;����͏����{�݂̍\���ƊW������܂��B��Q�N���[���Z���^�[�͂��݂��ċp����{�݂ł����A�P���ɓ����Ă������݂�R�₵�Ă���킯�ł͂���܂���B�܂��A�R�₷���߂̑O�����ł��ݎ����ψ�ɂ��邽�߁A�ׂ����j�ӂ��A�����Ċh�a���Ă���ċp�F�ɓ������܂��B���̉ߒ��œS��A���~�͑I�ʂ��܂��B�v�͑O�����ł��݂�j�ӂ��邽�߂̔j�Ӌ@�ɓ����ہA�j�ӌ������������ߑ傫�Ȃ��݂͂�����Ȃ��̂ł��B�j�Ӌ@�̐S�����͂��傤�ǐ�@��傫�������悤�ȓS�̉H������Ă���@�B�ŁA�ƒ�̃W���[�T�~�L�T�[�@���C���[�W���Ă��������B����ۂ��ƃ~�L�T�[�ɂ����Ă��A�����čׂ����Ȃ�܂���ˁB��͂�T�`�U�����ɂ��Ăق��荞�ނƍׂ����j�ӂ���܂��B�����͂���Ɠ����ł��B�傫�Ȋۑ����Ƃ����Ĕj�ӂł��Ȃ��̂ŁA����30����`50������炢�A���a30����ȏゾ�Ƃ�����`1/3�ȏ�Ɋ����Ă����Ȃ��ƁA�������ł��Ȃ��̂ł��B����Ŕ�������Ƃ��ɂ͐��Ď����Ă��Ă�����Ă��܂��B�������[�v��R�ނ������悤�ɁA���̂܂܂ł͔j�Ӌ@�Ɋ����t���܂��̂Ő��Ă��������Ă��܂��B
�@�܂��A�V���o�[�l�ރZ���^�[�Ɉ˗����Ē�̙�������Ă�������Ƃ������Ƃł����A�V���o�[����h������ė����l�́A�ƂƂ��Ďd�������Ă���킯�ł͂���܂���B�����܂ł��˗������l�̘J���̑�s���l�i�e�ʂ̂�������͉Ƒ��̐l�j�����Ă���Ƃ������߂����Ă��܂��B�ł����癒��}�̂��݂͈˗���̂��̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ʏ�A��̙�����Ǝ҂Ɉ˗�����A����͋ƂƂ��Ďd�������Ă���킯�ŁA����ŏo�����݂͑����Ǝ҂̐ӔC�ŏ��������Ȃ���Ȃ�܂���B����}���^�Ԃ̂ɈϔC��������̂́A�����܂ł��˗��傪���݂��^�����āi�ƒ낲�݂Ƃ��āj��������Ƃ����̍ق𐮂��邽�߂̂��̂ł��B��������Ƃ��˗���̏ꍇ�̙���}�͎��ƌn��ʔp�����ɂȂ�܂��B
�@�Ȃ��A�V���o�[�i�l�j�Ƃ����ǂ��A�u���݁v���^�����邾���̍s�ׂ́u�Ɓv�Ƃ݂Ȃ���A��@�s�ׂƂȂ�܂��B�u���݁v���^������ɂ́u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v�i�ȉ��u�p���������@�v�Ƃ����j�ɂ��A��ʔp�������͎Y�Ɣp�����̎��W�^���Ƃ̋����K�v�ł����A���̉^���ԗ��ɂ͕\�����K�v�ł��B�y�؍H���̎ԗ��Ɂu�Y�Ɣp�������W�^���ԁv�Ƃ����\�������đ����Ă��邱�Ƃ��悭��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����������ԗ��ɂ͕K���w��ʒu�ɕ\�����邱�ƂƉ����^��ł���̂��Ƃ������e���������Ə����[�i��̪�āj�̌g�т��`���Â����Ă��܂��B
�@�ł�����V���o�[�̕�������}���^�ԂƂ��ɂ́A�Ƃƍ�������Ȃ��悤�ɁA���Ȃ��̈ϔC������炢�A���Ȃ��ɂȂ�����ĉ^��ł���̂ł��B�����܂ł��r�o�y�я����ӔC�͂��Ȃ��ɂ���܂��B���ꂪ�����Ǝ҂ȂǂɈ˗������ꍇ�ɐӔC�́A�����Ǝ҂̎��Ƃ��݂ƂȂ菈���ӔC�͑����Ǝ҂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�X
���^�ċp�F�ł͂��݂͔R�₹�Ȃ��Ȃ�܂����B��Ă�������Δ������܂��B
Q;��Ă��͋֎~���ꂽ�ƕ����܂������A�Ƃōw���������^�ċp�F�ŔR�₵�Ă��_���Ȃ̂ł����B�����̏��w�Z�ɐݒu���Ă��������̑傫�ȏċp�F���P�����ꂽ�ƕ����܂������B
A; �u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v���_�C�I�L�V���ޔr�o�}���Ɣp�����̓K�������̊ϓ_����A�p������������������������A�p�����̖�Ă��ƊȈՂȔp�������^�ċp�F�̎g�p���K���i�@��16���̂Q�j����܂����B���̂��ߔp�����̖�O�ċp�A�������Ă��͈ꕔ�̗�O�������֎~�ƂȂ�܂����B���̖@���̏ł́A�u���l���A���Ɍf������@�ɂ��ꍇ�i��O�͉��L�̂Ƃ���j�������A�p�������ċp���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ���A��Ă�������Ɩ@���Ŕ������邱�ƂɂȂ�܂��B��Ă��Ƃ͓K�ȏċp�ݔ���p�����ɔp�������ċp���邱�Ƃł��B
�����P�R�N�S���P������͌����Ƃ��đS�Ă̔p�����ɂ��Ė�Ă����֎~����Ă��܂��B�܂��A�����P�S�N�P�Q������͑S�Ă̏ċp�ݔ��̍\���ɑ���K�����������Ȃ�A���̍\��������Ă��Ȃ��ċp�F�ɂ��Ă͎g�p���֎~����܂����B�ƒ�p�̏ċp�F�̂قƂ�ǂ́A���̍\��������Ă��Ȃ��̂Ŏg�p�ł��Ȃ��Ȃ�܂����B
�i�Q�l�j
�p�������ċp����ꍇ�A���̂P�`�R�̂����ꂩ�ɊY�����Ȃ��ꍇ�́u�p�����̖�Ă��v�ɊY�����A�����̑ΏۂƂȂ�܂��B������Ă����s�����ҁi�l�j�ɂ�5�N�ȉ��̒����A1000���~�ȉ��̔����̂����ꂩ���͗������Ȃ����܂��B
1. �p���������@�́u�\����v�ɓK�������ċp�F�Ŕp�������ċp����B
�@������ɏ]���čs���Ȃ��p�����̏ċp�A�h�����ʏċp�A�u���b�N�ςݏċp�A�����@���Ă̏ċp�́A��Ă��Ɠ����ł��B
2. ���̖@�ߖ��͂���Ɋ�Â������ɂ��s���p�����̏ċp
�@�E�X�ѕa�Q�����h���@�Ɋ�Â��a�Q���̕t�������̎}�̏ċp
�E�ƒ{�`���a�\�h�@�Ɋ�Â��`���a�ɜ늳�����ƒ{�̎��̂̏ċp�Ȃ�
3�A���v��������͎Љ�̏K�����ނȂ����̖��͎��Ӓn��̐������ɗ^����e�����y���ł�����̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂����
�@�����͒n�������c�̂����̎{�݂̊Ǘ����s�����߂ɕK�v�Ȕp�����̏ċp�i��F�����̂悵�Ă��A�ޗǂ̎R�Ă��A�͐�~�⓹�H�̑��Ă����j
�A�k�ЁE�����Q�E�ЁE�����Q���̑��̍ЊQ�̗\�h�E���}�����͕����̂��߂ɕK�v�Ȕp�����̏ċp�@�i��F�ЊQ���̉��}��E�З\�h�P���j
�B�����K���㖔�͏@����̍s�����s�����߂ɕK�v�Ȕp�����̏ċp�i��F�ǂ�ǏĂ������`���܂�A�����܂�A�啶���̑���Γ��j
�C�_�ƁE�ыƖ��͋��Ƃ��c�ނ��߂ɂ�ނȂ����̂Ƃ��čs����ċp�i��F�Ă����E�ȑ��≺�}�̏ċp�E���Ԃɂ����������݂̏ċp���j
�D�������̑����퐶���̏ċp�ł����Čy���Ȃ��́@�i��F�����t�����E�����E�L�����v�t�@�C���[���B���C�����q�E�Y�Ă��q�E�d�X�g�[�u�͂��ݏċp�F�ɂ�����Ȃ��̂Ŏg�p�ł��܂����A���݂�R�₷���Ƃ͋֎~�ł��B�j
�������A��O�I�ɔF�߂��Ă��邱���̏ꍇ�ł���Ă��͕K�v�ŏ����ɂƂǂ߂Ă��������B��O�͈͓̔��Ƃ����A���݂͊e�ƒ듙�ŔR�₵�ď������Ȃ����Ƃł��B�R�₷�ꍇ�́A�h�Ђ̖ʂ���������ԔR�₳���A���h���ւ̓͏o�ƘA�������肢���܂��B
�Ȃ��A���w�Z���̏ċp�F��P�������̂��A��L�̂悤�ɏ���������Ȃ��\���ł��������߂ł��B���̂����s�̌����{�݂ɂ͂��݉���̂��߂Ɏ��W�^���Ԃ�z�Ԃ��ēK�������ɓw�߂Ă��܂��B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P�O
�Ɠd���T�C�N���i�̏����̎d����
Q;�e���r�����@�A�①�ɁE�Ⓚ�ɁA�G�A�R���̂�����Ɠd���i���Q�N���[���Z���^�[�ɔ������Ă����܂ł̂悤�ɏ������Ă���Ȃ��̂ł����B�܂���������������ɂ́A�X�ǂŃ��T�C�N�������w�����Ȃ�������Ȃ��ƕ����܂������A�ǂ̂悤�ȏ���������悢�̂ł��傤���H
A; ����13�N�S���P������Ɠd���T�C�N���@�i����ƒ�p�@��ď��i���@�j���{�s����A
�Ɠd5�i�ڂɑ��ẮA�s�i�N���[���Z���^�[�j�ł͏���ɏ����ł��Ȃ��Ȃ�܂����B�����T�i�ڂ̏����Ɋւ��ẮA���T�C�N�����邱�Ƃ��`���Â����A���̌o��̓��[�J�[�ƃ��[�U�[�����S���邱�ƂɂȂ����̂ł��B���[�U�[�̕��S�������T�C�N�����̍w���ł��B
�@�����A�w�����ꂽ�d�C�X�┃���ւ��������ۂ̓d�C�X�ɂ́A�i���������`��������܂��B���̓d�C�X�����T�C�N���̎葱�������Ĉ����܂��̂ŁA���[�U�[�̕��̓��T�C�N�������Ɖ^�����������̓d�C�X�Ɏx�����Ă��������B�����A�����ւ��łȂ��A�P�ɔp������ꍇ�ŁA�w�����ꂽ�d�C�X���X���܂����ŋ߂��ɂȂ��Ƃ��́A���߂��̗X�ǂ������͓d�C�X�Ń��T�C�N�����i���[�J�[�����������Ă����čs���Ă��������j���w�����A���̃��T�C�N������i���ɓ\��t���Ă���A���ڑ�Q�N���[���Z���^�[�֔�������邩�A�������͎s�̑e�傲�ݎ��W�������p���������B
�@�Q�l�@�@�@�@�@ػ��������ڈ��iҰ���ɂ���ĈقȂ�j�@�@���������@�@�@�@�e�傲�ݎ��W����
�@�e���r�@�@�@�@�@�@2835�~�@�@�@�@�@�@+�@�@�@�@�@�@�@�Q�P�O�O�~�@�@�@�R�P�T�O�~
�@�G�A�R���@�@�@�@�@�R�U�V�T�~�@�@�@�@�@+�@�@�@�@�@�@�@�R�S�U�O�~�@�@�@�S�T�P�O�~
����@�@�@�@�@�@�@�Q�T�Q�O�~�@�@�@�@�@+�@�@�@�@�@�@�@�P�U�W�O�~�@�@�@�Q�V�R�O�~
�@�①�ɁE�Ⓚ�Ɂ@�@�S�W�R�O�~�@�@�@�@�@+�@�@�@�@�@�@�@�S�O�X�O�~�@�@�@�T�P�S�O�~
�@�����A��Q�N�����Z���^�[�֔�������䐔�������ꍇ�́A�����������Ȃ�̂ŁA���ځA
�r�o�҂����L�̃��[�J�[�w������ꏊ�ւ����čs�����T�C�N�����������ł��݂܂��B
A�i�����d��A�_�C�L���A���ŁA�r�N�^�[�A�j
�E���Îs���@�@������Ё@�P�C���W���Éc�Ə��@�@077-568-3003
�E����S���꒬���쌴�����{�@�����^�A������ЕF���c�Ə� 0749-21-3540
B�i�����A�O�m�A�V���[�v�A�\�j�[�A�x�m�ʁA�O�H�d�@�j
�E����S���꒬���쌴�����{�@���{�ʉ^�i���j�F���x�X�c�Ɖہ@0749-26-0202
�E��Îs����2-1-73 �@���{�ʉ^�i���j��Îx�X�V���c�Ɖ� 077-522-6632
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P�P
���z���ő��ʂ̂��݂������������̂����A�Ԃ��Ȃ��B���̂Ƃ��ɂ́E�E
Q;�]�ň��z��������̂ɕ������䓙�̑�^���݂�}����r�f�I�̑��ʂ̂��݂��o�܂����B���z���Ǝ҂���ɏ������˗�������A�p�������^������͈̂�@�s�ׂɂȂ邩��A�s���̈�ʔp�������W�^���Ƃ̋����������Ǝ҂���ɗ���ł���Ɖ]���܂����B�s���̋��Ǝ҂���������Ă��������B�܂��A���ł����Ă����֗�������ɗ���ł͂����Ȃ��̂ł����B
A;���̃V���[�Y�̂U�ł������܂������A�u���݁v�����W�E�^���A�������邱�Ƃ��ƂƂ��Ă����Ȃ��ꍇ�ɂ́u�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v�i�p���������@�j�ɂ��A��ʔp�����͎s�������̋��A�Y�Ɣp�����͒m���̋����K�v�ł��B���RA�s���̋���B�s�̂��݁i��ʔp�����j�͎��W�ł��܂���BB�s�̂��݂��W�߂�ɂ�B�s���̋����K�v�ł����AB�s�Ŕ����������݂�A�s�ɉ^���A�s�̏����{�݂ŏ������邱�Ƃ���@�ł��B��@�s�ׂ������Ǝ҂͂������ɉc�Ƃ̋�����������܂��B���̋��́u�֎~�̉����v�Ƃ����Ӗ��ł̋��ł�����A�����A���݂��^���ł���͔̂��������ҁ��r�o�҂Ƃ��̋����Ǝ҂݂̂ł���A�N�ł��������Ƃ��āu���݁v���^���ł���킯�ł͂���܂���B
�@���z���Ǝ҂��邢�͕֗�������ł���ʔp�����̎��W�^���̋��������Ă�����������܂����A�ǂ��͈̔͂̋��Ȃ̂��m���߂邱�Ƃ��K�v�ł��B��ʔp�����͋��G���A�̎s����z���Ď��W�^���A�������邱�Ƃ͋֎~����Ă��܂��B���Y�s���ł̈�ʔp�������W�^���Ƃ̉c�Ƌ������������Ɉ˗����������B���̖����Ǝ҂Ɉ˗������ꍇ�͈�@�s�ׂƂȂ�A�r�o�҂ł��邠�Ȃ����������܂��̂ł����ӂ��������B
���s���ʼnc�Ƃł����ʔp�����̎��W�^���Ǝ҂͎��̂W�Ёi����18,19�N�x�j�ł��B
�@���Ǝҁi�����j�@�@�@�@�@�Z���@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�b
�@���c�@���Y�@�@�@�@�@�@�@�鎔���k�R���ځ@�@�@�@�@36-7583
�@�X�R�@�M�L�@�@�@�@�@�@�@�x�㒬�@�@�@�@�@�@�@�@�@090-7099-9969
�i�L�j�������Y�@�@�@�@�@�@��{���@�@�@�@�@�@�@�@�@37-7382
�i���j�G���E�P�C�E�P�C�@�@��{���@�@�@�@�@�@�@�@�@37-2105
�i���j���g�@�@�@�@�@�@�@�@�k�V�����@�@�@�@�@�@�@�@32-5111
�i�L�j�L���L�J���Z�[�@�@�@�~�R���@�@�@�@�@�@�@�@�@32-8349
�@�V�c�@���@�@�@�@�@�@�@�@��c���@�@�@�@�@�@�@�@�@37-0056
�@�R���@���@�@�@�@�@�@�@�@�n�����@�@�@�@�@�@�@�@�@37-4654
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P�Q
�e�傲�݂������������̂����E�E�E�����炩����܂����H
Q;�e�傲�݂̏����̎d���Ƃ���ɂ�����l�i�ɂ��ċ����Ă��������B�e�傲�݂̓X�e�[�V�����ɂ͏o���Ȃ��Ƃ����܂����B
A;�{�s�ł͈�ӂ�30����ȏ�̂��̂ŁA�ڈ��Ƃ��đ傫�����P�l�ʁi18�g�ʁj�ȏ�̂��̂��u�e�傲�݁v�Ƃ��Ă��܂��B
�u�e�傲�݁v�̓X�e�[�V�����ɂ͏o���܂���B�����o����Ă����W���܂���̂ŁA���̗��p�҂̖��f�ɂȂ�܂��̂ł����ӂ��������B�e�傲�݂̏����̎d���ɂ͂R�ʂ�̕��@������܂��B�������A�����Ō����u�e�傲�݁v�Ƃ͉ƒ납��r�o����邲�݂̂��Ƃł��B���Ə�����r�o�����e�傲�݂́A��ʔp����������܂����A�قƂ�ǂ��Y�Ɣp�����ł��̂ŁA�s�̏����{�݁i��ʔp���������{�݁j�ł͏������܂���B���Ԃ̎Y�p�����Ǝ҂Ɉ˗����������B�i��O�I�ɉƓd���T�C�N���@�Ώەi��������ꂵ�Ă��܂��B�j
�@�e�傲�݂̏����̕��@�ł����A�܂��A�l�i�̈���������������܂��B
�@ �����ŁA���ځA�e�傲�݂��Q�N���[���Z���^�[�։^�э��ޏꍇ�E�E�E�]�ʐ��ł�����A�P�O��������Q�O�O�~�ł��B��t�̌v�ʂł��݂��ڂ����܂܂̏�ԁi�����Ԃ��Ɓj�ŏd���𑪂�A���ɂ��݂��w��̏ꏊ�ɍ~�낵����A��ԏ�ԂŌv�ʂ��A���̍��̏d�ʕ��̎萔�����x�����܂��B�s���̂��݂��Ƃ����ؖ��̂��ߖƋ��ؒ���t�ł��肢���܂��B
�A �e�傲�݂̌˕ʎ��W��\�����ޏꍇ�E�E�E�E�n�K�L�A�t�@�N�V�~���A���[���ŁA��Q�N���[���Z���^�[�˕ʎ��W��\�����ށB���T�y�j�������W�\����Ƃ��Ă���̂Ő��j���̌ߑO���܂łɎt�������̂͂��̏T�̓y�j���ɁA�ȍ~�̎�t�͗��T�̓y�j���Ɏ��W�Ɏf���܂��B�������A�����炩��Ԏ��A��������܂��̂ł��̎��Ɏ��W�y�j���̑I�����ł��܂��B�������A���W���Ɏ萔���̎x���������肢���܂��̂ŁA�Ɛl�̍ݑ�����肢���܂��B���W�^�������萔���͕ʕ\�̂Ƃ���ł��B���W���ɗ���ɂȂ�ꍇ�́A���O�Ɂu�e�傲�ݏ������v���w�����A�e�傲�݂ɓ\�t���āA�Ƃ̌��֊O�������͔���₷���ꏊ�ɏo���Ă����Ă��������B�\�����܂ꂽ�i�ڂƎ萔���i�e�傲�ݏ������j�����v���Ă���Ύ��W���Ă����܂��B
�B ���z���Ȃǂő��ʂɂ���A�^������Ԃ��Ȃ��A�e�傲�݂̌˕ʎ��W���˗����đ҂��Ă����Ȃ��i�����Ԃ��Ȃ��j�ꍇ�E�E�E�E�s���̈�ʔp�������W�^���Ƃ̋����������Ǝ҂Ɉ˗����������B���̏ꍇ�A����������̂Ɏ�t�łP�O��������R�O�O�~�����������܂��B�v���X���W�^�������́A�e�Ǝ҂ɂ���ĈقȂ�܂��̂ŁA�e���Ǝ҂ɂ��⍇�����������B�i�s���ɂ͂W�Ђ���܂��j
�ȏ�̂R�ʂ�̕��@������܂��̂ŁA�����łǂ̕��@����邩�͑I�����Ă��������B�Ȃ��A�ǂ̕��@���A�Ɠd���T�C�N���@�Ɋ�Â��u���T�C�N�����v�̗����͊܂܂�Ă��܂���̂ŁA�\���݂̑O�ɕK���X�Ǔ��Łu���T�C�N�����v���w�����Ă����Ă��������B�܂��A�����L�����p���i�@�Ɋ�Â��p�\�R����A�s�A�m�A�_�@��A�ω��ɂȂǂ́u�K����������v�i�ʎ��j�͎��W�����������Ă��܂���̂ŁA�����̕��@�͔̔��X���̓��[�J�[�ɂ����k���������B
|
�ʕ\�P�i�e�傲�ݎ��W�^�������萔�����\�j |
|
|
|
�i�@�@�@�@�@�� |
���l |
�P���i�~�j |
|
�� |
||
|
�A�R�[�f�B�I���J�[�e�� |
���ԁi90�p�j�ɂ� |
500 |
|
�҂@ |
�@ |
500 |
|
�Ԍ� |
�ꖇ |
500 |
|
�A���e�i�i���ޗp���ť�����ױ��Łj |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�ߑ��P�[�X |
�@ |
500 |
|
�����i�ؐ�����������j |
�@ |
500 |
|
��֎� |
��p |
500 |
|
��֎� |
�^���p |
1000 |
|
�P�l�ʁi�P�WL�ʁj |
�� |
500 |
|
�ߗފ����@ |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
����� |
�@ |
1500 |
|
��~�i�����܂ށj |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�G�A�R�� |
�Ɠd���T�C�N�����w���̂��� |
4510 |
|
�t���e���r32�^�ȉ� |
�Ɠd���T�C�N���ΏۊO |
500 |
|
�t���e���r45�^�ȉ� |
�Ɠd���T�C�N���ΏۊO |
1000 |
|
�t���e���r45�^������� |
�Ɠd���T�C�N���ΏۊO |
1500 |
|
���� |
�@ |
1000 |
|
�� |
||
|
�I�C���q�[�^�[ |
�@ |
500 |
|
�I�[�u�������W�i���^�j |
�@ |
500 |
|
������� |
�@ |
1000 |
|
������_���X |
�@ |
1000 |
|
���܂� |
�@ |
500 |
|
�����q�[�^�[ |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�J�[�y�b�g |
�@ |
500 |
|
�J�[�e�����[�� |
�@ |
500 |
|
���i�p���j |
�@ |
500 |
|
�K�X�u�ԓ�����i���^�̂��Ɍ���j |
�@ |
500 |
|
�K�X�e�[�u���R���� |
�@ |
500 |
|
�J�Z�b�g�f�b�L |
�@ |
500 |
|
�J���[�{�b�N�X |
�@ |
500 |
|
������ |
�@ |
500 |
|
�����@(�ߗށj |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�L�[�{�[�h�i���y�p�j |
�@ |
500 |
|
�M�^�[�i�G���L�M�^�[���܂ށj |
�@ |
500 |
|
�M�^�[�p�A���v |
�@ |
500 |
|
�r�� |
�@ |
500 |
|
�M���b�`�x�b�h |
�@ |
1500 |
|
����i�h���b�T�[�j1�� |
�@ |
1000 |
|
����i�h���b�T�[�j3�� |
�@ |
1500 |
|
�� |
||
|
��C����� |
�@ |
500 |
|
�N�[���[�{�b�N�X |
�@ |
500 |
|
�Ԉ֎q |
�@ |
500 |
|
�Ԉ֎q |
�d���� |
1500 |
|
�� |
||
|
���ʔ� |
�@ |
1500 |
|
���N���i���i�Ԃ牺�����j |
�@ |
1500 |
|
���N���i���i�}�b�T�[�W�`�F�A�[�j |
�@ |
1500 |
|
���N���i���i���[�������i�[�j |
�@ |
1500 |
|
�� |
||
|
�����i�V���܂ށj |
�@ |
500 |
|
�Ăтi�䏊�p�̏��^�̂��́j |
�@ |
500 |
|
�R�s�[�@�i�ƒ�p�j |
�@ |
500 |
|
�S���t�o�b�O |
�@ |
500 |
|
�R���| |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
���֎q |
�@ |
500 |
|
�T�C�h�{�[�h |
�@ |
1500 |
|
���� |
�@ |
1000 |
|
�O�֎ԁi�q���p�j |
�@ |
500 |
|
�O�֎ԁi��l�p�j |
�@ |
1500 |
|
�� |
||
|
���]�� |
�@ |
1000 |
|
���]�� |
�d���� |
1000 |
|
�Ŋ��@�i��p�^�������j |
�蓮�� |
1000 |
|
�Ŋ��@�i��p�^�������j |
�d���� |
1000 |
|
�W���E�^���i�d�C�J�[�y�b�g�܂ށj |
�@ |
500 |
|
��q |
�ꖇ |
500 |
|
������ |
�@ |
500 |
|
�Ɩ���� |
�@ |
500 |
|
�H���Z�b�g�i�Q�l�p�j |
�@ |
1000 |
|
�H���Z�b�g�i�S�l�p�j |
�@ |
1500 |
|
�����@ |
�@ |
500 |
|
�H������@�i���^�j |
�@ |
500 |
|
�H��˒I |
�@ |
1500 |
|
�� |
||
|
���ъ�i�P�������ȏ�j |
�@ |
500 |
|
�X�[�c�P�[�X |
�@ |
500 |
|
�p�� |
�@ |
500 |
|
�X�L�[�� |
�@ |
500 |
|
�X�^���h�Ɩ��� |
�@ |
500 |
|
�X�e���I�i�R���|�j |
�@ |
500 |
|
�X�g�[�u�i�d�C�E���j |
�@ |
500 |
|
�X�m�[�{�[�h |
�@ |
500 |
|
���̂��i������j |
�@ |
500 |
|
������ |
�@ |
500 |
|
���ׂ���i�ƒ�p�j |
�@ |
1000 |
|
�Y�{���v���b�T�[ |
�@ |
500 |
|
�X�|���W�}�b�g�i�R�܁j |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
��@ |
�@ |
500 |
|
����@ |
�Ɠd���T�C�N�����w���̂��� |
2730 |
|
�� |
||
|
�|���@ |
�@ |
500 |
|
���� |
�q���p |
500 |
|
�\�t�@�[ |
�P�l�p |
500 |
|
�\�t�@�[ |
�Q�l�p |
1000 |
|
�\�t�@�[ |
�R�l�p |
1500 |
|
�� |
||
|
�� |
�ꖇ |
500 |
|
�싅�� |
�@ |
1500 |
|
���� |
�@ |
500 |
|
�����^���X |
�@ |
1500 |
|
�m���^���X |
�@ |
1500 |
|
�a�^���X |
�@ |
1500 |
|
�� |
||
|
�`���C���h�V�[�g |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
���i�ؐ�����������j |
�Б��A���� |
1500 |
|
�� |
||
|
�e���r |
�Ɠd���T�C�N�����w���̂��� |
3150 |
|
�d�C�ѕz |
�@ |
500 |
|
�d�C�J�[�y�b�g |
�@ |
500 |
|
�d�C�X�g�[�u |
�@ |
500 |
|
�d�q�����W�i���^�j |
�@ |
500 |
|
�d��₮�炱���� |
�@ |
1000 |
|
�d���J�[�i�q���p�j |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�h���b�T�[�i�P�ʁj |
�@ |
1000 |
|
�h���b�T�[�i3�ʁj |
�@ |
1500 |
|
�g���[�j���O�@��i�Ԃ牺�����E���[�������i�[���j |
�@ |
1500 |
|
�� |
||
|
�g�� |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�l�`�P�[�X |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�ʂ������ |
���50�p�ȏ� |
500 |
|
�� |
||
|
�o�P�c |
18L�ȏ� |
500 |
|
�p�\�R���v�����^�[ |
�@ |
500 |
|
�p�\�R�����b�N |
�@ |
1000 |
|
�p�l���q�[�^�[ |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�r�[�`�p���\�� |
�@ |
500 |
|
�r�f�I�f�b�L |
���50�p�ȏ� |
500 |
|
�� |
||
|
�t�@���q�[�^�[ |
�@ |
500 |
|
�ӂ��� |
�ꖇ |
500 |
|
�z�c |
�ꖇ |
500 |
|
�u���C���h |
���50�p�ȏ� |
500 |
|
�u�����R�i�ƒ�p�j |
�@ |
1000 |
|
�v�����^�[ |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�x�b�g |
�ؐ��A�d�����A�p�C�v |
1500 |
|
�x�r�[�T�[�N�� |
�x�r�[�x�b�h |
500 |
|
�x�r�[�J�[ |
�@ |
500 |
|
�x�r�[�o�X |
�@ |
500 |
|
�x�b�h�pϯ�ڽ |
������٥������A�ݸ�� |
1500 |
|
�� |
||
|
���s�� |
�@ |
500 |
|
�{���i�I�j |
�@ |
1500 |
|
�|���^���N |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�}�K�W�����b�N |
���50�p�ȏ� |
500 |
|
�}�b�T�[�W�@ |
������ |
1500 |
|
�� |
||
|
�~�V�� |
�����ݎ��A�|�[�^�u���� |
500 |
|
�~�j�R���| |
���50�p�ȏ� |
500 |
|
�� |
||
|
�݂��@ |
�@ |
500 |
|
�������� |
�@ |
1000 |
|
�� |
||
|
�m���_���X |
�@ |
1500 |
|
�� |
||
|
���W�J�Z |
���50�p�ȏ� |
500 |
|
�� |
||
|
���[�������i�[ |
�@ |
1500 |
|
�� |
||
|
�①�ɁE�Ⓚ�� |
�Ɠd���T�C�N�����w���̂��� |
5140 |
|
���W���[�e�[�u�� |
�@ |
500 |
|
�� |
||
|
�� |
||
|
�a�_���X |
�@ |
1500 |
|
���[�v�� |
�@ |
500 |
�s���w�肷��K���������
�i�ߍ]�����s�̔p�����̌��ʉ��A�������y�ѓK���������Ɋւ������P�O���P���j
�i�K����V���j����10���ɋK�肷��K����������́A���̊e���Ɍf����Ƃ���Ƃ���B
(4)�@�e�ϖ��͏d�ʂ��������傫������
(5)�@�O�e���ɒ�߂���̂̂ق��A�s���s����ʔp�����̏����ɒ������x�������������
�i��̗Ꭶ�j�@�@�@�T�O����
|
�i�� |
�i�� |
|
��˗p�|���v |
�d�C������i���O�p�ۃ^���N�j |
|
���� |
�d�r�i��J�h�E�{�^���d�r�j |
|
LP�K�X�{���x |
������ |
|
�G���N�g�[�� |
�_�@�� |
|
�I���K�� |
�_�Ɨp�̐��p�E���ŗp�^���N |
|
�I�[�g�o�C |
�_�Ɨp�r�j�[�� |
|
�����@ |
�_�� |
|
�R�s�[�@ |
�p���i�����A�K�\�����A�I�C�����j |
|
���Ί� |
�o�b�e���[ |
|
�����ԕ��i |
�s�A�m |
|
�X�v�����O�i�����ԁE�o�C�N�j |
���d |
|
�p�{�[�h |
�v���p���K�X�{���x |
|
���ʑ� |
�{�E�����O�̋� |
|
�\�[���[�i���z�M�j������ |
�}�b�T�[�W�@ |
|
�ω��� |
�܂���� |
|
�^�C�� |
���u�i�������j |
|
�f�M�� |
��� |
|
�`�F�[���i�ԃ^�C���p�j |
���� |
|
�S�A���C |
�����J�[ |
|
�d�q�I���K�� |
�����W�t�[�h |
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P�R
���ݏ����ɂ́A������o��������Ă���̂ł����H
Q;���ݏ����ɂ͍���̂�����̂������g���Ă���̂ł��傤���H�P�T�N�قǐ̂ɁA�s�̕����琶���������i���܂̏o�O�u���j�ɗ��Ă����������Ƃ��A1����200���~�̐ŋ����A���݂ŔR�₳��Ă���Ƃ������b�������Ƃ�����̂ł����B�܂����̂Ƃ��ɁA1�l1������̂��ݔr�o�ʂ�1000g��1kg������u���݂̗L�����v���������Ƃ̂��Ƃł������A���܂͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���H
A;�@������͌��Z�����݂Ōv�Z���Ă���܂��B���Z���ł��獷���ւ����܂��B
�@�܂��A�����P�V�N�x�̂��ݏ����ɗv�����o��i���Z�����݁j����������܂��B
�@���|�������152,925��~�E�E���݃J�����_�[��|���ƂɌg����Ă���E���̐l����Ȃǂ̂��ݏ����W�Ŏg�����o��̂�
�@���ݏ������768,528��~�E�E���ݎ��W�⏈���{�݂̉^�]�y�шێ��Ǘ��o��
�N���ҕ���363,321��~�E�E�E�ċp�{�݁Aػ��پ����A�ŏI������̌��݂̍ۂ̎؋����N�����ԍϕ�
���v����ƁA1,284,774��~�ƂȂ�܂��B�������A������������萔���Ǝ������݂̔��p����̍Γ�123,000��~�����������ƁA������1,161,774��~�ł��B���̌o���365���ŒP���Ɋ���ƁA�S�~�����o��Ƃ���1��������3,519,927�~��������A�Γ��Ƃ���1��������336,986�~�������Ă������ƂɂȂ�܂��B���x�萔������������������1��������3,182,941�~���A�ċp�▄�ߗ��ď����Ɏg���Ă���Ƃ������Ƃ�������ł��傤���A���ۂ͓Ɨ��̎Z���ł͂Ȃ��̂Ŏ萔���⎑��������͎s�S�̂̍Ώo�̂Ȃ��Ŏg����̂ŁA�����o��Ƃ��ẮA336,986��~�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B15�N�O�Ɣ�ׂ��118�`136���~/���قǑ����Ă��܂����A�ċp�{�݂̘V�����ɔ����ێ���C�Ɍo����ނ̂�,����11�N�ɐV�ŏI����������݂��Ă���؋��̕ԍϊz�������Ă��邩��ł��B�t�ɐl������͂��߂��̑��̌o��Ȃǂ͔N�X�������Ă��邩������Ԃł��B
�@����A�����P�V�N�x���ɁA�X�e�[�V�������W�Ⓖ�ڎ����ݓ��Œ��ԏ����i�ċp���j���ꂽ�R���݁A�s�R���݁A�e�傲�݂̗ʂ́@26,268t�ŁA��݁E�ʁA�V���A�߯����ٓ��̎������ݗʂ� 1,218t�A�ŏI������Ɏ����܂ꂽ�D�₪�ꂫ�ނ̂��݂��A3,661t�ō��v�@31,147t�ł����B���̕���17�N�x�̑����ݔr�o�ʁi31,147t�j���s�̐l���i=68842�l�j1�l����ɂȂ����ƁA�N�ԂS�T�Rkg�̔r�o�ƂȂ�A1�l1�������肾��1,240g�ƂȂ�A�y���Pkg���Ă��܂��B�܂�����17�N�x�̂���1kg����̏����o���42�~�i�Γ���������37,3�~�j�ƂȂ�A�s��1�l����̔r�o�ʂS�T�Rkg/�N��42�~/kg���������1�l����̂��ݔr�o�Ə����ɂ������Ă���N�Ԃ̌o��͐Ԃ��������N����1�l�ɂ�19,026�~/�N�ƂȂ�܂��B
�@�܂�A���Ȃ������������悤�ɁA�Ɍ������1��352���~�����݂�R�₷���߂Ɏg���A�s��1�l�ɂ��N��19,026�~�̌o��ŋ����g���Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@���̂܂܂ł́A���݂̌��ʉ��ɓw�߂Ă���l�ƁA���ł����݂Ƃ��Ė������E���ӔC�ɔr�o���Ă���l�ł͕s���������K���łĂ��܂��B���̂��߁A�{�s�ł������ʂɓw�߂Ă�����������悤�ȁ��s�����S�u���݂̗L�����v������ɂ��ꂽ�{����l����K�v������܂��B�ŋߍ�����̉ƒ낲�ݗL�����K�C�h���C���������ꂽ���Ƃł��̂ŁA�s�ł͎��Ƃ��ݑ���܂߂đ��}�ɗL�����ɂ��Č������Ďs�����ӂ��͂��肽���ƍl���Ă��܂��̂ŁA���̎��ɂ͂������A�����͂����˂������܂��B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P�S
�V���ݏ����{�݂̌��v��͂���̂ł���
Q;���݂̎s�̏ċp�{�݂͉ғ����Ă���Q�S�N�������A�V�������������Ď{�݈ێ��̂��ߔN2��F���߂Đ������Ă���ƕ����܂����B�����Ԃł������^�]���ď���Ă���ƁA�ǂ�������ł��܂����A�C������o�J�ɂȂ�܂���B���ׂ̓��ߍ]�s�◳���������p����Ă��钆�����|�g���̐��|�H��́A�ߍ]�����s�Ɠ��������Ɍ��݂���܂������A���łɐV���������{�݂Ɍ��ւ����ꂽ�ƕ����Ă��܂��B������Ԃ����������Ƃ͏��m���Ă��܂����A��ɕK�v�Ȏ{�݂ł��B�������Ďg���Ȃ��Ȃ�����A�����Ԃ̂悤�ɑ�ԂƂ����킯�ɂ͂����Ȃ��Ǝv���܂��B���̓����炲�݂����Ďs�������ɑ���ȉe�����o��Ǝv���܂����A�s�Ƃ��ẮA�ǂ̂悤�ɍl���Ă�����̂ł����H�u���A�v�̂悤�ɓ��ߍ]�s�ɂ������ď��������Ă��炤�̂ł����A����Ƃ��V���������{�݂̌��݂��v�悳��Ă���̂ł��傤���B�����������������B
A;����15�N3���ɍ��肵���{�s�́u��ʔp�����i���݁j������{�v��v�̌v�潹�ޭ�قł́A����17�N�x�ɂ͐V�ċp�����{�݂̐����v������肵����18,19�N�x�Ō��ݍH���A����20�N�x����V�{�݉ғ��ƂȂ��Ă��܂��B�������A�s�����������ŁA�����̌v�悪�啝�ɒx��Ă��܂��܂����B�܂����ł͕����̎s�����������������Ă��ݏ����{�݂̍L�扻�v������肵�Ă��܂������A�s���������������߂Ȃ��ƂȂ����ߍ]�����s�Ƃ��ẮA���������Ē������|�̍L�掖���g���ɓ���i�����͋z�������j���A�Ⴕ���͒P�ƂŐV���������{�݂����萴�|���Ƃ����{���邩�̑I���𔗂��邱�ƂɂȂ�܂����B�������A�����m�̂悤�ɒ������|�g���i���ߍ]�s�A���쒬�A�������A���y���̂P�s�R���������j�ł́A���ɋߍ]�����s�����������ݔ����ʂŁA�V���ȏċp�{�݂����݂���Ă���A�ߍ]�����s�Ƃ��ẮA���܂̂Ƃ���P�ƂŐV�{�݂����݂���ȊO�̕��@�����Ȃ��Ȃ�܂����B
�@���݂̂Ƃ���A�v�悩��3�N�x��̕���23�N�x�ғ���ڎw���āA�V�{�݂̐����v������蒆�ł���܂����A�ȂɂԂ�ɂ��A���̂悤�Ȏ{�݂͐��̒��ɕK�v�Ȃ��Ƃ͒N�����F�߂�Ƃ���ł����A�قƂ�Ǘ�O�Ȃ��A�Z������͌����邱�Ƃ���A�v����u�G�ɕ`�����݁v�ɑ��邱�ƂȂ��A���̎{�݂����邱�Ƃ͗e�Ղł͂���܂���B���܌��L�{�݂Ɠ��K�͒��x�̎{�݂����낤�Ƃ����80~100���~�߂��K�v�ƂȂ�܂����APFI��@�Ȃǂ��g���o�������A�s�̎x�o��}����H�v���K�v�ƂȂ�܂��B�܂�����ł́A�������A���y���Ƃ̍����̖����̂Ă���Ȃ����Ƃ���A���ݏ����e�ʂ⏈���\�͂��ǂ̂��炢�Ō����ނ��Ȃǂ̐v�ɂ��傫���e����^���܂��B���Ɂu���A�����v�ɂ����ẮA����17�N�̔N���ɂ����ƌ��܂蕽��18�N4�����u���A�v�𓌋ߍ]�i�����s�j�Ɏ����Ă����ď��������Ă��炤���ƂɂȂ�A�s�̂��A�����{�݂ł����P�N���[���Z���^�[�͔p�~�ɂȂ����o�܂�����܂��B�����u���A�v�����́A�������̕��y�ɂ��������̏����{�݂ɗ]�T������������o�������Ƃł���A�N�X�����X���ɂ���u���݁i��ʔp�����j�v�����̎���Ƃ͎�Ⴂ������Ǝv���܂��B���ꂾ���u���݁v�Ɋւ��Ă͕��G�ł���Ƃ������Ƃ����������������B�������Ȃł́A�����{�݂̐V�ݐ����ɑ��Ă͕����P�V�N�x����u�z�^�Љ�`�����i��t���v���x���n�݂���܂������A���̂��߂ɂ́u�z�^�Љ�`�����i�n��v��v�����肵���Ȃ̏��F�Ȃ���Ȃ�܂���B�P�Ȃ�ċp�F�̌��݂����łȂ��A���ꂩ��̔p����������T�C�N�����ǂ����čs�����̓W�]���K�v�Ƃ���Ă���̂ł��B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P�T
���z�V�[�Y���ł��ˁB
�@���z���ɐ�����p�����i���z�p�����j�̏����́A���̂悤�ɂ��Ă��������B
�@ �������̈��z���ɐ�����p�����̏����ɂ���
�A �ƒ�̈��z���ɐ�����p�����̏����ɂ���
�i���ʁj
�@���������͉ƒ납��̈��z���ɕs�v�Ƃ���p������镨�́A���z�ו��Ƃ͈قȂ�A�p���������@�Ɋ�Â��K���ɏ�������Ȃ���Ȃ�܂���B���z�p�����̏����ӔC�͈��z�������鎖�Ǝҁi���z�������Ǝҁj�Ⴕ���́A�ƒ�̈��z��������ҁi���z�����ҁj�ɂ���A���z�������Ǝҁi���z�����Ǝҁj�ł͂���܂���B�p���������@�ł́A���z�����Ǝ҂��A���z�p�����̏����ӔC�����Ă͂����Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B
�i���Ə��̈��z�p�����̏����j
�@���Ǝ҂̈��z�p�����́A��ނɂ���ĎY�Ɣp�����ƈ�ʔp�����ɑ�ʂ���܂����A�����ŏ�������ꍇ�ȊO�́A�Y�Ɣp�����͎Y�Ɣp���������Ǝ҂ɁA��ʔp�����͎s�����ɏ������ϑ����邩��ʔp���������Ǝ҂ɏ������ϑ����Ă��������B���ƌn�p�����͎Y�Ɣp�����A��ʔp�������킸�A���̏����͎��Ǝ҂̔r�o�ҐӔC�������ł��B
�@���Ȃ݂ɁA�������̃��b�J�[����͋���������p�v���X�`�b�N�A�u�����̓K���X�����A�ɊY������̂ŎY�Ɣp�����B�����d���̊��d�r��ʂ��������Ŏg�p�����Ȃ���������Ȃ̂ŎY�Ɣp�����ł��B���ƌn��ʔp�����Ƃ͓���Ǝ҈ȊO�̎������i�����p���A�i�{�[���j������i���M�j�A�������Ȃǂł��B�����p�i�̃n�T�~�E��K�Ȃǂ̕��[��͋���������p�v���A���邢�̓K���X�����ɊY�����܂��̂ŎY�Ɣp�����ł��B��ʔp�����Ƃ��Ă͏����ł��܂���B�Y�Ɣp�����̏����ɂ̓}�j�t�F�X�g�i�Ǘ��[�j���K�v�ł��B
�@�܂����z�����Ǝ҂��A�p���������@�Ɉᔽ���Ă܂ŁA���z�p�����������ƂȂ��A�Y�Ɣp���������Ǝ҂��Љ��T�[�r�X�ɗ��߁A���z�p�����̏����Ɋւ��T�[�r�X�͍s�Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ̐��������A���z�������Ǝ҂̐ӔC�ɂ���舵����悤�ɂ��Ă��������B�Ȃ��A���z�����Ǝ҂��p����{���p�̎��ށA����p�̎��ނ͈��z�����Ǝ҂��s�v�Ƃ��Ĕr�o����p�����Ƃ��ď�������̂������ł��B
�i�ƒ�̈��z�p�����̏����j
�@�ƒ�̈��z������ҁi���z�����ҁj�͎��炪�r�o������z�p�������K���ɏ��������悤�Ɏs�����̎w���i�p���������v��j�ɏ]���Ĕr�o����`��������܂��B���̂��߁A���炩���߈��z�̍ۂɕs�v�ƂȂ镨������ׂĂ����Ƌ�Ȃǂ̑傫�Ȃ��͎̂s�������s�Ȃ��e�傲�ݎ��W�̃��[���Ɋ�Â��A�܂��e���r�E�G�A�R���A����@�Ȃǂ̉Ɠd���T�C�N�����i�͉Ɠd���T�C�N�����[�g�ɂĔr�o���邱�Ƃ��K�v�ł��B
�@�ƒ납�甭��������z�p�����͈�ʔp�����ɊY�����A���z�����Ǝ҂���z�ו����^������Ǝ҂���ʔp���������Ƃ̋���L���Ă��Ȃ��ꍇ�́A���z�p��������������Ď��W�^�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ɓi�p���������@�ᔽ�j�ɂȂ��Ă��܂��B�������A���z�����Ǝ҂���z�ו��^���Ǝ҂��A���z�p�������^���ł������[�u�Ƃ��āA�@���z�p���������z�����Ǝ҂��Ǘ����鏊��̏ꏊ�܂ʼn^�����邱�ƇA���̏���̏ꏊ�ɂ����Ĉ��z�p�������s�������͈�ʔp�������W�^�����Ǝ҂Ɉ����n�����ƁA�̂Q�_�����ʂňϔC����Ă���ꍇ�ɂ����ẮA���z�p����������̏ꏊ�܂ʼn^�����邱�Ƃ͉\�ł���Ƃ���邪�A���ځA���z�����Ǝғ����s�������̈�ʔp���������{�݂܂Ŕ������邱�Ƃ͔F�߂��Ă��܂���B
�@���z��������ƒ�̎����A���z�p�������s�����̎w���ǂ���r�o���������ꍇ���͎���s�����̔p���������{�݂܂ʼn^�����������ꍇ�ɂ́A���z�����Ǝ҂ł͂Ȃ��A�s�������������Ă����ʔp�������W�^���Ǝ҂Ɉ˗������Ă��������B��ʔp�������W�^���Ǝ҂Ɏ��W�^�����˗�����A���̈��z�p�����́i���j�Ǝ҂��݂Ƃ��Ďs�����̏����{�݂ɔ������ꏈ������܂��B
�i�Q�l�j���z���˗�����Ƃ��͒��ӂ��Ă��������I
���z���ɐ������p�����i�ȉ��u���z�p�����v�Ƃ����B�j�ɂ��āA���z�������Ǝҁi�ȉ��u���z�����Ǝҁv�Ƃ����B�j���A�p�����̏����܂ŕ����Đ������A�]�X�Ɗۓ������s���钆�Ō��ʓI�ɕs�@�����Ɏ��鎖�Ă��������Ă���܂��B���̂��߁A���ɂ����ẮA���z�p�����ɂ��ẮA�K�������u�p�����̏����ɋy�ѐ��|�Ɋւ���@���v�Ɋ�Â����K���Ȏ戵�����s���Ă��Ȃ��X�������邱�Ƃ���A���Ȃ�����z�p�����̎戵���Ɋւ���}�j���A�������肳��Ă���܂��̂ł����ӂ��������B�@�@
���Ǝ҂̈��z�p�����̏���
o���z�p�����́A���z�����鎖�Ǝ҂̐ӔC�ŎY�Ɣp�����ƈ�ʔp�����ɋ�ʂ��A�������Ȃ�������܂���B�i�r�o���ƎҐӔC�j
o���z�p�����̏����ӔC�����z�����Ǝ҂ɕ��킹�邱�Ƃ́A�r�o���ƎҐӔC�ɏƂ炵�ĕs�K�ł��B
o�Y�Ɣp�����ɂ��ẮA���z�����鎖�Ǝ҂̐ӔC�ɂ��K�������m�ɂ����A�ϑ��_��E�}�j�t�F�X�g�ɂ��Ǘ����K�v�ł��B
�ƒ�̈��z�p�����̏���
o���z������ƒ�̕��́A���z�p������K���ɏ������邽�߁A�e�s�����̎w���ɏ]���Ĕr�o���铙�A�ӔC����Ή������Ă����������Ƃ��K�v�ł��B
o�ƒ납�甭��������z�p�����͈�ʔp�����ɊY�����A���z�����Ǝ҂���ʔp���������Ƃ̋���L���Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����Ƃ��āA�ƒ납��r�o�������z�p�������^���E���������邱�Ƃ͂ł��܂���B�@�������A���z������ƒ�̕��̎����A���z�p�������ǂ����Ă��s�����̎w���ǂ���ɔr�o���������ꍇ���͎���s�����̏����{�݂܂ʼn^�����������ꍇ�ł����āA���z�����Ǝ҂ɑ��āA�@���z�p���������z�����Ǝ҂��Ǘ����鏊��̏ꏊ�܂ʼn^�����邱�ƁA�A���z�p����������̏ꏊ�ɂ����Ďs�������͈�ʔp�������W�^���Ǝ҂Ɉ����n�������̂Q�_�����ʂňϔC����Ă���ꍇ�ɂ����ẮA����ɏ]���Ĉ��z�p����������̏ꏊ�܂ʼn^�����邱�Ƃ͉\�ł��B�@�@
�Q�l�F���z���ɔ�������p�����̎戵���}�j���A���i���ȁj
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P�U
�u�������݁v�̎�������s�ׂ͋֎~�ł��I
�����̓��ɁA�s���݂̂Ȃ��A�������݃X�e�[�V�����ɏo�����V����A���~�ʂȂǂ̎������A�s���������O�ɔ�������ăg���b�N�ȂǂŎ�������s�ׂ����s���Ă��܂��B���̂悤�Ȏ�������s�ׂ������܂��ƁA�s���̊F����̕��ʔr�o�E���T�C�N���ӗ~�̒ቺ�ɂȂ��鋰�ꂪ����܂��B�������͎s�s���ƏZ���̋����Ői�߂Ă��鋤�ʂ̃��T�C�N�����i�L�����j�ł��B��������͂�߂Ă��������B
|
�@�@�p�g���[������ |
|
|
�@�s���̊F���u�����Ƃ��ă��T�C�N�����Ăق����v�Ƃ̎v���ŁA�r�o�����������݂� ���f�Ŏ�������l�����܂��B���̂悤�Ȏ�������s�ׂ�����l�̒��ɂ́u�s�̋������� ���Ă���v�Ƃ����l�����܂����s�́u��ʔp���������v��Ŕp�����̎��W�E�^���ɂ��� �̓X�e�[�V�������W�͈ϑ��Ǝ҂��������Ă��܂���B�v�X�e�[�V�������Ǘ����鎩����� ���������ŁA���݃X�e�[�V�����ɏo����Ă��鎑�����������s�ׂ܂ł͋K���ł� �܂��A����ȊO�͎�������s�ׂƂȂ�܂��B�s�Ƃ��Ă��A��������l�����������ꍇ �́A��������s�ׂ���߂�悤�w�����Ă��܂��B��������s�ׂ����������ꍇ�́A�N���[ ���Z���^�[�܂ł��A�����������B�s�ł��A�s���݂̂Ȃ���̖ڌ����Ȃǂ��Q�l�ɂ� �Ȃ���A�p�g���[�����������A�F����̏������Ɏ�������s�҂���肵�x���E�w �����Ă����܂��B |
|
|
�s���݂̂Ȃ���ւ̂��肢 �F������������s�ׂ����������ꍇ�́A�s�����Ɂi�ꏊ�A���ԁA�i�ځA�ԗ��i���o�[�� �Ȃǁj�A�������肢�������܂��B�F����̏������ɁA��������s�҂���肵�A �x���E�w�����Ă����܂��B�Ȃ��A�s���̊F���A��������s�ׂ������҂��A���̏�ŕ� �܂�����A�g���b�N�Ȃǂڐ��~���铙�̍s�ׂ́A�댯�ł��̂ł���߂��������B |
|
�@�@�@�@�@�@�@ |
�X�e�[�V�����ɏo���ꂽ�������ݎ�������s�ׂɑ���s�̌����ɂ���
�i�W�Ҏ����j
1�@����
�@��������s�ׂ͈ȑO����s�Ȃ��Ă������A�ʂ����Ȃ���E�̖����l�B�����X�̗Ƃ�s�ׂƂ��āA�܂�������Ə��Ȃǂ̎����邽�߂̍s�ׂƂ��ėe�F����Ă����B�o�܂����邪�A���̓����̎s�̌����Ƃ��ẮA�X�e�[�V�����ɏo���ꂽ���_�Łu���݁v�ł���s�̏����{�݂ɔ��������u���݂̑��ʁv������̂�����A�s�Ƃ��ẮA�e�F�����Ă���Ƃ������Ƃł����B�������A�ߔN�͒���������ʂ�I�蕪���鉹���₩�܂����Ƃ��A�V��������I�蕪���`���V�E�G���ނ͎U�炩������ł́A�X�e�[�V�������Ǘ����Ă��������Ă���Z���̊F�l�ɑ�ςȖ��f���������Ă���ƂȂ��Ă���A���������s����M�����ă��T�C�N���ɋ��͂��Ă��������Ă���Z���̐M���𗠐�Ȃ��悤�ɂ��Ă����K�v������Ƃ������n����A��������K�������Œ�߂�Ƃ���������Ȃ��Ă��܂����B
�Q�@��������s�ׂ̖��_
�@ ��O�҂̂�����ɂ��n��R�~���j�e�B�̈��S�E���S�����������
�A �u��̌����Ȃ��v�s������ػ��ق��Z���͐M���ł��Ȃ�
�B �����̂̎��v�̉����E�E�E�킸���ł��邪���p���v���s�ɊҌ������
�C ����≮���ɂƂ��Ă͎d�����̓���ɂ�����E�E�\�肵�Ă����Î����̎������̗ʁA�����W�܂�Ȃ��B
�D �Z���Ƃ̐M���E�����W�̏�ɐ��藧���Ă���ػ��كV�X�e����j��s�ׂł���
�E �ߔN�̓r�W�l�X�Ƃ��đg�D�����ꂽ�`�ł���Ă���A���͂�ʼn߂ł��Ȃ��ƂȂ��Ă��Ă���B
���̂��ߋߍ]�����s�s���Ƃ��Ă��A�ȉ��̌����������A�[�������Ă������ƂƂ��܂��B
�R�@�s�Ƃ��Ă̌���
�P�j �X�e�[�V�����Ǘ��͎�����ɂ���
�������݂Ƃ��Ĕr�o���ꂽ�V���E�G���A��݁A�ʁA�_���{�[���A�y�b�g�{�g���A���p�b�N�́A�L�����Ƃ��čė��p��ړI�Ƃ���Ƃ����Z���ƍs���̋��ʔF���̉��ŁA������Ǘ����ɂ���X�e�[�V��������s���ɏ��n�������̂ł���B�������݂Ɍ��炸��ʂɁu���݁v�͒n��Z�����Ǘ�����X�e�[�V����������W�������_����s���̊Ǘ����ɒu�����B����܂ł́A���ʂ��ꂽ�i�����j���݂͒n��Z���i��������j�̊Ǘ����ɂ���Ƃ݂Ȃ����B
�@�䂦�ɁA�������݂̎�������s�ׂ̓X�e�[�V�����̊Ǘ��҂��鎩����̏����čs�Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������������n��Z���i���X�e�[�V�����Ǘ��ҁj�̏����������ł̎�������s�ׂɑ��Ă܂ōs�����K���������Ď����܂邱�Ƃ͓���B
�Q�j �X�e�[�V�����Ǘ��҂ɖ��f�Ŏ������݂���������i�ގ悷��j�s�ׂ́A�ޓ��ł���
�W�c����̂悤�ɂo�s�`���̖��Ԓc�̂Ɖ���Ǝ҂��_��ɂ���ĉ�����s�Ȃ��Ă���悤�ȏꍇ�͖��炩�ɗL�����̔��������Ă���킯������A�c�̂̊���������Ƃ������m�ȖړI�̌��ɍs�Ȃ��邽�߂ɐ�L�̈ӎv�͖��m�ł���B���������Ɏ�������ΐޓ��߂ɂȂ�B�����悤�ɁA�X�e�[�V�����ɕ��ʂ��Ĕr�o���鎑�����݂͒P���ɔp������ړI�Ƃ����s�ׂł͂Ȃ��A�s���̗v���ɏ]���ďZ�����������肵�ėL�����Ƃ��Ă̏��i���l�����߂āA�u�s���ɏ��n����s�ׁv�ł���A���炩�ɏZ������L�҂̈ӎv�i���s���ɏ��n����Ƃ����ӎv�j�ɔ�����ގ�s�ׂ́A�O�`�I�ɂ���ϓI�ɂ��ޓ��߂��\������v�������Ă�����̂ł���B
�@�������A���̂悤�Ȍ����������Ă��A�����ɂ͎�������s�ׂ��Y�@��̔ƍ߂Ƃ��Ď����܂邱�Ƃ͓���ۑ�ł���Ƃ����B�Ȃ��Ȃ�A�^�o�R���̃|�C�̂Ă��ƍ߁i���Ƃ��Δp���������@�̑�T�𐴌��̕ێ��j�ł���̂Ɏ����܂�Ȃ��̂Ɠ������R�ł���炵���B�i���ꂾ���̐l�����̐����g�߂��A���ʂ����҂ł���Ƃ͌���Ȃ��B�j
�R�j���ʂ͏�ᓙ�̉��������Ĕ����K���݂�������A����p�g���[����[���̋����ɂ����ʂ������Ă��������B
��������s�ׂ�ƍ߂Ƃ��ė����邽�߂ɂ́A�p����������ᓙ���������A�u�X�e�[�V�����ɏo���ꂽ�������̏��L���v�𖾂炩�ɂ���K�v�i�����̓���A�ꏊ�̓���A�q�ϓI�A��ϓI���ʂ������Ɓj������A���̂��߂ɂ͌Î��ނ�ʁE��݂ɏ��L�ҁ��r�o�҂̖��O�L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i���w��ܐ��̓����Ɣr�o�Ҏ����̖��L���O��ƂȂ�j����ɔr�o�҂���������p�����Ƃ��ĔF�����Ă�����ƍ߂̗��͂�������̂ƂȂ�B���Ȃ��Ƃ�����ł͔r�o�������ɐ�L�̈ӎv������Ƃ͌����ɂ����̂ł���B�X�e�[�V��������w��Ǝҁi�ϑ��Ǝҁj�ȊO�̎��W���֎~����ɂ��Ă��A�t�ɗL�����ł���Ǝ咣�����Δp���������@�i���ɂ����W�^���̐����j�̓K�p������B
�@���̂��߁A���ʂ͒n��Z���i��������j�ɃX�e�[�V�����Ǘ���O�ꂵ�Ă��炤�ƂƂ��ɃX�e�[�V�����ɁA�u���������s�̍s������ɏo�������̂ł��邱�Ɓv������ӎv�\���̒��莆�����Ă��������A����p�g���[����[�������̋����ɂ��A��������s�ׂ̗}����}���Ă����悤�ɂ��Ă��������B�܂��A��������s�ׂ̑����ꏊ�̃X�e�[�V�����Ǘ��҂ɂ����������֎~���x�����钣�莆���f�����Ă�����������A�W�c��������ɋɗ͏o���Ă��������悤�Ɏw�����Ă��������B
�S�j�p�����Ƃ݂Ȃ��s�����w�肷��҈ȊO�́u���W�E�^���̋֎~�v���[������
�@�X�e�[�V�����̊Ǘ��͎�����Ƃ��邪�A�X�e�[�V�����ɏo���ꂽ�������݂͒N�̂��̂ł��邩�Ƃ����l�����ɂ͓�킠�邪�A��͖��啨��L�̍l�����ŁA�����̂���L�̈ӎv�������ď��L�����擾����i���@239���j�Ƃ������̂ƁA���͖��@240���̈⎸���E���̍l�����ł��邪�A���Â����L���̍������ア���A�������݂̊Ǘ��ӔC���ǂ̂悤�ɍl���邩���ۑ�ƂȂ�B�����Ŕp���������@�ɒ�߂�s�v���Ƃ��Ĕp�����Ƃ݂Ȃ��āA�u���W�E�^���v���֎~���邱�Ƃ���Ԗ���ł���B�u��ʔp���������v��Œ�߂鏊��̏ꏊ�ɒu���ꂽ�p�����̂����A�ė��p�̑ΏۂƂȂ���̂Ƃ��Ďs�����w�肷����̂ɂ��ẮA�s�����w�肷��҈ȊO�̎҂́A��������W�E�^�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肷��B���R�A��ʔp�����̎��W�E�^���ɂ��ẮA�p���������@�ɂ���āA�s���̋��������W�E�^���Ǝҁi���W�ϑ��Ǝ҂��܂ށj������ʔp�������Ȃ킿�s�����v��Œ�߂�p�����i�������݂��܂܂��j�͎��W�^���ł��Ȃ��B�������A�o�s�`�����Ԃ̏W�c���������Ƃ�����̂ŁA���̎��͎s���̎w��̏ꏊ�i�X�e�[�V�����j�ł̉���ɂ͔z�����K�v�ł��B
�Ȃ��A����̉ۑ�Ƃ��āA�ƒ낲�ݗL�����Ƃ��킹�w��ܐ������Ă����Ȃ��ŁA�����������Ĕ����K���݂��Ă������ǂ��������E�������Ă����悤�ɂ������B
�u���݁v�̎��W�^���́A�s���̎w�肵���҂����ł��܂���
�p���������@�ɂ��A�X�e�[�V�����ɏo���ꂽ���݂́A��ʔp���������v��Ɋ�Â��āA���W
�^������܂��B�s�����w�肷��҈ȊO�̎��W�E�^���́A�p���������@�ɂ����W���^�����o����
����B
�����������o���ۂ́A�u�ӎv�\���v�����Ă��������@
�@�@��������s�ׂɑ��C�X�e�[�V�����ɏo���ꂽ�������݂𒅎��Ɏs�̃��T�C�N�����[�g�ɂ̂��邽�߂̑[�u�Ƃ��āu�������݂��s�ɏo�������ł��邱���v�������ӎv�\���\���쐬���Ă��������B�ӎv�\���\�͎s���̊F�l�̈ӎv���������̂ŁC�������݂��o�����ۂ��o���������݂̂悭������Ƃ���ɓ\�邩�Y���Ďg�p���Ă��������B
����́A�������s�����A�ߍ]�����s�Ɏ������Ƃ���
�o�������̂ł��B�@����������@�r�o�Җ��@�����@��
�E�E�������̎�������֎~�E�E�E�E
���̗L�����́A�s�̃��T�C�N�����W�ɋ��͂��邽�߂̂��̂ł��B
�Z���̈ӎv����������Ȏ�������i�ގ�j�s�ׂ͂�߂Ă��������I
��������������s�ׂɑ���K���ɂ���
�{�s�ł́A�Ƃ肠�����A�L��ł̌[���Ƃ��܂������A��ᓙ�ŋK�����Ă��鎩��
�̂�����܂��B�ʂɑ����������́A�����_�ł̍l�����ł���A���{�I�Ȃ��̂ł�
����܂���B�ȉ����Q�l�ɂ��āA����̖{�s�ł̋�̍���������������B
�@�s�Q�l�t
���@���Ŏ������݂̎���������֎~���Ă��鎩���̗�E�E�A���������̂Ƃ���
����
�����s���c�J��@�E�E�E�E���|�E���T�C�N�����̉���
�@http://www.city.setagaya.tokyo.jp/topics/seisou_re/mochisari.htm
���֎s�@�@�E�E�E�E�p�����������̉���http://www.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/env/seisaku/gomi/motisari/motisari.htm
���@��������h�~�v�j�𐧒肵�Ă��鎩���̗�
�����s�@http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/01_kakuka-page/04_sangyo-kankyo/05_cleansuisin/kurin_mochisariboushi.htm
���u���������s�̍s������ɏo�������̂ł��邱�Ɓv�����Ă��鎩���̗�
���Ύs�E�E�E�E�ӎv�\���V�[�g��
http://cms.city.tsukuba.ibaraki.jp/041100/modules/wordpress/index.php?cat=10
��錧�߉ώs�E�E�E�A�ӎv�\�����̓\�t
http://www.city.naka.ibaraki.jp/hp_phone/template/freepage.htm?id=2005100615525720899&l_id=03&m_id=03
���@�[����p�g���[���̎����̗�E�E�E�g�o�ȂǂŌ[��
�����s�@�E�E�E�[���ł̂��肢
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P�V
![]()
![]()
![]()
|
���Ǝ҂̔p�����̏����ɂ��āA��p���������@��ł́A���̂悤�ɋK�肵�Ă��܂��B |
|||
|
���Ɗ����ɔ����Ĕ���������ʔp�����i���X�⎖�����̂��݂��܂ށj�́A�s�̒�����W�ł͎�舵���ł��܂���i�X�e�[�V�������W���܂���j�̂ŁA���̕��@�ŏ������Ă��������B
|
���W�^���Ƌ��Ǝ҂ֈ˗�������@ |
|
�����{�݂Ɏ��Ȕ����i�������݁j������@ |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
�� |
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
�� |
|||
|
|
|
|||
|
|
�� |
||||
|
|
|
![]()
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�P�W
���Ə��E���Ǝ҂̊F�l�ցE�E�E�E�E�����ӂ��������I
�@�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���i�ȉ��u�p���������@�v�Ƃ����B�j�̔�������������Ă��܂��̂ŁA���Ɗ����ɔ����Đ����鎖�Ƃ��݂͖@������юs�̂��ݔr�o���[���i�p���������v��j�Ɋ�Â��K���ɏ����E���������Ă�������悤���肢���܂��B
�����Ɗ����ɔ����Đ�����p�����́A���߂Œ�߂�p�v���X�`�b�N�A�p�K���X�A���������A���ꂫ�ނȂǂQ�O��ނ́u�Y�Ɣp�����v�ƎY�Ɣp�����ȊO�̔p�����i������u���ƌn��ʔp�����v�Ƃ����B�j�ɋ敪����܂��B�E�E�E�E�E�p���������@��Q���i�p�����̒�`�j
�����Ǝ҂́A���̎��Ɗ����ɔ����Đ������p����������̐ӔC�ɂ����ēK���ɏ������Ȃ���Ȃ�܂���B�E�E�E�E�E�p���������@��R���i���Ǝ҂̐Ӗ��j
�����Ƃ��݁i�Y�Ɣp�����⎖�ƌn��ʔp�����j���ƒ�p���݃X�e�[�V�����ɖ��f�ŏo�����Ƃ͕s�@�����Ƃ݂Ȃ���܂��B�܂����ȏ����ł����Ă�����������Ȃ��ċp�F�ł̏ċp�͋֎~����Ă��܂��B
�@���l���A�݂���ɔp�������̂ĂĂ͂Ȃ�Ȃ��B�E�E�E�E�p���������@��P�U���i�����֎~�j
�@���l���A���Ɍf������@�ɂ��ꍇ�������A�p�������ċp���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�E�E�E�p���������@��P�U���̂Q�i�ċp�֎~�j
�@�����i��Q�T���j�E�E��P�U���y�ё�P�U���̂Q�̋K��Ɉᔽ�����҂́A�T�N�ȉ��̒�����������1000���~�̔����A���͂���Ȃ���B�����̍߂͖����ł�������B
�i�p�����̏������j
�� �s�������́A���̋����ɂ����Ď��Ɗ����ɔ������ʂ̈�ʔp�������鎖�Ǝ҂ɑ����Y�p�����̌��ʁA�^�����ׂ��ꏊ�A���̉^���̕��@���̑��K�v�Ȏ������w�����邱�Ƃ��ł���B�E�E�E�E�p���������@��6���̂Q�@��5��
�� ���Ǝ҂́i�s�������̒�߂�j��ʔp���������v��ɏ]���āA���̈�ʔp�����̉^�����͏����𑼐l�Ɉϑ�����ꍇ�ɂ͖@��V���12���ŋK�肷����ȗ߂ɒ�߂�҂Ɉϑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E�E�E�E�p���������@��6���̂Q�@��6��
�� ���Ǝ҂͈�ʔp�����̉^�����͏������ϑ�����ꍇ�͐��߂Œ�߂��ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E�E�E�E�p���������@��6���̂Q�@��7��
�����E�E�E�E�E�E�p���������@��6���̂Q�@��6���ˑ�25���̔����K�p
�@�@�@�p���������@��6���̂Q�@��V���ˑ�26���̔����K�p�E�E3�N�ȉ��̒�����������300���~�ȉ��̔����B���͂���̕��ȁB
�Ȃ��A�p���������@��P�Q���4���̎Y�Ɣp�����̉^�����͏����A���@��12���̂Q�̓���Ǘ��p�����̉^�����͏����ɂ��Ă��A��L�́u��ʔp�����v���u�Y�Ɣp�����v���邢�́u����Ǘ��p�����v�Ɠǂݑւ��邾���ł���A���l�ɔ������K�p����܂��B
����ʔp�������W�^���Ǝ�
�@�p���������@��7���͈�ʔp���������Ɓi���W�^���Ƃ��܂ށj�ɑ��鋖�̊����������Ă��܂��B���̂Ȃ��ő�7���15���̈�ʔp���������Ǝҁi���W�^���Ƃ��܂ށj�͊��ȗ߂Œ�߂鎖�����L�ڂ������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��Ē���L�ڂ��`���t�����Ă��܂��B����̋L�ڂ�1����P�ʂƂ��������̓��ɍs�Ȃ����������L�ڂ��K���ɋK�肵�鎖�����L�ڂ���ƂȂ��Ă��܂��B�K���̎��W�^���Ǝ҂̋L�ڎ������ɂ́A�p�����̎�ނ��ƂɎ��W���͉^���N�����A���W���i���Ə����j���͎����A�^�����@�y�щ^���悲�Ƃ̉^���ʂ��L�ڂ��܂��B�Ȃ�����͖������܂łɁA�O�����ɂ�����L�ڂ��I�����Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�܂���7���16���ł́A�O���̒���͊��ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��5�N�ԕۑ����Ȃ���Ȃ�܂���B�����1�N���Ƃɕ����A����5�N�Ԏ��Əꂲ�Ƃɕۑ����邱�ƁB�ƂȂ��Ă��܂��B�@
�@���̏����Ɉᔽ�����ꍇ�́A������30���̓K�p�ɂ��30���~�ȉ��̔����ɏ������܂��B�܂�A�����Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�������̌��i�����Ɉ���������܂��̂ŁA������������邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��̂ŁA�����ӂ��������B
�����ƌn���݂́A���Ǝ҂��ӔC�������ēK�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɓu�p�����̏����y�ѐ��|�Ɋւ���@���v�ɒ�߂��Ă��܂��B���ȏ������ł��Ȃ��ꍇ�Ɍ����āA���̏������Y�Ɣp���������{�݁i�Ǝҁj�Ȃ�A���͈�ʔp���������{�݁i�����ł���͎̂��ƌn��ʔp�����̂݁j�ɏ������ϑ����邱�Ƃ��ł��܂��B
���������ۂ́A�ƒ낲�݂ƌ����������Ȃ��ꍇ������A�Y�Ɣp�����Ȃ̂Ɉ�ʔp�����Ƃ��Ď����݂������i�����Ə��A���Ǝҁj������A�����ȏꍇ�ɂ͂��݃X�e�[�V�����ɉƒ낲�݂ƈꏏ�ɔr�o�������������܂��B
�������������ݖ����������邽�߂ƁA���ƌn���݂̌��ʉ��E�r�o�}�����������i���邽�߂ɁA���ʁu�ߍ]�����s�p�����̌��ʉ��A�������y�ѓK�������Ɋւ�����v�Ɋ�Â��u�p�����Ǘ��ӔC�ҁv���e���Ə��A���Ǝҁi���Ɗ����̑召���킸�j�őI�C���������A���݂̌��ʁE�K���r�o�ɓw�߂Ă��������悤�ɂ��肢������̂ł��B���łɁA�ƒ낲�݂Ɋւ��Ă͒n�掩����Łu����₩�����i���v��I�o���A���݂̌��ʉ��E�������y�ѓK���r�o�ɓw�߂Ă��������Ă���Ƃ���ł�����A���K���ł͂P������50kg�ȏ�̎��Ə��ƂȂ��Ă��܂����A����ȉ��̎��Ə��ɂ����Ă��������`���ł͂���܂��A���Ɗ�����n��ōs�Ȃ���Ƃ̎Љ�I�ӔC�Ƃ��āu�p�����Ǘ��ӔC�ҁv�����I�C���������A���ƌn���݂̓K���r�o�y�ь��ʉ��E�������v��̍���ɓw�߂Ă��������悤�ɂ��肢������̂ł��B
��
�u�p�����Ǘ��ӔC�ґI�C�́v�͎s�������ۖ��͑�Q�N���[���Z���^�[�֒�o���������B
�Ȃ��A��o���ꂽ�l���́A���̋Ɩ��ɂ͗��p�������܂���B
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�Q�O
���ݔ����ʁA���W�ʂ̐��ځ@�@�E�E�E�E�G�N�Z���ʕ\
�m���Ĕ[���I�S�~�̂͂Ȃ������p���������V���[�Y�E�E�E�Q�P
�@�萔���ו����̌����ɂ���
�����̑O��
�@���ƌn���݂̔����萔����10kg����150�~����300�~�ɒl�グ�������Ƃɂ��A����18�N3���c��Ŏ��₪����c��{��c�ŁAM�������萔���̍ו������������Ă����Ɖ������ɂ���
������
���@��Q�N���[���Z���^�[�֒��ڔ�������ꍇ
�ƒ낲�݁E�E�E�P�O�����@�Q�O�O�~�@�@�����u��
���Ƃ��݁E�E�E���ƌn��ʔp�����@�@�@�P�O�����@�R�O�O�~
�@�@�@�@���Ə�����̎������݁i�ʁA�т�A�_���{�[���A�V���E�G���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�O�����@�Q�O�O�~�@���������A���ڂ͔F�߂Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@
�� ���Ƃ��݂̃X�e�[�V�����r�o��F�߂�ꍇ
���Ƃ��݂̐�p�w��ܐ�������B�E�E�E�E�s�����W����
�@�@��p�w��܁i45د�ّ܁j�@�@�R���ݑ܁@�@1���@�U�O�O�~
�@�@��p�w��܁i20د�ّ܁j�@�@�R���ݑ܁@�@1���@�S�O�O�~
�@�@��p�w��܁i45د�ّ܁j�@�@�s�R���ݑ܁@�@1���@�X�O�O�~
�@�@��p�w��܁i20د�ّ܁j�@�@�s�R���ݑ܁@�@1���@�U�O�O�~
�@�@��p�w��܁i45د�ّ܁j�@�@�������ݑ܁@�@1���@�T�O�O�~
�@�@��p�w��܁i20د�ّ܁j�@�@�������ݑ܁@�@1���@�R�O�O�~
���R
���Ƃ��ݑ�ɂ��ẮA�]������A��������w���E�[�����Ă��Ȃ��������Ƃ���P�̖��ł���B���ł�50kg/���r�o�̎��Ǝ҂𑽗ʂ��ݔr�o���Ǝ҂Ƃ��āu�p�����Ǘ��ӔC�ҁv�̑I�C��r�o�v�������w������悤�ɂȂ��Ă��邪�A���ꂳ�����Ă��Ȃ��B���s�ł�20kg/���𑽗ʂ��ݔr�o���Ǝ҂Ƃ��Ă��邪�A�{�s�͊Â�����B�����������āA�����Ǝ��Ə��w�����������ׂ��ł���B�܂��A���{�݂֔�������鎖�Ƃ��݂̒��ɂ́A�Y�Ɣp�����ɋ敪����镨�������������Ă���A�r�o���Ǝ҂ւ̃���������y�т���Ȃ�[���E�w����O�ꂵ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���B�v�͉�����ʔp�����ł��艽���Y�Ɣp�����ɂȂ�̂����A�܂����Ǝ҂ɂ͔����Ă��Ȃ��B�P���Ɏ��Ǝ҂́u���݁v�Ȃ瓖�ċp�{�݂֎����߂Ώ��������Ă����Ǝv������ł���̂ł���A�������U�A���{�݂֔������ꂽ�ꍇ�̎w���͔��ɍ���ł���B���݂͔r�o����鎞�ɕ��ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͑匴���ł���B�u������Ύ����A��������݁v�Ƃ����̂́A��p�ƎY�p�̋敪�̎��Ƃ��݂ɂ����Ă͂܂邱�Ƃł���B
��Q�̖��́A���݁A���{�݂Ŏ��Ƃ��݁i�����Y�p���������Ă��邪�j�Ƃ��ď������Ă��鎖�ƎҐ��́A���Ǝ҂ɂ������ƒ��ڔ������Ɛ������킹�Ă��V�O�O�Ђł���B��Ǝ��Ə����v(16�N��)�ł́A�s�����Ə��͂Q�W�O�O�Ђł���B�P���Ȉ��Z�ł͎c��Q�P�O�O�Ђ̎��Ƃ��݂͂ǂ��ŏ�������Ă���̂ł��낤���B�����炭�S�~�X�e�[�V�����Ɉ�@�ɏo����āA�ƒ낲�݂Ƃ��Ď��W����Ă���Ǝv����̂ł���B�i�ߏ��̎G�݁E�����d�o�����A�����֒��ڔ������Ă�Ƃ�����������Ƃ��Ȃ����A���������W�^���Ǝ҂Ɉϑ����Ď��W���Ă�����Ă���̂ł��Ȃ��B�܂��A��U���ɂ����ƁA�^���X������O�̃X�e�[�V�����ɂǁ`��Ƃ��݂���ꂽ�^���X�̃_���{�[�������ς܂�Ă���̂��悭��������B�E�E�E�P����10��m��ł͂Ȃ����A���̂��Ƃ�����c��3/4�̎��Ǝ҂́A��@�ɃX�e�[�V�����ɂ��݂��̂ĂĂ��邱�Ƃ̎��Ԃ����@�����Ƃ���ł���B�j�܂��́A�����Q�P�O�O�Ђ̑���ǂȂ����邩�ł���B���Ƃ��݂��X�e�[�V�����ɏo�����Ƃ͈ᔽ�ł���B�Ƃ����Ǝ҂Ɏ��W�ϑ�����Ƃ����[���͂������K�v�ł��邪�A���łɕF���s��Č��s�E���l�s�Ŏ��{���Ă���悤�ɁA���ʂ̎��Ƃ��݂Ȃ�L���ł̃X�e�[�V�������W�����F����Ƃ��������i���Ƃ��݂̏����̎d���̑I�����̂P�Ƃ��āj���K�v�ł͂Ȃ����Ɠ��������������ʁA���Ƃ��݂̐�p�w��ܐ��̓��������_�Ƃ��ē��������܂����B�ڍׂɂ��Ă͕ʎ��u���Ǝҗp���ʗL���w��ܐ��x�̓����̒�āv���Q�Ƃ��ꂽ���B��N���ۂɋ��c�������ۂɂ́A�V�{�݊����Ɠ����ɁA�ƒ낲�ݗL�����i�L���w��܁j�����ƈꏏ�ɍl�������B�Ƃ������Ɓi���ӔC�Ȕ����j�ł��������A����ł͂��ɂȂ�̂��A�S���킩��Ȃ��B�u���Ȃ��v�ƌ����Ă���悤�ɂ������Ȃ������B
�@��R�̖��Ƃ��āA����15�N�x����V���G�������������݂Ƃ��ĕ��ʎ��W�����{�����ہA���ʂ̒蒅�[�u�Ƃ��āA���ڔ������鎑�������i�Î��A�r���A�ʁA�߯����فA���p�b�N�A�_���{�[���j�͎萔����Ə��������Ƃ��Ă��܂����B�������A�������Ǝ҂̒��ɂ́A���т͔����Ė������̂����r���A�c�ƍs�ׂŏo�������e����A�����Ŕ������Ă���҂������肵���̂ŁA�����P�W�N�x����́A���̎������������̎萔���Ə��̍����폜���Ă�������B�Ȃ��Ȃ�{���A���Ɗ����ɂ���Đ�����S�����A�K���X�����A�p�v���X�`�b�N�ނ́u�Y�Ɣp�����v�ł��邩��A�u�����Y�p�v�Ƃ��Ă����{�݂ł͏������Ȃ����̂ł���B�����A�����̏����̕��@�ɂ��A��������L�����ɕς��邱�Ƃ��ł��邩�����ꂵ�Ă��邾���ł���A�������Ǝ҂ɂƂ��Ắu���݁��p�����v�Ƃ����F���ł����Ȃ��B����Ȃ�u���݁v�Ƃ��ėL���Ŏ����ق����A�Ó��ƍl����̂ł���B
�L���ɂ��邱�Ƃɂ���āA���ƎҎ��g���RR��^���ɍl���Ă���邱�Ƃ����҂��Ă���B
�����̂܂܂��ƁA���܂ł����Ă����Ǝ҂̂RR�̊��N�͑������Ȃ��Ǝv������ł���B
�܂��A���������݁i�V���A�G���A���ށj���������邽�߂ɔ����������Ǝ҂��Q�Ђ������Ƃ����ꍇ�A����͎������Ƃ��Ď����Ă����̂Ŗ����ŁA��������̏��������邽�߂Ɏ����Ă������Ǝ҂͗L���ɂ���B�Ƃ����̂��������Ɍ�����s�������ł���ƍl����B
���Ǝ҂́A���������������ɂł���Ƃ��Ă��Ă��A���ۂ́u���݁v�Ƃ��āu�����v�����������߂Ɏ����Ă���̂ł���A�����̔��f�Ŏ��������悤���j�Ӗ��͏ċp���悤���A�u�����v����s�ׂ͓����ł���B���������͖����ɂ��A����͗L���ł͕s���E�s���ݍs���ɕs�M����������錳�ł���B����䂦�ɁA�ƒ낲�݂̔r�o���[���ł͎������Ƃ��ăX�e�[�V�����ɏo���Ă��Ă��A���ڔ������ꂽ�ꍇ�́A�����L���Ƃ���̂��K�ł���Ɣ��f������̂ł���B�������A���Ǝ҂��s���ł��邱�Ƃ���A���������s�̕��ʂɋ��͂��Ă�낤�Ƃ���Ă��鎖�Ǝ҂̍D�ӂ��ɂ��ł��Ȃ��̂ŁA�������Ǝ��������i�V����G���A�_���{�[���̌Î��A���邢�͊ʁE�т���敪�����Ď��������Ƃ��ďo���Ă�����������̂Ɍ���B���ڂ��݂͎��������Ƃ݂͂Ȃ��܂���B���邢�͏ċp��������]����镨�����������Ƃ݂͂Ȃ��܂���B�j�Ƃ��āA������ꂽ��ԂŁA�������Ǝ҂����������Ƃ��Ă̈ӎv�����������̂ł���A��L�̂悤�Ɏ��ƌn��ʂ��݂��R�������̎萔���ň����悤�ɂ������Ǝv���܂��B
���ۂ̘b�A�����������Ǝ҂��疳���Ŏ����A����邾���y�b�g�{�g���̂ӂ�����Ƃ�ʂ̈��k��ƁA�т�̃J���b�g�H��ւ̔�����ƁA�Î��̔��o�ȂǂŁA�����̌o��������Ă���A���̕����Ԏ��ł���Ƃ������Ƃł��B���Ǝ҂���������鎑�������Ŏ��v���������Ă���Ƃ������Ǝ҂̉��������܂�������Ȍ������͎��Ԃ��炵�āA��ԈႢ�ł��B���{�݂Ƃ��ẮA���Ǝ҂���̎��������Ȃ�Ă���Ȃ��̂ł��B�u�����B�Ŏ��ȏ������Ă��������v�ƌ��������̂��{���ł��B������䖝���āA����悤�Ƃ��Ă���̂ł�����A�E�E�E�E�E�Â��ł��ˁB�{�s�̍s�����B��Q�N���[���Z���^�[�ł́A���Ǝ҂̎��������̔����ɍۂ��ẮA���{�݂ł́A�L���E�����̔��f���������Ȃ��̂ŁA���ۂŎ萔���Ə��̋����������悢�̂ł͂Ȃ����B�Ǝ咣�������A���܂��ɁA�������Ă���̂ł��낤���B������̐��|��d���݂Ɠ����ł͂Ȃ����B����ɂ̓}���Ƃ����������ɁE�E�E
���s�̎Q�l��ł́A��R�s�́A�S�Ė{���ŗL���ɂ��邩�����̌��Ƃɂ��邩���f���Ĕ����҂��ׂĂɋ����o���Ă���A�����{�݂ɉ^�э��ނ悤�ɂ��Ă��܂��B�܂��A�L��̎����g������PFI�ł̉^�c�����Ă��鏈���{�݂͂����ƃV�r�A�ȑΉ��i�����ƌn��p�ɎY�p���������Ă���Ύ����ċA�点�铙�j�����Ă���悤�ł��B�܂��ߗׂ̎s���̏Z��������A�u�ߍ]�����s�̂��݂Ɋւ���w���͊Â���낢�B������r�o���[����������Ǝ���Ȃ��̂�v�Ƃ͂悭�������t�ł��B����ɓ����Ă��̂��Ƃ��悭������܂����B���ہA���W�ɂ��돈���ɂ���V�r�A�����i�łȂ��̂ł��B���������u����������v�Ȃ̂ł��B���̂��Ƃ��s���ɂ��ݏo�����[�������Ȃ��������ő�̌����ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���̂ł��B�ł�����A���̍ہ��萔�����ו������Č������Ƃ����@��ɁA���݂̕��ʂ�r�o�ɂ��Č��i�ɂ��āA���Ȃ��҂ɂ̓y�i���e�B��^���邮�炢�̌��������p�z�[�}���X���邱�Ƃ��K�v�ł���悤�ɍl���܂��B����ŕ��͋C�Ƃ��Ċ����Ă���͎̂s���́A�����ƌ��i�ȏ��u�₲�ݏ����{������҂��Ă���悤�Ɏv���܂��B
����18�N4������_���{�[�����������݂ɉ��������ɂ��A�����悤�Ȃ��Ƃ��N����܂����B�R���݂Ƃ��ďo����Ă����_���{�[������炸�ɒu���Ă������̂ł����A���{�݂ւ̎s������̖⍇���ɑ��āA4������́u�������݁v�Ƃ��ďo���悤�ɂȂ�܂����Ɛ�������Ɣ[�����Ă����l����ł���A�t�ɁA�u����Ő�����A����ł����v�Ƃ��J�߂̌��t�܂ł����Ă��ꂽ�肵�܂����B�����A�̐S�̊��ۂ̂ق��ł́A���ɉE���������ċ���ɂ́A�R���݂Ƃ��ďo���ꂽ�_���{�[����s�R���݂̓��ꕨ�Ƃ��Ďg��ꂽ�_���{�[���͂��ׂĉ�����Ă���悤�ɂƂ̎w�����o���������o�܂�����B����Ȃǂ͌���̏�m��Ȃ��҂̓T�^�I�ȗ�ł���B���Ǝ҂���̎��������̈����ɂ��Ă����l�̉߂��͂������Ȃ��B���{�݂Ƃ��ẮA���Ǝ҂���̎��������͗L���ň���肽���Ƃ��������v��������B
��S�̖��Ƃ��āA���ꂩ��̏z�^�Љ���ǂ��`�����Ă����̂��Ƃ����r�W������
�S���s�Ƃ��Ď�����Ă��Ȃ����Ƃ����ł���B����������A�V�{�݂ɂ��킹�ėL�������܂߂����W���@���������Ă����A�Ƃ��������ɂȂ���̂ł���B�i���ɂ����邪�A�C�ɑ������킹��Ƃ����A�S�����t�Ȕ��z�����o�Ă��Ȃ��̂ł���B
�ʏ�A�C���ɍs���Ƃ��A���[�L���O�ŗ����d���p�Ȃ̂��A�J�W���A���ŗ����̂��A���邢�̓X�|�[�c�̂��߂̃V���[�Y���̂����炢�́A���߂Ă��甃���ɍs���̂����ʂł��낤�B������C�����肩��g���������߂�Ƃ����̂́A�Ȃ锭�z�B
�@����́A�Ƃ������Ƃ��āA�RR���i��MOTTAINAI�^�������������Ď�g�݂��Ȃ���Ă��錻�݁A�ƒ낲�݂̗L�����͂������̂��ƁA���Ƃ��݂ɂ��Ă�����u����K�v������B���̂����ŐV�{�݂̐v�E�{�s�������v�悪����Ă�����̂ƍl����B
�@��N�x�i17�N�x�j�Ɋ��ۂɒ�N���Ă���u����}�̃`�b�v���v���Ƃ�u�p�v�����e�탊�T�C�N���ŋ`�����ۂ����Ă���v���X�`�b�N���e�����g���C���v�̎���������Ȃǂ������Č�������ׂ��ł͂Ȃ����낤���B���Ǝ҂ɋ��߂錸�ʉ��E�������̊��҂͑傫���B���W�܂̗L�����Œ��ڂ��W�߂��u�e�탊�T�C�N���@�v�̉������T���Ă��邱�Ƃł͂��邵�B�����������A���O�̏�����܂����z�@�̊�{�ɉ������r�W������{�s�Ƃ��Ăǂ̂悤�Ɏs���⎖�Ǝ҂Ɏ����Ă����̂��B����̔p�����s���̂����������Ă���Ƃ���ł���B
�@�@�@
| �@�@�@�@�@���@�@�݁@���@���@�ʁ@�́@���@�� | ||||||||||||
| �@ | �P�ʁF�� | |||||||||||
| �{�ݖ� | ���@�@�@�� | �@�敪 | 10�N�x | 11�N�x | 12�N�x | 13�N�x | 14�N�x | 15�N�x | 16�N�x | 17�N�x | ||
| ��Q�N���[�� | �R���� | �� �@ �c | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| �@�@�Z���^�[ | �� �@ �� | 18,535 | 19,102 | 19,830 | 19,275 | 16,655 | 16,344 | 16,021 | 16,043 | |||
| �� �� �� | 3,561 | 3,526 | 3,938 | 5,348 | 7,155 | 7,722 | 7,530 | 7,655 | ||||
| ���� | �ƒ�n | 780 | ||||||||||
| ���ƌn | 6,875 | |||||||||||
| �� �@ �v | 22,096 | 22,631 | 23,769 | 24,624 | 23,811 | 24,069 | 23,551 | 23,698 | ||||
| �s�R���� | �� �@ �c | 1,361 | 1,303 | 1,254 | 1,293 | 1,265 | 1,297 | 1,203 | 1,129 | |||
| �ρ@�� | ||||||||||||
| �� �� �� | 1,162 | 1,107 | 1,173 | 1,001 | 1,042 | 794 | 542 | 463 | ||||
| ���� | �ƒ�n | 268 | ||||||||||
| ���ƌn | 195 | |||||||||||
| �� �@ �v | 2,523 | 2,410 | 2,427 | 2,294 | 2,307 | 2,091 | 1,745 | 1,592 | ||||
| �e�傲�� | �� �@ �c | 47 | 19 | 46 | 19 | 19 | 19 | 18 | 21 | |||
| �ρ@�� | ||||||||||||
| �� �� �� | 517 | 588 | 745 | 414 | 428 | 720 | 910 | 957 | ||||
| ���� | �ƒ�n | 493 | ||||||||||
| ���ƌn | 463 | |||||||||||
| �� �@ �v | 564 | 607 | 791 | 433 | 447 | 739 | 928 | 977 | ||||
| �������� | ���c | �V�@�� | �[ | �[ | �[ | �[ | �[ | 266 | 297 | 323 | ||
| �G�@�� | �[ | �[ | �[ | �[ | �[ | 108 | 116 | 121 | ||||
| �ϑ� | �r �� | 511 | 504 | 477 | 453 | 415 | 501 | 490 | 472 | |||
| �J �� | 255 | 243 | 236 | 213 | 198 | 142 | 133 | 123 | ||||
| �߯����� | 49 | 66 | 73 | 88 | 101 | 107 | 123 | 131 | ||||
| ���p�b�N | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 19 | 18 | 17 | ||||
| �����ݎ��� | 13 | 11 | 12 | 26 | 26 | 22 | 21 | 31 | ||||
| �� �v | 846 | 838 | 813 | 795 | 755 | 1,165 | 1,198 | 1,218 | ||||
| �� �v | 26,029 | 26,486 | 27,800 | 28,146 | 27,320 | 28,064 | 27,422 | 27,485 | ||||
| �ŏI������ | �{�ݎc�� �@ | �[ | �V������ | 3,359 | 3,035 | 3,706 | 3,349 | 3,466 | 3,353 | 3,215 | ||
| (��1�E2�ذݾ����E�����j | ||||||||||||
| �� �� �� | 1,837 | 400 | 270 | 400 | 285 | 376 | 279 | 446 | ||||
| �� �@�v | 1,837 | 3,759 | 3,305 | 4,106 | 3,634 | 3,842 | 3,632 | 3,661 | ||||
| �t�F�j�b�N�X�i���p�E��艫�j | 3,237 | �[ | �[ | �[ | �[ | �[ | �[ | - | ||||
| �� �@�@�v | 5,074 | 3,759 | 3,305 | 4,106 | 3,634 | 3,842 | 3,632 | 3,661 | ||||
| �� �@���@�@�v | 31,103 | 30,245 | 31,105 | 32,252 | 30,954 | 31,906 | 31,054 | 31,147 | ||||
| ���������݂̈ϑ����W�y�сA�V���E�G���̕��ʉ���́A�����P�T�N�x�����{�B�@�@�@�@������18�N�x�����W�S�ʈϑ� | ||||||||||||
| ����17�N�x | �i���j | ���W | ������ | ���v | ||||||||
| ���ԏ����� | 17,193 | 9,075 | 26,268 | ����17�N�x�̑����ݔr�o�ʂ́@�@�R�P�C�P�S�V�� | ||||||||
| �ŏI������ | 3,215 | 446 | 3,661 | �l���i68842�l�j1�l����N�S�T�R�����A�̔r�o�B | ||||||||
| ����ػ��ٗ� | 1,187 | 31 | 1,218 | 1���сi25000���сj���ƔN�P�Q�S�U���� | ||||||||
| �v | 21,595 | 9,552 | 31,147 | 1�l1�����肾�ƂP�Q�S�O���ƂȂ�B | ||||||||
| �����P�V�N�x���Z������ | (�P�ʁG��~) | �����P�V�N�x�̂��݂P��������̌o�� | ||||||||||
| ���|������ | 152,925 | ����ް�A�����֘A�A�l���� | ���v�o������ݔr�o�ʁ�30�~/kg | |||||||||
| ���ݏ����� | 768,528 | ���W�E�����o�� | ���v�o������ݔr�o�ʁ�42�~/kg | |||||||||
| ���v | 921,453 | |||||||||||
| �N���ҕ� | 363,321 | ���ݏ����o��Ƃ���1������@�R�C�T�P�X�C�X�Q�X�~���������Ă���B | ||||||||||
| ���v | 1,284,774 | 1�l����̔N�o��́A�S�T�R�����~42�~/kg=19,026�~ | ||||||||||
| �萔�������Ǝ������ݔ��p����Ƃ��āA123,000��~�̍Γ����Z������ | �E�E�E�E | �@�Γ��������������v�o������ݔr�o�ʁ�38�~/kg�@�Γ�����������1�l����̔N�Ԃ��o��P�V�C�Q�P�S�~�����̌v�Z�͓Ɨ��̎Z���ł͂Ȃ��̂ŁA����_�ł��B | ||||||||||
| ���ƒ낲�݂̗L���w��ܐ��x�����̌��� | ||||||||||||
| 1���сi�Q�C�V�l�j�Ƃ��ĂP�O��������S�Tد�ّ܂P�Q�T�����K�v | ||||||||||||
| 1���сi�Q�C�V�l�j�łT�P�C�R�V�P�~��125���Ŋ����1���S�P�P�~�ƂȂ�B | �E�E�E�戵�萔��5%�����l�������1���S�S�O�~���Ó��ȉ��i�ݒ� | |||||||||||
| �����ƌn���݂̗L���w��ܐ��i���Ǝҗp���ʎw��܁j�����ɂ��� | ||||||||||||
| �R���݂S�Tد�ّ܁i10�����j1���U�O�O�~�A�s�R���݂W�O�O�~�A�������݂T�O�O�~�E�E�E���ȁH | ||||||||||||
![�e�L�X�g �{�b�N�X: ����́A�������s�����ߍ]�����s�Ɏ������Ƃ���
�o�������̂ł��B�@����������@�r�o�ҁ@���@��
�E�E�E�������̎�������֎~���܂��E�E�E�E](image002.gif)

