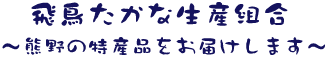|
|
| 「たかな」について |
起源
この地方の「たかな」の起源には諸説ありますが、一説には、古代に九州から大和へと古代朝廷(神武天皇)が移ったのに伴い、九州からもたらされたと伝えられています。
エピソード
古くから、塩漬けした「たかな」の握り飯が郷土料理として伝わっています。これに関しては、15世紀の南北朝時代末期に、吉野から追われ現在の熊野市五郷に逃れた南朝の王族を、地元民がたかの握り飯でもてなしたという言い伝えが残っています。
また、江戸時代中期の歌舞伎「伊勢音頭恋寝刃」の中に、主人公「油屋のお紺」に「たかな寿し」を作って持たせたという話もあり、古くからの伝統食であることが分かります。
たかなの品種について
三重のたかなには、「赤大葉高菜」と「三重緑辛1号(青大葉高菜)があります。両者とも熊野市内で生産されていますが、飛鳥「たかな」は前者の赤大葉で、葉の表側が赤紫色をしています。青大葉に比べて辛味が強く、ワサビや大根おろしのようなピリッとした辛さがあります。
飛鳥「たかな」でご飯を包む際手が紫色になりますが、これは着色しているからではなく、赤大葉の特徴です。この特徴を活かして、染物もおこなっています。
|
|
栄養について
「たかな」は、緑黄色野菜の一種でβカロチン、ビタミン、ミネラルを豊富に含んでいます。
βカロチンは、活性酸素や過酸化資質を除去して細胞を活性化する作用があり、老化防止にも効果があると云われています。
また、最近の調査では、アントシアニンという色素を多量に含み、高い抗酸化力を有していることが分かってきています。
|
 |
100グラム当たりの栄養素含有量
βカロチン 2300μg
エネルギー 45kcal
カルシウム 280mg
たんぱく質 4.1g
ビタミンC 67mg
ナトリウム 1700mg
脂質 0.4g
炭水化物 6.3g
他の食物と比べると・・・ |
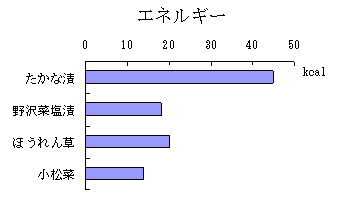
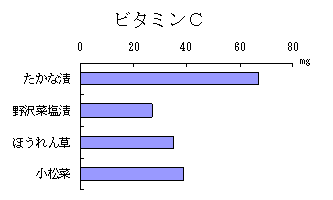 |
たかなの食べ方
めはり寿し
たかな漬けでご飯を包んだおむすび。各家庭それぞれで工夫したご飯をたかな漬けで包んで食べます。
お漬物
漬物としてもいい味なので、刻んでそのままというのもおいしい。ピリッと辛いたかな漬けは、ご飯の友として最高です。食欲がない時でも、このピリリとした辛味が食欲をそそります。
その他、様々な料理に活かせます。
|

|
美し国「三重の伝統野菜」に
「たかな」が選ばれています。
|
|
飛鳥の「たかな漬け」は、
東紀州たかな漬けとしてEマークの認定品です。
Eマークとは
食の安全・安心への関心が高まるなか、地域で生産され、原材料や製法など素性が明らかな食品が注目されています。
こうしたことを背景に、各都道府県では、地域の原材料の良さを活かして作られた「地産地消タイプ」の特産品に「Eマーク」を与えています。 |
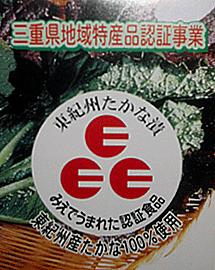 |
|
|
|