TEL. 059-235-0536
��514-0817 �O�d���Îs���������X�������R1732-11
���j�Ɖ��v
�_�o��y�n���Nj掖��N�\
| ���@�@�@ �� | �� �@�� | �� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� |
| ���� �R�N | �P�U�S�U | �ɐ�����ё��� ���������q���_�o�䐅�J�w�ɒ��� |
| �c�� ���N 7�� | �P�U�S�W | �_�o�䐅���� ����7,200�� �_�o�������}�䖔���q�����ɔC�� �_�o�䐅�Ǘ��X���𐧒� |
| ���� �S�N | �P�U�T�W | �_�o�䐅�Ǘ��u����X�v���� |
| ���� �W�N | �P�U�W�O | �_�o�䐅�Ǘ��u��v���� |
| ���� 12�N | �P�W�V�X | �l�b�앪����菑���� |
| �@�@ 23�N | �P�W�X�O | �����g����ᐧ�� |
| �@�@ 24�N | �P�W�X�P | �_�o�䕁�ʐ����g���n�� |
| ���a 16�N | �P�X�S�P | �_�o��p���H���C�H������ |
| �@�@ 19�N | �P�X�S�S | �哌���푈�̉e�����H�����f |
| �@�@ 24�N 6�� | �P�X�S�X | �y�n���ǖ@���� |
| �@�@ 26�N 3�� | �P�X�T�P | �y�n���Nj�ɉ��g �˖A�{���A�_�o��ɉ��� |
| �@�@ 27�N 9�� | �P�X�T�Q | �_�o��y�n���Nj�A������ |
| �@�@ 28�N | �P�X�T�R | �_�o�쉈�ݗp�����ƂƂ��ĉ_�o��p���H���C�H���ĊJ |
| �@�@ 28�N 9�� | �V | �䕗�ɂ�����n����h���� |
| �@�@ 29�N | �P�X�T�S | �V�ƍ�z�n���p���H������ |
| �@�@ 30�N11�� | �P�X�T�T | �ؑ�������ݒu |
| �@�@ 32�N11�� | �P�X�T�V | �˖A���˖A�{���A�p�����ݒu ����H���C�ɒ��� |
| �@�@ 35�N 3�� | �P�X�U�O | ����H���� ��r���H���C |
| �@�@ 40�N 4�� | �P�X�U�T | �N����_�����݂ɒ��� |
| �@�@ 42�N10�� | �P�X�U�V | �䕗34���ɂ�蓪��H���݃u���b�N��� |
| �@�@ 45�N 7�� | �P�X�V�O | �䕗2���ɂ�蓪��H�E�݃u���b�N��� |
| �@�@ 46�N 3�� | �P�X�V�P | �N����_������ |
| �@�@ 46�N 9�� | �V | �䕗29���ɂ�蓪��H�E�ݎ��Ĕ�� |
| �@�@ 47�N 9�� | �P�X�V�Q | �䕗20���ɂ�蓪��H�~���ǔ�� |
| �@�@ 49�N 7�� | �P�X�V�S | �W�����J�ɂ�蓪��H�E�ݎ~���ǔ�� |
| �@�@ 54�N12�� | �P�X�V�X | ����H�쏰�H���C�ɒ��� |
| �@�@ 55�N11�� | �P�X�W�O | ����T�C�t�H���H������ |
| �@�@ 56�N3�� | �P�X�W�P | �@�@�@�@�V�@�@�@�@�@ ���� ����H�쏰�H���� �˖A�n���≺�A�{�����A�]�|������ |
| �@�@ 57�N8�� | �P�X�W�Q | �䕗10���ɂ��q��h�ƐV�Ǝ搅����� |
| ���� 3�N10�� | �P�X�X�P | �Îs�������n���Ɏ������V�z |
| �@�@ 4�N11�� | �P�X�X�Q | ���R�c�n���p���H���C�ɒ��� |
| �@�@ 5�N 3�� | �P�X�X�R | �@�@�@�@�@�V�@�@�@�@�@ ���� |
| �@�@ 5�N | �V | �_�o��p���H���C�H���v����� 57,800���~ �k��6,159�� |
| �@�@ 6�N | �P�X�X�S | �@�@�@�@�V �@�@�@�@�ɒ���@�@ 630,000,000�~ |
| �@�@ 9�N | �P�X�X�V | ���ԏꐮ�� �ʐ�430�u |
| �@�@10�N | �P�X�X�W | �˖A���˖A�V�ƁA�ؑ��A�]�|������ �˖؊|�̋����C |
| ����13�N 3�� | �Q�O�O�P | �_�o��p���H���C�H���v�H�@�@���H����629,324,000�~ |
| ����13�N10�� | �Q�O�O�P | �@�@�V�@�@�@�v�H�L�O���T |
�P�@�J�c ���������q��
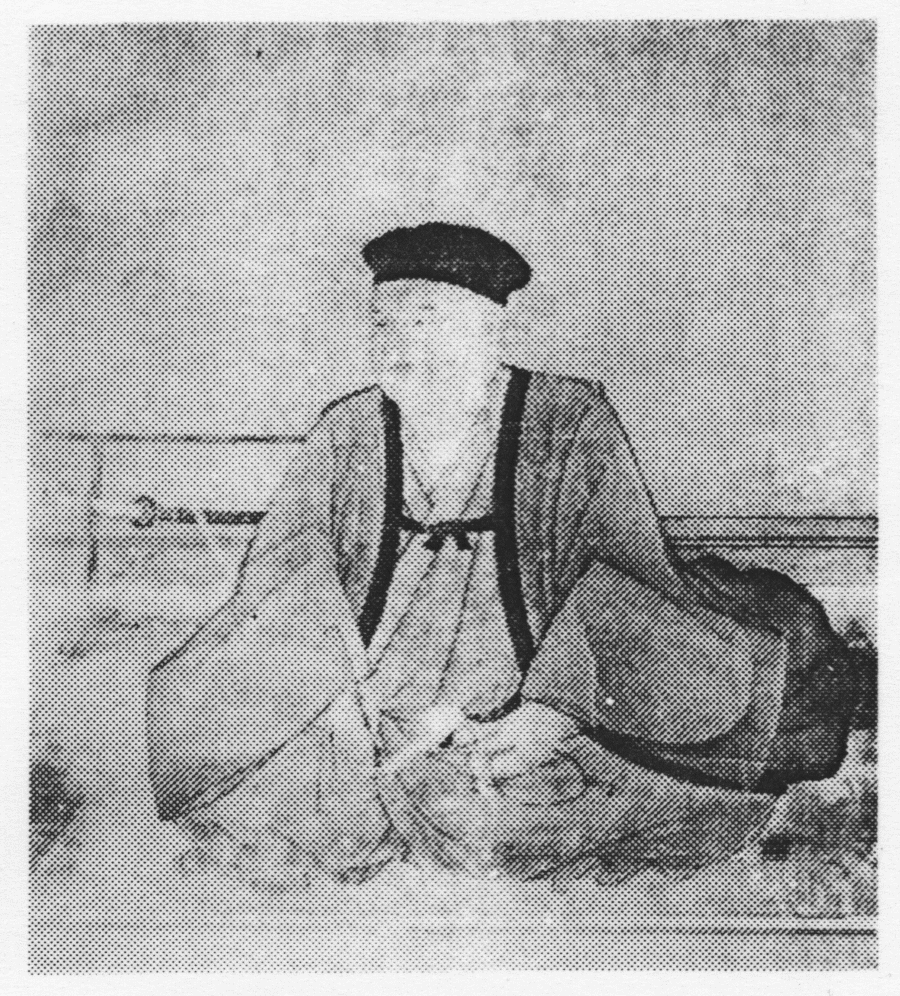
���͔V�F�i�䂫�Ƃ��j�i���Ƃ̖��͔V���i�䂫�܂��j�A���i12�N�i1635�j�V�F�Ɖ��߂��j�A�����q�͒ʏ́B
�c�����N�i1596�j���B�l���ɐ��܂�܂����B
�c��17�N�i1612�j17�˂ňɐ��Ôˎ�i�ɉ���j�������ՂɎd���܂����B
�c��19�N�i1614�j19�˂ő��~�w�A���a���N�i1615�j20�˂œ��Đw�ɏ]���đ��������A���a5�N�i1619�j24�˂œ��쎁�����s�����z���̍ہA���Ղ�薽�����Ă��̐}�ʂ������A�܂����N�A����C�z�̍ہA���̌��ς������o���čH���ɏ]�����A���̎�r��F�߂��܂����B
�X�Ɍ��a7�N�i1621�j26�˂̂Ƃ��A����r36�˂ŕa���A���̎k�q���r11�˂ŏP���A���̂��ߐ��r����̌�Еt�������Ղɖ������A�]��ɔh�킳��܂����B
���i2�N�i1625�j�]��̍��̑��鯂ɍۂ��A���Ռ��̊O�������ˎ傩��̐\���ɂ��A���i16�N�i1639�A44�ˁj�܂�15�N�Ԏ]��˂ɋq�b�Ƃ����ق����A�S���̂��Ƃ�����A���ߘ\�ܕS�ł���܂������A���i6�N�i1629�j7���ɂ͘\��ܕS��^�����A��7�N8���A�ܕS�Α�����Ę\�����������A����̂ق��S�C30�l��V�c270���������܂����B
���̊ԁA���r�����C������V�݂��邱�Ǝ���95�����A���ʐ�2,200�����ɋy�т܂������A���̍ł������Ȃ���̂́A���̗L���Ȗ��Z�r�̉��C�H���ł���܂����B���̂ق��A������̐��H�̕t�ւ��������ʂł����������т��c���܂����B
���i16�N�i1639�j�]����A����A��18�N�i1641�j46�˂Ŗ����ɂ��]��Ɍ��킳��A��19�N�i1642�A47�ˁj�y�ѐ���3�N�i1646�A51�ˁj�̑��鯂ɍۂ��A�����˂̖��ɂ��ɐ��A�ɉ�̗̓�������A�Ԃ��ɂ��̎S������@���A�䉁�̉��ǁA�a���̊J�w�A���r�̉��C���s���܂����B���̑�Ȃ���͈̂�u�S�_�o���y�ш��R�S�R���V�c�̊J�w�ŁA�_�o���ł͐��������q���̈⓿���ÂсA����(�݂��܂�)�_�Ђ����������J��܂����B
�c�����N�i1648�A53�ˁj�A��a��s�i�R��A��a�̖��{�J��̌ܖ��Ύx�z�j�ƂȂ�A�������N�i1658�A63�ˁj�ɉ��s�ɓ]���A�ɐ����ɉ�Ɉڂ�܂������A��C�̏�a��s���S�̂��ߍĂя�a��s�ɕ��E�A����4�N�i1676�j81�˂Ŏ��E����܂ŁA29�N�ԑ傢�Ɏ��т��グ�܂����B���E��͈ɉ���ɉB���A�ى��ƍ����A�����ɐe���݂܂������A����8�N�i1680�j3��20���A85�˂ŕa�f���A���s�i���݂̈ɉ�s�j�������������ɑ����܂����B
�@���͎ߒq�����m�i���Ⴍ�������j�Ƃ����B
�s���������q�V�F����N�\�t
| �V�c | ���� | ���� | ���@�R | �ˁ@�� | ���@�@�@�@�� |
| ��z�� | �c���� | �P�T�X�U | �L�b�G�g | ���B�l���ɂďo�� �i���ߔV�ށA���i�P�Q�N�Ȍ�V�F�j |
|
| �㐅�� | �P�V | �P�U�P�Q | ����G�� | �������� | �ɐ��Ôˎ員�����ՂɎd����i�P�V�ˁj �\�P�T�O�� |
| �V | �P�X | �P�U�P�S | �V | �V | ���~�w�ɏ]���i�P�X�ˁj |
| �V | ���a�� | �P�U�P�T | �V | �V | ���Đw�ɏ]���i�Q�O�ˁj �\�Q�O�O�� |
| �V | �T | �P�U�P�X | �V | �V | ���s�����z���A����C�z�̍H�ɏ]���i�Q�S�ˁj �\�R�O�O�� |
| �V | �V | �P�U�Q�P | �V | �V | ����r�a���ɕt���̌�Еt���ɗ��]�i��1�� �Q�U�ˁj �\�S�O�O�� |
| �V | �X | �P�U�Q�R | �V | �V | �\�T�O�O�� |
| �V | ���i�Q | �P�U�Q�T | ����ƌ� | ����r | ����˂ɏo�d�̂��ߗ��]�i��Q��j ���̔N�ω����s�o�c���o�݉Ƃ̎��c�����ǂ��_�Ƃ��ڏZ�����ށi�R�O�ˁj |
| �V | �S | �P�U�Q�V | �V | �V | ����S���쒬�쓌�����r�A�����s�암�����c�r�A��o�s���]�����]��r��z�� �ؓc�S�O�ؒ��X��R�厛�r�z���ɒ���i�R�Q�ˁj |
| �V | �T | �P�U�Q�W | �V | �V | �����x�S���Z���g�얞�Z�r�����ɒ��� �ؓc�S�O�ؒ��X��R�厛�r�v�H �����s�O�J���O�J�r���z �O�L�S��������{���ےr��z���i�R�R�ˁj |
| �V | �U | �P�U�Q�X | �V | �V | ���̔N�]�˂Ăі߂���\�P�O�O�O�� �Ԃ��Ȃ��]��ɏo���i��R��j �ω����s�L�c���r�K�m�r���z�i�R�S�ˁj �\�P�T�O�O�i�O�ɓS�C�҂R�O�l�j |
| �� �� | �V | �P�U�R�O | �V | �V | �O�L�S���������␣�r���z �ω����s���䒬���r���z�i�����R�T�ˁj �\�Q�O�O�O�i�O�ɓS�C�҂R�O�l�A�V�c�Q�V�O�j |
| �V | �W | �P�U�R�P | �V | �������� | ���Z�r�������� �����x�S���Z���Y�����T�z�r�z���ɒ���i�R�U�ˁj |
| �V | �P�P | �P�U�R�S | �V | �V | �ω����s���c�䒬��m�J�r�z���ɒ��� �i�R�X�ˁj |
| �V | �P�Q | �P�U�R�T | �V | �V | �ؓc�S�R�c�����A�c�_�Г��r��z�� �i�S�O�ˁj |
| �V | �P�S | �P�U�R�V | �V | �V | �����s��������蓯�V��Ɏ����h��z�� �����s�����A�ؑ��A�t���V�c��� ������̐��H�ւ����Ƃ��������s�j�i���a�V�N�ҁj�̋L������i�S�Q�ˁj |
| �V | �P�U | �P�U�R�X | �V | �V | ��m�J�r���� �O�L�S�܋���֒r���z�ɒ���i�ʂ����j ������ɂċ��]�A�A���i�S�S�ˁj |
| �V | �P�W | �P�U�S�P | �V | �V | �����ɂ��]��̏����ٌ��̂��ߗ��] �i��S�� �S�U�ˁj |
| �V | �P�X | �P�U�S�Q | �V | �V | �ɐ��A�ɉ��ۂɕt�������˂̖��ɂ��̓����@�A�䉁���ǁA�a���J�w�A���r���C���s���i�S�V�ˁj �\�P�O�O�O�� |
| ����� | ���ۂR | �P�U�S�U | �V | �V | �������� �ɐ����ő��� �_�o�䐅�H���ɒ���i�T�P�ˁj |
| �V | �c���� | �P�U�S�W | �V | �V | �V�� �_�o�䐅�����i�����V,�Q�O�O�ԁj ��a��s�ƂȂ�R��A��a�̖��{�J��̌ܖ����x�z�i�T�R�ˁj �S�C�҂R�O�l��a������ |
| �㐼�@ | ������ | �P�U�T�W | ����ƍj | �V | �ɉ��s�ɓ]�������A���N��C�̏�a��s�����̂��ߕ��E�i�U�R�ˁj |
| �� �� | ����S | �P�U�V�U | �V | �V | ��a��s���E�i�W�P�ˁj �ɉ���ɉB�� |
| �V | �W | �P�U�W�O | ����j�g | �������v | ���̔N�R���Q�O���a�f�i�W�T�ˁj �ɉ��썮�����������ɑ��� |
| �V | �P�Q | �P�U�W�S | �V | �V | �����_�Ќ��� |
| �� �� | �吳�S | �P�X�P�T | ���̔N�P�P���P�O�� ���܈ʒǑ� �i����Q�R�T�N�j |
�Q�@�g�D�̕ϊv
�i�P�j �_�o��p���H�̎n�܂�
���i19�N�i1642�j�A�ɐ��̍���u�S��т͋H�Ɍ�����鯂ň�͊F�͎����A���n�͊F���ł���܂����B�����3�N��̐���3�N�i1646�j�ɂ͍Ăы���Ɍ������A�_���͉쎀���O�ł���܂����B���ڔˎ員���������͍]�˂ɍ݂��Ă��̎����A�Ɛb���������q���Ƌ��ɒÂɖ߂�A�����q���ɖ����ė̓��������܂����B�n��̎S������ĉ���������q���́A�ˎ�̋����ĉ_�o�䐅�J�w�̑�H���ɒ��肵�܂����B���̌˖ؑ��ʼn_�o�삩�番�����A���H���@��i�߁A�������Ő���3���i�����䤔�����g�a�j���āA�������A�_�o�n��܂ŖԂ̖ڂ̂悤�ɗp���H���߂��炻���Ƃ�����̂ł���܂����B
�H���͑��l�B�̐l�͂ɂ��A�����q���͐w���ɗ����Ďw���ɓ�����܂����B�y�n�̍���𑪂邽�߁A��Ԃɒ𗧂ĕ��ׂ��Ƃ����G�s�\�[�h�������悤�ɑ�ϓ���H���ł���܂������A�r���ɃT�C�t�H���̌��������p����Ȃǔ����q���̗D�ꂽ�Z�p�Ƒ��l�����̌��̂ɂ��ނ悤�Ȑh��̉ʂāA�c�����N�i1648�j�Ɋ������܂����B���H�̉�����7,200�ԁi13�q�j�ŁA�{���A����A�ɑq�ÂȂlj_�o�̑��X14�P��600�����̓c�������̌b�݂��邱�ƂɂȂ�A�P���߂��̎��n�̓y�n���������̂ł���܂����B
�������A�������̎l�b��Ő���3�����č�������_�o�ɑ���܂������A�����ΐ��̔z���ő������N���܂����B�����q�́A���ʂ��ω����Ă���Ɍ����Ȑ��̔z�����o���Ȃ����̂��Ǝv�Ă��d�˂܂����B������A�Ȃ̏��ւ���p�����Ă͂��ƕG���������܂����B���ւ̎n�܂�ɔA�����E�ϓ��ɂقƂ���܂����B���̌��������p�����̂��l�b�앪���ŁA�Ȍ㑈�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ����Ƃ��`�����Ă��܂��B���b���������͐[�������q�̓����A���N�ɐ��_�{�ɎQ�q���A�_�y���t���喃���Ă��̌��N�Ǝq���ɉh���F��܂����B
���̖v��i1680�j�A�l�b�앪���_�ɐ����_�Ёi���ɔ����q�{�Ƃ����j���������A���ւ̊��ӂƖL����F�肷��ՓT���s�Ȃ��A���̗����A�ʐ����J�n���邱�ƂɂȂ茻�݂Ɏ����Ă��܂��B�l�b�앪���{�݂́A���a47�N6��20���A�Îs����ψ�����j�ՂɎw�肳��܂����B
�s�_�o��̈ێ��Ǘ��t
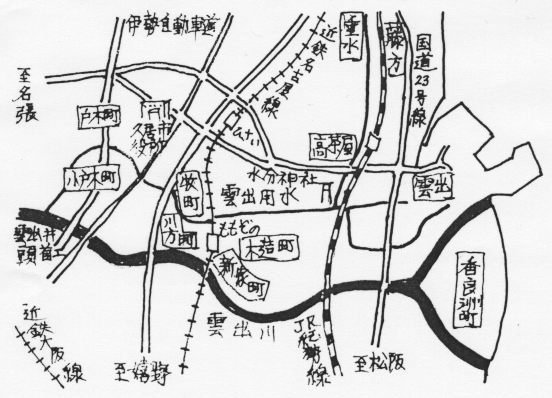
�_�o�䂪��������ƁA���������q�͌c�����N�i1648�j�_�o��������}�䖔���q�����ɖ����āA�p���̊Ǘ��ɂ��čׂ����w�������܂����B
�䐅�́A���r�Ƃ������āA��J�̂Ƃ����ʒ��߂���ŁA�_�o�삩��搅���鐅�ʂ̉������������̊Ǘ�����A�a���炦�A��h�̔j���C���ɂ��Ă���ɒ��ӂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃǎw����^���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�o�p���H
���������q����}�䖔���q�ɏo���ꂽ9�����̂���5�������グ��ƁA���̒ʂ�ł����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�� �������������̂�������Ɍ�A�ׁX�����A���A�ΕU�������n�n�悩�ցA
�@����������Ȃ����A�������쐅�悭�̂�Ƃ��O�����A�t��J
�@�ӂ�\�C�F�Ɍ�n�n�����������̌˂������\�A���i�A�˖ؔV�����q�ɂ�
�@�\�t��ԁA��X���k�d��
�� ����̂����āA���O�Ð얘�̈�a���܂�L�V�ҁA�����f����ւ���
�@�\��
�� �������_�o�܂ł̈�a���܂�A���n�݂����ˌ��L�V�n�A��
�@�̓�����ɏC���d��ւƁA�����X����\�n���A�������Ƃ��ǂ��Ɋ̂������
�@�O����A���䐅���݂���ɂ��₪�ォ���L�V�͑�����֑��́A��܂܂�
�@�����\�ԕ~��
�� �l��̂킯�܂����A�k����`�n�A���̎��X�������\����ԁA��
�@�����ӌ�A������n�n���Ƃ��Ă킯�����\�ԕ~��A���X���k�����܂�\
�@��n�n�}�������։\����
�� �˖��_�o�܂ł̊ԑ���̋`�j�t���Â�̑��ɂĂ��a���d����̉��L
�@�V�ҁA�L�̂ɍ����\����A������̂Ђ����d�ԕ~��
�i�����̓Ǔ_�͓ǂ݂₷���悤�ɕҏW���܂����j
�ƁA����悤�ɉ_�o��̊Ǘ��ɂ��ď����}�䖔���q�Ɏw�����e���X�ōs�킹�܂����B���̌�A����4�N�i1658�j�A����8�N�i1680�j��2��ɂ킽���āA�_�o��苽���ցu����X�v�u��v���o����A������N���̎ɏ������Ė���邱�Ƃ����Ă��܂��B���N�̈䋽���́A�{���A������A�q���A�V�Ƒ��i�ȏ�A���v���s�j�A���X���A��쑺�A�������A�������A�������A���ё��A�_�o�����L����Ă��܂��B
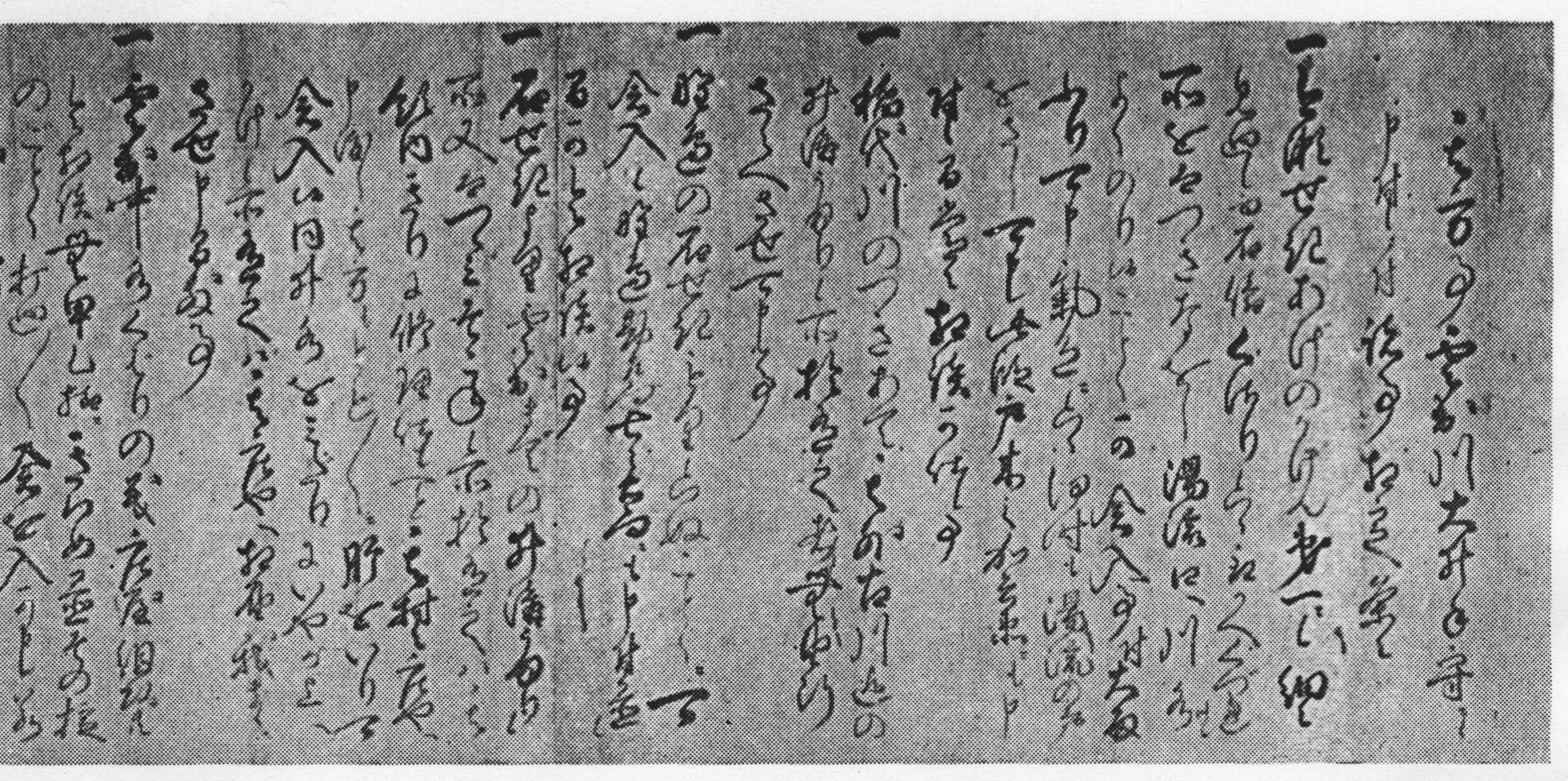
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�o�䐅�|��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�o�{�����@�}��ƕ���
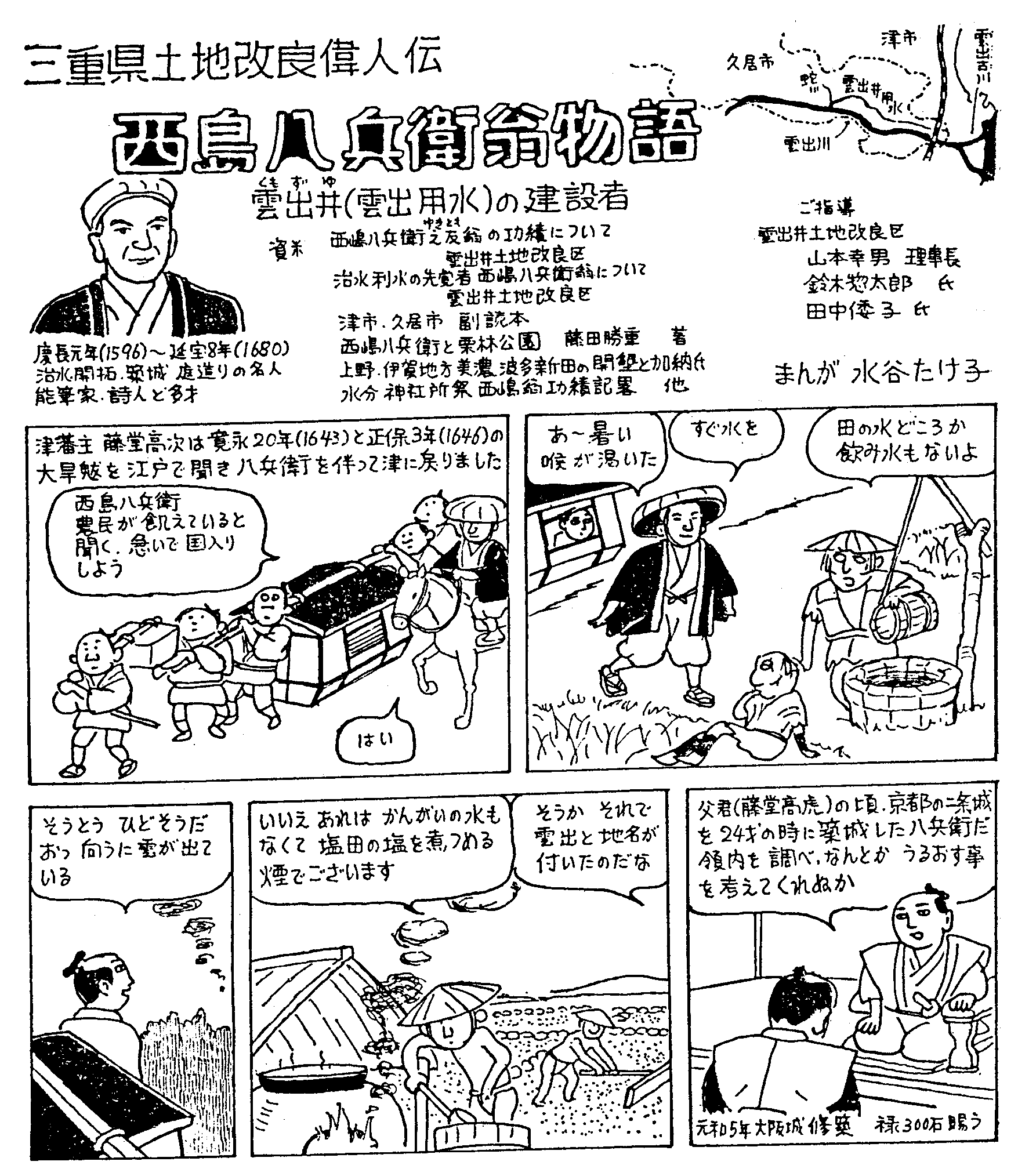
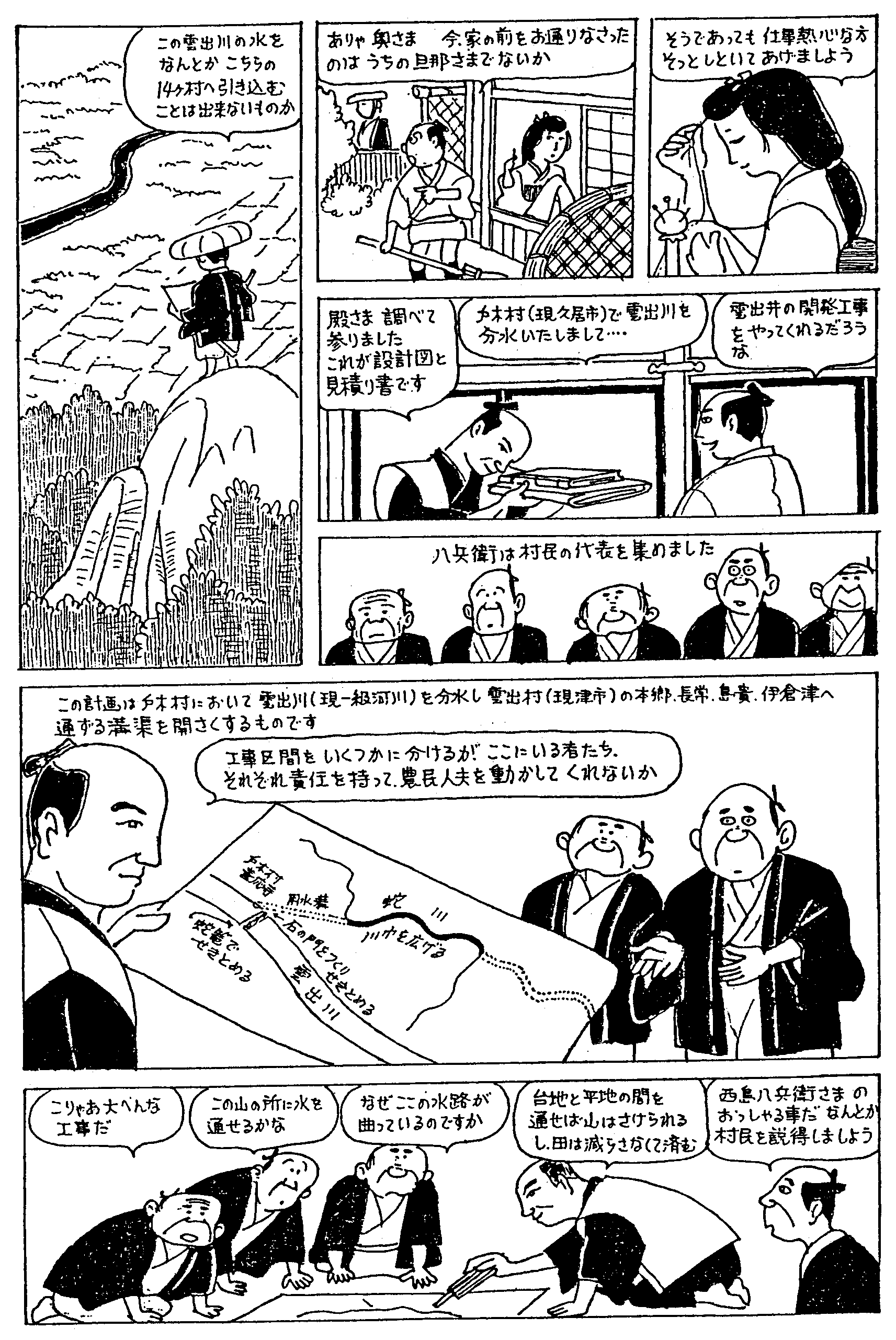
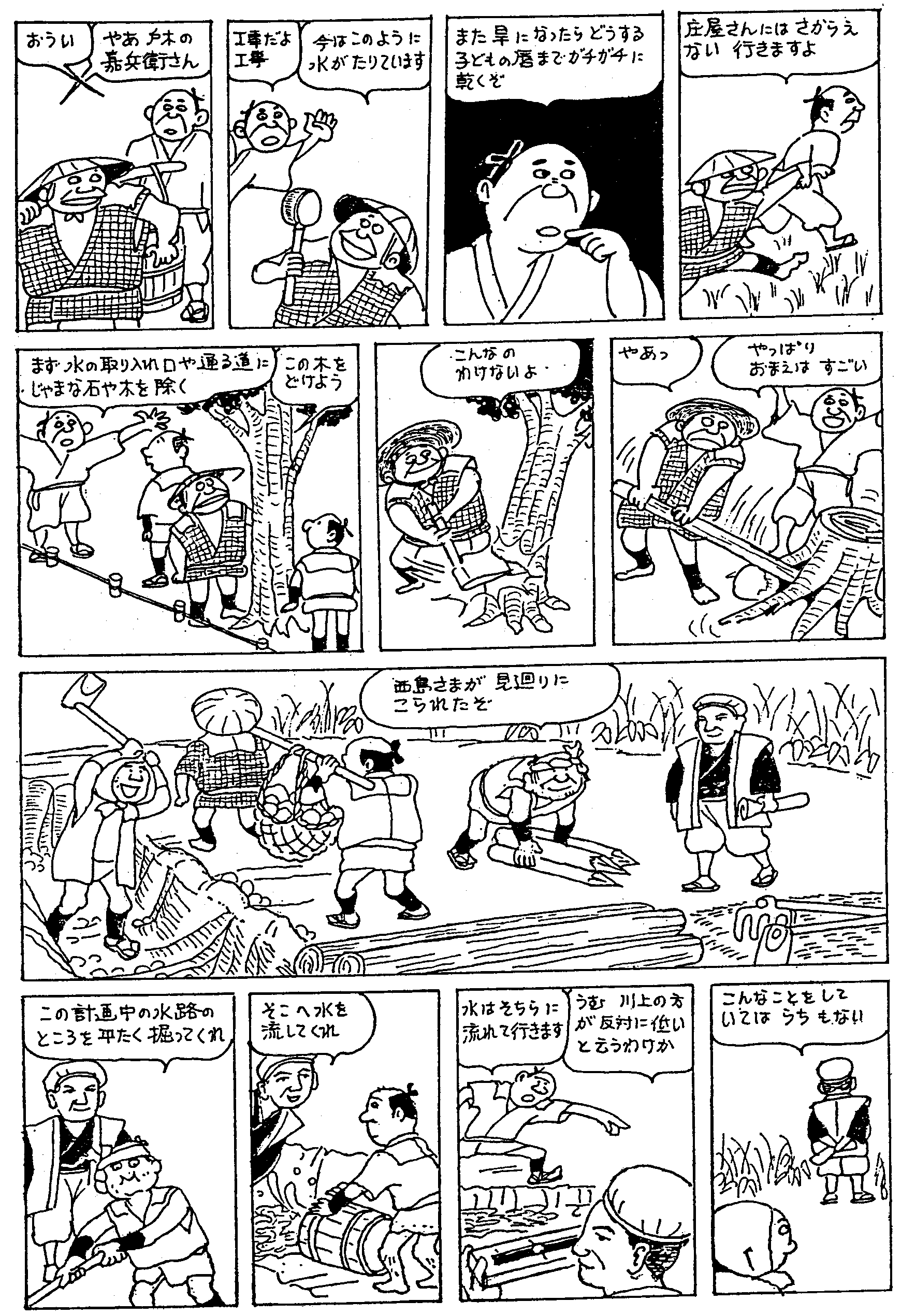
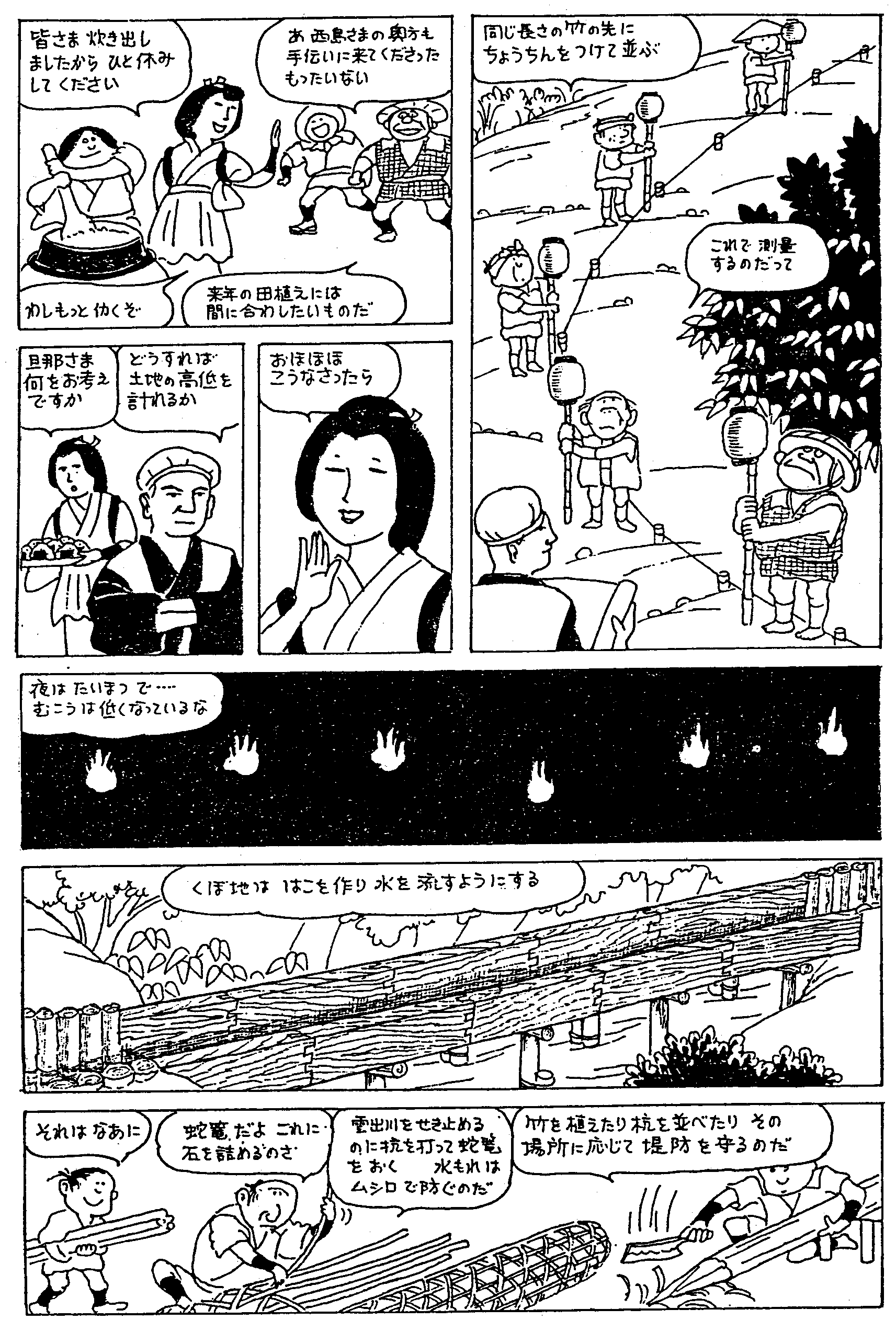
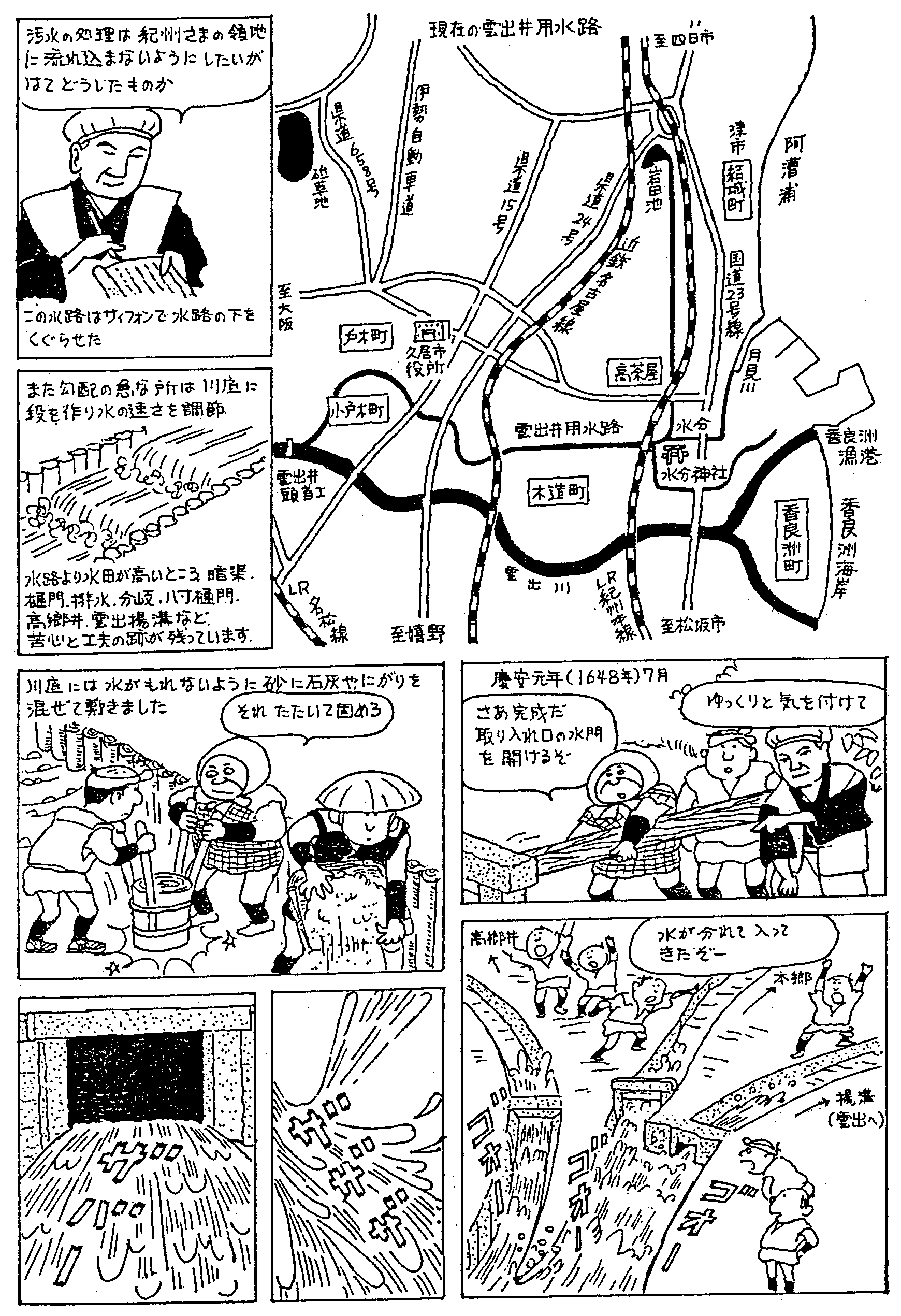
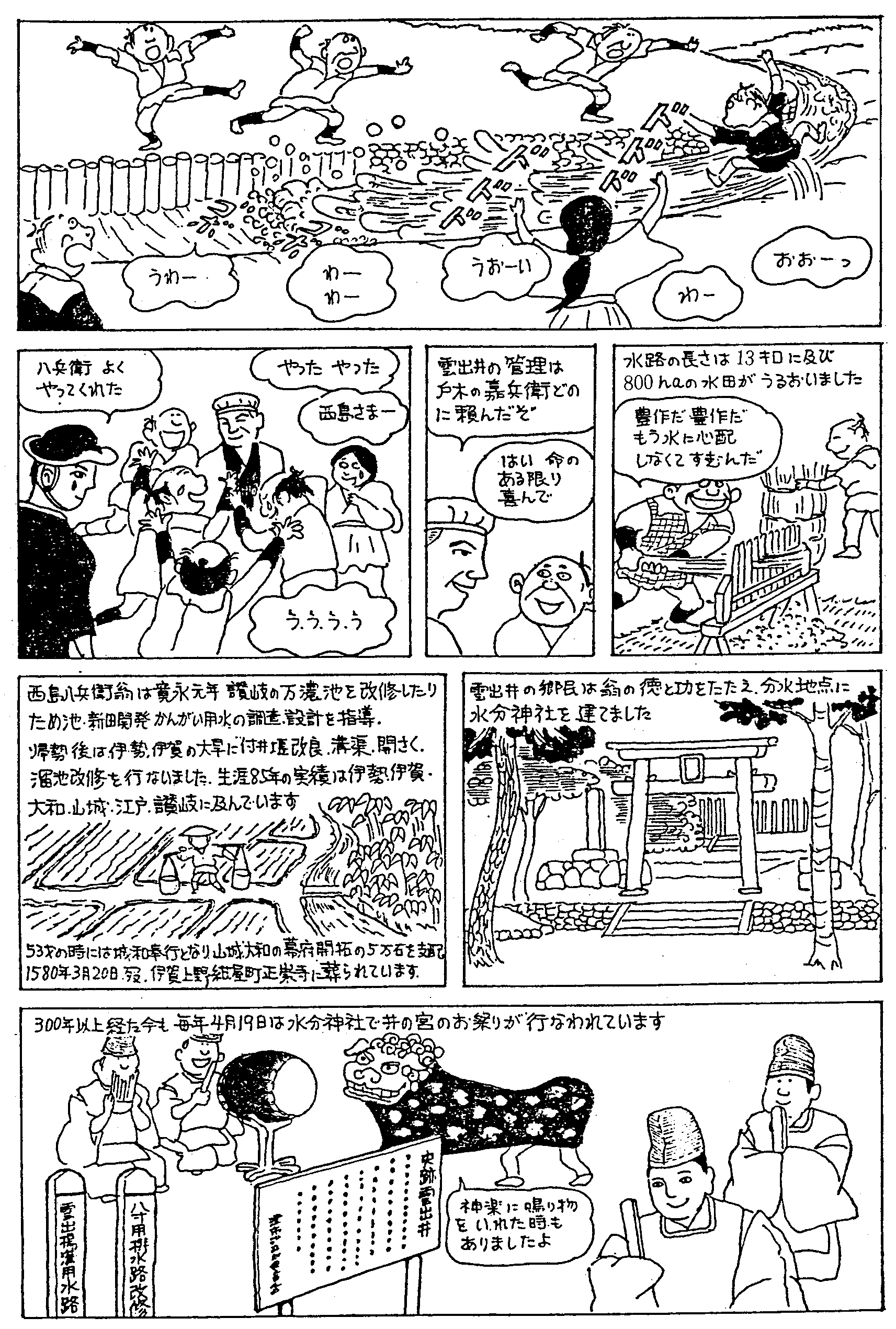
�o�i�[�X�y�[�X
�_�o��y�n���Nj�
��514-0817
�O�d���Îs���������X�������R1732-11
TEL 059-235-0536
FAX 059-235-0537
�ۗL�l�f�[�^�Ɋւ��鎖���̌��\