|
=自叙= ラジオの不思議を求めて 著者:ラジオ少年
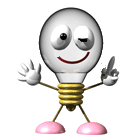 真空管は小学校のころからのあこがれだった。
真空管は小学校のころからのあこがれだった。
国民学校2年生の夏、終戦を迎えた。
毎日、何度も「中部軍情報」をラジオから聴いてきたが、それも玉音放送で終わり、ラジオから流れる歌やドラマも春を感じさせるさわやかなものに変わっていった。
このころラジオのスイッチを入れるのは父親だけが出来て、家族がつまみを回すとピーといって治まらない。いわゆる並四というラジオだった。
終戦になって中国から引き揚げてきた七っつぁんという人が近くにいた。
そこへ遊びに行くとラジオの中身を見ることが出来た。
七っつぁんはラジオの修理が出来るといって、村の人たちは調子の悪くなったラジオを持ち込む。その修理を見に行くのが楽しく、不思議でならなかった。
4年生のころからラジオを作ってみたい。でもラジオはまだ各家庭にもなく、わが家でも父親以外はラジオをさわることが出来ないものだった。
初歩のラジオ(月刊誌)を読むようになったのもこのころで、学校の教科書は家で読んだこともなかったのに、ラジオの本はかじりついて読んだ。
ラジオを作りたい。
親に何度もいったけど、いつも返事は「中学になったら」だった。
釘にエナメル線を巻き、電池をつないで電磁石を作ってみたり、その電磁石でモールス信号のまねをして遊んだ。
電磁石のカチカチと付いたり離れたりする部分を接点にしてみたらブザーになった。
なるほど。この先に自転車の鈴を置けばベルになる。
この遊びは、後に高校入試問題に出て念願の志望校に行けた貴重な体験だった。
目に見えない電気にだんだんと興味は湧くばかり。
5年生から6年生にかけては模型モーターをよく作った。
本に作り方があったのだろうか、缶詰のブリキを伸ばして剪定ばさみ(内緒)で切って加工する。
村には工具や材料(部品)を売る店はなかったから、すべて家にあるもので作っていた。
モーターは整流子を作るのが一番やっかいで、ブラシと共にこの部分は真ちゅうや銅板を使ったように記憶している。
エナメル線だけはどこで買ったのか家にあった。
だんだんとラジオが村にも普及してくるとNHKラジオ巡回相談が村にもきた。そこへもよく行き、それをだまって見ていた。
あるとき、中学の先生が学生を数人連れて見学に来た。
私を見て「君はまだモーデルモーターだな」と先生は言った。
しゃくに障ったのでこの言葉ははっきりと覚えているが、部品や作り方のマニュアルをセットにした教材を指しており、小学生の君には、ラジオはまだ無理だと言うことだった。「ラジオは中学になってから」という私の父親も元小学校の先生だった。
釘にエナメル線を巻いて電池をつなぐと磁石になったり、その磁石を応用してモーターが回る。右手の法則やフレミングの法則を知らなくてもなんとなく解るけど、なぜラジオは鳴るのか。この不思議はいつまでも残る。
中学一年生。いよいよ私のラジオ製作の解禁だ。
中学にはラジ研といってラジオ研究クラブがあった。
早速、そのラジ研クラブに入ってラジオを作るのに必要なものを教えてもらった。
家で小遣いをもらいアルミのシャーシーを買った。
学校には購買部があって、ラジオの部品は二つ村を越えた遠くの町(といっても、その後の町村合併で私たちの役場はその町に行ってしまった)のラジオやさんが運んでくれる。
次の週には真空管ソケット4個とビスナット。次は電源トランス....。
でもすべてシャーシーには部品に合った穴が開いているわけでもなく、ドリルとリーマー....、そう、シャーシーパンチもあったっけ。
ラジ研のおかげ、工具は学校にそろっていたので助かった。
1学期中かかって部品がそろい、配線も出来た。
そんなに難しく時間がかかるのかというと、難しいのは資金(小遣い)ぐりとおねだりの時間。いつの時代も同じか....。
もう一度、誤配線はないかチェックをしてスイッチを入れたのは夏休みに入ったころだった。
4本の真空管のフィラメントが灯りだすと、マグネチックスピーカーからかすかなハム音が出た!
なんと感動的な一瞬だ。
でも、それ以上な変化はなかった。
しばらくブーンという音を楽しんでいたけど、求めるラジオの放送は入らない。
調整するところは同調バリコンと再生バリコン(豆コン)だけで、どれを回しても放送は入らない。
クラブの担当の先生に助けを求めると、2〜3配線ミスを見つけてもらい、やっとラジオが鳴った。
こんなうれしいことはなかった。
でも、いやな性分で感情をあまり出さない私は、ただニヤッとしただけだったのだろう。
初代並四の真空管構成は、57−56−12Aー12Fだった。
それから半年ぐらいは、その1台のラジオを作っては壊し、壊しては作っているうちにオームの法則しか知らない私にも、ラジオのことがなんとなく解ってきた。
そのうちに5球スーパーヘテロダインがよいということで作ってみると、並四とは比べものにならないラジオだった。スピーカーもマグネチック型からフィールド型ダイナミックスピーカー、この音の違いにもびっくりした。
このころからラジオの標準が5球スーパーになっていた。
中2のときは何台作っただろう。
村にうわさが立つと注文が続き、5台10台と作っているうちに作るのも早くなった。
5球スーパーだと納期は2日とかからなかった。
頼まれて作るラジオは裸のままというわけにもいかず、キャビネットにダイヤルとツマミの穴あけまでやる必要がある。横行ダイヤルが流行るとダイヤルの糸かけにも手間がかかった。
がむしゃらに作っていたころ、「作るのは誰にでも出来る。修理が出来なければラジオをやっているとは言えない」と、わかったようなことを言う人がいたけど、こんなに作っていると部品の一つひとつの働きもわかるようになり、5球スーパーなら修理で困ったことはなかった。
近所の人が大きな風呂敷包みにラジオを包んで持ち込んできたことがあった。
口数の少ない人で「鳴らない」の一言。
キャビネットからだしシャーシーを裏返してびっくり。ぐしゃぐしゃの配線だった。
「これラジオやさんで買ったの?」と聞くと、雑誌で見た懸賞で当たったという。それを東京まで行って2万円払ってもらってきたと言うから2度びっくり。
原因はいわゆるイモハンダで、ハンダ付けをやり直したら直ったものの、当時の5球スーパーはいくらぐらいで売られていたのだろう。
中3になってからはデンチク(電気蓄音機)を2台作った。
縦型の大きなキャビネットの上の蓋を開けるとレコードプレヤー。中段にラジオ本体、下にはスピーカーというのが一般的だった。
最初の発注者はうちの親戚だった。雑貨屋と工務店をやっていてお金持ちだったと思う。
組み立てていくたびに、その都度部品代をもらって作っていった。完成間近になってスピーカーを買うと言ったら、おばさんが「どうしてもスピーカーはいるものか?」と質問されたのには困った。
2台目はうちにもほしくなって、親との交渉で「高周波1段付き3バンドスーパーヘテロダイン」だった。
これも何度も言ったのだろう。家族みんなが覚えた名称だった。
このころまでは測定器は1台もないままラジオ製作と修理をやってきたけれど、要らなかったのではなく、もちろんほしかった。
「テスターがほしい」。この言葉も1年間は言い続けたように記憶している。
おねだりもいろいろ考えて、テスターがないと感電死するかも知れないということも言ったように覚えているから、おかしくなる。
で、1台のテスターが入ったのもこのころだった。島津電気のちょっといいやつだった。
うちにデンチクがほしかったのは、中2のとき先生が学校のデンチクを作って生徒を集め、レコードをかけてくれた。
スピーカーから出る大きな音で聴いたとき、すごいと思った。
8インチのスピーカーだったと思う。
当時の標準は6.5インチで6半と言っていた。
中学校のラジ研クラブもだんだんとメンバーが減り、2年生、3年生のときには本当に好きな3人だった。
このころ高校進学はクラスの半分にも満たなかった。
学校の勉強は嫌いだけど、オームの法則しか知らないでは話にもならず、ラジオのことを学べる学校を探したら、県下でただ一つ「電気通信科」のある工業高校があった。
いよいよ進路を決めるとき志望校を書かされたので、迷わずその工業高校を書いて提出したら担任の先生から「ばか!」と叱られた。
その工業高校はいいけれど、第2志望校に誰もが目指すという名門校を書いていたからだった。
そんな名門校は行く気もなかったけど、どうしても第2志望を書けと言うから書いただけで、本命の工業高校以外は全く希望しなかった。
でも運良くその工業高校にはいることが出来て、みんなラジオ好きばかりと思っていたら、第1志望の名門校は無理だからといって、やむなくここに来たというのも半分ぐらいいた。
志望校の書く順序が逆だったことをこのとき知った。
しかしさすが専門校だけあって、中にはすでにオーディオに走っていたものもいた。2A3という真空管も彼らに教えてもらった。
彼らは高忠実を求めるため「f特」だの「歪」をさかんに言う。
それに反発していなかったら、もう少し早くオーディオに関心を持ったのだろう。
アンプをいくらフラットにしても、耳の周波数特性や聴く環境などで、耳に入る音の周波数特性がフラットになるはずがない。
若さゆえの反抗だった。
それよりもラジオが鳴るのはなぜだ。
こちらの方が興味があり、これもクラス仲間の誘いがあって、戦後再開されたアマチュア無線に傾いていった。
たまたま家には中学のころ作った短波を受信できる3バンド電蓄があったので、7メガや14メガで聞こえるハム(アマチュア無線家)の交信を傍受していた。
KAやKR6のコールサインがよく受信できた。
KAは日本に駐留しているアメリカ人、KR6は沖縄駐留のアメリカ人だった。
自分で電波が出せる。無線で話ができる。
だんだんと
アマチュア無線にのめり込むことになり、2年生のとき無線従事者国家試験で第2級アマチュア無線技士をもらった。
早速、無線局開局の申請をするのだが、当時は放送局並の申請書が必要だった。
公共の電波を使うのだから、プロもアマチュアも区別はないということだ。
無線局の予備免許が下りたのは3学期も終わりころだった。
ラジオの真空管より少し大きな真空管を使って送信機を作る。
自分で作った機械で未知のハムと交信する。
胸のときめきはラジオを作ったときを思い出させる。
それにハムはいい人ばかりで、学生でありながら一人の人間として話が出きる。
これは、ハムで味わういちばん大きな喜びだった。
学校では無線学を学び、家では無線を楽しむようになってからは、ラジオが鳴るのが当たり前に感じるようになっていた。
でも、無線学を教える先生は「ラジオが鳴る?このことにもっとおどろけ!」「何故だともっと怒れ!」と言ってくれた。いい教えだった。
いよいよ社会へ足を踏み出した、その第一歩は民間のラジオ放送局だった。
毎日音を扱う仕事柄、アンチオーディオに終止符を打ち、よりよい音で送出しなければならない。
それに学生時代から好きだったジャズを聴くために、
オーディオは欠かせなくなっていった。

| 

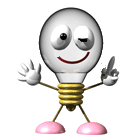 真空管は小学校のころからのあこがれだった。
真空管は小学校のころからのあこがれだった。