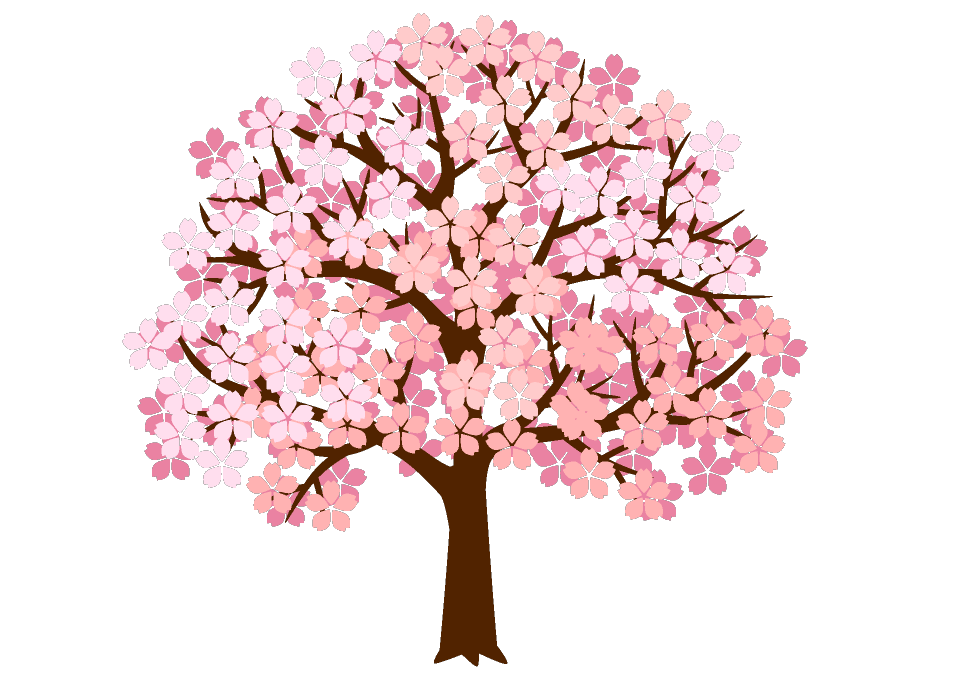 |
行政書士さくらい | TEL 090-4233 -5695 三重県亀山市 |
| トップページ (ご挨拶) |
業務一覧 | 業務への 取組の考え方 |
事務所・活動(営業)方針等 | プロフィール | 連絡先 | 相談無料です |
| 遺言 1 遺言について(自筆証書遺言の法務局保管制度) | ||
| 遺言には、従来から、公証役場で作成される公正証書遺言と自筆による自筆証書遺言があります。 2019年に自筆証書遺言を各地の法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」ができました。 現在、遺言書の利用はまだ多くないですが、未婚化の進展等で、近い将来、3人に一人が遺言書を残す必要がある社会状況となることが見込まれ、そのために安価で安全な遺言制度が必要という社会的要請から、遺言書保管制度が創設されたものと考えます。 この制度の大きな利点として、従来、自筆証書遺言(自宅保管)での問題点として指摘されていた、 ①「遺言書の紛失・改ざん・破棄・隠匿のおそれ」が、(法務局保管により、)ないという点、 ②「方式不備で無効になるおそれ」が、(法務局職員が確認するため、)ないという点、 ③「相続人に遺言書の存在が知らされないまま遺産分割がされるおそれ」が、(相続開始後、法務局に遺言書が保管されている旨を相続人等に通知することから、)ないという点 があげられます。 また、相続手続きを進める際に、裁判所の「検認」が不要(自筆証書遺言(自宅保管)では裁判所の「検認」が必要で、通常は2月程度かかる)であるとともに、制度利用面では、3900円という安価で利用できます。 公正証書遺言との対比では、自筆証書遺言では、とりわけ、内容無効リスクを避ける観点からも、できるだけシンプルな内容のものであり、かつ相続財産額的に多額でない場合に、より適性があると考えます。 昭和30年代以前に生まれた世代は婚姻率の高く、遺言は自分には関係ないという方が多いですが、昭和40年代以降の世代は未婚率が高くなってきており、子への相続ではない財産処分の必要性から、今後、遺言書を書くことは当たり前の時代となっていくものと考えられます。 |
3種の遺言についての比較で、個人的な見解も含まれます。
| 遺言 2 種類別の適性(秘密証書遺言を除く) | |||
| 公正証書遺言 | ・病気等で公証役場に出向くことができない場合、又は自筆能力がない場合 ・比較的多額の資産があり、遺産の分配をきっちりとしようとする場合 ・複雑な内容の遺言の場合 |
 |
|
| 自筆証書遺言 (法務局保管) |
・遺言内容がシンプル(財産を包括的に規定する(例:「全財産を○○に遺贈する」、「全財産を妻○○○○に相続させる」等))な場合 →シンプル遺言の具体的事例 ・比較的資産が多くなく、できるだけ安価で安全に、遺言を残したい場合 ・将来に変更の可能性があっても、とりあえず遺言を残したい場合 |
||
| 自筆証書遺言 (自宅保管) |
・時間をかけて書き換えをしていく場合 (※ 改竄、紛失、見つからない等のリスクが伴う) (※ 安価(3900円)で利用できる上記の自筆証書遺言書の法務局保管制度ができたことにより、費用が掛からない(保管費用無料)、書き換えが随時にできる以外には自宅保管の優位性は考えにくい) |
||
| ※補足 上記のとおり各遺言の適性を書きましたが、複雑な遺言が自筆証書遺言はできないということではありません。 また、考え方次第でどれを使うかも変わります。 例えば、「遺言は一生の締めくくりの一回限りの行事」ととらえるならば、遺産額によって変わりますが一定の経費をかけて、公正証書遺言で安全、確実なものを残す、というのも一つの考え方だと言えます。 公正証書遺言は同一遺言者が何度も作成することを前提としてないため、相続人、遺贈人、遺言執行者が先に亡くなることを想定した予備的な内容を考慮したり複雑なものとなる場合があります。 自筆証書遺言(法務局保管)は、安価(3900円)であり、費用面からは内容変更が容易であるので、それが必要となる事実が発生することが考えられる場合や遺言内容について変更する可能性がある場合であっても、まず作成したものを保管制度を利用し、内容を変更することとなった場合に、必要に応じて変更等の手続きをすればいよい、と考えることができます。またそのように考えることで、よりシンプルな形式の遺言にすることができます。 ただ、内容については、内容無効を避けるため、専門知識を持つ行政書士等にご確認いただいたほうが無難です。 |
| 遺言 3 種類別の制度要件・諸条件比較(秘密証書遺言を除く) | |||||||||||||||||||
種別 (保管場所) |
制度要件 | 安全性 | 相続後の紛争 | 相続準備性 | 費用・更新性 | 備考 | |||||||||||||
| 申請・出向き場所 | 職員出張制度 | 証人 | 自筆能力 | 紛失・改竄等リスク | 本人意思 | 方式不備無効 | 内容無効 | 事前準備性 | 裁判所「「検認」 | 必要経費 | 更新の容易さ | ||||||||
| 公正証書遺言 (公証役場) |
公証役場(2回出向) | ○(自宅できる) | 要 (2名) |
不要 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 低い | ○ | 不要 | 高価 ※5 |
難 ※5 |
||||||
|
自筆証書遺言 (法務局) |
通常 | 法務局 (1回出向) |
× | 不要 | 要 | 安全 | 安全 | 安全 | ※2 | ※3 | ※4 | 不要 | 3900円※5 | 容易 ※5 |
|||||
| シンプル | 安全 | 低い | 参考 | ||||||||||||||||
自筆証書遺言 (自宅) |
通常 | 不要 | ー | 不要 | 要 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | 要 | 無料 ※5 |
随時可能 | |||||||
| シンプル | 安全 | 低い | 参考 | ||||||||||||||||
| ※1 専門知識を持つ行政書士等に事前確認を行えば無効リスクはほぼなくなる。 ※2 シンプルな遺言の場合はほぼ安全。 複雑な内容の遺言の場合は専門知識を有する士業者に事前確認を行えば無効リスクはほぼなくなる。 (公正証書遺言の場合は、依頼先の士業者と公証役場職員がチェックを行う) ※3 シンプルな遺言の場合は「低い」。 複雑な内容の遺言の場合は専門知識を有する士業者による事前確認により、相続に伴う紛争の発生を低くできる。 (公正証書遺言の場合は、依頼先の士業者と公証役場職員がチェックを行う) ※4 自筆証書遺言の場合は、遺言者自身が財産リストの作成や本人・両親の戸籍謄本の取得等、事前準備が望ましい。 (公正証書遺言では、これらを揃え、遺言書作成時点のものを作成) ※5 公正証書遺言は、自分で行えば遺産額によっては数万円程度(公証役場手数料+証人2名経費)からできる。 ただ、通常は士業者に依頼することが多いため、少なくとも相続遺産額の2%程度はみる必要があり、その費用面から、内容変更は一般人にはハードルが高いと考えられる。 自筆証書遺言は、法務局保管制度利用の場合、経費3900円(自宅保管の場合は不要)で済む。 士業者に内容の事前確認を依頼すれば、その経費として数万円程度見込む必要がある 内容変更については、自宅保管の場合は随時でき、法務局保管の場合でも費用面からは容易である。 |
| 遺言 4 主な観点からみた整理 | |
| 主な観点 | 説明 |
| 遺言書の安全性、相続後の紛争リスクを低くする観点 | ○公正証書遺言は、紛失、改ざん等のリスクとともに、本人意思面や方式不備無効リスク、数名の専門家が内容を確認し作成するため内容無効リスクはほぼなく、また相続後の紛争発生のリスクは低く、最も安全性が高い遺言形式で言える。 ○自筆証書遺言(法務局保管)は、紛失、改ざん等のリスクがなく、本人意思面や方式不備無効リスクもないが、複雑な内容のものとなれば、内容無効や相続後の紛争リスクが上がる。ただ、できるだけシンプルな遺言にすることや士業者の事前確認により、そうしたリスクは公正証書遺言並みに下げられる。 ○自筆証書遺言(自宅保管)は、紛失、改ざん等のリスクのほか、遺言者の状態によっては本人意思面でのリスクが避けられない。また、方式不備無効、内容無効、相続後の紛争発生リスクもあるが、できるだけシンプルな遺言にすることや士業者の事前確認により下げることができる。 |
| 相続手続き開始への準備性 |
○公正証書遺言は、作成段階で相続人確認及び財産目録を作成するとともに、相続開始時に裁判所の「検認」が不要であるため、ほぼ財産目録の時点修正だけで、相続手続きを進めることができる。 ○自筆証書遺言(法務局保管)は、相続開始時に裁判所の「検認」が不要であるが、保管申請時に相続人の確定と相続財産一覧の作成が必ずしも必要とされないため、相続手続きをスムーズに進めることができるよう遺言者が予め別途準備しておくことが望まれる。 ○自筆証書遺言(自宅保管)は、裁判所の「検認」に2月程度要するため、それまで開封ができない。その間に相続人の確定と相続財産一覧の作成をする。(遺言者が予め用意しておくことが望まれる) |
| 費用と内容変更の容易性 | ○公正証書遺言は、変更は制度的には自由にできるが、費用面からは一般人には何度も変更することは難しい。 ○自筆証書遺言(法務局保管)は、3900円の手数料だけであるので、内容変更等は費用面からは容易にできる。 ○自筆証書遺言(自宅保管)は、費用が掛からず、自由に随時内容の変更できる。 |
| 遺言 5 シンプル遺言の具体的事例 | ||
| 事例 | 遺言の内容の文例 | 摘要 |
| 甥や姪への遺贈 | ※ 甥への例 1 私は全財産を甥○○○○( 年 月 日生)に遺贈する。 2 遺言執行者として甥○○○○を指定する。 |
子どもがいない方、「おひとり様」など |
| 夫婦で相互に相続 | ※ 夫から妻への例 1 私は全財産を妻○○○○( 年 月 日生)に相続させる。 2 遺言執行者として妻○○○○を指定する。 |
子どもがなく、夫婦に兄弟姉妹がいる場合にあって、その財産を配偶者のものとする場合 |
| 親から家を継いでいる長男へ相続 | 1 私は全財産を長男○○○○( 年 月 日生)に相続させる。 2 遺言執行者として長男○○○○を指定する。 |
長男の兄弟姉妹の持つ「遺留分」の考慮が必要 |
| ※遺言執行者: 例えば、遺贈の場合、土地や家屋といった不動産の登記は 被相続人→相続人→遺贈を受ける人 へ異動することとなるが、遺言執行者が指定してあれば、その人の印で登記が進められる。(指定がしてないと、相続人全員の印鑑が必要となり、協力が得られない場合や相続人に意思能力がない人や行方不明の人がいる場合、登記に時間が要することとなる。) |
| 遺言 6 自筆証書遺言の方式不備「無効」を避けるための6つのポイント | ||
| 事例 | 説明 | |
| 自筆 | 遺言自体はすべて自筆によること。 | |
| 押印 | 押印は、必ずすること。認印でも可(朱肉を使用する印鑑、できれば実印が望ましい) | |
| 日付 | 日付は、年月日をきっちりと書く。(「吉日」では無効となる) | |
| 氏名 | 氏名には、人物特定のため、生年月日、肩書、住所等のいずれかを併せて記入のこと (※、住民票等の記載通りに記入) |
|
| 内容の訂正 | ・訂正の仕方が厳格であるので、文言・字句の誤りは、書き直しが望ましい。 <訂正方法> →訂正部分に、二重線を引き、その部分に押印をし、その上の空欄に訂正する文言を書く。 →さらに、遺言書の末尾や余白に「五行目六文字削除し六文字追加した」等と訂正に関する追記をし、自筆で署名する。 |
|
| 単独遺言(連名は無効) | 連名の場合(例:夫婦連名)は無効となるので、作成する場合は別々に作成する。 | |
