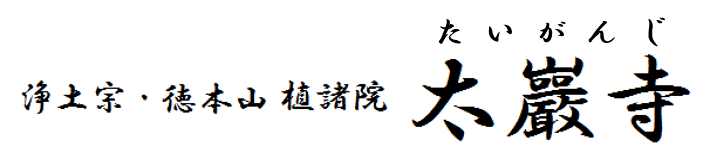太巖寺縁起
太巖寺は奈良時代、行基菩薩によって開創されました。往古は寺領が370余石で、60有余坊の大伽藍の大寺院でした。 その後江戸時代の初期、浄土宗中興の祖と言われる総本山知恩院第32世霊巖大和尚の高弟・徳蓮社本誉太巖大和尚により、この地に開山されました。
現在の本堂は、嘉永4年(1851)太巖寺第21世重蓮社恩誉懐冏和尚によって再建されました。 再建当時すでに境内には藤の木があり、その頃から「藤の寺」と呼ばれていたと記録されています。(浄土宗大辞典編纂委員会監『新纂浄土宗大辞典』より)
また藤の木については、明治初年に相撲力士 明星岳が「藤の木のごとく粘り強く逞しく、長く立派な花を咲かせるような関取になれるように」と藤の苗木を植え、仏前にて祈願したとも伝えられています。
寺院概要
名称
宗教法人 徳本山 植諸院 太巖寺(とくほんざん じきしょいん たいがんじ)
宗派
浄土宗
山号
徳本山
所在地
〒519-0162 三重県亀山市住山町273
住職
小林 菅美(かんび)
開基
奈良時代 行基菩薩
本尊
阿弥陀如来
札所等
伊勢国鈴鹿郡八十八箇所 第四十九番札所