|
マイコンから始まったパソコン
1980年
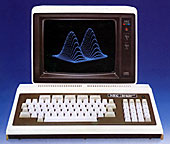 PC-8001からパソコン始まる
PC-8001からパソコン始まる
1980年(昭和55年)はパーソナル・コンピュータの花盛り。これまでマイコン界のリードを取ってきた商品は、アップル社のアップルll(現在のMac)、コモドール社のPET2001やCBM3032、ラジオシャック社のTandy TRS-80などアメリカからの売り込みだった。しかし、我が国も負けてはいられなかった。
日本電気がマイコンキットTK-80を発表したのが1976年。マイクロソフト社がBASICを発表したのが1975年、あのウインドウス95から20年前のこと。日本電気も独自のN-BASICを載せたPC-8001を発表したのが1979年だった。これに負けじと我が国の家電メーカーから続々とマイコンが発売された。
1980年1月号のマイコン誌(電波新聞社発行)の広告ページを見ると、日本電気PC-8001(写真、168,000円)、シャープMZ-80C(268,000円)、日立ベーシックマスターMB-6881(148,000円)などが競い合っている。MZ-80Cは10万円高になっているが、これには10インチ程度のグリーンのモニター(CRT)とデータレコーダー(カセットデッキ)が一体になっているためで、本体(キーボード共)だけでは16万円程度が標準になって出てきている。このあと東芝や富士通が続いて発表するが、各社とも搭載する言語(当時はOSでなく言語だった)は独自のBASICが使われた。
1982年には日本電気が16ビットマシーンPC9801シリーズを発表して、BASICからMS-DOSの時代に突入することになった。DOSはディスク・オペレーティング・システムの略で、やっとBASICで活躍してたカッセットテープからフロッピー・ディスク(FD)を使うようになった。
表計算ソフトはマルチプランや○○カルクなどがあったが、1984年にロータス1-2-3が日本上陸をした。表計算にデータベースとワープロの機能を搭載とあって、ほしくてたまらなく、8万円余したロータス1-2-3を働かすために16ビット機を買うことになったのが翌1985年だった。これは仕事で本当に重宝した。
一方、アップル社は1983年に世界初のGUI搭載のパソコン「Lisa」が発表され、現在のようにデスクトップ上で作業が出来、マルチタスクというのも画期的ではあったが、本体価格220万円もした。早すぎたパソコンと言われながらも翌1984年には、GUIを搭載しながらもシングルタスクにすることでコストダウンを図りMacintoshは個人でも購入できる最初のGUIパソコンでもあった。とはいえ、初代 Macは本体価格60〜80万円もする高価のため、興味はあるが高嶺の花だった。
|
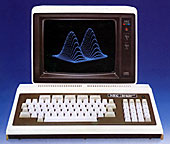 PC-8001からパソコン始まる
PC-8001からパソコン始まる
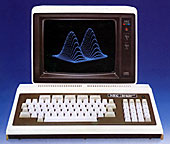 PC-8001からパソコン始まる
PC-8001からパソコン始まる