|
マイコンから始まったパソコン
O S
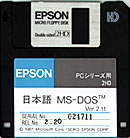 EPSONがPCシリーズ用として出したMS-DOS
EPSONがPCシリーズ用として出したMS-DOS
OSをふり返ってみよう。
今ではパソコンの大半はWindowsで、割合は少ないがMacOSがある。またネットワーク関係でLINUXが小さくて重宝がられている。これに落ち着くまでは、様々な言語やOSがあった。
CPUが理解してくれる言語は機械語(マシン語)で、BASICは人間語に近い言語の通訳をやってくれるので、高級言語と呼ばれていた。1980年代に入ってまもなくC言語なども開発されている。また企業などで使われる業務用には、コボルとかフォートランという言語でプログラムが書かれていたが、私なんかはワカラン。
8ビットで使われたOSは主にCP/M-80で、先ほどの高級言語から、データ・ベースや表計算、ワープロなど、このOS上で動かせていた。CP/Mとは、Control Program for Microcomputer の略で、デジタルリサーチ社の開発です。
16ビットでは、そのままCP/M-80を書き直してCP/M-86が使われた。この80とか86は、使われているプロセッサーから取った名称で、80はi8080、i8085、Z-80など80系を指し、86は16ビットのi8086というわけです。
しかし、このころからSeattle Computer Products の Tim PatersonがCP/Mを改良して16 ビットの i8086 / i8088用として86-DOSを開発し、後にマイクロソフト社がその権利を買い取りMS-DOSとなった。ここで動くマルチプランは表計算ソフトとして一躍有名になったが、後にロータス1-2-3にそのお株を取られてしまった。次から次へとMS-DOSで使えるアプリケーション・ソフトが各社から出されるようになって、パソコンOSの標準化が図られてきた。
MS-DOSはCP/Mをよく研究して、CP/Mの欠点などをカバーした使いやすいOSだった。そのためIBM-PCや日本IBMのマルチステーション5550に採用されたことも、大きく影響を及ぼしたのだろう。
このMS-DOSは、後にWindowsに成長するもので、アップル社が開発してきたMacOSとはまったく違ったOSだった。
WindowsとMacOSを見てみると、デスクトップでは同じゴミ箱があるけど、Win(Windowsの略)のゴミ箱はファイルやフォルダーを捨てる箱だけに対し、Macはフロッピーディスクなどを抜くとき、そのアイコンをゴミ箱に捨てると、自動的にフロッピーが飛び出してくる。それとフロッピーもそうであるが、外部接続装置をつなぐ(差し込む)と、そのアイコンがデスクトップに表示される。大きな違いだと思う。
しかし、WindowsもXPになって、すごくMacに近くなったようで、Win落ちこぼれの私にも少し使えるようになった。反面、MacもOSX(オーエス・テン)になってWinに近づいている。これはMacが開発してきた漢字トークの流れを打ち切って、UNIXを基にしたOSにしたため、その約束事を継承しなければならないものがあったのだろう。Macの使い勝手を残したUNIX機とも言えるのではないだろうか。MacもG5が発表されCPUも64ビットになった。個人が使うワープロと表計算程度にはデカ過ぎるような気がする。
もうパソコンを越えたようなMacのG5最高グレードの機種と、20年前のNEC PC-9801と同じ値段というのは、高いのか安いのか....。
| 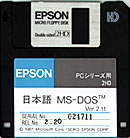 EPSONがPCシリーズ用として出したMS-DOS
EPSONがPCシリーズ用として出したMS-DOS
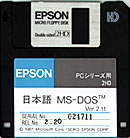 EPSONがPCシリーズ用として出したMS-DOS
EPSONがPCシリーズ用として出したMS-DOS