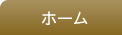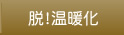干拓事業

干拓以前の内湖 (M25年測図)
昭和 19年に干拓事業が着手され、戦局拡大に伴い働き盛りの成人男子のほとんどが徴兵された。干拓事業に従事する労働者は、県内外の師範学校等の学徒動員や外国人の強制労働(捕虜)だった。
B29の爆撃機の爆音や空襲警報のなかで、人力による作業が進められた。戦争により資材及び電力の不足等のため工事は一進一退で、地区内工事は昭和22年頃まで進展がなかった。
排水が進んだ地区に昭和 21年 11月、第 1陣の入植がはじまり、泥海での生活のなか営農と干拓工事に従事された。
■干拓工事と入植の主な経過
| 昭和18年 | 県庁内に琵琶湖対策審議会を設置 | |
| 10月 | 内湖の測量開始 | |
| 10月30日 | 農地開発営団より職員派遣 | |
| 11月 | 計画樹立 | |
| 12月12日 | 起工式 | |
| 昭和19年 | 8月10日 | 工事開始 |
| 昭和20年 | 8月15日 | 終戦により工事は一進一退 |
| (23年頃まで地区内工事は中断状態) | ||
| 昭和21年 | 11月 | 第1陣入植(宿舎で共同生活) |
| 昭和22年 | 1月 | 第2陣入植(宿舎で共同生活) |
| 10月 | 農林省に引継ぎ | |
| 昭和23年 | 幹線排水路の掘削開始 | |
| 昭和24年 | 入植者住宅の建築開始 | |
| 昭和25年 | 干拓地区内土地の入植者への売り渡し | |
| 5月 | 琵琶湖干拓水茎開拓農業協同組合設立 | |
| ブルドーザーによる地均し工事 | ||
| 9月 | ジェーン台風(災害救助法の適用) | |
| 昭和26年 | 用水取水樋門工事 | |
| 昭和27年 | 5月30日 | 水茎工区事務所閉鎖 |
| (琵琶湖干拓建設事務所(安土町内)に残務引継ぎ) | ||
| 昭和28年 | 4月1日 | 水茎干拓土地改良区設立 |
| 4月29日 | 完成式の挙行(於北里小学校講堂) | |
| 昭和29年 | 干拓地区内の電気工事開始 | |
| 秋 | 電灯が灯る | |
| 昭和30年 | 3月 | 近江八幡市合併 |
| (野洲郡北里村、蒲生郡岡山村他合併) | ||
| 昭和34年 | 9月26日 | 伊勢湾台風干拓堤防決壊(災害救助法の適用) |
| 昭和37年 | 1月 | 簡易水道工事着手 |
| 昭和38年 | 6月28日 | 簡易水道工事完成 |
| 昭和47年 | 開拓行政打ち切り・・・一般行政へ移管 | |
| 琵琶湖干拓水茎開拓農業協同組合解散 |
■主要施設
| 名称 | 延長(m) |
|---|---|
| 地区外用水路 | 856 |
| 地区内用水路 | 16,631 |
| 計 | 17,487 |
| 地区外取付道路 | 2,112 |
| 地区内道路 | 16,886 |
| 計 | 18,998 |
| 承水溝 | 7.040 |
| 地区内排水路 | 16,003 |
| 計 | 23,043 |
| 排水機 | Φ800 Q=1.25m3/s | 2台 |
| Φ500 Q=0.50m3/s | 1台 | |
| 計 Q=3.00m3/s |
| 揚水機 | 野田(牧) | Φ500 |
| 放流樋門 | 野田及び今堀 | 2.5m×2径間 各1箇所 |
■用水(干拓計画)
| 用水量 | 日最大減水深 | 10mm |
| 最大単位用水量 | 0.00185m3/s.ha | |
| 損失 | 閘門、通船などの損失を含め30% |
■排水(干拓計画)
| 名称 | 日雨量 (mm/日) |
到達時間 (hr) |
流域面積 (ha) |
湛水量 (m3) |
単位排水量 (m3/s.ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東部承水溝 | 204 | 3 | 209 | 156,800 | 0.020 |
| 西部承水溝 | 204 | 5 | 829 | 684,000 | 0.018 |
■造成面積
| 地目 | 計画地積(ha) | 造成面積(ha) |
|---|---|---|
| 田 | 154.3 | 154.3 |
| 畑 | 5.2 | 5.2 |
| 施設用地 | 56.6 | 54.9 |
| 計 | 216.1 | 214.4 |
| 〔参考資料:公有水面埋立計画、滋賀の土地改良〕 |