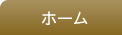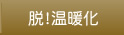直売施設「とろっこ村」

平成13年に元水茎まちづくり委員会が、直売施設を立ち上げました。地元の農家が栽培した野菜を、出来るだけ安価で地域の皆様に提供し、地域の活性化に取り組むための拠点施設です。
なお、とろっこ村の名称は、水茎干拓堤防の築造、田んぼの地均工事(田んぼに水を張るために、田んぼの高さを水平にする為の工事)等の主要な土砂の運搬につかわれた車両「トロッコ」に由来していて、先人の干拓工事の苦労を忘れないための命名であると共に、現物を敷地内に保存展示しています。
「とろっこ村」が目指すもの
地域の活性化
とろっこ祭りは地域住民のみでなく、近隣都市住民も参加するイベントであり、参加者を通じて子ども同士を始めとする各世代毎の交流の促進が図れると同時に、地域内ではとろっこ村で販売する作物への工夫も生まれ、農業への意欲も育ち地域の活性化が進むと考えています。
地球温暖化防止への取り組み
とろっこ村を通じて、地元で収穫された農作物は地元で消費することにより、農作物の輸送距離は最小となり、輸送に要した化石燃料の消費量も最小となって、地球温暖化防止に大きく協力することになります。
「元水茎まちづくり委員会」発足の経緯と、”とろっこ”の名前の由来
苦労を共有する入植者の共同精神は強く(※下記コラム参照)、各人が配分を受けた土地の均平作業は”トロッコ”を使用して、入植者たちの共同作業で進められました。
しかし入植後半世紀を過ぎると世代交代、生活、経済、農業等を取巻く環境は著しく変化し、入植者同士のかかわりにも変化が見られるようになってきました。
そこで、入植当時の精神を取り戻すために、「元水茎まちづくり委員会」を立ち上げ、平成13年に直売施設による活動を行う事となりました。
直売施設のネーミングは、入植当時、苦労して地均(土地の均平)作業に活躍した、”トロッコ”を通じて、入植者同士の絆を取り戻したい、として「とろっこ村」としました。
そして、平成13年より、とろっこ村としてお世話になった皆様方への感謝の気持ちを「とろっこ祭り」として表すことになりました。
とろっこ祭り

直売施設「とろっこ村」で1年に一度、農産物の収穫と、地域の皆様にお世話になった感謝の気持ちを表すために、"とろっこ祭"と名付けて、毎年10月にイベントを行っています。地域の内外住民と地元の交流を兼ね、農産物の販売、バーベキュー、ジャンボかぼちゃコンクール等のイベント行い、多くの人々が参加し賑わっています。
水茎干拓地の入植
水茎干拓地は、昭和20年以前は水深約3.0mのびわ湖の内湖でしたが、太平洋戦争当時の緊急食料増産計画に基づいて干拓工事が実施され、昭和21年にポンプで内湖の水を排水し、陸地化され新天地が生まれ、この土地に昭和21〜22年頃より入植が開始されました。
入植者は土地配分計画に基づき、配分を受けた土地(内湖の水をくみ出しただけの湖底で、道路水路も完備していない泥沼の土地)の中で、高台の耕作に便利な個所を選んで、まず雨露を凌いで寝る事の出来るバラック建てで、電気水道、井戸もない所での生活を始めました。
一方、生活するための食料は当時自給自足で、まず食料生産が最重点課題でした。配分を受けた土地は、湖底の不陸のままで、水稲作付けの為にはこの不陸を均平化する作業、排水路、道路建設が同時進行作業で進められました。学童の生活は、道路が整備されていなかったため、自宅から干拓地を出るまでは素足で、既存集落で足を洗ってから、履物を履いての通学でした。
また、飲料水等の生活用水は、数百m離れた承水溝(干拓地を囲む排水路)まで水汲みに行き、天秤棒に担いで運ぶという状況で、現在では考えられない生活でした。