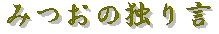
[1999.1.7.~12.28.まで]

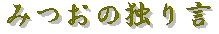
〔 2004.1.17~12.5まで分 〕
〔 2003.1.7~12.27まで分 〕
〔 2002.1.6~12.30まで分 〕
〔 2001.1.7~12.21まで分 〕
〔 2000.1.8~12.31まで分 〕
〔 1998.8.3~12.31まで分 〕
| 12月28日 | ダンディなおっさん |
|---|
| 最近、街行く紳士、観光地を闊歩するかっこよいおっちゃん、
電車の中でひときわ目につくダンディなおっさん等、老齢化が進み、かなりな年齢のように見受けられるにも拘わらず、
そのファッションやいでたちは、男の私でさえ惹きつけられる魅力を感じる老紳士に、たくさんお逢いすることがある。 私は、ファッション感覚が全くなく、いつも「もう少し身なりを何とか考えたら・・・」とよく言われる。このような男に 男のダンディズムを語る資格は、全くないが、でも敢えて私なりの講釈を書いてみたくなった。
「ダンディ」とは、「洗練されたおしゃれ」「粋な身なり」と解釈出来るが、それに「知性、風格」が加われば、
それこそ本当のダンディなおしゃれと言えるのではないかと思う。そして先日ある女性から、「女性が魅力を感じるのは、
香りをうまく着こなしている男」と付け加えられた。
最近の若い男性には、化粧をしたり、香水を付けたりしている人もたくさん居るが、本当に必要なのは、むしろ
ある程度加齢された男性ではないだろうか。日本の男性は、香水に関して保守的でアレルギーが強いように思うが、
若いころの体臭は、清潔にしてさえしていれば、むしろ好感を持てる。しかし加齢と共にそうした若さの体臭は消え失せ、
老臭という体臭へと変化して行く。そうなった頃に新たな香りを補充し、香水で装うことが必要ではないだろうか?
しかし余り付けすぎて、人に不快感を与え、「香水が強烈過ぎて、気持ちが悪くなった」などと言われるようでは
台無しである。付け過ぎず、TPOにふさわしいことが大切ではないだろうか。 さわやかな香りが気持ちを高揚させたり、鎮静させたり、雰囲気をなごませる効能があるのは、誰でも感じる ことだろう。それに頭の上から足の先まで、個性的にファッショナブルにおしゃれしている老紳士に知性と風格を 感じたら、正に「ダンディなおっさん」そのものである。私はそのような若々しい「おっさん」に憧れている。 |
| 12月20日 | ゼロエミッション |
|---|
| 「ゼロエミッション」って余り聞き慣れない言葉ですが、エミッション(emission)
即ち廃棄物をゼロ(0)にしよう・・という構想のことです。1994年に国連大学(本部・東京)の顧問であったグンタ・パウリ氏が
提唱し、産業界からの廃棄物を何とか再加工して、別の産業の原料に再利用し、さらにその廃棄物を別の産業の原料に再々利用するという、
循環利用でエミッションをゼロにしようというシステムです。
そもそもの発想は、地球温暖化の一因である産業廃棄物の処理方法を、再資源化していく循環システムの構築から始まって、
各産業界の企業からの取り組みが先行し、機械産業、化学、自動車、食品業界、酒造業界などからスーパーや各家庭廃棄物までその輪が
広がってきました。地方自治体も参画し、地域、産業界、住民、行政、と全ての人間がゼロエミッションに取り組むことは、大いに結構なことだ。
滋賀県の愛東町では、廃食油を公用車の燃料にしたり、菜の花を栽培し、菜種油を燃料にする試みも始めている。又京都の木津町の団地では、
各家庭からの生ゴミでたい肥を作り、そのたい肥を農家が引き取り、そのたい肥で野菜を栽培し、その野菜を団地の家庭に安く販売する。
そしてまたその家庭から出る野菜のくずが、再びたい肥にされ野菜の栽培に使われるという循環システムを取り入れている。また一方大阪のアメリカ村では、
古雑誌を資源にいろいろな建材を造り柱や床に活用出来るように商品化している。 このように大量生産され、大量消費され、大量廃棄物の出る世の中を循環共生社会にし、ゼロエミッションにすることによって、資源の有効活用が地球の温暖化を防止し、 現代社会の悩めるジレンマを打開してくれるという、自然の生態系を模倣した素晴らしい社会システムだと思う。もっと技術革新され全世界中で活用されるようになれば、 正に絶賛すべき産業革命ではないだろうか。 |
| 12月13日 | 噛む |
|---|
| 少年犯罪、登校拒否、学級崩壊、いじめ等すぐ「キレる」年少者の問題が多発していて、
社会問題化している。その原因の一つに、食生活が挙げられている。インスタントラーメンやハンバーガー、ケーキ、デザート類、
ドリンクなど、ほとんど噛まずに飲み込める加工食品をたくさん食べる子供ほど、心身が不安定で、問題行動を起こしやすい傾向に
あるらしい。イライラする、すぐカッとなる、根気がない、あきっぽい、情緒不安定な子供は、「噛む」食生活が足りないのではないだろうか。
「噛む」ということは、脳の発達、言葉の発音の発達、味覚の発達、肥満防止、歯の病気の予防、がん予防、胃腸の調子を整える、
噛む力をつけて気力を養う、そして健康で健全な判断力と思考力をも養う大きな要因を造り上げるものだと言われている。
このことをもっと認識して、親達が噛むことの大切さを子供に教え、なんでも噛める丈夫な歯と、歯を支えている周囲の
丈夫な組織体を持った子供を育てるために、毎日の食生活を考えて食べ物の選び方に神経を使ってほしいものだ。 確かに最近の食品には、軟らかくて、美味しくて、見た目も良い、子供好みの食べ物が多く、そしてすぐ手頃に買える環境が整っている。 その為子どもの好みに引きずられたり、忙しさのため食生活をおろそかにしている親達が多いのだろう。しかしその認識不足が、 我が子の将来に禍根を残すことのないように、「噛む」ことの重要性を教え、歯並びの良い丈夫な歯を持ち、健全な思考力や判断力を持つ子どもに育てて ほしいものだ。生きていくのに「食べること」は欠かせない。食べることに「噛む」ことは欠かせない。噛むために「丈夫な歯」は欠かせない。 「歯」の大切さをもう一度考えてみよう! |
| 12月3日 | 携帯電話 |
|---|
| 爆発的なブームを巻き起こしたポケットベルも今や昔、
それ以上に便利な携帯電話の普及で、情報伝達や交信のシステムは一変した。実業界や生活基盤での
活用は筆舌に尽きぬ利便性で、正確性とスピードは飛躍的に向上した。その為の経済的貢献度は認めざるを得ない。
ただ何となく気になることは、小学生や中学生のほとんどの生徒までもが、携帯電話を常に持ち歩いて、暇が
あれば長電話をしていることである。彼等には今どうしても伝えなければならない用件がある訳でもなく、遠くて
会えない相手と久しぶりに会話をしている訳でもない。今日学校で合ってきて充分しゃべり尽くしてきた友達と、
始まりもなく終わりもない、目的もないおしゃべりを延々と繰り返しているだけである。はた目には長い無駄話に
思えても、彼等には少しも長くなく楽しくしゃべり続けている。そしてまた次の友達にのべつくまなしに電話をして、
同じように際限なくしゃべり続ける。
自分の考えを他人に聞いてもらいたい気持ちは誰だって持っていると思う。しかし彼等の会話には、自分の意見
や考え方ではなく、独りになることが耐えられず、一人でものを考えることを避け、自分の気持ちを言葉にして正確に
表現することなく、あいまいな今の気分を「・・可愛いい~」「超 むかつく~」「・・うっそー!」といった乏しい
感嘆語でいっしょに笑い、うなずき合うだけである。そういう時間を持つことで、仲間意識や共感をお互いのために
確認しあっているだけである。このように言葉らしい言葉も必要とせず、仲間うちだけに通用する単略語が暗号か
信号のように浸透していて、他人には通じない内輪だけのサインのようなもので、コミュニケーションを成立させている。
このような無意味な長電話が、彼等の仲間意識にとっては都合がよく、説明や論理の展開といった面倒な手続きが
いらない分、快適でもあるのだろう。 そしてこの長電話代を、苦しい家計費の中から顔をしかめながら親達は支払っている。どうも日本の政治の形態に よく似てると思わないか?無駄と思われる子供達(行政)の出費を、親(国民)が賄っている。無駄な出費が日本経済の 建て直しの一翼を担っているのなら、これもまた理不尽な現象と思わざるを得ない。どう考えても発展性のない無駄な 言葉を費やして、思考を重ねない長電話の彼等に日本の将来を託すには、一抹の不安を拭いきれない。 |
| 11月26日 | 少子化 |
|---|
| 近年老齢化と共に少子化が進み、日本の人口問題が取りざたされることが多くなってきた。
厚生省の試算では、2008年から益々少子化が進み、人口は減り続け、80年後には今の人口の半分の6,000万人位にまで減ってしまうのでは
ないだろうかとさえ言われている。計算上ではそのペースで減り続けたら、3,400年には一人になってしまうという計算だという。
まさか一人にはなってはしまわないだろうとは思うが、何故人口が減っていくのだろうか? その原因を考えると、まず結婚しても
子供を作らない。特殊出産率では平均 2.08人産まなければ、人口の維持が出来ないと言われているのに、1997年の統計では、日本では
1.39人だという。これでは少子化が進んで当たり前である。子供を作らない理由には、経済的理由がある。日本の平均的文化水準、
教育、知育水準を維持しょうとすれば、お金と時間がかかる。夫婦二人力を合わせても、二人の子供を育てられない。1.39人が限度だという
判断の結果だろう。
しかしそれ以前に、結婚に対する考え方、取り組み方も変わってきて、生涯独身を志す人達が増えている。
その理由の一つには、女性の社会進出が顕著になり、経済力が備わってきて、男性観が大きく変わってきている。三高とか五高とか
いわれて、男性に求める条件や要望が厳しくチェックされる。よく「あなたの求める男性の要件は?」との質問に答える女性の
要望には、「そんな男が居るか?」と思う条件を並べ立てている。「出来れば・・」とか「願わくば・・」とかの前置きがあれば
まだしも、「・・・でなければ絶対いや!・・」とかなり厳しいお申し立てである。女性にとって都合の良いことばかり並べ立てて、
それが満たされなければ、結婚などしない方が気ままに自由を謳歌出来ると、お考えの女性が多いらしい。 最近ではほとんどお見合いの話も聞かなくなった。人のためにお世話をする仲人さんも少なく、世話をしてもらった恩義で、お世話を し返す人もいない。他人の面倒をみるどころか、自分の生活が精一杯なのだろうか? だからその男女の仲介をビジネスにしている会社や 組織、またインターネットでも男女の紹介や仲介をするサイトもたくさんある。でも現実はなかなかうまくまとまらないことが多いそうな。 日本の将来のためにも、若い男女のために力になって、ジョイント役をかって出てやって欲しい。そして安心してたくさんの子供に囲まれて、 平和で和やかな家庭団らんの姿が、たくさん見られる社会の到来を希求したいものである。 |
| 11月10日 | ファッション |
|---|
|
制服という統一された服装がある。看護婦、スチュワーデス、バスガイド、銀行、商社、デパートなどの社員の制服は、何故か男性の目を引きつける。
その職場のイメージが女性らしさと訓練された知性を連想させるのか、男性にはない女性の特性を生かした才能の表現に憧れを感じてしまう。
こういった制服の制度は、永い歴史の中で認められ「・・・らしさ」の象徴であるのだろう。
一方世のファッションの変遷は目まぐるしく変わっている。頭から靴の先まで時代の移り変わりを如実に物語っている。
ひところの流行は、同じデザイン、同じスタイルで皆一様に制服に近いような、同系統で一時代をいろどっていた。
しかし最近の流行は、非常に多様化され、その人の個性を強調する主体性が重んじられ、自分らしさを表現するファッションが
感じられる。「他人とは違うもの」をどこかで身につけ、自分らしいアイディンティティーを主張しているように思う。非常に結構なことだ。 若い人は、カラフルで快活で見ていてすがすがしい美しさがあって気持ちが良い。それにひき換え年寄りには、 一目で「老人用」と判る色柄やデザインで、個性や自分らしさを表現する雰囲気を感じさせない。年をとると体形も崩れ、 若者と同じスタイルを維持するのは、確かに難しく同じファッションを求めようとはしないが、如何にも年寄りくさいイメージ だけは打破して欲しいものだ。若者はカラフル、年寄りは地味な色柄と決めつけて、それが「・・・らしさ」と思っている 先入観を払拭して、年輩者も勇気をもってカラフルな色柄やデザインの外観のファッションで、自己表現と自己演出をして 欲しいと思う。その心意気を「色気」というのではないだろうか。世間の慣習というか、固定観念に縛られることなく、 妻任せ、子供任せにせず、自分の好みで、着たい服をカッコ良く着こなす服装研究をして欲しいと思う。気持ちで 若い人に負けずに、大いに熟年ファッションを楽しんで欲しいものだ。 |
| 10月25日 | 身近な健康管理 |
|---|
|
◆厳しかった残暑が去り、急に秋の到来で気温が下がりました。極端な温度の変化で体調を崩しやすくなります。
最近、ハウス栽培やバイテクの進歩で食品に季節感がなくなってきました。例えば夏のスイカやなすびやきゅうり等はからだを冷やす作用があり、冬の
いも類は、からだを温める作用があります。だからこれらを季節の区別なく食べていると、体のリズムが狂ってくる。食べ物は旬のものが安くてからだに良い。 ◆夏バテを防ぐには、ビタミンB1、Cが良い。食品として、落花生、豚肉、大豆、いも類、ビールも良い。 ◆食べ物は胃の中で、体温ほどに温まってから消化吸収されるため、お酒も熱燗は早く吸収されるが、冷や酒は吸収が遅いため、飲み過ぎになる。 飲み過ぎたら、ビタミンC、B1、葉酸、ナイアシン、Mgが良い。食品として、果物(特に柿)、梅、貝類、緑黄色野菜、ピーナッツ、大豆などが良い。 ◆妊婦、授乳婦さんは、ビタミンB6、C、A、D、E、K、パントテン酸、葉酸、Ca、Mgの補給を心がけた方が良い。食品としては、魚類、貝類、落花生、 緑黄色野菜、じゃがいも、レバー、マーガリン、牛乳など・・・ということは、好き嫌いをせずに何でもいろいろ食べなさいということになる。当たり前の ことか・・(笑!) ◆抗生物質を飲んでいる人は、ビタミンB2、Kを摂ると良い。食品としては、卵、納豆、牛・豚レバー、ブロッコリー、ほうれん草、海藻等が良い。 ◆チョット一服の時は、コーヒーをお奨めします。コーヒーは、大脳の働きを活発にし、思考力や計算能力を高め、筋肉をほぐし疲労回復に役立つ。 胃や腸を刺激し、消化作用を活発にし、2日酔いを防ぐ効果もあり、善玉コレステロールを増やす作用もある。 ◆近年酸性雨の影響が懸念されているが、酸性雨に含まれるアルミニウムは、アルツハイマーの原因になると言われている。浄水器は、アルミニウム を取り除くのに効果があるのでお奨めする。 |
| 10月12日 | ねたみ根性とひがみ根性 |
|---|
| 人間誰しも長所と欠点を持っているものだ。自分にも素晴らしい能力と才能をを持っているにも拘わらず、
他人が自分の持っていない特徴を発揮しているのをみると、何故かうらやましく思う。そしてひがみ根性でその人を批判しこき落とそうとする。
何と恥ずかしい性(さが)だろう。こんなむなしい根性からは無縁でありたいと思いながら、ついはまりこんでしまうのが人間の情けない悲しさである。
自分より素晴らしい人、優れた人、豊かな人、幸せな人、賢い人、そして背の高い人、スタイルの良い人、金持ちの人・・・・「ねたみ」の対象は数え切れない。
また自分だけが何故こんなみじめな思いをしなければならないのだろう。自分だけが何故こんな苦労をしなければならないのだろう。
自分だけが何故こんな目に遭わなければならないのだろう・・・・と「ひがみ」の種も尽きることがない。 しかし自分がうらやみにくんでいる人も、その人なりに悩み苦しんでいることは必ずあり、また自分が勝手に被害者意識で 他人を見たり考えたりしているだけで、他人が自分に対してはそれ程優越意識を持っていないことが多いのではないだろうか。 にもかかわらず、自分よりいいことをする人、自分が出来ないことをあっさりしてしまう人には、素直に認め評価しようとせずに、 何となくしゃくで、悔しい感じが先走って、気持ちよく好意的に誉めようとしない。人間として何と情けないと言うかあさましい根性だろう。 このような気持ちは、自分でもチャンと解っていて、正しい考え方、正直な気持ちとは思っていない。何とか人の幸せや喜びをわが喜びとし、 人の悲しみを我が悲しみとすることが出来るように、他人に惑わされることなく、自分自身をしっかりみつめ、自分を向上させるための 努力を怠らないようになりたいものである。嫉妬と被害者意識・・即ち「ねたみ」と「ひがみ」という醜い根性は廃絶したいものだ。 |
| 10月4日 | ハングリー精神 |
|---|
| 草刈りをした。大きく育った雑草は、根こそぎ抜き取るのは大変である。ところが湿地帯の草は、
いとも簡単に抜き取れる。土が軟らかいからだけではない。よく見てみると根が短いからあでもある。植物は地中の水分を吸収するのが
根の働きだから、湿地帯のような水分の多い所では、根が大きく育つ必要がないからである。大木の根は何処まで延びているのだろうと
思うほど広く大きく根を張っている。植物の成長に水は欠かせない栄養であり、生命源である。水を求め根を張る、水の豊富な所では、
その根を張る必要がないから、自ら根の成長を止めてしまっている。実に簡単な自然の摂理である。
植物がそうであるように、どんな小さな生きものであっても、いのちあるものは自ら生きていくための知恵を、しっかりと身につけて
けなげに生きている。いわんや人間も生きていくために、絶対欠かすことのできない栄養を求めて、そして大きく育つために学ぶという文化を
創りあげている。もしその栄養の根源である「水や食べ物」が得られなかったら、どうしたらその空腹を満たすことができるかを、必死に考え
工夫するだろう。人間の数ある欲望の中で一番我慢出来ないのは空腹だろう。ハングリーであることが人間を最も奮い立たせる要因であるはずである。
「欲しいから求める。その為に考え工夫する。」でも今の我々は、何でも満たされ与えられすぎているから、考え工夫し学ぶことを忘れてしまっているのでは
ないだろうか? いやもしかして湿地帯の草のように、自ら育つことを止めてしまっているのではないだろうか? 食べること、遊ぶこと、生きていくことに何の不足もなければ、何も考えなくても良い。何かにつけて過剰なほど便利になって、 なまくらものに都合の良い社会になってしまった。昔から「生活の知恵」と言われるように、人間の考え工夫する能力は、すばらしい潜在能力を与えられている。 その能力が今日の文化的な社会を築き上げてきたのだが、今やその文化が逆に人間、殊に青少年の考え工夫しようとするハングリー精神を阻害している 要因になっているようにも見受けられる。ハングリー精神を身に付けさせるために、食べ物を与えるな・・・と言うのではない。そんなことをしたら、 死んでしまう。-(笑)- 必要以上に与え、教えるのではなく、育てること。育てることより共に考え学ぶこと。その為の土壌づくりと水加減が問われている のではないだろうか。人間は、ことに青少年は基本的に根強く大きく育ちたがっているのだ。その成長しようとする意欲をかきたたせるものは、 もう少し欲しい、もうチョット気に入らないというハングリー精神ではないだろうか? ハングリー精神が、人間の潜在能力を引き出させる、 そして「考え努力する人間」の成長に欠くことの出来ない栄養源であると思う。 |
| 9月21日 | 親と子 |
|---|
| 最近 長崎県で保険金をかけた16歳の男の子を、母親が殺害した事件が報道された。この事件
以外にも子供に対する虐待や、世話の怠慢、自動車内への放置など、常識では考えられない親の我が子に対する行動が多すぎる。
また逆に、高校3年の女子生徒が、自分の彼の父と共謀して、自分の父から1億5千万円おどし取ろうとして狂言誘拐恐喝事件を
起こしている。これ以外でも不登校、家出、無断外出、いじめや恐喝など少年少女に関わる難問題が続出している。
親も親なら子供も子供、いずれにしても親と子供との関係が異状であることには間違いない。一体何故このような理不尽な
社会現象が多発してきたのだろうか?
社会不安や将来不安から来る経済的、精神的不安定さが、親子の離反の要因にもなっている反面、一卵性母子とも
呼ばれているほど親密すぎる親子関係もある。様々な家庭、いろいろな親子関係があるのは当然だが、戦後特に
近年の家庭崩壊というか親子離反というか、世代の考え方の乖離は甚だしいように感じられる。子供が家に何日も
帰ってこなくても、何とも関知しない親がいるかと思えば、門限8時とか9時とか、厳しい制約を押しつけている
家庭もある。近年は核家族という親子別居生活が一般的で、子供が親の老後を面倒みる義務感も薄れている。にも
拘わらず親は、過保護とも思える愛を子供に尽くしている。義理とか恩義とか孝行とかいう倫理観のない子供達が、
どうして育ってしまったのだろう? どうも理解できない親子の関係を、もう少し何とかならないものだろうか? 最近生まれてくる子供は、妊娠中に男女の区別も判別出来、生む時間もコントロールできるそうな。また精子バンクも ある。昔から「子供は神様からの授かりもの」で神聖なものとして、大切に育ててきた時代から、人工的に意図的に 「手に入れるもの」という考え方に変化し、子供を自分の所有物という考え方になってきたとすると、人間という 尊厳や人権まで稀薄な扱いになってしまう危険を感じてしまう。親も子供も人間であるならば、人間として 立派な人格を尊重されるべきである。人間が人間らしく生きる為には、今 何かが欠如しているように思う。 そこが分からない、見いだせないほどこの世の中が複雑なんだろうか? 頭を冷やしてゆっくり考え直して みようではありませんか。 |
| 9月13日 | 厚底サンダル |
|---|
| 最近若い女の子の間で、15~20センチもあろうかと思われる厚底のサンダルが流行っている。
その不安定な履き物で転倒して死亡したとのニュースも聞いている。馬鹿げた話だ。いくらニューファッションだからといって、死と交換してまで
流行を追うこともなかろう。あの厚底サンダルを履いて歩いている姿は、見ていてもハラハラするような不安定さ、ひざを曲げて重心を前に移動
し、足先に全神経を集中しながら不格好な姿勢で歩いている。本人はご満悦だかどうかは知らないが、見ている方は決して美しい歩き姿とは思えない。
ちなみに履き物とかかとの関係を検証してみると、まず素足で立ってみて、少しかかとを浮かせてみると、姿勢が良くなるのが分かると思う。
だからつま先よりかかとの部分が2センチくらい高くなっているのが、姿勢も良くなり腰への負担も軽減する。そしてかかとは、歩くときの膝や腰への
衝撃を吸収するところなので、厚くて硬く、安定性のある靴やサンダルが良いとされている。だから当然細いかかとのハイヒールや厚底サンダルなどは、
重心が左右にずれやすく、ねんざの原因になる。 厚底サンダルを履いている女の子は、皆くじいたりつまづいたりしたことがある、と自白していながら、凝りもせずに履き続けている。 体にも悪く、姿勢も悪く、醜い歩き姿にも関わらず、流行を追うのは何故だろう? その女心は男性には理解し難い。 一部の例外的な事例かもしれないが、死をも招きかねない厚底サンダルを履くのは、控えた方がよろしいんじゃないでしょうか? |
| 8月27日 | 労働スタイルの変遷 |
|---|
| バブルの崩壊、経済不況、景気の低迷、企業倒産、リストラの推進、新規採用の抑圧、失業率の上昇、
労働スタイルの多様化という流れで、日本の労働環境はコロッと変わってしまった。戦後の経済成長華やかなりし頃の学歴偏重主義、終身雇用制度は
だんだん影をひそめ、実力主義、個性派重視、少数精鋭の生産性効率重視の雇用体制になってきた。その為より安い労働力を求めて、資本の国外移転が
進んでいる。国内の雇用は空洞化になり、ますます失業者が増え、主婦や新卒若年層など潜在失業者を計算すると、ゆうに10%以上の失業率を
越えるのではないだろうか。ヨーロッパの若年失業率が20%ほどになっていることから比較すれば、まだましなほうだと安心していていいのだろうか?
新卒では大学男子の90%台、女子の80%台、短大の70%台の新規採用率となると、残りの新卒者は、どうすれば良いのだろう?
そこで正規雇用に代わって登場してきたのが、派遣社員、契約社員、パート、在宅、フレックス勤務など労働の多様化と選択できる労働市場の柔軟化である。
このような労働スタイルの変革は、労働者にとって必ずしも不利益とは限らない。子育てや介護、趣味や生活目的に合わせて仕事を選び、時間を調節できるのは、
むしろ好都合でもある。そういう労働市場の背景があるからなのか、或いは親のインフラが、整備されているのをあてにしているからなのか、最近の若者達には「フリーター」とか
「だめ連」と称する人達が多い。彼等には定職がなくても、危機感や切迫感も感じられない。「今の間に自分のやりたいことをやっておく」「先が読めないのに
目標や志望は決められない」と言いながらアルバイトやパートで小遣い稼ぎをして、食いつないで、定職にこだわらない、働かない、結婚しない、焦らない、
気負わない・・・でも自分で「ダメなヤツら」と自認して「だめ連」といい、反抗するでもなく、反体制でもなく、無抵抗で不服従をユーモア化して楽しんでいるのだ。 以前の会社に忠誠を尽くす「永久就職」主婦の「家庭内永久拘束」といった労働に対する固定観念にとらわれている人達からみれば、彼等の生きざまは、 「異常」に映るかも知れないが、時代の背景から生まれた、自然発生的な思想で、現状の労働環境からの産物としての補完的現象でもあるのだ。 労働市場の多様化と柔軟化は、これからも進み「働くこと」「生きること」に対する考え方は、益々変遷していくことだろうと思う。でもそこで、 一つだけ断っておきたいのは、これからどんどん進む高齢化社会を支えるのは、彼等「フリーター」や「だめ連」を含む若者達であることである。 |
| 8月15日 | 終戦記念日 |
|---|
| 今日54回目の終戦記念日である。政府主催の戦没者追悼式が日本武道館で行われた。
それも遂先日、強制的とも思われる国旗国歌法施行に伴い「君が代」を初めて斉唱して行われた。しかし何となく
空々しい感がして、国民の関心はもう一つである。それもその筈、終戦の年に生まれた人は54歳になっている。
ほんとうの戦争の悲惨さを体験している人は、65歳以上位の人達だろう。だから日本の85%の人達は戦争体験者
ではないのだから、解らないことではない。
戦後54年間いろいろな形で「戦争」を語り、平和を祈願し、日本の復興のために努力されてきたお陰で、
今日の平和で文化的な生活を享受出来るようになったのである。ところが今世の中を動かしている世代は、「戦争を知らない子供達」
が成人して子供を育てている時代である。「戦没者追悼式」と言っても、世間のお墓参り位の体感だろう。いやもっと無関心かも知れない。
こんなことを書くと、戦争体験者から猛烈にお叱りを受けることだろう。でも現実は、それだけ安定した平和な生活の中で、
戦禍の悲惨さや敵国の恐怖を感じない平穏と安心の中で、満足している証左であろう。この平和を維持することは、
非常に結構なことだが、来るべき21世紀へどう引き継ぐかを、真剣に考えなければならない責務が残されていることを忘れてはならない。
世界に目を向けると、すぐ隣国の北朝鮮のミサイルの再発射の脅威と南北朝鮮の緊張、旧ユーゴのコソボ問題、インド・パキスタン関係、
中東問題、アフリカ内紛など民族、宗教、国境などをめぐって紛争が繰り返されている。我々がそれを対岸の火事のように、安閑と
していては、不見識である。政府も国旗国歌法や通信傍受法のほか、日米防衛協力のためのガイドライン関連法を成立し、
続いて安保基本政策に有事法制の整備をも検討している。平和と安全を確保するためには、来るかも知れない危険と脅威に対して、
万全の防衛体制を考えておくことは、必要である。しかし必要以上に国家意識が強すぎると、国家管理、国家統制に結びつき、
隣国を含む世界を刺激して、再び「戦争」という悲劇を呼び起こす危険がないとは言い切れない。そこのところを我々は注意深く
監視し、行き過ぎないように注視しなければならない。 |
| 8月13日 | 平均寿命の異変 |
|---|
| 日本人の平均寿命は世界一だという。非常に結構なことだし、誇りにしても良いことだと思う。
しかし毎年順調に延び続けてきた平均寿命が、昨年男性に関しては0.03歳短くなったということらしい。その原因が自殺者が大幅に増えたことに
起因するというから、びっくりする。厚生省の発表によると、1998年度の自殺者は、31,734人でその内男性が 22,338人で、前年より8.240人増えて
その内男性が 6.437人増えているという。なかでも50歳代の中高年の男性が半分以上占めているとのこと。これを聞いただけで、誰でもすぐ
近年の経済不況によるリストラ、営業不振、職場の労働環境の悪化、生活苦に主因があるのだろうということは、想像出来るだろう。
最近の医学や医療の進歩で、循環器疾患などの死亡率が下がって、男性も平均寿命が延びて当然であり、また悪質な流行病が発生して、
多数の死亡者が出たとか、阪神大震災のような災害によって多くの犠牲者が出たとか、特異な災難があったなら理解出来るが、自殺増が
平均寿命を引き下げたのでは、誠に空恐ろしいことである。 日本は四季に恵まれ、温和な気候風土で、知的水準も高く経済水準や医学水準も高く、国民の生活も健康志向がうるさいほど認識されているのに、 生命の尊厳が、経済不況による自殺によって引き裂かれてしまっている現況に、何とも悲惨で情けない思いが、強く胸を打つ。 阪神大震災後の仮設住宅内での老人孤独自殺、バブル崩壊後の借金逃亡自殺、リストラ恐怖からの加重労働自殺など、人間として生きることに絶望して この世を去らねばならない人達の心情は、計り知れない苦脳の境地だろう。いくら世界一の長寿と言えども、人間として「生きる喜び」「生活の楽しみ」 が伴わなければ、長寿の価値も誇りもない。長寿国日本の寿命も、その年齢の長さだけを誇張するのではなく、その内容や質を検討し改善されなければならない。 |
| 8月4日 | 河川・湖沼管理 |
|---|
| 近年の生活環境の変化によって、河川や湖沼の水質汚濁が大きな社会問題としてクローズアップされてきました。
我々の生活用水としての水源を、生活排水によって出すチッソやリンなどによって、富栄養化現象を呼び起こし、アオコや赤潮を発生させてる。
これは植物プランクトンの異常発生による現象で、この植物プランクトンが増えるとそれを食べる動物プランクトンも増えてしまい、水中の酸素を
多量に消費してしまいます。すると魚も住めなくなってしまいます。当然 生物の植物連鎖環境が崩れ水質汚濁が進みます。
水質汚濁の防止や河辺の自然環境を保護することについての先進国のドイツでは、以前は耕地や町の利便性から、「河川は真っすぐの方がよい」と
いうことで、直線の河川改修工事を進めていましたが、川の自然浄化作用や防災や自然環境保全のためには、河川の自然の姿、即ち蛇行する水の流れの方が
ベターであるという調査結果のもとに反省し、また元の姿に復元し直しながら、同時に水害防止の堤防を造ったり、水辺散策も出来るようにしたり、
生物の生息出来る水辺林なども造って、景観保全にも配慮した復元運動を展開しています。
河川や湖沼というのは、単に治水や利水という目的のためにだけ管理するのではなく、川自体、自然自体が持っている多面的な働きと、生物の生息のための
多様性を配慮して管理しなければならないと思います。日本でも1981年に「河川環境管理のあり方について」という答申がだされ、1990年には
川を改修する場合には、生物の生息場に配慮した「多自然型川づくり」の通達も出されてます。今回建設省は、来年度から市民参加の河川管理に取り組むことになり、
その業務を担う民間非営利団体(NPO)の支援に乗り出すことになった。その内容は、河川流域の動植物の保護、水質の環境モニタリング、ガイドブックの作成や情報の収集と発信、
環境整備の取り組みに対し、必要な経費や資材を国が助成したり、活動拠点となる施設の提供などを行います。そして別に「河川レンジャー制度」を創設し、
川や流域の自然や文化、昔ながらの知恵や幅広い情報を持った人を選び、環境モニタリングを行ったり、河川利用者への情報の提供やアドバイスの役割をも
担ってもらうという計画も立てています。 このように市民参加による河川管理には、それぞれの地域の気候や風土、歴史と文化を生かした川造り、動植物のすみつく自然環境、その地域の市民と川との 関わりを再構築するのがNPOの狙いです。非常に結構な計画である。どうか市民活動の知恵と工夫とエネルギーで河川管理活動が行われ、美しい水と豊かな自然の 復元によって、我々の生活用水も、きれいな水が安心して確保されるように、又動植物のすみつく自然な水辺環境が整うことを期待したいものです。 |
| 7月26日 | スピーチ |
|---|
| 何かの会合でのスピーチ、結婚式でのスピーチなど人前でのスピーチは、誰でも緊張するものですね。 くどくどと何を言っているのか判らないような長いスピーチも、聞き飽きます。また極端に簡単なのも誠意を感じません。 良く3分間スピーチと言われるように、3分にうまくまとめられていると、良い印象を残し好感が持てます。その印象も その人の人柄が出ていると、楽しく聞いていられます。そこで私なりに感じることを整理してみると、先ずユーモアを交えて 適度に虚構を入れる。しかしほんとうの「うそ」はダメ、うそを言うなら「誰でも判る明らかなうそ」を冗談で言って、 核心については、真実を述べなくては失礼である。そして自分のキャラクターを前面に打ち出して、誠意をもって気持ちを 素直に表現すれば、聞き手に理解してもらえると思います。時には流行語や方言もスパイスとしては効果的だが、基本は正しい美しい ことばで話すべきだと思います。話術もさることながら、内容を明確に表現出来ないと、聞き手を引きつけ良い印象を残すことは 出来ないと思います。「えーー」とか「あーー」とか「あのーう」とか 言おうとすることを考えながら話しているのは、話の主旨をまとめずに、 行き当たりばったり言っているように感じて、余り好印象を持たれません。事前に考えておいて、それを3分間ぐらいの長さにまとめて、 くどくならないように最後は、スッキリ締めてお礼を言う。経験の頻度もあるが、矢張りテープにでも取って、何回も練習すれば除々にコツが分かってきて、 本番で緊張せずに、自信を持ってスピーチ出来るのではないでしょうか。 |
| 7月19日 | ノータイ・ノースーツ |
|---|
| 夏本番を迎えて、男性のネクタイとスーツ着用の慣例は、いかにも耐え難く気に毒である。
近年の地球温暖化防止対策にかこつけてかどうかは分からないが、「上着着用不要、ネクタイなしOK!」の動きが目立ってきた。
その代わり、室内冷房を28℃に設定して、エネルギー削減することによって、地球温暖化防止に一役かおうというのが目的である。
非常に結構な話である。関西広域連携協議会が「サマーエコスタイル・キャンペーン」と名付けて、経済団体や企業、自治体にも
呼びかけている。今夏計画通り3ヶ月間実施すると、温暖化ガスの二酸化炭素排出量を約8万トン削減出来る計算らしい。
地球温暖化防止対策は、世界的な大きな問題で、我々ももっと認識を深め、対策を講じて協力しなければならないと思う。 しかしその反面ノーネクタイ・ノースーツ姿の男性のファッションは、何となくだらしなく見えるし、マナーとしてもとても正装とは 見てもらえない慣例がある。ならばYシャツに代わるニューウエアのデザインを考えてくれる人は居ませんか? どうも日本の男性の感性は、旧来からの先入観から抜け出す革新的思考力に欠けているように思う。女性のファッションが、 目まぐるしく変遷しているのに比べて、男性のファッションは十年一日の如く進化がない。そろそろこの辺で、思い切って 思考革命をしてみては如何なものでしょうか? 京大大学院工学研究科の中村泰人教授が提唱し、京都市が策定している 「京のアジェンダ21」でも、エコアパレルデザイン革命として「品格のある夏の男性用ビジネスウエアの開発」を目的と しているそうな。私は大賛成である。もし好感者が増え、人気が沸騰して全国的に愛用されるようになったら、衣料業界の 振興にもつながり、不況打開の起爆的要因にでもなれば、大成功じゃないですか。地球は冷め、体も冷め、頭も冷めれば 男は冷静になる。そして涼しい日本の夏を過ごしましょう! そうしましょう! |
| 7月10日 | 地方分権 |
|---|
| 中央省庁を1府22省庁から1府12省庁に減らし、省庁のスリム化と国家公務員数の削減を
目指し、官僚主導から政治主導にするために内閣機能の強化を計り、中央省庁の権限も地方行政に移譲しょうという、
地方分権整備法と中央省庁改革関連法が、2001年1月から施行されることになった。
規制緩和と地方分権という言葉は、もうイヤと云うほど聞かされてきた。しかし 官僚の省益優先や縄張り意識、
民間業者との癒着、地方に対する「上下・主従」関係の権威など、官僚にとっておいしいごちそうを放そうとしないための抵抗と、
政治の怠慢と無力から今日まで永い間ほったらかしにされてきた懸案の課題である。中央から地方へ権限、行政権が
移され、「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係になり、地方が中央に対してへこへこせずに、対等にものが言える
ということは画期的な制度改革である。しかし一つ気に入らないことがある。地方分権の行政基盤である財源移譲が
見送られたことである。機関委任事務が廃止されはしたものの、半分ほどが法定受託事務に名を変えて残している点である。
結局は地方への関与・介入を捨てきりたくないお上意識に未練があるのだろう。永い歴史の中で培われた官僚主導主義は、
なかなか簡単には排除しきれないガンであろう。
先日 石原慎太郎都政を取材するため、都議会の審議の模様が、テレビに映し出された。何より驚いたのは、多くの
都議員が居眠りしていることである。日本の首都、いや世界の巨大都市 東京の都政を預かる都議会の議員さん達の姿である。
都議会議員選挙の時の姿勢と対比してみてください。全く別の人格に見えてしまうのも、私だけでしょうか? この人達に、
これから国に変わって都政を委ねることになるのですよ。大丈夫だろうか?
地方自治体の自己決定権は大幅に増える。条例制定権も拡大する。それだけ自治体の責任は重くなるのです。
都議会(や県議会)という地方議会の役割が大きくなるだけ、都民、県民、市民の地方行政への関心も深まり、
監視の目も厳しくなるのです。居眠りしていて、真剣に討議にも加わらずに、住民の信頼を得られるだろうか?
まだ地方議会議員さん達に、地方分権の意識も現実味をおびていないだろうが、都議会議員さん達のような無責任な
地方自治体造りの姿勢だけは、謹んでほしいものだ。 |
| 7月4日 | 子育て |
|---|
| 生物は全て子孫を育て、その継続と繁栄を持続させる為の環境造りをするのが、
自然の摂理である。人間も当然の行為であり義務である。ところが近年の日本は、子供をつくらず、少子化が進み高齢者が増え、平均年齢は
年毎に上がっている。総理府の世論調査では、「結婚したら子供を持つべきだ」と答えた人は84.5% 「そう思わない」
は10.4%である。ところが18歳~39歳の女性に限定すると、「持つべきだ」は72% 「そう思わない」は2割を越えている。
一般論としては、子供は欲しい。しかし現実的には子供は育てにくい。だから子供づくりを抑えているのが感じられる。
その理由として、女性は「自由時間がなくなる」42.7%「思ったように働けない」31.8%のように仕事と育児の両立の
難しさが主である。一方 男性は「教育にお金がかかる」49.6%と約半分の人が経済的理由を挙げている。だから
育児に社会的支援の必要性を求めている人は、75.5%にものぼっている。その支援の内容は「育児中の夫婦が大いに
働けるような環境整備」63.8% 「税負担の軽減」33.4% 「児童手当など現金給付」27.9%など矢張り「金」である。 昔と違って一般社会的に文化水準が高く、生活費、教育費、交際費もバカにならない。夫も家庭を支える義務感は充分持っているが、 この経済不況下では満足のいく収入が期待できない。やむを得ず妻も共働きに出ざるを得ない。というより女性の社会進出と 社会的地位向上のためにも、大いにその能力を発揮してもらわなくてはならない。そいう状況の中で「子育て」をどうするか? を考えるとき、確かに困難なことが幾多と湧出してくる。「子育ての出来ない男は、お父さんではない」と云われるように、 「夫は仕事、妻は家庭」という定説は、今や完全に崩壊している。でも夫は経済的にも家庭を支える義務を負わされる。 その両立は夫婦平等に考え、義務化されるようになってきた。ほんとうに男は大変である。だから「子供をつくらない」では 日本の人口構造は、益々不安定になり、将来を危惧せざるを得ないことになる。そこで一日24時間を、1/3づつに分け、 8時間を仕事、8時間を家庭(子育て)、8時間を睡眠。というローテーションを夫婦で交互に組み合わせるという訳には いかないものだろうか? ・・・無理だろうな・・・? |
| 6月22日 | 介護保険制度 |
|---|
| 高齢化の進んだ日本の65歳以上の人口は、現在15%ですが2050年には32%、つまり3人に1人が65歳以上
と言うことになります。その内介護が必要な人と云われる、寝たきり、痴呆症、精神的肉体的虚弱老人などの割合は、65歳で1.5%、85歳以上で2.4%
にもなっているそうです。「介護したり」「介護されたり」するのは、誰もが何時かは経験する道でもありますが、しかし核家族化が進んでいる現在では、
その介護力は極端に弱まっています。約4割の高齢者が独り暮らしか老夫婦二人暮らしで、介護したり介護されたり出来ない生活環境になっている人達も
たくさん見受けられます。介護期間も65歳以上で亡くなった人の平均寝たきり期間は、8.5ヶ月にもなっているそうです。
「要介護者」とは、肉体的または精神的に何らかの障害によって排泄、入浴、食事などの日常生活が不自由になり、独りでは生活出来ないので、
誰かの介護が必要な状態の人のことです。その介護は、ある程度の専門的知識も必要で、医療が大きく関わることになりますので、
要介護者の介護は「医療保険制度」「老人福祉制度(法)」「老人保健制度(法)」という制度の中で行われることになっています。
しかしこの介護に必要な費用は、かなり多額な負担になりますので、公的な財政事情や私的な経済負担を総合的に勘案して、
要介護者の救済に応えるために考えられたのが、「介護保険制度」なのです。 この制度は、いつかは必ずと言っても良いほど自分の身の回りにも降りかかってくる問題なので、よりよい利用のために、 関心を持って勉強する必要があると思います。要介護者をもつ家庭の労力、時間、精神的、経済的負担は大変なものです。 特に老人性痴呆症を併発している場合のご家庭のご苦労は、筆舌に尽きません。1月19日に「ボケ」と題して この「みつおの独り言」にも書いたこともありますが、記憶障害や思考力の低下、人、時、場所の分別が出来なくなったり、 その人の人柄が失われる人格低下を来たし、徘徊、昼夜逆転、叫声、嫉妬・被害妄想、幻覚、鬱(うつ)などの症状が現れますと、 もう手が付けられなくなります。この痴呆症の人は、65歳以上で6.3%、85歳以上では3~4人に1人は居られると云われています。 これほど大きな社会問題になっている痴呆症の、効果的な治療法もまだ確立されていませんが、発病にはその人の過去の生活、 老後の社会参加、生きがい様式などが関係していることを理解し、あくまでも受容的な介護が求められる事にならざるを得ません。 かなり忍耐と努力が必要とされる介護ですが、このことは国民的理解と協力によって、法的に制度化されることは、 必要不可欠なことであり、来年4月から施行されることも、むしろ遅きに失した感さえします。制度の詳しい内容については、 ここでは割愛しますが、明るい21世紀の日本の福祉行政のために、この「介護保険制度」が充分に機能し、老後の不安が 解消され、生きがいのある高齢社会の実現を、切に願っております。 |
| 6月14日 | ボランティア |
|---|
| 数年前の山陰・北陸地方でのロシア船からの重油流出事故や、4年半前の阪神・淡路大震災の時には、
全国から沢山のボランティアの人達の協力があって、人の善意の尊さが改めて評価された。そして高齢社会を迎えるにつけて、
社会福祉の充実が叫ばれるようになって、益々ボランティアの重要性が見直されてきた。
数年前に東北地方にボランティア論とボランティア実習が必須の短大まで出来てきた。「本来ボランティアは、
自発的で個人の正義感や協調性の善意から行われるべき筈のものが、学校での必須科目でそれを評価することは、
進学や就職に有利になるということだけで履修する学生も出てきて、自発性、自主性というボランティアの理念を
ネジ曲げ、強制するもので、偽善者を作ることにもなりかねない。」とか「ボランティアの振興など、公的責任で
行うべき社会福祉を、人任せ的にあいまいにし、公的責任を転嫁し、安上がり福祉にしょうとするものだ。」などと
批判し、反対する人達もいる。そしてボランティア論を学ぶ学生自身にも、そう思う人もいるかもしれない。
しかし この短大には、「看護学科」介護福祉士の養成課程でもある「人間福祉科」それと「地域社会学科」
の3学科があり、いま世の中に求められている、様々な不自由や悩みを背負っている人々を支援、援助するために
必要な課題を勉強する学科として、評価しても良いのではないだろうか。世の中の見ず知らずの人達に対する理解と共感、
正義感に燃える責任感と倫理性、人の命や生活を見守り、自分を捨てて愛の手を差しのべる気持ちは、独りよがりの
関心しか持たない人や学校の偏差値だけを、唯一の評価基準としか見ない人達には、とうてい共鳴してもらえないだろう。 地域社会に根ざすボランティアを目指す人達には、理論や理屈だけでなく、その街、人の住む所についての観察力、 フィールドワーク力、心理、精神力を体験、実習の中から身につけて、気の毒な人達の手助けになって、人間としての 気高い生きざまをして欲しいと願っている。現に実践し体験している実行力は、口先だけの理屈や要領の良さだけでは、 何の説得力も持たないことを解ってほしいものだ。 |
| 6月5日 | 愛国心と戦争 |
|---|
| 今世界中で注目を浴びているユーゴスラビアのコソボ紛争は、もとはといえばコソボ自治州に居住する
セルビア人とアルバニア系住民の対立を、ミロシェビッチ大統領が、アルバニア系住民を虐殺したり、追い出しにかかったことから紛争が始まった。
その根源は民族対立である。一方パキスタンとインドの対立を増長させている核開発競争。北朝鮮やイラクなどへの核査察問題の根源は、国家、民族、
宗教、政治などが絡み合った愛国心の延長上に由来する国家行動である。
我が国も第二次世界大戦までは、「我が民族の誇りは・・・」「我が民族の独立を勝ち取ろう・・・」「敵対する横暴な〇〇人種を排除せよ・・・」
など国家、民族主義が敵対意識を高揚し、紛争や戦争を繰り返してきた。この歴史も聞こえは美しく聞こえるが「愛国心」という片寄った地域愛が、
バックボーンとなっているのは、皮肉ではあるが現実ではなかっただろうか。
こうした「愛国心」→「戦争」という図式を造り上げているのは、その国の教育である。幼少のころから徹底的に民族愛、愛国心を押しつけて、
他民族、他国家に対する対抗意識が、排他的な対立主義を造り上げているのではないだろうか?このような美しいひびきを持つ愛国心の危険性を
認識し、相互の不信感をつのらせることのないような、国際的信義感を尊重する制度、教育の道を構築することが急務ではないだろうか。
20世紀は戦争の時代であった。しかし来るべき21世紀は、全世界が「地球は一つ!」同じ人間である信頼感を持って、国際平和で安心出来る地球で
ありたいと願っている。 |
| 5月24日 | ドメ・バイ |
|---|
| 「D・V」とか「ドメ・バイ」とか聞き慣れない言葉が、最近話題になっている。正確には、ドメスティック・バイオレンス(DomesticViolence)といい、
短縮して「D・V」とか「ドメ・バイ」と云っているらしい。直訳すれば、家庭内暴力のことだが、主旨は「夫や彼氏からの女性(妻や彼女)に対する暴力」を指している言葉で、
セク・ハラ(SexualHarassment)とは内容を異にしている。女性の地位向上、男女の格差を是正する考え方は最近特に話題が多い。 日本古来から男尊女卑的な男社会が永年続いてきた。その為女性はしいたげられて、耐えて耐えて男の下馬をなめさされてきた。ほんとうに気の毒であった。 「戦後 強くなったのは、女と靴下」などと揶揄されているが、結構なことではないか。当然あるべき姿に戻ろうとしているのだ。 男女平等、男女同権、同じ人間として当然だろう・・・。
ところが現実の社会では、女性は力がないから口先で男に挑む、男は口で負けるから腕力でねじ伏せようとする所に「ドメ・バイ」が起こってくる。
お互いが相手を認め、相手の言い分を聴く耳をもって、一歩づつ引き下がれば、和合し合えるのに、お互いが自分の我を通そうする所に問題が発生する。
人間の感情は、なくてはならないが、度を越すと今度は手がつけられなくなる。困ったものだ。それを抑えるのは「理性」である。
何でも必ず両者に言い分はあるが、お互いが自分の立場を主張すれば衝突する。お互いが相手の立場に立って理解し合おうと前向きに譲り合えば、・・・
どうぞ・・・どうぞ・・・と手を差し伸べるようになる。そのチョットした気持ちと姿勢と考え方で、ドメ・バイは防げるのではないだろうか?
口で云ったり、文章で書けば簡単だが、現実はそう甘いものじゃない。いろいろな事情や状況がそこにはあるのだから・・・。それも解る。
しかし「ドメ・バイ」はいかん! そこのところを理性で抑えて、英知を搾り合って男の暴力のない世の中にならないものだろうか? |
| 5月12日 | ゆとりある心 |
|---|
| 春のまぶしい光に照らされた鮮やかな新緑を眺めていると、何となく もうじっとしていられない
すがすがしさをおぼえます。日頃運動不足を自認している私も、このさわやかな春の風に当たってからだを動かしてみようと、自転車をこぎだした。
めったに自転車にも乗らない私でも、何とか走れるものだ。自転車に乗りながら、ふと こんなことが頭をよぎった。
この自転車のタイヤと地面とが直接ふれている道幅はどの位だろう・・・?ちょっと降りてタイヤを見てみると、約3㎝位のものだろうか・・。
私は3㎝幅の道路しか使っていないのだ。じゃあ3㎝幅の道路があったとして、その道を自転車で走れるだろうか?それは絶対無理だ。どんな上手な
人でもまずすぐ倒れてしまうだろう。3㎝しか使わない道路でも、それを支えてくれるゆとりある道幅があるからこそ走れるのです。
我々は遂そのことを忘れがちになっている。 私達は自分の力で生きていると思っている。しかし その周囲には、目に見えるもの、目に見えないもの、さまざまな事柄や人達の 支えによって生かされているのです。自分一人の力だけでは生きられないのです。ゆとりある心が、支え合って生きている人生を、広角的に見る眼を 養ってくれるのです。 下農は雑草を作り、中農は作物を作り、上農は土を作るという言葉がありますが、立派な作物は立派な土壌によって作られるのです。目に見える作物ばかりにこだわって、その土壌作りになかなか目が 行き届かないという戒めの言葉を、よく読みとらなければならないと思います。 3㎝幅の自転車道を走れる為には、ゆとりある広い道路があって、始めて安心して走れることを実感して、自分がいろいろな人達や世の中の全ての 事柄に支えられて、生かされていることを感じた一日だった。 |
| 5月5日 | こどもの日 |
|---|
| 母の日があり、お情けで父の日を作ってもらっているが祝日ではない。母の日や父の日には、感謝の気持ちとねぎらいの気持ちが
込められているが、こどもの日には、健やかに育って欲しい気持ちと将来に対する期待感が含まれている。鯉の滝登りのように勇ましく激流に立ち向かって欲しい願いを込めて、
鯉のぼりを立てて端午の節句を祝っている。しかし現実の子供達には、親や社会が願っている思いとは裏腹に、いじめ、学級崩壊、児童虐待、非行事件など
社会問題化している行動で頭を悩ますことが多い。学校が悪い、家庭が悪い、社会が悪い、などと責任を押しつけ合って、問題解決の処方せんはなかなか見いだせないでいる。
中央教育審議会は、昨年6月「幼児期からの心の教育の在り方」について、家庭での親のあり方、役割を強調する答申まで出している。そして今年の2月には
「子供の未来と世界について考える懇話会」として政府が動き出した。世の中の偉い先生方が提言していることは、決して間違っていないが、
ただ紙に文章を書くだけで、子供の教育問題や子育てが簡単に変えられる程単純なものではない。各家庭の事情も千差万別で、教育論、育児書通りにはいかない複雑な現実がそこにある。
全く give up 寸前の状態になっている。 じゃあ どうすれば良いのだろうか? 何も手を施さずに放任しておいて問題解決が出来るのだろうか・・・。 私は基本的には、信頼関係に尽きると思う。親や社会は学校や先生を信頼し協力する。先生は親や子供を信頼する。 そして親は我が子を信頼する。学校や社会や政治家の悪口ばかり云わずに、また先生も家庭や社会に問題を押しつけることなく、 信頼と協力関係を保ちつつ、子供達の長所を見出す努力をすることだと思う。そこで私は「3A」つまり3つの「あ」を提言してみよう。
|
| 4月29日 | みどりの日 |
|---|
| 昭和天皇の誕生日の4月29日が昭和天皇のご逝去により、平成元年以来「みどりの日」として
祝日に制定された。その要旨は「国民が自然に親しむと共に、大地の恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日」と定められている。
新緑の鮮やかさが眼にまぶしく、新しい芽生えは「これからだ!」とスタートの気概を感じ、実にすがすがしい気分になる。
だから私は緑が大好きである。特に新芽の黄緑は最高だね。そういう時季である4月29日が「みどりの日」と命名されたのは、
当を得て適切な名前であると思う。
「みどり」即ち山や森の木々の営みは、今更筆舌にするまでもないが、鳥や動物達に住処や食べ物を与え育てている。雨水を蓄え川や地下水を
生み出し、又光合成による炭酸同化作用によってきれいな空気を提供してくれている。そして我々人間に美しい景色とすがすがしい気分を与えてくれる。
木々のみどりの功績は万人が認めている筈である。にも拘わらず木材、薪、紙を造るために見境なく樹木を切り崩し、ゴルフ場やリゾート開発のために
根こそぎ大自然を破壊してしまっているのは、一体誰なのだ! その結果、多くの動物が絶滅したり、CO2の増加と共に地球の温暖化も進み、全ての自然の
バランスを失っている。何と情けないことか・・・! 「国民が自然に親しむと共に、大地の恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日」とするためには、一本一本の木に対する愛着の気持ちを忘れてはならない。 どうも経済的効果を期待し、一部の人の利益の為に多くの人を犠牲に陥れているのではないか。今日「みどりの日」をいま一度見つめ直し、 自然と共生していく為の手法を、反省と共に考え直そうではないか。でなければ大自然からのしっぺ返しが、すぐそこまで来ているのだ。 空気も水も土も木も美しくきらきら輝く素晴らしい地球を、宇宙で一番輝く星にしようではありませんか。 [ みどりを愛する みつお ]
|
| 4月24日 | 陽は沈む |
|---|
| 我々の子供の頃は、学校から帰ってくると、友達の家へ遊びに行ったり、
近くの山で木の実や野いちごを見つけたり、神社の馬場で草野球をしたり、小川で魚を捕ったり、裸で泳いだり、走ったり、跳んだり、
とにかく遊びに夢中になって、宿題なんか全く気にも止めていなかった。そして夕陽が沈み、あたりが暗くなって、やっと一日の終わりを
感じ取ったことだった。
今の子供達はどうだろう?自然の草木や風を肌で感じ、あの美しい夕陽をどれだけ見ているだろう。都会では、高いビルに囲まれて、
空気はスモッグに覆われて、美しい夕陽の色合いもないかも知れない。そして その時間帯は塾で勉強やレッスンに励んでいるのだろう。
また塾に行かない子供達は、遊ぶ友達がいないから、部屋の中でファミコンに夢中になっているのだろう。
人間形成にとって一番大事なことは、幼少時代に友達との付き合い、人と人との結び合いが、どれだけ大切なことかを、
遊びの中から学ぶことだと思う。人間にとって一番弱いところは、孤独であり、孤立された一人ぽっちの時であろう。
人は、人との結び合い、触れ合いなくしては生きていけない動物なのです。だから人と人とがどうして結び合い、
どうして助け合い、どうして分かち合い、また どうして争い、どうして仲直りして、お互いの考え方や生きざまを
仲間の間で反映し、融合していくかを、遊びの中から学び取っていくのが大切なことだと思う。
夕陽を見ることが、一日という時間の終わりを教えてくれると同時に、地球の全ての資源もまた無限ではないことも
理解しなければならない。世界中の人々が、我々の仲間なら、その仲間と資源を共有しなければならない。
空気が汚れ、水が汚れ、土も汚れ、食べ物が足りなくなってきた。ねえ・・そうだろう。フロンガスでオゾン層が破壊され、
地球の温暖化による自然破壊、CO2、熱帯雨林、核問題、そしてダイオキシンで土も水も空気も犯され、人体に危険を及ぼし、
生活を脅かしている。
全てのものが無限であると思っていたことの間違いを、今初めて肌で感じて、科学文明の後始末に振り回されている昨今である。
来るべき21世紀は、20世紀の過ちを取り戻し、宇宙に眼を向けた自然回復に取り組まなければならない世紀になるだろう。
その為には、何をしなければならないか、何が出来るのかを、遊びの中から、人と人との関わり合いの中から、学び取ってほしいものである。 |
| 4月18日 | 人の一生 |
|---|
| 今 自分の生きざまは、これで良いのだろうか? 今日までの年月を永く感じたか、短く感じたか?
楽しかった期間は、瞬く間に過ぎ去り、時間の経過を忘れ去っていた。しかし苦しかった期間は、その苦境からの脱出を思い願うことばかり考えて、
なかなか思うように事がはかどらない焦燥から、とても永く感じる。このような感覚は誰しも思い当たる節があるだろう。
人の一生は、誰しも限られた時間帯であって、永久に生きられるものではない。その与えられた時間を有効に費やされるならば、
人間として最も価値有る人生である筈である。しかし実際は、その多くの時間を浪費しているから、短く感じ満足のいく結果が
生まれてこないのではないだろうか。
例えば、今は仕事が忙しい、仕事が一段落してから・・・しよう。或いは定年退職し時間に余裕ができたら・・・しよう。そしてまた考えよう。本も読もう。
音楽も聴こう。旅行もしょう。趣味も楽しもう。世のため人の為になるようなこともしょう。あれもしよう、これもしよう・・・と。
自分の死を考えないで、永久に生きられるかのように、時間に関しては実におおらかに使っている。
いろいろ思いめぐらす事を実行出来るその年まで生きられる保証はない。今やらねば、出来る日が来るとは限らない日まで
延期しょうというのは、生命の限界を考えない愚劣なことではないだろうか。
人生を短くするのも永くするのも、与えられた時間の使い方、つまり生き方一つであると思う。「今日が最後の日になるかもしれない」のである。
人生を生きることは、それ以上に死ぬことを考えて、今日一日を、今この時を生涯かけて学ぶべきことではないだろうか。今日までをアツという間に
過ぎ去ったと感じている自分のふがいなさを反省し、自分の生きざまを真摯に見直したいと思っている。 板村真民さんの「二度とない人生だから」という詩を読み返してみよう・・・ 二度とない人生だから 二度とない人生だから 二度とない人生だから 二度とない人生だから 二度とない人生だから |
| 4月11日 | 統一地方選挙 |
|---|
| 今日 4月11日は全国統一地方選挙の前半戦で、東京、大阪はじめ
12都道府県知事選と44道府県議選や11カ所の政令市の市議選も同時に行われる。最近の選挙は行われる度に投票率が下がっている。
何故だろう? 政治不審で行政に対する期待も薄らぎ、政策発表に対する信頼感もない。それ故無党派層と呼ばれる浮動票が多く、 政党に対するこだわりもない。。最近の行政は誰が携わっても同じ事。だから投票しても一票の重みなど有権者に伝わってこない。 だから投票しても無駄なこっちゃ・・・と思っている人達が多いからだろうと思う。もし そういう気持ちで誰も投票しなかったら、 選挙とは一体何なのか? 議会制民主主義とは何なのか? を根底から問い直さなければならなくなる。
政治が悪い。行政に信頼感がない。もう議会など必要ない。などと全て否定的に排他的に無視するのなら、有権者としての
義務も権利も放棄していることになる。自らの義務を履行せずに、権利だけを主張し、政治批判するのは理にかなった言動ではない。
まず自らの一票を投じることの意義をしっかり認識して、投票所に足を運んでもらいたいものだと思う。 昨今の深刻な不況に対する地方独自の景気対策や雇用対策、来年4月からの介護保険制度、少子高齢化対策、 地球温暖化対策、ダイオキシン問題にゆれるゴミ処理対策などの環境問題、地方財政難に対する行財政改革、青少年教育問題など 数え上げれば枚挙にいとまがない程の解決すべき課題が山積している。これらを適切に対処していかねばならない地方議会議員を選ぶ選挙が、 今回の地方選であることを認識しなければならない。地方分権によって、より良き地域づくりの為に、我々住民の為に真摯に取り組んでくれる議会を つくってくれるにふさわしい地方議員を真剣に選ぼうではないか。その為には、まず投票所に行こう! |
| 4月2日 | 生きがい |
|---|
子供が成長し自立力や独立心が高まってくるにしたがって、子供や家族は、親に対する思いやりや気遣いから、
親に対して必要以上に仕事を取り上げ、至れり尽くせりの面倒を見ている人が居る。親は「うちの息子や嫁は、良く気を使ってくれて、何から何まで
してくれるし、何もせずに寝て暮らしているようなものです」なんて云って、からだを動かす事も、頭を使って考えることもしないで生活していると、
からだの至る所に障害が出てくることになります。
だから親は、子供や家族の手助けに甘えることなく、自分の事は自分でする。出来ることは積極的に行動し、精神的にも自立するように心がけることが必要だし、 家族は、その点を理解し、必要以上に仕事を取り上げる事のないように、家庭内でも何らかの役割を担ってもらうような心遣いをすることが必要だと思います。 家族のために、世の中のために、誰かのために何らかの形で役に立って、喜んでもらえること程嬉しいことはない。人間は希望や目標を持って、 前向きに生きること。そして自分の存在感を認めてもらい、人に感謝してもらえる何かを与える。その為に努力する。多少つらいことがあっても、 成就できた時の喜びは又格別な満足感に浸れるものなのだ。そんな「生きがい」を求めて、健康で元気で人生を歩むことこそ「生きがい」そのものであると思う。 |
| 3月21日 | 改正男女雇用機会均等法 |
|---|
| 今日まで人種差別、部落差別、障害者差別、男女差別、出身校差別等々、人が人としての人権に、何らかの差異を原因に
差別が繰り返されてきた。今尚この問題は、全世界的なテーマとして、多くの国々で又広い地域で議論の場が持たれている。非常に難しい問題だろうと思う。
しかし その難題から逃げていては解決の道は開かれない。コツコツと一つ一つ差別解消の道しるべが築かれていることは、大変喜ばしいことだ。
今回 4月1日から施行される「改正男女雇用機会均等法」もその一つで、働く女性の味方として、ジェンダー・ハラスメント(社会的な性別差の悩み)
の解消の起爆剤になって欲しいものだ。 この改正法の詳しい内容については、ここでは省略させていただくが、この法律は、
差別というよりセクシュハル・ハラスメント(SexualHarassment)[略してセクハラ=性的嫌がらせ]防止対策としての意味が主な特徴だろうが、
倫理的な意識改革だけでは問題が解決出来ずに、法的規制で対応しなければ収まらないところに、人間の倫理観の欠如を恥ずかしく思う。
職場、仕事だけでなく、最近のコマーシャルで「子育てをしない男は、父親ではない」などと家庭内での父親と母親との役割分担をも排除し、
男女画一化された社会構成や家庭環境を目指している風潮になってきた。それはそれで結構だが、一方 同時に改正労働基準法も、4月1日から
「女性保護規定」が撤廃され、女性の職場での時間外、休日労働、深夜業の規制もなくなり、女性からすれば「女だから・・・」という甘えも
許されないということになり、義務感も課せられ、逆にプレッシャーを感じながらも、勇気と覚悟も必要になってくるだろうと思う。
権利が保証される裏には義務も存在することを認識して、男女お互いが仲良く協調できる社会構築を目指して、努力しょうではありませんか。 |
| 3月13日 | お茶 |
|---|
| 何となく疲れて眠気が出てきた。チョット一服しょうと熱いお茶を飲んで体を休めていると、しばらくして眠気もとれ、
頭がはっきりして元気がでてきた。お茶は日本古来から頭痛除去の効果もあり、生活に密着した飲料として親しまれてきたが、何故そんなに効能があるのか
不思議な気がする。そこで お茶について少し調べてみた。
お茶の成分には、カテキン、カフェイン、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、βカロチン等が含まれていて、カテキンはタンニンの中の化学成分で、
正しくはポリフェノールと呼ばれる。このポリフェノールは水溶性なので、お湯にそのまま溶けて酸化を抑制し、アドレナリンの分泌を抑え、血圧も下げる効果がある。
その上カロリーがほとんどないというのもヘルシーである上に、老化やガンの初期の兆候を予防する効果もあると云われている。
そして お茶の葉の約半分がカテキン、つまりポリフェノールということなので、効率も良いということになる。
また お茶を100g飲めば、一日に必要なビタミンCのほとんどが摂取できるということらしい。ただしβカロチンとビタミンEは、脂に溶ける成分なので、
お茶を飲むとことで直接全て摂取出来ないが、葉っぱそのものをすって作る抹茶からは摂取する事が出来るのである。 そのようにお茶には、ポリフェノールやカフェインやビタミンの作用で、眠気をさまし、疲れを癒し、活力を生み出す効能があるのである。 緑茶は蒸気でむして作られるが、発酵させて作る紅茶、ウーロン茶なども同じ材料から作られ、世界的には紅茶が最も多く愛飲されている。でも日本人には 緑茶が一番口に合っていて、最近 自販機での売り上げもトップを誇っているという。日本古来からのお茶に注目し、もっとお茶を飲み、お茶でリラックスし、 健康的なお茶国民になろうじゃないか!! 断っておくが、お茶屋さんからは1円の賄賂ももらっていないことを付記しておく。誤解のないように・・・。 |
| 3月9日 | 少年少女問題 |
|---|
| ここ数年 少年少女問題で「いじめ」「家出」「教師への暴力」が増え続けているという。いろいろ議論百出している中で、
政府は、現行の少年審判手続きを大幅に見直す少年法改正案を、法制化しょうと考えている。確かに少年少女問題は、深刻で難しい問題である。問題解決には、
ある程度法律の力で抑制するのも致し方ない部分もあるとは思う。
学歴偏重主義による詰め込み学習の歪み、親の過保護による甘え、経済力や生活文化の向上による忍耐力の減退、社会の倫理観・道徳観の変化、夢や希望をいだく
将来志向の不透明さ、等々 社会制度、環境、教育観など諸々の意見が続出している。
相手の気持ちになって接する思いやりの心をもつ「共感性」と理屈抜きで相手の話を聴いてあげる「傾聴性」があれば、自分の主義主張を押しつけたり、
排他的に誰かに何かに責任転化するような逃避主義は、なくなって「信頼と信頼」「気持ちと気持ち」「心と心」の結びつきで、解決の糸口が見いだせるのではないだろうか?
そんな簡単な甘いもんじゃないとおっしゃる方も居られるとは思うが・・・。 |
| 2月17日 | ゼニのなる記 |
|---|
| この景気の悪い昨今、お金の貯まらない私に、忠告を含めて教えてくれた教訓をご披露してみよう。
勿論このような言葉は、星の数ほど巷にあふれている。解っていても知っていても実行出来ないのが人間の弱さ。 でも敢えて反省の意味を込めて 書いてみよう。 |
|
| ゼニのたまる人 | ゼニのたまらぬ人 |
|---|---|
| 感謝の生活をする人 | 常に不平不満を云う人 |
| 収入以下で生活をする人 | 見栄を張りぜいたくする人 |
| 夫婦仲の良い人 | 夫婦仲の悪い人 |
| ゼニや物を大事にする人 | 物やゼニを粗末にする人 |
| 健康に心がける人 | 悪友を持つ人 |
| 独立自尊心の強い人 | 依頼心の強い人 |
| 仕事を趣味とする人 | 道楽の多い人 |
| 一事につらぬく人 | 三日坊主の人 |
| 常に節約する人 | 常に借金をする人 |
| 儲けをあてにせぬ人 | 一攫千金の夢をみる人 |
| 徳は元、財は来るぞよ 徳つめば、ゼニは自由になるものと知れ ! ! | |
| さて あなたはどちらが多い? 私は右が多い! 自慢にならないなア・・・ショック! 反省!! | |
| 2月7日 | 環境ホルモン |
|---|
| 先日 大阪市森之宮のゴミ焼却工場の敷地内土壌から、21,000ピコグラム(1ピコグラムは1兆分の1)の
ダイオキシンが検出されたと厚生省から発表があった。環境庁が昨年11月に発表した、住宅地でのガイドラインは土壌1g当たり1,000ピコグラムだから、
基準値の21倍ということになる。しかし厚生省は「環境庁の基準は、居住地の汚染土を口にした場合の危険度を基準にしているのであって、
ゴミ焼却場の土壌にそのまま当てはめることはないので、直接人体への影響はない」とのことでした。
しかし 最近このように「環境ホルモン」と呼ばれて、特にダイオキシンが人体に及ぼす影響について注目され、大きく報道されることが多くなっているのは、
そのダイオキシンが、ゴミ焼却場だけでなく、工場、製鉄所、石炭、車の排気ガス等いろいろな所から排出されていて、空気や水や土壌を汚染し、
食品(特に農産物、海産物)を介して、畜産物、農産物から体内にも蓄積される危険性があるからである。
環境ホルモンは微量でも影響度が高く、体内に蓄積され長時間経過しても、後日影響を及ぼしてくると言われている。動物の臨床実験では、
妊娠しにくくなったり、生殖機能の異常、生殖器の奇形、甲状腺の機能障害が確認されているという。人間も男性の精液量の減少、精子の活動の低下、
奇形率が増えたり、又 女性の母乳からもダイオキシンが検出されている。また一説には、口に入るもの以外にも、合成洗剤、殺虫剤、塗料、化粧品、
合成ホルモン薬にも含まれる場合もある等と言われている。
こうして体内で、生殖に関係する体の機能に悪影響を及ぼすという点でホルモンと呼ばれ、生活環境から起因する有害物質なので「環境ホルモン」と
呼ばれているのだろうと推察出来るが、これ全て人間自身がまいた種なので、人間自らがその種をつまみ取り、子孫に迷惑をかけないようにしなければならない。 |
| 2月3日 | ガン |
|---|
| 昨年の春 私の兄が膵臓ガンで入院し大手術の結果、お陰で今は養生しながら元気で暮らしている。
初期発見で対応が早かったので助かったが、もし発見が遅かったら非常に怖いところだった。その為ガンに対する関心も高くなり、いろいろと勉強
する気持ちが強くなってきた。
最近の食生活で、高脂肪・高蛋白の食事が話題になってくるようになってきたのは、矢張りガンとの関わりが大きいからだと思います。
|
| 1月28日 | 息子の結婚 |
|---|
| 日頃ほとんど親子の会話がなく、何を考えているのかさっぱり判らない息子から、ある日突然「結婚しょうと思っている」
と言い出した。息子に彼女らしい女友達が居ることは知っていた。矢張り彼女との結婚を決意したようだ。私は、結婚は本人の問題なので、彼女以外の親兄弟のことは
余り関心もなく、深くこだわらない方だが、一応結婚という大きな節目のイベントなので、一通り聞き 式のスケジュールについても問いただした。
矢張り一番の問題点は、資金のことのようだ。日頃から経済観念の薄い、金使いの荒い生活ぶりから、充分な貯金がある訳がない。だから当然のことながら、
彼は彼なりによく考えて、余り派手なことは避けて、余分なお金を使わないように計画を立てていて、「予算はこうなるから約○○円ほど面倒みてほしい」と頼んできた。
私は直ちに「分かった!応援してあげよう」と即答した。その訳は、彼の説明と計画と考え方に共感する所が多かったからだ。今までの彼に対する印象と評価では、
とうてい納得できるような生活ぶりではなかったが、年と共に成長し人間としても、もうそろそろ嫁をもらっても良いのでは・・・と思える年齢と考え方と人格が備わってきたように
判断できたからだ。いろいろと心配し、頭を痛めてきた息子も、やっとここまで成長してくれたのか・・・と感無量の思いだった。
「この息子は私の息子だ。自分の息子を信じ、彼に全てを任せよう・・」と心に決め、一切口出しすることを控えた。そして結婚式も無事終えることができた。
何から何まで全て自分自身の手でやり遂げた。勿論100点満点ではなかったが、まず合格点は付けられるできばえだった。 |
| 1月19日 | ボケ |
|---|
| 老人性痴呆症(アルツハイマー型痴呆症)に悩む家族が増えている。この病気は、もの忘れが重度に進行した病気だが、
誰でも もの忘れはするもので、何でも全て記憶出来たら、人間はもたない。年老いてもの忘れを自分自身で解っている記憶システムは、まだ正常な状態で問題はないらしいが、
ただ通常憶えている必要のある言動を忘れてしまっているところに問題がある。
本人は全くもの忘れに気付いていなくて、昔のことはよく憶えているのに、昨日や今日の新しい出来事を記憶できずに、同じことを何度も質問したり、食べたての食事を
すぐ又食べたり、初対面の人の名前や顔をなかなか覚えられなくなったり、道に迷ってうろついたりするようになってくると、これはもうほっとけないボケの進行が進んでいると云われている。 この病気は、人間の脳には新しい記憶を蓄えるタツノオトシシゴの形に似た海馬というものが障害を受け、脳の中にβアミロイドが沈着したり、神経細胞に異常にリン酸化されたτ(タウ)蛋白質が 増えてきたり、アポリポ蛋白E4を持っている人がかかりやすい等と云われているらしいが、要は140億個以上あると云われている脳細胞が、 除々に死滅して少なくなってくることによって、脳機能が衰え、記憶、判断、行動処理に不都合が生じてくるということらしい。 だから常に脳細胞に刺激を与え続けて、活性化しておかなければならない。頭を使い、手足を動かし、人間関係を大切にして神経回路の働きを活発にしておかなければならない。 ということまでは解ってきたが、さて それでは一旦アルツハイマー型痴呆症にかかった人を、どうして早期に完全に治すか?・・・ということになると、まだ確実な治療法は確率されていないらしい。 どうか賢い先生方に研究していただいて、この高齢化が進んでいる現代社会で、こういう深刻な心配事を、早く取り除く治療法を開発してほしいと願っている私です。 |
| 1月15日 | 成人の日 |
|---|
| 今日1月15日は、全国で170万人もの新成人を迎えて、各地で成人式が行われましたが、大人への門出を祝ってもらっている彼等は、今何を考えているのだろう。 最近の若者にとって、気になる一番の問題点は、経済環境の悪化のために就職状況が氷河期を迎えていて、将来に対する不安と夢の喪失だろう。社会に出て自分の能力を 発揮しょうとする以前に、その活躍の場すら与えてもらえない焦燥から、社会という森を観ることより、自分という個人の木しか見えない孤立感に陥っているのではないだろうか。
その点は彼等の責任でもなく気の毒に思う。しかし一般的に今の若者が全てそうだとは決して思わないが、成人としての社会参加の一歩である選挙権の行使も履行しようとしない。即ち
日本という森、地域社会という森を観る眼を失っている若者が多いように思う。
又 最近の伝言サービスを利用した殺人事件や、インターネット通販による青酸カリ自殺事件のように、情報社会の利便性を逆手にとっての無頓着な行動は、
不特定の人達の集まる社会より、個人対個人の関係に情報機器を使いこなす知識と理知にしか、活用の場を見いだせないでいる。
ポケベル、携帯電話、インターネットは情報通信社会における身近な機器として、若者の生活行動スタイルを変革させた要因になっているのは確かである。
その情報社会の進歩とスピードに、柔軟な思考力と機敏な応用力を駆使する能力は認め評価できるが、それを社会という広域な世界での効率的な利用のためのメディアであるという
認識が欠如し、個人の衝動的な欲得に悪用されては、成人としての良識と責任と自覚を疑わざるを得ない。 |
| 1月7日 | 春の七草 |
|---|
| 春の七草と言っても、何のことか解らない人も多いのではないだろうか。七草とは七種(ななくさ)とも書き、
人日(じんじつ)ともいう。昔から正月七日の朝、せり、なずな、ごぎょう、はこべら(はこべ)、ほとけのざ(たびらこ)、すずな、すずしろ、という
七種類の草を入れた粥(かゆ)を食べると、その年の邪気を払い万病を取り除くと信じられて来た。その為私も子供の頃には、七種類の草が入っていたかどうかは
判らないが、うまくもない粥を1月7日の朝食に食べさせられていたことを憶えている。 このような行事は、元は中国の風習で、日本に伝来したものと言われ、江戸時代には五節句の一つに定められていたと言われていて、 どこの家庭でも行われていた慣例だった。ところが最近は正月のしめなわ(注連縄とも標縄とも七五三縄とも書く)もめっきり少なくなり、門松などめったにお目にかかれない。 国旗に至っては全く影を潜めてしまった。勿論七草かゆなど食べた人などいないだろうと思う。もっとも七種類の草を間違いなく揃えて調達することすら、かなり難しいことだろう。 仮に揃ったとしても、七草かゆを食べて万病を除くと信じている人が、どれだけ居るだろうか? このように昔からの風習や慣例も、年とともに徐々に姿を消し、時代の移り変わりを 如実に感じるこの頃である。しかし一つ不思議に思えるのが、最近は年々初詣にお参りする人が増えている現象である。 神社で何をお願いしているのだろう? 神様だって、一度にそんなに沢山の人からいろいろお願いされても、全部聞き入れる訳にいかないだろう。 景気回復や商売繁盛を願う人が多いのだろう。景気回復もとうとう神頼みしか残されていないようになってしまったのだろうか? |

〔 2004.1.17~12.5まで分 〕
〔 2003.1.7~12.27まで分 〕
〔 2002.1.6~12.30まで分 〕
〔 2001.1.7~12.21まで分 〕
〔 2000.1.8~12.31まで分 〕
〔 1998.8.3~12.31まで分 〕
