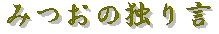
[2000.1.8.~12.31.まで]

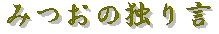
〔 2004.1.17~12.5まで分 〕
〔 2003.1.7~12.27まで分 〕
〔 2002.1.6~12.30まで分 〕
〔 2001.1.7~12.21まで分 〕
〔 1999.1.7~12.28まで分 〕
〔 1998.8.3~12.31まで分 〕
| 12月31日 | 世紀末ストレス解消法 |
|---|
|
20世紀も今日でさよなら・・と思うと、何となく複雑な気持ちになる。ハッピーエンドなら、すがすがしい気持ちで新ミレニアムを
迎えられるのだが、どうもそうは思えない。何故?だろう? この20世紀は、過去の世紀に比べてもあらゆる分野で、科学技術と
開発力で飛躍的な進歩を遂げた。そのお陰で人類は、多大の恩恵を受けた。しかしその反面、人間の醜い欲望の葛藤の犠牲のもとに
戦争や飢餓、環境汚染と地球の温暖化、エイズやガンを始めとする難病の発生、凶悪犯罪の多発等々難しい課題を残してしまった。その上
我々の住む日本は、バブル崩壊の後は無惨な経済環境に陥り、世界一の借金大国、企業倒産と失業者続出、将来不安を抱え込んだまま新世紀を
迎えようとしている。
グローバルな見地からみても、近視眼的見地からみても、何だかうやむやなストレスが充満している。誰でも大なり小なりの
ストレスは持ち合わせているものなのだが、どうすればこのストレスを発散して、明日からの新世紀を迎えたらいいのだろう?
ただ切歯扼腕して20世紀を終えるのは心残りだ。言論の自由、表現の自由という隠れみのがある。一方「口は災いのもと」という
格言もあって、いろいろな人に舌禍を引き起こす要因になることもあるが、ここは一つ4月1日のAprilFools'Day(万愚節)を見習って、
今世紀末の今日に限って、言いたい放題まくし立てて、腹に溜まったストレスを一気に放出するイベントを開催してみては如何なものかな?
昔 京都の八坂神社の境内で、大晦日に「悪口祭」という言いたい放題をいううっぷん解消祭りがあったという。また井原西鶴の
「世間胸算用」では、オケラ参りで賑わうくだりのなかで、「神前の灯火暗くして、互いの顔の見えない所で老若男女が、左右に
別れ悪口を言い合う」とある。これを真似て暗闇に中で、親戚、近所、知人、有名人など相手の名誉もプライドも何のその、
良いこと悪いこと遠慮会釈なしに言いたい放題なことを言ってまくし立てる。そのやりとりを周囲で聞いて腹を抱えて、拍手喝采して
大笑いする。自分が言いたいことも、誰かが言ってくれる。自分が言いたければ、躊躇することなく言い放つ。そうすりゃ腹の虫も
少しは収まるだろう。あくまでもイベントの中だけの悪ふざけというユーモアを介しての放言である。 ストレスを解消するには、腹の中に溜まっているうっぷんを口にすることで、可成りすっきりするものだ。20世紀のしこりを 残さず、さっぱりした気分で21世紀を迎える為には、今日しかない。大いに言いたいことを言って、新たな気持ちで新ミレニアムを 迎えたいものだ。 |
| 12月17日 | 世紀末話題語 |
|---|
|
その年の話題性を表す漢字を、1995年に「震」と決められて以来、96年には「食」、97年には「倒」、98年には「毒」、
昨年99年は「末」だった。世紀末の今年は「金」と発表された。シドニー五輪の金メダル、金大中大統領と金正日総書記との南北首脳会談、
国民的人気ものの成田きんさんの死去、金融不安状勢など納得のいく「金」話題だった。金にキン差で投票が多かったのが「乱」だった。
産業・経済界、政界、教育、医療、警察、芸能、スポーツ界、それに家庭まで乱暴・乱脈・反乱・混乱と「乱」続きだった。3位は、
新世紀、新ビジネスの「新」だった。「倒」「毒」「末」と暗いイメージの漢字が続き、今年も「乱」が1位だったら、余りにも
世紀末としては暗すぎる。キン差ではあるが、「金」「新」が仲間入りしてくれたのが、せめてもの慰めであろう。何とか新世紀の来年は、
顔のほころぶ明るい話題が増えて欲しいものだ。 ついでに20世紀末の「創作四字熟語」の入選作が、住友生命から発表された。やはり今年の世相をよく反映していて面白いので、優秀作の一部を 列挙しておこう。
|
| 12月12日 | 日本らしさ |
|---|
|
戦後の日本は、今日のゴロ合わせではないが、1・2、1・2、1・2(平成12年12月12日)とかけ声をかけてランニングを
しているようなリズムで、すばらしい経済発展をしてきた。資源の少ない日本は、諸外国から原材料を輸入し、緻密性と精勤さと研究熱心さ
で、品質、性能、価格、独創性で付加価値を付け、諸外国の製品に劣らない工業製品や精密機器で、世界の市場をリードし先進工業国に
のし上がってきた。その為国民みんなが有頂天になって、バブル経済に陶酔し、ヨッシャヨッシャとお祭り気分で、お酒で理性を失って
酔っぱらっていたようだ。ところが酔いが醒めて我に返った時には、実体のない泡の中で夢を見ていたのだった。
地価や株価やゴルフ会員券は根拠のない相場、金融市場は不良債権の山、貴金属も諸物価もとてつもなく高騰し、それに引きずられる
ように賃金もスライドしてインフレを助長していた。もう何もかもむちゃくちゃな経済市況を造りあげてしまっていた。そのような
現実性のない市場経済に気がつかなかった日本人は、バカとアホの寄り合いとしか言いようのない国民になってしまっていた。金融界や
デパートを始め各業界で倒産は相次ぐし、失業者は続出し、それに追い打ちをかけるように、世界でも有数の安全性を誇っていた
原子力発電所では、放射能漏れは起こすし、高度な技術力を結集して開発した筈のロケット打ち上げは失敗続き、人の生命を預かる
病院までも手術ミス、薬・点滴ミスなどの医療事故、食品会社の食中毒騒ぎ、学校の先生や警察まで不祥事続発、「17歳」が話題になったように
青少年の凶悪犯罪の多発・・・・等々、もう枚挙にいとまがない。ほんとうに一体どうなってしまったのか?これが本来の日本の姿なのか? いや!そうは思いたくない! 私の住む近江には、近江商人という偉大な先人の精神が深々と息づいている。「勤勉・努力、忍耐・寛容、 始末・倹約、陰徳・善事」と主にこの8つの精神が近江商人の神髄であると教わってきた。近江商人だけではない、日本国民には、 本質的に知的で勤勉性や倹約精神が宿り、働き過ぎとまで言われるように努力家であったからこそ、半世紀で今日の経済大国を築き あげてきた実績が物語っている。その裏付けとなるものに、富士総合研究所が、この20世紀に日本で生まれ世界に誇れるようになったものを 「モノ」「文化」「技術」の面で探ったアンケートによると、1位 インスタントラーメン、2位 カラオケ、3位 ヘッドホンステレオ、 4位 家庭用ゲーム機など世界を席巻しているものがたくさんある。決して失望してはならない。来る21世紀には、全国民の創意工夫で日本を 立ち直らせ、世界に羽ばたいてほしものだ。現在の日本は、本来の日本の姿ではない。真の日本らしさを世界にアピールするのは、 21世紀にその姿を見せてくれるだろう。ほんとうの日本は、これからだ! |
| 12月4日 | 流行新語 |
|---|
|
言葉は、その時代を反映して、新しい会話のコミュニケーションを創り出してくれる。巷に横行する若い世代の会話に「食べれる」
「生きれる」などの「ら」抜き言葉や「超うれしい」「超むかつく」など「超・・・」語、「告白する」を「こくる」、「徹夜する」を
「オールする」など短略化したり、何か冗談を言うと「何でやね・・・」とつっこまれる。言葉の遊びは、その人の人柄を反映して、
結構面白い。
今年の世相を反映して、国内で話題になった言葉を選ぶ「日本新語・流行語大賞」に「IT革命」と「おっはー」が選ばれた。
その他に田村亮子の「最高で金、最低でも金」、高橋尚子のニックネーム「Qちゃん」、田島寧子の「めっちゃ悔し~い」や
「ジコチュー」「パラパラ」「十七歳」「『菅』対『民』」「わたし的には・・」がベスト10に選ばれた。 なるほどこれ等の言葉には、マスコミを賑わした一時期があって、今年の流行新語で面白かった。今までにも多くのタレントの ギャグや感嘆語などで一世を風靡した言葉がたくさんあったが、それも時代と共に消え去っていく。所詮その時代の一過性の言葉で、 日本語として定着するほどのものではない。流行とは、そういうもので、過去を振り返った時に「そういう言葉もあったなあ・・」と 懐かしむ時代を反映するものとして、決して悪いことではない。そして来年はまた、どんな事が起こるのだろう?どんな言葉が流行るの だろう?と期待する楽しみもある。こんなせちがらい世の中で、楽しい面白い言葉でユーモアーを楽しむぐらいの表現の自由、言論の 自由があってもいいんちゃう? 「そりゃ・・別にいいじゃん!」 |
| 11月24日 | 時の流れに身をまかせ |
|---|
|
川の流れを誰も止めることは出来ない。時の流れも誰も止めることは出来ない。時は、自分の意志とは関係なく平等にむらなく
流れている。この時間を地球の自転と公転によって測り数字によって表して、過去から現在、未来を表現している。1秒、1分、
1時間、1日の積み重ねの中で、無意識に時間を消費して、一生を終える有限の人生であることを自覚したとき、人はその時間を
どのように感じるだろうか? 同じ時間でも苦しかった時のその時間の長かったこと、楽しかった時のなんと短く感じたこと、
時間というものは、その人その時の主観によって、その流れのスピードが変わってしまう不思議なものです。万人に公平に与えられる
時間の長さをどう感じるのか?人間としてどちらが意義ある時間なのか?「光陰矢のごとし」だから「時は金なり」「人は一代名は
末代」など時間に関することわざもいろいろある。時間は自然現象の中では無限だろうが、人の一生という観念からすれば有限で
あるだけに、時間の無駄使いについて戒める言葉が多いように思う。しかしその時間が無駄であったのか、有意義であったのかは、
後から感じることで、「今」の時点ではほとんど解っている人は少ないと思う。自分で無意味な時間と思っていることも、後で意義
ある時間であったと思い直すことも度々ある。逆に限られた時間を有効に活用して一生懸命努力しても、結果的に無駄であったと
思うことも度々ある。いづれにしても後で後悔をしないように、自分が満足できたらそれでいいのだ! 時の流れを目で見ることも手でつかむことも出来ない。森羅万象全てのものが、勝手に移り変わって「時」が流れ変わっていく だけである。だから「時は変化である」と定義付け出来るのではないだろうか。変わりゆく「時の流れに身をまかせ」結果を楽しむ 余裕のある人生で終わった方が、満足感があり有意義と感じるような気がする。そしてその一生涯が短く感じ、楽しい人生だったと 思えるのではないだろうか? つらく苦しい思いを続けて、長い人生がやっと終わったと死ぬ間際になって思うような「時」の 使い方では、あまりにも惨めじゃないですか。時間の流れを止めることが出来なければ、その時間の流れに逆らわず、自然体で 我が身をまかせ、結果を楽しむような毎日でありたいと思っている。「鳴かざれば、鳴くまで待とう ほととぎす」・・・・そう・・ いづれ鳴くだろう・・・。 |
| 11月13日 | 共働きと非行少年 |
|---|
|
少年法が改正された。相次ぐ年少者の非行が続発する中で、対策に苦慮して、遂に法的規制でおどしをかけようというのである。
昔に比べて年少者の非行が暴力的になり凶悪化していることは事実である。その原因は、いろいろ議論百出している中で、最も
大きな要因は、親子のコニュニケーション不足による親子の意志の断絶だろうと思う。そしてその原因に夫婦共働きのために起こる
夫婦間の心の融和不足ではないだろうか。
妻が仕事から帰ってきても家事をしなければならない。夫が帰ってきても誰も居ない。仮に妻が居たとしても「ただいま!」と
言っても「お帰りなさい!」の返事もない。「ああ・・疲れた!」と夫が言えば「私だって仕事で疲れているのよ!」と妻が言い返す。
「ちょっと手伝ってちょうだい!」と妻が言えば、「仕事で疲れて帰ってきたのに、まだ家の仕事までさせるのか!」と反論する。
このような夫婦の会話の連続の生活を、日常の当たり前のような環境で育った子ども達との間で、相手を思いやる心や協力する姿勢、
融和の精神がはぐくまれるだろうか?
「ただいま!」「お帰りなさい! お疲れさま!」「何か手伝おうか?」「じゃあ お願い! お風呂にお湯はっていただける?」
「いいよ・・」「ありがとう! 助かるわ!」「子ども達は?」「今 宿題してるんじゃない」「すぐ ご飯の用意するから・・ちょっと待ってくださる?」
「いいよ! お前も疲れているんだから、ゆっくりすれば・・・」・・・・という会話で日常暮らせば、家庭の平和は全く雰囲気が
違ってくる。
夫婦共働きによって、経済的に恵まれてくると、子ども達にも各々個室を与え、親子が顔を合わせることもなく、二階の子ども部屋へ
駆け込んでしまって、ドアーを閉め、中から鍵を掛けて密室の中で、各自が自分だけの子どもの世界を創り上げてしまっている。
親と子どもの関係を夫婦が自らぶち破っていて、嫌悪な親の雰囲気の中へは、子ども達は自然な気持ちでは入り込めないで居る。
そのことに親が気づかず、子どもに不安を抱かせ、情緒不安定、社会性の欠如、判断力の未熟さも手伝って、生涯悔いの残る不祥事を
起こしてしまっているのではないだろうか? そういったこともだんだん判ってきたのか、家の間取りにも工夫が凝らされ、リビングルームを通らなければ、二階の子ども部屋へは 行けないレイアウトにしたり、リビングルームの隣に子ども部屋を作ったり、何とか親子の接触を身近な関係にしようという試みが なされるようになってきた。私は非常に良い着眼点だと思う。そして男女共同参画社会、男女平等、夫婦平等というあくまでも対等であり、 フィフティフィフティの均衡のとれた社会環境を創り上げることに、男も女も理解を深めて協力し、円満で平和な家庭の構築こそ、 健全な青少年の育成と非行少年の絶滅につながるものと思う。今日の問題の起因は、大人社会、夫婦間に責任があることを自覚しなければ ならない。 |
| 11月6日 | わたし達とわたし共 |
|---|
|
我々が仲間のことを、「私達」と呼んだり「私共」と呼んだり、何の躊躇もなく呼び合っていますが、以前に尊敬する先輩から
たしなめられた事がある。「達」というのは、「全てに達した人」のことで、あらゆる面で秀でている人を意味するのだから、
一般には使わない方が良いと教えられた。「共」は共に、一緒にする仲間を指すのだから「謙そんの気持ち」を表現する為に、
普通は「私共」と呼びなさいとのことでした。
また「人」という字も、左右に支え合う形になっているのは、お互いに協力し合って、支え合う生活をする人を「人」と呼び、
その集団を「人々」と呼べるのであって、その精神のないひとは、「ひと」であり、その仲間は「ひと共」であるという。 人間の呼び方で、その人の人格を傷つけるような呼び方は、決して好ましくないとは思いますが、日本語にはたくさんの表現方法 があって、どの時にどう使い分けするのか判らない言葉が多すぎる。英語の「 I 」と「You」、「We」と「Your」のように、 もっと簡単にならないものだろうか? 最近の言葉使いには、ちょっと言い損なうとその揚げ足を取られて、ひんしゅくを買うことが 多すぎるように思う。それが教養のなさを暴露しているのだが、私はいつも恥じばかりかいている。何とか自分たちのことを、 胸を張って「私達」と呼べるように、そして人から「あの人達」と呼んでもらえるようになりたいものである。 |
| 10月29日 | 食べ物と性格 |
|---|
|
私たちは、酸素を吸って生活しています。取り込んだ酸素から約2%の活性酸素が出来ますが、この活性酸素のはたらきがウイルスなどの
外敵から身を守ってくれていることが分かってきました。しかしその反面、活性酸素は身体を酸化させ、老化、ガンの元凶にもなるという
善悪両面を持ち合わせているようです。
活性酸素は、運動不足、喫煙、ストレス、紫外線、環境汚染物質などによって作られるが、食べ物によって抗酸化物質を作り、その
毒性を消してもくれます。お茶のカテキン、赤ワインのポリフェノール、緑黄色野菜のビタミンC・E・β-カロチン、ウコンのクルクミン、
大豆のイソフラポンなどが抗酸化物質を作り出します。このように自然の食べ物には、身体にとって悪いものを上手に取り除く機能を持ち合わせているのです。
食べたものは、血となってからだじゅうに運ばれ、必ずその結果に影響を及ぼします。たばこを吸えばニコチンが、酒を飲めばアルコールで
酔っぱらい、覚醒剤によって覚醒作用、麻薬によって麻薬作用がおこります。当たり前のことですが、それだけ食べ物の影響は大きいということです。
人間は、穀物・野菜・肉類を5:3:1で摂るのが良いと言われますが、肉食の多い人は、野獣のようにどう猛な人が多く、菜食主義者は、
馬や牛のようにおとなしい人が多いように思われます。また辛いものが好きな人は、辛口の意見をいう人が多く、甘いものが好きな人は、
意見も甘口の人が多いのではないでしょうか。 最近テレビでも料理番組が結構人気を博していますが、食べ物によって性格が変わってくるとしたら、非常に興味深くなってきます。 健康の3大要素は、食事・運動・休養であることは、誰でも解っていますが、食べ物で体調が変わり、考え方が変わってくれば、性格も 変わってくることは、充分考えられますね。近年健康志向や飲酒運転の規制などで、お酒を飲む親父が少なくなって、怖い親父が少なくなって きたのに反して、ダイエット志向で甘いものを食べなくなった女の人が多く、怖い存在になってきたと思いませんか? と 思う私自身が 弱い男になってきたような気がする。「医食同源」も生きているが、「性食同源」も付け加えたいが、如何なものでしょう? |
| 10月19日 | パラリンピック |
|---|
からだに何らかの傷害を持つ人々のオリンピック、シドニー・パラリンピックが、昨日18日、南半球ではじめての開催のシドニーで、
29日まで12日間の大会の幕が開かれた。1960年にローマで1回目が開催されて以来11回目となる、最大規模の大会として、
従来にない関心が世界から集まっている。前回のアトランタ大会と比較してみると、下の表のようになる。
日本は、過去最多の151人の選手と89人の役員、計240人が、18競技の内14競技に参加する。先日のオリンピックが、
女性主権の主張と地元オーストラリアの先住民アボリジニを表面に民族解放を強調した大会だったように思う。今回のパラリンピックは、
身体の不自由な人や知的障害のある人達が、日頃鍛えた技と力を競い合うのだが、障害者スポーツとは何を主張し、何を強調しようとするのだろうか?
身体にハンディを背負う人達も、健常者と同じ権利と自由を享受出来るように、バリアフリーな設備や近代的リハビリー設備と技術によって
年々その主権が認められつつある。今回の主催国オーストラリアは、障害者対策は世界でも進んだ国であり、障害者スポーツにも力を注いでいる
国ではある。しかし世界的には、まだまだ遅れている国々もあり、日本も必ずしも進んでいるとは言えない国の一つであるように思う。 それでも上の表でも分かるように、パラリンピックの規模は、正に世界的に関心度も高く121の国と地域が参加するということは、 オリンピックの500カ国参加と比べてみても、その参加意識の高さも理解出来る。パラリンピックを障害者のスポーツと捉えるのではなくて、 道具を使ったもう一つのスポーツと認め、障害者と健常者との共生を図るスポーツ競技の在り方として発展させて欲しいものだ。 長野での冬期パラリンピックが、障害者スポーツの認識を高め、その高揚の契機となって、日本国内でも日本パラリンピック委員会(JPC)の 設立や障害者スポーツ支援基金も創設され、本腰で力を入れだしてきた雰囲気が感じられ、非常に良い傾向である。今回のシドニーで、 たくさんのメダルでも獲得するような活躍があれば、多くの感動を呼び、またいっそう盛り上がるだろう。障害者には出来ないこともあるだろう。 でも障害者でしか出来ないことに健常者は感動するだろう。そこに障害者と健常者との共生が生まれる。それでいいのだ。傷害をもって いても健常者に負けない激しい肉体のぶつかり合いを、敬意を持って観戦しようではないか。そして国民を挙げて応援しようじゃないですか。 |
| 10月17日 | スポーツ少年 |
|---|
|
先日のシドニーオリンピックで活躍した選手達の多くは、5~6歳から始めたとか、極端な例は3歳から始めたとか、幼少年期から
そのスポーツに取り組み、英才教育を受けて国際舞台に躍り出てきている選手がたくさん居る。確かに最近の少年スポーツの発展はめざましい。
以前は、少年のスポーツといえば、スポーツの形らしい遊びの類であった。しかし近年は、子どものからだと健全な精神の育成のためという
大義名分を掲げて普及、推進させてきた。少年達がスポーツに親しむのは非常に結構なことではあるが、試合や大会での成績が過大評価
されるようになるにつれ、「勝つ」ことがそのスポーツの最終目的のような取り組み方に変わってきたように思う。マスコミも低年齢選手の活躍を
取り上げ、コーチや監督などの指導者や親も試合での好成績が、すばらしい評価の対象になっている。その為「勝つ」ためには、
過剰なまで懸命に練習に打ち込んでしまっている。その結果ひざが痛み、足首を故障し、ひじや肩に異常を訴えたり、からだのどこかに
異変が起こっている事例がたくさん出ている。子どもは、骨、筋肉などがまだ発育中で、充分な体力が出来上がっていない状態にも拘わらず、
無理な練習で故障してしまっているのである。
練習時間を縮めたり、少々のからだの痛みをかばっていては、「そんなことでは試合に勝てない」といって厳しい練習を続けてさせて、
子どもに一生取り返しのつかない傷を負わせてしまってまで、「勝つ」ことがそれほど大事なことなのか・・・?疑問である。
確かに体力の限界まで鍛え上げ、苦しい練習に耐え抜き、その結果試合でその成果が達せられた充実感と達成感は、スポーツの
世界でしか味わえない醍醐味であろう。しかしその反面レギュラーに選ばれたいために、友達や同僚をけ落としたり、試合に勝つ
ことが、人間として優れていると思う間違った優越感を持つようになると、精神教育はマイナスである。学校の成績が良いからといって
人間として優れているとは限らないのと同じである。 少年スポーツを健康なからだと、健全な精神教育の手段として普及、推進させるために、その子どもに合った練習量で、医学的にも 裏付けられた個人個人に合ったトレーニングによって、その子の潜在的な才能を向上させるような指導体制が望まれる。基礎体力作りと、 筋力アップの必要な時期と、高度な技術や戦略を身につける時期とをわきまえて、大きな大会で好成績を修められるようなスポーツ教育を 期待したいものである。少年スポーツのあり方についてもう一度良く考えてみたいものである。 |
| 10月12日 | 失敗は成功のもと |
|---|
|
去る10日に、スウェーデンの王立科学アカデミーから2000年のノーベル化学賞を、筑波大学名誉教授の白川秀樹氏(64)と
アメリカのカリフォルニア大学サンタバーバラ校のアラン・ヒーガー教授(64)とペンシルベニア大学のアラン・マクダイアミッド教授(73)
の三人に授与されることが発表された。日本では、1949年に湯川秀樹博士が初めてノーベル賞(物理学賞)を受けて以来、物理学賞では
朝永振一郎氏と江崎玲於奈氏、文学賞では川端康成氏と大江健三郎氏、平和功労賞では佐藤栄作氏、化学賞では福井謙一氏、医学生理学賞では
利根川進氏以来白川秀樹氏で9人目の快挙である。
「導電性高分子の発見と開発」という難しい研究が受賞の理由らしいが、そもそも大学で実験をしていた学生が、高分子化合物のポリアセチレンの
合成の際に、間違えて触媒を大量に入れてしまったことが、今回の研究と発見のきっかけになってしまったという「怪我の功名」だったらしい。
専門家から見れば全く非常識な行動が、結果的に常識をくつがえしたのだから、素人は「怖いもの知らず」で面白い。「科学は常識を疑うことから
始まる」と言われているが、失敗を恐れて非常識なことを敢えてしようとしない。でも今回は、金属しか電気を通さないと思われていた常識を、
ポリアセチレンに化学的処理を施すと、電気を通すようになるという従来の常識をくつがえす結果を発見した訳である。 「実験とはよく見ること。予期せぬことが起きたとき、そこから何かを学びとること」という白川教授の説が、ほんとうに具現化し、 物理と化学の融合といわれる実験化学の成果が、ノーベル賞につながったのだから、予期せぬ非常識な失敗と思われる実験が画期的な 新発見をもたらしたことを見逃してはならないと思う。失敗を失敗として置き去りにするのではなく、その原因や以後の対策を真剣に 取り組まねばならないことを、白川教授は教えてくれたように思う。白川教授は、「シリコンの半導体を小さくするのは、限界が見え始めているが、 電気を伝える導電性高分子(プラスチック)を開発したことにより、より小型化できる可能性を示した」とも示唆している。近年の 科学の進歩は目覚ましいが、それも多くの失敗から端を発して、苦労の末開発されてきたのだと思う。私達も失敗を恐れず、失敗を 教訓にして成功に導く努力をしなければならないと思った。 |
| 10月4日 | オリンピック回顧 |
|---|
シドニーオリンピックもたくさんの感動をもたらしてくれた。月日が経てば忘れてしまう感動を、懐かしい想い出の一つとして
記録にとどめておきたい。私なりの印象を列記してみよう・・・・。
|
| 9月24日 | 1と2との重み |
|---|
|
第27回夏期オリンピック・シドニー大会が開催されている最中である。各種目で死力を尽くして熱戦が繰り広げられている。
各選手が日頃の練習の成果を全力を尽くして戦い、金メダルを目指して頑張っている姿には、ほんとうに感動する。その中でも
八日目の柔道男子100キロ超級の決勝戦での篠原信一選手への判定には、我々日本人なら誰しも納得出来ない不可解な判定結果では
なかっただろうか?対戦相手のフランスのダビド・ドイエ選手の内またをを透かして背中から畳に投げ落として一本を取ったかに見えたが、
審判は篠原選手が肩から落ちたことから、相手のドイエ選手のポイントと判断し、「有効」のポイントと判定してしまった。その
一瞬の判定ミスと思える結果が、優勝を逸し銀メダルの2位ということになってしまったことは、観戦したほとんどの人達が不信に
思ったに違いないと思う。
国際柔道連盟(IJF)の理事会でも、この問題を審議の対象に取り上げ、日本側からの抗議文書が届いた場合、審判委員会で審議し、
篠原・ドイエ戦での審判員3人に、何らかの罰則をするというコメントを発表しただけで、結果判定が覆ることはないということは確認
された。当然全日本柔道連盟もIJFに対して抗議文を提出することを明らかにしているし、日本各地からIJFに対しての抗議や質問の
E-mail が1400件以上も届いているという。
メダル獲得という結果には違いないが、優勝(金メダル)と2位(銀メダル)との差には、1と2という数字の差だけの問題ではない。
国際社会から受ける評価、国内で受けるその後の待遇、生涯を通じて有形無形の特典がその人の人生をも大きく左右することにも繋がる。
当然本人の不満、憤り、悔しさ、無念は一生心の中に残り、ぶつけようのない感情が渦巻く精神状態が死ぬまで続くことになるのである。 篠原選手の優勝決定戦での1敗は、4年に1度しか行われないオリンピックという国際大会での戦績としては、大相撲の本割り 一番の1敗位の重みではない。当の篠原選手は、インタビューに答えて「感想もなにもない、弱いから負けました」と感情を押し殺して、 本意でもないのにスポーツマンシップらしさを繕っているが、そんなきれい事で済まされている心情ではないことぐらいはお見通しである。 団体競技で一人が失敗したら・・・リレー競技で一人が落ちこぼれたら・・・点数競技で1点の差で・・・などなど「1」という数字の 重みは、枚挙にいとまがないほどある。人生において、たった1つ、たった1回、たった一瞬の出来事が、その人の将来に大きな影響を及ぼす 結果になりかねないことを、オリンピックを観ていて痛切に感じた。「1」は、全ての原点であり、「1」と「2」との重みの差を 改めて認識しなければならない。それにしても篠原選手は気の毒であり、このような不条理なことがまかり通るIJFの組織を改革 しなければならないと思う。 |
| 9月13日 | 理想と現実 |
|---|
|
「あなたは、将来どんな夢を持っていますか?」「・・・いや・・別に・・」「理想は、何ですか?」「・・・いや・・持ってもしょうがないでしょう」
と何とも空虚な将来像しか持っていない人達が増えてきたように思う。また一方将来像について語る人がいたとしても、「あの人は理想論ばかりで、どうも
現実的でないなあ」とか「・・・さんは、夢のような話ばかりで、どうも・・・」などと批評されるのは、迎合されている言い回しとは思えない。
何かの会合や会議でも、「まあ・・企画はよさそうだけど、果たしてどんな効果が期待できるのだろう?」とか「まあ・・趣旨は解るし、悪くはないと思いますが、
ちょっとその日は都合がつかないので出られません」などと、無駄骨を掘らないように、貧乏くじを引かないように逃げに廻ろうとする。
「先の100より今50」という言葉がある。利益追求の実業界では、将来の保証のない可能性よりたちまちの現実に追われていると、「今50」に
眼が移ってしまうのも解らぬことではない。しかし計画の先は理想であり、理想が叶うのが夢であろう。理想とは、その人が最も良いと思う考え方であり、
それが叶えられる夢に現実性がなくてもかまわない筈である。”理想と現実のギャップ”とよく言われる。当たり前である。理想から生まれる夢は、
その人の求めている希望であり、「・・・したい・・・となりたい」という願望の気持ちであるならば、それが現実的に叶わなくても致し方のないことである。
そういう夢を描くことが、向上心を植え付け生きがいにつながっているのではないだろうか。目先の利害に惑わされずに、将来に向かっての道しるべとなる理想への
思いが大切なことである。 夢を持ち理想を追いかけることなく、毎日の生活をだらだら過ごしていて、いったい何処へいくのだろう? 夢を描きそれが叶わぬ現実に落胆するぐらいなら、 今日一日を、いや今この時を気楽に生きている方が、ストレスが溜まらず精神的に楽であると思っている人が多いのだろう。とするならば、 将来に対する願望もなく、努力する向上心もなくなることになり、後は下り坂を転げ落ちるだけである。それを他人のせいにしたり、慌てて急に 助けを求めたり、後悔をして悩んでも手遅れである。”理想と現実”のギャップのあることを認識したうえで、夢を持ち続けることが 大切なことではないだろうか? 夢を描かない人達、理想を追おうとしない人達がいたら、もう一度自分の将来について、よく考え直してみては如何なものでしょうか? |
| 9月7日 | オリンピック |
|---|
|
1896年にアテネで行われたオリンピックが、今年で27回目となり、20世紀最後で最大の規模で、オーストラリアのシドニーで開催される。
今回のシドニー夏期オリンピックは、大会運営費だけで約26億豪ドル(約1700億円)で、200カ国・地域からの参加で史上最多最大の
スポーツ祭典となるようだ。
我が日本も29競技、268人の選手、439人の役員を含む選手団で参加することになった。開会まであと7日、
国民の関心も徐々に盛り上がり、メダル獲得の皮算用も千差万別で、各自勝手なことを口にし、罪のない五輪談議を楽しんでいる。
その内で注目度の高いのが、マラソンじゃないかな?次いで柔道、水泳、野球、サッカーなどであろう。オリンピックがこんなに世界のスポーツ競技の
関心と注目を浴びるのは、歴史ある全世界的な権威のある大会が、4年に一度しか行われないことのため、この年に競技生活での
コンディションと実力を頂点に持ってくることの難しさが、金メダル獲得の難しさにつながり、オリンピック優勝の名誉を国民的英雄に
祭り上げているからであろう。
先月甲子園球場で、夏期全国高校野球大会が行われ、熱闘甲子園が盛り上がったが、オリンピックはそんな国内の高校球児だけの
対象競技の比ではない。正に地球規模の大祭典であるだけに、世界中が沸き上がるのは当然であり、我々も感心を持つのは当然である。
しかし日本のオリンピックでの金メダル獲得成績は、ロサンゼルス大会の10個以来、ソウル大会4個、バルセロナ大会3個、アトランタ大会3個と
だんだん減ってきている。その上金メダル獲得の実績のあるバレーボールは、今回は男女とも予選敗退で出場すら逸している。
どうしてだろう?
日本の競技の多くは、企業活動で支えられてきている。にも拘わらず最近の経済不況のあおりで、企業が支えきれずに撤退が相次いできている。
その為競技人口は減り、国家的取り組みも薄れ、少年期からの英才指導体制もなく、その指導者の養成すらも希薄である。
世界の頂点を極めようとするからには、それなりの国家的規模での資金的援助なくして、個人や民間だけの力だけでは、そりゃ難しいのじゃないだろうか? |
| 9月2日 | 風呂好き |
|---|
|
温泉旅行が人気を集めている。家庭でもほとんどの家にお風呂が用意されるようになってきた。日本人の風呂好きはいつから
始まったのだろう? いろいろ調べてみると、仏教が伝来した西暦538年頃「施浴」(入浴を施す)として、慈善行為的な事業
として始まり、風呂が庶民の生活の中に広まってきたようだ。
室町時代になってくると、一部の武家や公家が「湯殿」を持つようになり、時々人を招いて「風呂ふるまい」をするように
なってきた。「風呂ふるまい」に招かれることは、可成り贅沢なおもてなしを受ける意味合いがあり、招待の表現も「風呂に招く」
という表現をしていたそうだ。
江戸時代の1591年に、伊勢与一という人が、今の東京の呉服橋あたりで、銭湯の営業を始めた。料金は永楽銭一枚。
近くの住民が集まり、世間話に花を咲かせ、コミュニケーションの輪が広がる銭湯文化の始まりであった。石鹸はなく「ぬか袋」
で、タオルなどなく手ぬぐいや着替えの着物を四角い布に包んで持ち歩き、風呂場に敷いて利用していた。そこから「風呂敷き」
と呼ばれ、現在にまで受け継がれてきている。
明治時代になって、銭湯は全国に広まり、日本人の風呂好き文化の原型が作り上げられてきた。時が進み1921年、
文部省主催の「生活改善同盟」が、「台所、風呂、便所のような水利用の設備は、近くに集めるのが良い」と提案されてから、
今まで離れにあった便所や風呂も家の中に設備されるようになってきた。
便利になり、気持ち良い風呂文化は、目覚ましい勢いで我々の生活に溶け込み、今やいろいろな趣向を凝らした浴室が取り入れら
れ、家庭入浴を切り離しての生活など考えられない時代になってきている。そのため、あれ程繁栄を極めた銭湯も、今や陰を薄め、
新しい時代に対応するための趣向を凝らした健康志向やレジャー志向、癒し志向などを取り入れた温泉気分の風呂屋さんに変換を
余儀なくされている。 風呂についての効能については、「からだのふしぎ Part2」にも簡単に説明していますので、 時間があれば、一度ご覧下さい。風呂に入って「いい湯だなあ・・・・」と鼻歌を唄いながら、幸せを感じる生活をエンジョイ しようじゃありませんか・・・。 |
| 8月25日 | いじめ |
|---|
|
もうすぐ夏休みも終わろうとしている。海や山や観光地で、家族や友達との明るい楽しい歓声が乱れ飛んでいる。見ていて
すがすがしい、ほほえましい光景に遂口元がゆるんでくる。そこには暴力やいじめ等見苦しい雰囲気など少しも感じられない。
なのに9月から学校が始まると、また校内暴力やいじめ問題が発生してくるのだろうか。
豊かな自然や遊び場からインドアーのテレビゲームや漫画雑誌の世界に入り込むと、人間関係が苦手になり、非社会的行動に
歯止めが利かなくなるのだろうか? 子ども達は、家庭や地域の中で、遊びの中から自由領域と禁止領域、許される行為と許され
ない行為との区別を認識出来る判断力を学んでいくものだろうと思う。
学歴偏重主義からくる受験戦争による学力中心主義教育、心や素質を見逃して、過度の管理教育を推し進めようようとする先生
の広角的配慮不足や初期対応のまずさ、夫婦共稼ぎ家庭における親子のコミュニケーション不足、自殺の手法などを教える報道や
いじめで笑いを取ろうとするテレビのバラエティー番組など社会環境の悪化が自己中心的な人格形成につながり、ひいては、
生きる目標や価値観の欠如となって、人間関係を無視したり、いじめ、暴力、殺人などキレる行動の根源となっているのでは
ないだろうか?
通信教育大手のベネッセコーポレーションの高校生対象のアンケート調査によると、今後30年後の学校でのいじめに関する
問いでも、86.7%の生徒が「いじめは減るとは思わない」と答えている。この認識は見逃してはならない大きな数字だろうと
思う。その背後にあるデーターに
|
| 8月16日 | 戦後半世紀 |
|---|
|
8月15日、「今日は、何の日ですか?」と問いかけると、「終戦記念日」とか「戦争が終わった日」と答える人は
何人かは居る。ところが、「今日は、どんな日ですか?」と聞くと、そりゃさまざまな答えが返ってくる。「明日から
嫌な仕事が始まる日」「郷里から自宅へUターンする日」「別に・・普通の日」「甲子園へPLを応援に行く日」
などなど全く「終戦の日」とは関係ない個人の自由を謳歌している平和な日常生活が浮かび上がってくる。
全国各地で、戦没者を慰霊する終戦記念日の慰霊祭が行われたり、当地近江八幡市では、戦争中の苦しかった
当時の食料事情を解ってもらおうと「すいとん」の試食会を企画したりしている。戦争体験者は、「こんなもの、
思い出したくもないわ!」とか「懐かしい味だけど、二度とあのような時代には戻りたくないね」と、戦争の悲惨さを
感じさせる発言が多いにも拘わらず、子どもや若い世代の人達は、「おいしいね」とか「今度家でも作ってみよう!」
とか、なかなか好評のようだった。時代も変われば、食べ物も変わるものだ。「すいとん」とは、醤油で味付けした汁に
小麦粉の団子と、かぼちゃやタマネギなど少量の野菜を入れた代用食で、食料の不足した戦争中から戦後にかけてよく
作られた代表的な献立なのだが、不思議にも食べたことのない若い世代には、珍しさもあるのだろうが、「おいしい食べ物」に
変身するのだから不思議である。
このように平和な日本になった反面、おとなりの韓国、北挑戦は、平和への第一歩を踏み出そうする大事業が行われた。
1950~53年にかけての朝鮮戦争時代に、朝鮮半島で南北に生き別れになった離散家族の相互訪問で、半世紀ぶりの
肉親との涙の再会が実現した。テレビでその映像が映し出されると、もう表現のしようもない感動が胸を打つ。同一民族だけではない、
同じ家族である。親子、兄弟、姉妹でありながら、民族分断のあおりを食って50年もの間、顔を合わすどころか、その消息すら
はっきりしない不安と焦燥のなかで、悲しみと苦悩に耐えて生き抜いてきた家族との対面は、どう受け止めてあげたらいいのだろう?
人ごとではあるが、人ごとのように思えない感動で我ながら息が詰まる思いがした。そこでこの歴史的再会を記録するために、
南北両国の声明を書いておこう。 韓国の声明
|
| 8月4日 | 良い子・悪い子・普通の子 |
|---|
|
少年犯罪が多発している昨今、世間の人達や先生は「あの子は良い子でしたよ」とか「普通の子でしたよ」と人物評価を
している。その「良い子」「普通の子」の評価基準はどこからきているのだろう。世間で良い子と評価されている子が、
世間を驚かせるような悪い事件を起こす。良い子なら事件を起こす筈がない。じゃあ悪い子なのか? 悪い子を良い子と
判断ミスしていたのだろうか。「一般に良い子と思われている子が危険な存在で、普通の子であっても、最近の子は
すぐキレる」などと言う評論家らしき人達もいる。「それじゃ、悪い子が良い子なのか?」と屁理屈を言いたくもなる。
良い子が悪い子で、悪い子が良い子ならば、普通の子はどういう子なのか? こうなってくると、もう訳が解らなくなってくる。
良い悪いは、所詮比較の問題であって、絶対的な基準などあるとは思わない。「あの子は頭がよい、マナーが良い」
「あの子は成績が悪い、聞きわけが悪い」など何を基準に評価しているのだろう。このような比較だけで、子どもの
評価を繰り返していると、子どもは上っ面だけは世間の良い子のイメージを繕って、自分を抑えている内面では、
全く違う一面を増幅させていて、事ある時にキレて爆発させてしまっているのではないだろうか? 基準のはっきりしないことに、良い子、悪い子と決めつけるのでなく、その子自身がものの善悪の判断の出来る世の中、 即ち大人の生きざまを鏡として映し出すことが先決ではないだろうか。世の大人達は、自分のことを棚に上げて、 まだ判断力の乏しい子ども達にその責任を押しつけて、良い子・悪い子を作り上げているのではないだろうか? これからは、キャラクターを尊重し、個性的な才能を重視して、その能力を磨き可能性を期待する時代では ないだろうか。その過程で「良い子・悪い子・普通の子」の烙印を押しつけるべきではないと思う。 良いことも悪いことも紙一重の差で、ちょっとした見方の判断で、全く違う結果になる方向に変わってしまうことが 多いように思う。その一瞬の判断が正しく出来る社会であってほしいし、大人達がその判断を誤ってはならない。 大人にとって都合の良い子ではなく、その子にとって良い子とはどういう子なのか、良く考えてみたいものだ。 |
| 7月28日 | 色こそいろいろ |
|---|
|
夏も最盛期になってくると、太陽光線が目にまぶしく、全ての色が鮮やかに映えてくる。この色の源泉は光で、
その波長の違いからいろいろな色彩を作り出し、我々の感覚に刺激を与えてくれる。色の違いによって内蔵や神経系、
内分泌系にも作用して、集中力を高めたり、疲労度を軽減させたりして、いわゆる「癒し」に大きな貢献をしてくれるだけに、
日常生活に切り離すことの出来ない効能がある。海、山、建築物、ファッション、写真、絵画・・・・などなど書き尽くすことが
できない全てのものに、いろいろ影響を及ぼしている「色」ではあるが、実業界に於ける企業戦略に、この「色」を
切り離して考える訳にはいかない。
企業イメージを高めたり、商品に付加価値を付けるために色や形にこだわり、パッケージングや広告に神経を使う。
商品の販売戦略に「AIDMA」原理がある。即ち Attention(注目させる)、Interest(興味を持たせる)、Desire(購買意欲をそそる)、
Memory(記憶させる)、Action(行動、買う)という意識高揚に「色」は不可欠な存在である。五感のうちで視覚に
訴える影響力は最も大きく、聴覚や触覚よりも効果は高いと言われている。色は、人の想像力をかきたて、商品の中身や品質までも
連想させてしまう。 またオフィスや住宅環境では、壁、天上、カーテン、調度品などの環境色彩調節によって、作業能率や電力消費量にも影響し、気分や癒し にも効果がある。ストレス解消のための色彩心理を応用して、心身の健康バランスを保つ心理療法など、「色」をエネルギーとして 活用する研究が進んでいると言われている。赤色は、覚醒効果があり、体のバランス感覚を悪化させるが、青色は、沈静効果や免疫改善作用もあり、 バランス感覚をよくする。黄色は集中力を高め思考、判断力を高める効果があると言われている。このようにこれからは、キャラクターと癒しが 重視される時代を迎えるに当たって、企業も個人も色彩パワー戦略がその決め手になるのではないだろうか。正に「色こそいろいろ」な分岐点に なるような気がするがどうだろう? |
| 7月21日 | 不良食品の謎 |
|---|
|
雪印乳業の黄色ブドウ球菌入り牛乳による集団食中毒事件で、世間が大騒ぎをしている最中に、森永乳業の
異臭牛乳、キリンビバレッジの異臭スポーツドリンク「キリンスピード」、生活協同組合コープこうべ製の
かび付き「アップルチーズケーキ」、山崎製パンのかび付き惣菜パンに味の異常なデザート、敷島製パンの
かび付き黒糖蒸しパンの発生・・・と建て続けにマスコミを騒がせる不良食品事故が相次いだ。このようなことは、
今急に発生したのではなく、潜在的に原因があり、起こりうるべきして起こった事故だと思う。
食品業界ではHACCP(総合衛生管理製造過程)を導入していれば、社会的に信用出来る食品会社
であるという先入観的な風潮があって、会社はその上にあぐらをかいて、衛生管理をおろそかにしていたことも
一つの原因ではあった。
しかしその裏にもう一つの大きな原因があると思う。それは、流通市場の過当競争であると思う。
食品納入業者は、大手のスーパーやコンビニのチェーン店に定番としての帳合いを確保することが、安定的売り上げ
を確保出来、市場シェアーを拡大出来る大きなメリットになる。その為には昨今のような買い手市場(買方が売買の主導権を握る環境)では、
スーパーやコンビニのバイヤーの言いなりにならざるを得ない状況になっている。一方末端の店舗では、
健康志向の高揚で製造月日の新しい商品、新鮮な商品を消費者が求めるため、バックヤードに在庫を持たずに、
コンピューターによる売れ筋商品の管理をきめ細かくすることによって、発注から納品までの時間をだんだん短縮させ、
約束納期が守られなかったら、機会損失補填として売価で損失補償を納入業者から取り上げるという、厳しい取引条件を突きつけている。
その為流通業界では、如何に物流をスピードアップするか?・・・が最大の納入課題になっている。その上納入価格は、
過当な売り込み競争で、益々厳しくなり、利益確保をするためには、人員削減によるリストラで、経費削減による利益追求を余儀なくされる。
という厳しい経営を強いられている。人手の足りない製造工程で、完璧な衛生管理を求められても、どこかで手抜きの作業か、
細部管理で手が回りかねることも出てくるのであろう。だからといって安全でない不良食品を出荷しても致し方がないとして許されるものでもない。
社会的信用を確保するためのHACCPは、あらゆる細菌や微生物を滅菌することで、食品の安全性を高める管理
システムで、塩素などの薬剤の使用が増え、空調や噴霧施設に莫大な投資を強いられる。大量生産をしようとすれば、
その設備はより大規模化され、薬剤の使用はより一層増大し、必要以上に有用な菌まで殺してしまい、危険性は
高まって、ひとたび何かミスがあれば、その被害は拡大する。 今回の事故は、巨額な設備費をかけてでも大量に、安く、早く納入しなければならない食品業界と、テレビCMを 始めとする誇大広告につられたり、一流ブランドを買うという見栄で食品を選びがちな消費者への警告ではないのだろうか? そこで私達は、何を基準に安全と考えるのかを見直し、食品メーカーは厳しい流通市場ではあるが、単なる食品ではなく、 安全な食べ物を提供できる製造管理と販売・物流管理を見直して頂きたいと思う。 |
| 7月16日 | 趣味と仕事 |
|---|
|
自分の好きなことをしていると、遂時間を忘れって没頭してしまう。そしてその時間の割には疲労度も少なく、
また続けたくなってくる。ところがそれが仕事となると、後でどーっと疲れが出てきてうんざりする。そんな思いをした
人達はたくさん居るのではないだろうか。趣味とは、仕事を離れて自分の時間として使っている楽しみだろうとは思うが、
もしその趣味が仕事として活動できれば、そんな結構なことはない。例えば、プロ野球選手、プロサッカー選手、
プロゴルファーなどのプロスポーツ選手、歌手・役者・タレントなど芸能人、将棋・囲碁のプロ棋士、画家・彫刻家、
作家・・・など、もともと好きで始めた事が、その才能を生かして、職業として自分の仕事として活躍している人達も
たくさん居る。そういう人達は趣味を仕事としている訳で、こんな恵まれた条件はないはずである。にも拘わらず、
苦痛に満ちた毎日で、趣味とはかけ離れた思いで暮らしている人達が多いのは、どうしてだろう?
趣味は自分の為に自分の時間として自由に使っているのに、仕事となると社会の為に他人の為にその時間を使い、
報酬という対価のために、義務と責任を負う労働時間という名に転化させられてしまう。そこに趣味と仕事とは同一視
できない苦悩が生じてくる。もし余暇と労働、休日と勤務、趣味と仕事という時間振り分けをしなくても良い環境が出来たら、
こんなすばらしい生きざまはないのではないだろうか。
好きな時に好きなことをして、何らかの形で自己表現が出来る活動が、結果として人のためになる仕事として、
世の中に認めてもらえれば、趣味と仕事とは同じ活動の枠組みの中にいることになるのではないだろうか。そうなれば、
何歳まで働いて、何歳からは老後として静かに遊んで暮らす、というスキームも必要がなくなる。自分の好きな
ことに生きがいを感じながら、死ぬまで続けられたら、最高の人生航路であり、感悦極まりない事だろうと思う。
いま私は、その方向に近い生きざまに大いに満足している。 これからの日本は、終身雇用制度や年功序列的な賃金制度も除々に薄れ、自己の才能や資質、個人のキャラクターが 社会的に評価されるような個性派重視の傾向になりつつある。そうなれば趣味がその人のアイディンティティとして 社会に評価され、仕事と同じ活動の枠組みの中で活躍できる時代が来るのではないだろうか。そのような豊かな 人生を過ごしてくれる人達が増えることを私は祈っている。 |
| 7月9日 | 人間144歳 |
|---|
|
あなたは120歳まで生きられる。もしかしたら144歳まで生きられるかも知れない。いやもうそんなに長生き
したくないという人もいるかも知れない。しかし理論的にはそういう計算が成り立つらしい。それは脊椎動物は、
大人に生育するまでに費やした年月の5~6倍は生きることが出来るという説を聞いたことがある。ならば人間に
あてはめて計算すると、解りやすい成長過程は、歯の成長過程であろう。
先ず幼児時代は3歳までに乳歯が生えそろい、6歳頃に第一大臼歯が、12歳頃に第二大臼歯が生える。18歳頃に
第三大臼歯(親知らず)が出てきて、24歳頃にあごの関節が石灰化して完全な大人に生育することになる。このように
人間は6年周期で成長過程が形成されていて、大人に生育するのに24年かかると言うことになります。だからその
5倍としても120年、6倍の寿命とすれば144歳まで生きられるという計算になるということです。
しかし現実には、なかなかそうは生きられない。医療技術の進歩や良い薬の開発、衛生環境の整備など人間尊命の
研究努力は続けられてはいるが、交通事故や自殺もあり、ガン、脳卒中、心臓病、各種内臓疾患などの病気などで
早く寿命を亡くしてしまっている人達がたくさん居る。世界一の長寿国の日本でも、女性で84歳、男性で78歳位の
平均寿命である。理論的寿命の144歳の約半分で命を落としてしまっていることになる。平均寿命を144歳に
することは先ず不可能だろうとは思うが、それに近づけるにはどうすればいいのだろう?
難しいことはさておき、私達のできることは、先ず何でも「良く噛んで食べよう」ということです。噛めば噛むほど
唾液の分泌が良くなり、唾液がガン細胞の増殖を抑える効果があることが解ってきたということです。そして噛むことにより、
脳の血流を促進し、脳血栓や脳卒中を予防する効果もあるという。その上あごを丈夫にするだけでなく、あごの動作が
脳へ血液を汲み上げるポンプ役を果たしてくれることにより、心臓の負担を軽減し心臓の病気にもならないということです。 もう一つ簡単なことは、「良く笑いましょう」ということです。胸の鎖骨の間に胸骨という骨があり、その裏側に胸腺がある。 笑うことにより、目尻が下がって口角が上がります。この時にその胸腺が刺激されて、ホルモンが分泌される。 この胸腺ホルモンが、ガンを攻撃する免疫力を持つナチュラルキラー細胞(NK細胞)を活性化することが解ってきたということです。 「良く噛んで、良く笑いましょう!」そうすれば、病気にならずに120歳、努力すれば144歳まで生きられる? ほんとかな? 挑戦してみてください。 |
| 7月2日 | ヒトゲノム |
|---|
|
次から次ぎへと聞き慣れない新語が飛び出してくる。ゲノムとは全遺伝情報のことで、人の遺伝子の全塩基配列
が解読されたということで、世界にいろいろな論戦を巻き起こしている。今日DNA鑑定とかDNAチップという
革命的な方法で、既知の遺伝子の変異を迅速に検出することは可能になっている。それに加えてヒトの全ての遺伝子
のデーターベースが出来、それを利用する事が出来るようになれば、個々の遺伝子の生体内での機能を解明することになり、
画期的な難病の治療薬の開発にもつながる可能性もあるという。こんな大ニュースを無視する訳にいかない。
原子力が平和的利用にも軍事的利用にも使われるように、開発とか発明には必ず善悪両面の利用効果が生まれてくるもので、
このヒトゲノムも、一つ間違えるととんでもない心配事が含まれていることを見逃してはならない。今回の「ヒトゲノム解読成功」の
発表までには、10年ほどの複雑な対立や競争の歴史を経て、ようやく結実した和合の成果発表であったという。
以前にアメリカ国立衛生研究所(NIH)の研究者であったクレイグ・ベンダー氏が、民間研究期間であるセレーラ・ジェノミクス社を
設立し、製薬会社の委託を受け微生物のゲノム解読を進め、インフルエンザ菌から始めて約30種類の生物のゲノムを解読するに
至ったという。しかし一方「ゲノムの解読データーは人類の共通の財産である」と主張する日米欧が進めるヒトゲノム計画を率いる国立ヒトゲノム研究所
という公的研究機関との間で、解読合戦が繰り広げられ、両陣営間で遺伝子特許の是非や、解読データーの公開について対立していたが、
遂にクリントン大統領やブレアイギリス首相までも立ち上がらせ、両陣営の和解と合意を取りつけ、両陣営共同で解読完了を発表するに至った。 ヒトゲノム解読の完了は、将来的にはガンやアルツハイマーの治療薬や、一人一人の病気の個人治療法の開発の可能性も期待できるという 楽しみもある反面、遺伝子操作によるクローン人間の出現や、特定の遺伝子を持った人達への差別や、プライバシー侵害の危惧など、倫理、人権面での 法整備の確立が求められることになる。解読情報をインターネットで検索できるデーターベースに公開したり、世界の研究者にも公開されることは、 結構なことだが、商品化を目指す研究開発競争や特許に関わる競争対立で、新たな論争が懸念される。出来るだけ早く世界的な規模で話し合い、 新たなルールを確立し、後世に禍根のないような平和的開発に活用してもらいたいものだ。 |
| 6月25日 | IT革命 |
|---|
|
IT(Information Technology)とは、情報技術と約されて、最近この「IT革命」という言葉が盛んに
使われてる。携帯電話、PHSなどのモバイル(移動)通信の爆発的な普及やインターネット利用者の普及で、
我々の生活や産業構造に大きな変革をもたらしていることは確かです。昨年(1999年)で携帯電話、PHSが5700万台を
越え、パソコンの国内出荷台数が年間1000万台に近づき、ネット利用者数は2700万人で、普及率も21.4%、
世帯普及率でも19.1%に達して来たとのこと。確かにもうここまでの浸透率になれば、無視できない数字である。
だから今行われている衆議院選挙でも、各政党が将来構想にIT革命を選挙公約に取り入れて、具体性のない構想の
花盛りである。「全国民に端末器を無償配布する」とか「IT担当大臣を創る」とか、訳の解らない森喜朗首相は、
ITを「イット」と呼んで、ひんしゅくをかって笑われていたり、それを対立候補者の相手攻撃の材料にして、こき下ろしを図った
り、ITも「アッ痛ッティティ・・・」と苦笑している。
私がパソコンを買ったのが5年前、その頃にはこんなに早く情報通信技術の進展があるとは思わなかった。勿論
将来的にパソコンの普及が進み、生活に密着した存在になるであろう・・・と思い首を突っ込んだことは確かではあるが、
その進化のスピードの速さに驚いている。もう私もとても付いていけなくなってきた。 2000年度版の「通信白書」が公表されて、
その予測では、2005年にはネット利用者は60%を越えるだろうし、電子商取引は今の20倍を越え7兆円に達し、
ネット関連ビジネスは31兆円以上に膨れあがるだろうと予測している。 インターネットは当然のことながら、インターナショナルなWeb市場であるだけに、その情報もグローバルな見地から 取り組まなければならない。今度の沖縄サミット(主要国首脳会議)でも、このIT問題が議題にあげられる予定にはなっているらしいが、 私達末端の国民の生活や将来に、具体的にどのような影響や指針を与えてくれるのか、そして今深刻化している少子高齢化の 進む日本国民に、デジタルディバイド(情報格差)の心配がクローズアップしてこないだろうか? ものすごい勢いで 進む国際化の流れに、多くのおじん、おばん達が付いていけるのだろうか? いささか心配である。今選挙(今日投票日)が 行われているが、次期政権者の対応とリーダーシップに期待したいところだが、どうだろうなあ? 無理だろうなあ・・・! |
| 6月16日 | 南北首脳会談 |
|---|
6月13・14・15日と二泊三日間。韓国の金大中大統領の朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の平壌訪問
での金正日総書記との首脳会談は、全世界にセンセーショナルな衝撃を与えた。その結果
各マスコミは、南北分断から「55年もの長期間の緊張と対立から・・・」と半世紀にわたる長さを強調 しているが、私は「たった50年余り・・・」と思いたい。同じ民族が、朝鮮戦争で血を流し合い、北緯38度線 を境に南北に分断されてから、政治、思想、経済、教育、文化などいろいろな面で行政機構が異なると、 たった55年で、こうも世の中が変わってしまうものか?とびっくりする。日本との国交のない北朝鮮の国内の 実体は、僅かな一部のマスコミ報道からでしか量り知ることが出来ないので、詳しくは解らないが、今までの 報道の内容から察すると、余りにも南北の差は大きすぎるように思う。
ここで朝鮮半島における南と北の国の差異を列挙することが目的ではない。今 日本は衆議院選挙のまっただ中
である。そこで選ばれた議員さん達が、我が国の政治を司ることになるのである。政治が国を変えるのである。
朝鮮半島の南北の国は、その政治、主義、思想が違ったから今日の差異が生じてきたことを理解しなければならない。
政治はそれ程恐ろしい結果を生み出す根源である。
朝鮮半島の南北統一なんて、そう簡単な事ではないと思う。いろいろ難しい課題と手法が、気が遠くなるほど、
気が狂いそうになるほど山積みされていることは、容易に推察出来る。そのような難題の山を作ってしまったのは、
政治・思想の違いが原因である。一つ間違えば、たった50年でこうも変わってしまうことを、見逃してはならない。 今後対話を重ねて、紆余曲折しながら、南北統一への道を歩んで行くのだろうが、ほんとうの統一国家になるには、 おそらく50年では無理ではないだろうか?それも全世界の理解と協力体制があってのことだろうが、それでも なかなか難しいことのように思う。その理由を列挙し出したら、もう切りがないほどのことが想像できる。 でも南北首脳会談が、将来的には世界にとっても、アジア諸国にとっても、我が日本にとっても、朝鮮半島にとっても 非常に明るい希望の持てる第一歩であったことには、間違いない。どうか南北朝鮮統一国家の達成が、世界の平和と 緊張緩和に大きな貢献をしてくれることを期待して、永い目で応援しなければならないと思う。近くて遠い国であった 北朝鮮に暖かい愛の手を差し伸べようではありませんか。 |
| 6月11日 | 道草 |
|---|
|
世はスピード時代、「時は金なり」「遅い事ならブタでも出来る」「急げ!急げ!」「早くしなさい!」
などこのようなせせこましい言葉の中で生活していると、いらいらしてストレスが溜まる。急いで歩いて、けつまずいて
怪我をする。スピードを出して運転して、大事故を起こす。あわてて仕事をして、大事なことを見落とす。この高速社会に
ついて行けない人達は、星の数ほど居るのではないだろうかと思う。「急がば回れ」という言葉もある。ちょっと
遠回りをしたり、道草をしたり、ゆっくり歩いてみて、のんびりと辺りを見回してみると、気分はリラックス、集中力も
出てきて、以外に何か新しい発見もあるかも知れない。
特に子ども時代の遊びのなかで、山や川、夕焼け空、田んぼや林の中から、自然の美しさや多様さ、季節の移り変わりを
体感するのは、こののんびりさがなくては、とても経験出来ない。でもこの自然観察の目を養うことは、子供時代には
非常に大切なことではないだろうか。最近のお母さんが我が子にいう言葉で、一番多いのが「早くしなさい!」らしい。
朝から晩まで、顔を見たら「早くしなさい!」ばかりでは、子どもが観て、考え、判断する暇など生まれてくる訳がない。
もう少しのんびり、健やかに育ててやって欲しいものだ。 子ども達ばかりではなく、大人の社会も同じ事。夫婦共働きで、時間に追われながらあわただしく生きている。 その為、からだと心のバランスを失って、健康障害を起こしたり、異常で残忍な社会事件を引き起こしたり、ノイローゼ になり、いたたまれず、最後は自殺にまで追い込んでいる原因は、この世の中のスピード狂が犯人ではないだろうか? 何でも急ぎ過ぎて、人間として大切な感性や優れた資質を刈り取られたり、人生の喜びや楽しみをかみしめることなく、 心や体をぼろぼろににして、自分自身の可能性までも喪失してしまっているように思えてならない。もう少し 遠回りしたり、道草して、遠い所を眺めて観る余裕を持ってみては如何なものでしょうか?そうすれば「時は金なり」の 真髄に触れられるかもしれないと思う。 |
| 6月7日 | 食品と健康 |
|---|
|
原始時代の人間の食べ物は、野や山や海で確保した食べ物を、その場でほとんどそのまま食べていました。
その内「火」を発見し、味を良くする方法や保存を良くする方法などを考え出し、文明・文化の向上につれて、
現代のような複雑な食品環境に変遷してきました。採ったものをすぐ食べれば多くの問題はないのですが、食べるまで
の時間がかかれば、腐敗、品質劣化、食中毒などの問題が派生してきます。そのため防腐剤、着色剤、甘味料、漂白剤などの
化学物質が開発され、より美味しく、より保存性も良くなり、見た目もより美しくはなってきました。しかし
その反面いろいろな健康管理上の問題点や、新たな病気の発生の危険性も出てきました。人間はさらなる研究を進め、
最近では遺伝子組み換え食品という、訳の解らない先端技術を駆使するところまで進化してきました。遺伝子組み換え食品の
功罪は、まだはっきり解りませんが、人類の将来的な人工問題、食料危機を考えると、あながち否定ばかりは出来ないところです。
食品売り場に並んでいるたくさんの食品は、何からどのように作られ、どんな添加物がどれだけ使われ、どの程度の食品としての
価値があるのか、健康的にどの程度の有害性があるのかないのか? 難しく考えると全く訳が解らなくなってくるのが実体だろうと思います。
健康管理上なくてはならない野菜や果物まで、化学肥料や防虫剤、殺虫剤などの化学薬品なしでは、大量生産出来ない技術の開発が
進んでいます。でも我々は、その恩恵でたくさんの品種と量に恵まれて、安心して食料を確保することができているのです。
もし全ての添加物を廃止したら、瞬く間に食糧難に陥り、社会的大問題に発展し、逆に多くの犠牲者が生まれることは、火を見るより
明らかです。 ならば、この恵まれた食料状況を感謝しながら健康を維持し、「死ぬまで元気」に暮らせる方法を考え、実行してこそ 人間としての価値ある生き方ではないだろうか。「食べ物」「食べ方」については、もう嫌と言うほどいろいろな方法で聞かされ、 健康志向の関心度も高く、皆さん充分解っておられる方が多いとは思いますが、その内でもたった一つだけ実行していきたいことは、 「一日3食、規則正しく、何でも好き嫌いを言わずに、良く噛んで食べること」・・・簡単なようで、なかなかこれだけが守れないことです。 何とか続けて実行したいものです。 |
| 6月2日 | 衆議院解散 |
|---|
|
今日6月2日衆議院が解散され、13日公示、25日投票日と決まり、いよいよ選挙戦が始まることになった。
今回の選挙は、比例代表定数が20人削減され、新議席480席を目指して選挙戦に入ることになった。
森喜朗首相は、前首相の小渕恵三氏の急逝のため、急遽首相に就いて58日目にして、衆院解散でその真価を問われる選挙でも
ある。日本の人口1億2668万6千人(1999.10.01総務庁推計)の国民の頂点に立つ人には、それなりの政治力、
統率力、指導力、人徳をも兼ね備えたリーダーシップを発揮出来る人でなければならない。
平成の時代になってから、日本の首相を務めた人は、竹下登氏に始まり、宇野宗佑氏、海部俊樹氏、宮沢喜一氏、
細川護煕氏、羽田孜氏、村山富市氏、橋本竜太郎氏、小渕恵三氏、と森喜朗氏で10人目である。12年で10人。
最近の首相で一番長期政権を担ったのは、そのひと頃前の中曽根康弘氏の5年が最長である。どうしてこうも入れ替わり立ち替わり
日本のトップが変わるのだろう? 今回も森首相の「神の国」発言が飛び出して、首相としての資質や政権の正統性まで
論議を巻き起こしていて、選挙後の続投が危ぶまれている。場合によっては、また政権交代か首相交代があるかも知れない。
そうすると平成時代11人目の新首相誕生ということになるかも知れない。12年で11人なら、ほとんど毎年首相が代わって
いるようなものである。これでは国際社会で日本の政治の信任を得ることが出来る訳がない。
羽田孜氏が首相就任後、ナポリ・サミット出席に備えて、欧州各国を歴訪したとき、当時のドイツのコール首相が
「私がお会いする日本の首相は、あなたで何人目でしょうか。とても覚え切れません」と言われたその直後、羽田氏は
退陣に追い込まれて、ナポリ・サミットに出席したのは、その後任の村山富市氏だった、という笑い話にもならない
あきれたトップ交代劇までやっている。これでは諸外国の首脳が、日本を冷淡な視線で見下すのも無理からぬ事だと思う。 |
| 5月23日 | 生きること・死ぬこと |
|---|
この世に生を受け、始めての出会いは両親であろう。そして幾多の人との出会いを重ね、配偶者という生涯の伴侶との出会いを
通して、我が子との出会いを重ねていく。そして両親との別れ、配偶者との別れ、我が子との別れ・・・と、必ず出会いは、別れの始まりである。
言葉を換えれば、生きることは、死ぬことの始まりである。その生きることの難しさを、悩みとして真剣に戦って死んで行く。
人間として、どのように生き、どうあるべきかは、非常に難しい課題であろう。私たちは、少しでもそのヒントや参考になる方策を
求め続けている中に、有名な言葉や諺に巡り会うことが出来る。
しかし一番難しいのは、必ず来るであろう人生のしめくくりを、どうあるべきかを考えることであろう。そこで
|
| 5月15日 | ひとりNGO |
|---|
|
滋賀県近江八幡市出身の栗本英世さんは、ほんとうの一人で貧しいカンボジアの子ども達の救済の為に、奮闘努力
しておられます。「カンボジア子どもの家」支援代表として、NGO(非政府組織)活動を進めておられるのです。
カンボジアは、30年にわたる長い内戦を乗り越えて、ようやく今、国土復活を目指して頑張っておられます。
昨年(1999年)4月にASEAN加盟を果たし、国際社会の仲間入りをしたところです。ところが国民は、
国土の至る所に地雷が埋め込まれていて、ひとつ間違えば被爆して片足切断、両足切断を強いられる大事故に巻き込まれる
危険と背中合わせの中で暮らしています。そして国民の識字率は、30%以下であろうと思われる教育水準で、
字が読めないから仕事もなく、生活は貧困を極めています。親が教育を受けていない為、学校教育の必要性を
感じていないので、子どもの教育に理解が乏しいようです。教育よりも生活の為に子どもは、仕事を強いられているようです。
カンボジアの人口は、1,100万人ですが、その半分は15歳以下の子ども達です。その幼い子ども達が、
人身売買、幼児売春、エイズ、児童労働、ストリートチルドレンなどの諸問題の対象者なのです。「貧しいからしょうがない!」
の一言で片づけられる問題ではないはずです。貧困が原因とはいえ、カンボジアの将来を担う子ども達に、
自分で考え、理解する力を身につけさせるには、学校教育は不可欠であると考え、その為にひとりで力を注いでおられるのが
栗本英世さんなのです。
子どもの居る家庭にひとたび病人が出ると、医者にかかる費用もなく、ただ死を待ちます。どうしてもお金が
必要になると、子どもが売られて行きます。10数歳の幼い子どもが、暗がりで客の手を引き、売春させられる姿に
心を痛め、「どうしたらいいのか? 今、何が出来るのか?」の課題の中から、「教育」以外にないと考え幼児教育に
取り組んでおられる栗本さんなのです。
苦しい資金調達と、親達に教育の必要性を説得しなければならない難しさを乗り越え、一つの村に一つの
小さな粗末な寺子屋を作り、現在その「カンボジアこどもの家」は、8村8校、先生18名、生徒1,200名にまで
開設する事が出来、識字教育を進めておられます。それ以外に、親のいない孤児を20名養育しておられます。
勿論その程度では、まだまだ充分ではなく、各地の多くの村にも寺子屋の開設を必要とし、早期開設を切望されているのです。 たった一人で、このような苦難のNGO活動をされ、我が身を捨て、歯をくいしばって頑張っておられる栗本さんに、 尊敬と敬愛の念を禁じ得ません。私たちの恵まれた環境に比べて、カンボジアは天国と地獄ほどの差の生活レベルでは ないでしょうか・・・・。私たち国民一人一人の善意と好意で、「カンボジア子どもの家」の支援をしようではありませんか。 どうか、栗本英世さん!くじけず頑張って下さい。及ばずながら声援を送らせていただきます。 |
| 5月4日 | みっちゃん |
|---|
|
幼児や小さな子どもに対して「・・ちゃん」と呼んでいるのは、可愛くて親愛の情が伝わってくる。特に女の子に対しては、
「・・ちゃん」と呼んであげると、本人も優しさと若さを認めてもらっているような気分で、ご機嫌がよさそうだ。
しかしある年齢以上になると、何となくしらじらしく感じるのは、呼称の表現に無理があるのだろう。如何にも親しさを
誇張しているようであり、年を不透明にして若さを力説しているように感じて、自然な親愛感を感じない。しかし
小さいときから「・・ちゃん」と呼ばれている間柄だと、それが自然に受け止められる。ところが余り親しくない間柄で
「・・ちゃん」なんて呼ばれたりすると、「何でやね?」と違和感を感じるものだ。
最近首相になったばかりの森喜朗氏が、始めてロシアを訪問して、次期大統領のプーチン氏と会談して、これからは
お互いに「ヨシ」「ワロージャ」とファーストネームで呼び合うことを約束したとの記事を見て、お互い初対面同士が
気安くファーストネームで呼び合って、親愛感や信頼感が感じられるだろうか? 何となく無理矢理信頼感を押しつけあって
いるようで不自然である。
日本語の呼称は余りにも沢山あり、相手の年齢や地位や立場と状況によって、いろいろ使い分けしなければならないし、
それが的確でなければ、不自然さや違和感を感じて失礼になったり、不自然さを感じるのは難しいものだなあと思う。
私の名前の「三男(みつお)」を幼い頃から「みっちゃん」と呼ばれて久しいが、余り親しくない友人や知人から
「みっちゃん」なんて呼ばれると、しらじらしいなあ・・・と感じることが多くなってきた。同窓会や同年会などを
すると、何故だか「ちゃん」呼びを連発しているのが目立つ。永い間のご無沙汰の穴埋めを「ちゃん」呼びで埋めようと
している無理を感じるのは、私だけだろうか? 「ちゃん」呼びをするのは、ちゃんとした間柄だけにとどめるべきだ。時と場合によっては相手を軽視してり、 見下げたりしているように受け止められかねない場合もある。その点の日本語の使い分けは非常に難しいが、よく気配りして 正しい呼称で呼び合えるようになりたいものである。 |
| 4月20日 | 4月20日 |
|---|
|
4月20日、今日は私の誕生日です。私には誕生日という特別な意識はほとんどありませんでした。
幼い頃から誕生日のお祝いなど、あまりしてもらったことがなく、何ら特別な意識を持つことなく、今日まで
過ごしてきた。ところが世間のメディアや幼稚園、学校、友人、いろいろなグループ間に於いて、その人の
誕生日をお祝いする習慣が育って来ると、誕生日の持つ意味や重みが変わってくる。そして年を重ねるに従って
自分の年齢が気になってくる。特に数え年でなく、満年齢で数えるようになってくると、正に正味何年生きてきたかを
実感するようになってくると、誕生日の意識が高くなり、より一層自分の年齢を気にするようになってくる。
もう一つ私の意識を高めた理由は、毎年のように子ども達からいろいろな形でプレゼントを頂いたり、お祝いを
してもらっていることである。私自身は子ども達に、それほど誕生日のお祝いをしてあげた覚えがないのに、
三人の子ども達は、それぞれその子なりの表現で、私を祝ってくれる。何とうれしいことか。それにはもう一つの
理由がある。私は妻を亡くして17年、男親一人で子ども達3人を育ててきた為、子ども達にしてみれば、唯一の
親を思う気持ちが高いのだろう。私は、自分ではもう子離れしているつもりなのだが、子ども達が親を忘れずに
誕生日にその気持ちを見せてくれるのには、ほんとうに感激する。3人の子ども達よ!「ありがとう!」 そしてもう一つ楽しいのは、同じように育ててきたつもりの子ども達だが、3人とも全く違う個性であることである。 それは当然のことだが、親からみれば不思議な事だし、楽しみなことである。何でこのような性格に育ったのかなあ・・? と考え思い浮かべることが、おもしろくてたまらない。これからどのように成長していくのかなあ・・・と想像するのも 楽しみである。親子って・・ほんとうに・・いいものだなあ・・・。 |
| 4月7日 | 情報革命 |
|---|
|
インターネットの出現によって、我々の生活が大きく変わろうとしている。18世紀の産業革命によって世界は、
大変革を遂げた。情報の革命は①文字の発明②本の誕生③印刷技術の発明によって飛躍的な発展を遂げた。今インターネットの
普及は、産業革命をはるかに凌ぐ情報の大変革期を迎えようとしていると言われている。確かに情報の質と量と速さはもう
ここで説明するに及ばない。世界中でこの情報の活用方法について経済、産業、商業、金融などあらゆるジャンルで血眼になって
研究し活用合戦が繰り広げられている。日本も大分賑やかになってはきたが、まだ世界から遅れをとっている。日本でインターネットの
発展、普及が遅れている理由の一つには、日本人の意識や認識の持ち方の違い、特に経営トップの意識の薄さ。二つ目には、社会的制度や
規制の問題、特に電子商取引に対する規制。三つ目には、英語に弱い言語の問題が挙げられると思う。
私たちは、家庭から学校から社会からいろいろな経験を経て、さまざまな知識を積み重ねてきた。そして自分なりの考え方を養い、
それを固定観念として、信じて社会生活を営んできている。その信念が世の中の変遷に柔軟に対応することに邪魔になっているのではないだろうか?
過去の常識、過去の経験、過去の固定観念を見直し、時代に対応するための自己啓発に努力すれば、柔軟な発想力と独創性は磨かれ、
時代の変遷を的確につかみ、新たな情報を把握することが出来るのではないだろうか。その点インターネットや E-mail の利用価値は底のない
情報の宝庫のように思う。 私も家族との連絡は、ほとんど mail で行っている。仕事、友人、親戚、メル友、H.P関係などアドレスを持っている人には、 全て利用している。海外旅行した時の添乗員さんや、ツワーでご一緒した人との帰国後のお礼メッセージや情報交換なども、 何となくほのぼのした心情の交流になる。E-mail は、手紙のように形式にとらわれることなく、簡潔に要点だけでことが足りるし、 逢って言えないことも、mail なら不思議と自然に伝達出来るのは何故だろう? この不思議な魔力と今や収集出来ない情報はないと言われる インターネットの活用で、世界に目を向けて情報革命の波に乗って飛躍しようじゃないですか。 |
| 4月2日 | バンコクへの家族旅行 |
|---|
|
近年アジアの国々でもタイへの旅行が増えているらしい。タイは、ミャンマー、ラオス、ベトナム、カンボジア
などの隣国の内でも、特に経済の発展のめざましい国で、有数の観光地の多い所でその人気が上昇気運に乗っている
発展途上国です。その人気に便乗して、娘夫婦や息子夫婦や孫達も一緒に一族8名でバンコク旅行を楽しんできた。
わずか3泊4日の短い日程しか取れなかったが、皆にぎやかに楽しく観光し、日程が足りなかったのが残念でならなかった。
アユタヤ遺跡、王宮、ワット・プラケオ(エメラルド寺院)、ワット・ポー(涅槃寺=ねはんじ)、ワット・アルン(暁の寺院)、
チャオプラヤ川のランチクルーズやラマ4世時代の運河を利用した水上マーケット、タイ舞踊のディナーショー、
タイ伝統のトラディショナル・タイ・マッサージ(古典式マッサージ)など3泊4日とはいえ、正味2日間しか観光
出来ない日程で、飽きることのない充実した旅行だった。特に最大の見所は、1784年にラマ1世国王が建立した
ワット・プラケオで、その内でもエメラルド色のひすいで作られた高さ66㎝の座仏像は、すばらしい仏様だった。
バンコク市内は、活気に満ち溢れ、さまざまな屋台が街中いたるところに建ち並び、朝夕を問わず自転車がにぎやかで、
三輪車の荷台を客席に改造したミニタクシーと言える乗り物が人気のようです。街角、公園、広場には多くの人達が
たむろし、特に僧侶の姿が目につきます。タイでは、男性は一生に一度、僧侶になるのが普通だとも言われています。
その期間は、禁酒、禁欲の修行期間だそうです。
タイ料理は、日本人にはちょっと癖のある匂いが気になりますが、メニューは豊富で、味付けも確かで、何より
値段の安さが魅力です。特に果物が豊富なのも魅力です。 |
| 3月26日 | 警察刷新会議に思う |
|---|
最近の一連の警察不祥事に絡み、警察改革について議論して、その審議内容を公開し警察行政を見直そうという
意図で、有識者6名の初会合が「警察刷新会議」として開かれた。今後月3~4回のペースで開催される予定だという。
非常に結構なことだと思う。そこでこのような国の行政に関わるその他の委員会の委員の報酬を、簡単にまとめてみると、次の表のようになる。
そこで、私はふと思い出した。ある記事で梅原 猛(哲学者)氏が、だいたい次のように述べられている。
A県だけのことではない。政府の審議会にしても、ほとんど政府が決めたことを学者や文化人の権威を借りて合理化
するにすぎない。学者や文化人も多くは委員に選ばれたことを名誉とし、ひそかに行政の意を察し、行政の意に添わぬことを
発言することを慎むものである。このような飾りとしての審議会は、具体的な施策に結びつかず、百害あって一利なしと思う。』 座長の氏家斉一郎さん、大森政輔さん、大宅映子さん、中坊公平さん、樋口広太郎さん、顧問の後藤田正晴さん、今回は、 国民の期待と感心度は、非常に高いと思いますので、しっかり審議して裏切らないでくださいね。よろしく頼みますよ。 |
| 3月21日 | ジュニア議会を見て |
|---|
| 私の町のケーブルテレビで、子供の視点からまちづくりを検証し、子供の意見を
学校や社会に生かすことができるように、積極的な意見表明をするジュニア議会が放映された。子供の権利条約に規定された
子供達が、大人社会に対して自由に意見を表明できる「意見表明権」を行使できる公的な機会であり、「子ども参画社会」
をめざす目的でもあります。大人が子どもの意見や提言を謙虚に聞き、教育や行政に反映し、豊かで、平和な住みやすい
まちづくりを考える企画としては、すばらしい内容で感動した。
市内の3つの中学校から21人の代表者が、市議会さながらの規律正しいシステムで、次々と自分の意見や提言や質問を
発表し、行政の責任者がそれに答える方法ではあるが、その内容がほんとうに中学生が考えている問題だろうか?とさえ
疑いたくなるほど程度の高い質疑内容でびっくりした。その内容を列挙してみると
今どきの中学生は・・・なんて見下げたものの見方をしている人が居たら、このジュニア議会を見て欲しいものだ。 ほんとうに今の中学生は、しっかりしていて、大人顔負けである。そりゃ一部の生徒には問題の残る生徒も居るかもしれないが、 総じて良く考え、社会を良く観ていて、良く勉強している。もっと大人達も子ども達の意見や提言を真剣に受け止め、 街づくりや行政に反映させるような取り組みを考えるべきだと感じた。今の少年少女達の飛躍に将来を託そう! |
| 3月17日 | 夫婦生活 |
|---|
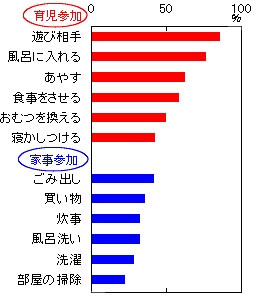 「男は仕事、女は家事と育児」という古来からの固定的な役割分担の考え方が、夫婦共稼ぎ家庭の増大の傾向の中で、
公平負担を望む妻の不満が続出し、妻の過度な家事負担は、益々少子化を招く原因として、「男女共同参画社会」の
確立を進めようとしている。しかし1998年の厚生省の調査では、左のグラフの通り、家事への夫の協力は、
全て半分にも満たない参加状態である。
「男は仕事、女は家事と育児」という古来からの固定的な役割分担の考え方が、夫婦共稼ぎ家庭の増大の傾向の中で、
公平負担を望む妻の不満が続出し、妻の過度な家事負担は、益々少子化を招く原因として、「男女共同参画社会」の
確立を進めようとしている。しかし1998年の厚生省の調査では、左のグラフの通り、家事への夫の協力は、
全て半分にも満たない参加状態である。
共稼ぎ世帯での妻の家事負担は、8割を越える家庭が77.6%もあり、夫が全く何もしない家庭は、27.6%
だという。その為妻の家事時間は、共稼ぎ家庭で平均3時間半、4時間以上は27.1%だという。6歳未満の子供が
居る家庭では、8割が妻中心。1歳未満の乳児の居る家庭でも、何もしない夫が1割居るという。
このような現状の中で、共稼ぎ世帯での妻の満足度は、5年前の58.2%から52.4%に減っている。反対に
妻の不満度は、41.8&から47.6%に増えているという。 |
| 3月13日 | 季節の食べ物 |
|---|
| 八百屋さんやスーパーに並ぶ果物や野菜を見て、その時折の季節を感じたものです。
しかし最近は、バイテク技術の進歩やハウス栽培や輸入食品の多様化で、その季節感がこんがらかってきましたね。
ところが人間の体は、自然にその時期にその旬の食品を求めたがるようになっています。それは何故でしょう? 食べ物には5つの味と5つの性質に分類されます。 5つの味とは
|
| 3月6日 | 批判好き |
|---|
| ひと頃芸能界で、ミッチー・サッチー論争がにぎやかだった。それが一段落したら、デビー夫人・マリアン論争、
その次は、デビー夫人の著書「ちょっと一言よろしいかしら」に対する酒井プロデューサー論戦と著書批判。一方横山ノック前大阪府知事のセクハラ問題、神奈川県警の不祥事問題、
続いて新潟県の女性監禁事件に絡む新潟県警本部長や警察局長不祥事事件批判等々マスコミは、そりゃ忙しい・・・。他人の批判は何故か関心度も高く、
人気がある。でも誰でも他人の批判は喜んでするが、自分に対する批判ともなると、目頭をつり上げて反論したり、言い訳をする。確かに是々非々で、間違っていることに対しては、
反省と共に改善してもらわなくてはならない。しかし人間十人十色で、この多様化時代には多岐亡羊として真実を確定し難いことが多いのではないだろうか? 先日もあるテレビ番組で、「大人から見た若い娘への批判ベスト10」なる放送があった。ちなみにそれを列挙してみると・・・
自分の若い頃を振り返ってみると、何らかのへんてこりんなことを、平気でやっていたことが、少なからずあったものだ。 年いって出来ないことを、若い時に気ままに振る舞うことは、若さの象徴であり、活力の表現でもあるのではないだろうか。 自分の娘が、外で何をしているかも知らないで、他人の娘を批判しているのは、お門違いのように思う。そのような人が、 自分を批判されたら、どんな顔をするのだろう? 他人を批判する前に、今一度自分自信を振り返って見ることから始めたら如何なものでしょうか? |
| 2月25日 | チョコレート |
|---|
| 先日のバレンタインデーに、義理チョコをいただいたチョコレートが、
まだたくさん残っている。製菓会社の商業デモンストレーションなのか、真の女性心理の社会行為なのか、そのルーツと
実体は知らないが、実に上手に社会現象化させてしまったものだ。まあこのようなお遊び的なフェスティバルも、罪のない
楽しみとして悪くはない。
ところで、このチョコレートが日本に渡来してきたのは、江戸時代で、当時は疲労回復剤や薬用飲料として食されていたらしい。
ヨーロッパや中南米でも、不老長寿の秘薬として用いられていたという。明治時代になって、栄養価の高い高級食品として製造され始めたが、
現在のようなお菓子として普及し始めたのは、戦後のアメリカ進駐軍の影響によってもたらされたという。
チョコレートが脚光を浴びだしたのは、古来から薬用品として珍重されてきたように、健康志向がささやかれるようになってくると、
科学的にその効果や効能がクローズアップされてきて、単なるお菓子ではなく、健康維持や病気の予防や改善に良い食品としての
評価が高まりだしたからである。そこで、このチョコレートの魅力を検証してみよう。
|
| 2月21日 | 七つの悪行 |
|---|
インドの偉大なる政治家マハトマ・ガンジーは、無抵抗、不服従を敢行し、
イギリスからのインド独立運動を指導した。彼は、次の七つを人間の悪行、社会悪としてアピールし続けた。私たちも
その精神を今一度見直し、反省の糧にしなければならない。
|
| 2月15日 | 箸 |
|---|
| 食堂やレストランなどで食事をしている人達の「箸」の持ち方を見ていると、
上手な箸の使い方をしている人は、姿勢も良くマナーを心得ているように見えて非常に感じがよい。平均若い人達、特に
年少者や幼児は、まだ不慣れな格好をして食べている。最近は、スプーンやフォークを使う食事が多く、箸の使い方の練習が
少ないのではないだろうか。でも日本では、まだまだ箸を使う食事が一般的で、三度の食事に欠かせない貴重な存在です。
わしづかみに握り、お茶碗を口に持っていってかけこますような食べ方は、決して美しい食べ方のようには思えない。
視覚的に美しく、物理的には、箸を固定した上で開いたり、閉じたり出来る持ち方は、どんなものをつまんでも、
箸を持つ位置はほとんど移動しないので、安定して使いやすく合理的な持ち方な筈です。子供の時に根気よく親が
教えてあげれば、誰でもできるはずです。
では、持ちやすい箸の長さは?ということになると、一般的には21㎝、レストランや料亭で長いものは23.5㎝、
子供用の割り箸では6.5㎝のものもある。その人にふさわしい長さの算出法は、中指の先から手首までの長さの1.1~1.2倍。
又は、人差し指と親指の長さの1.5倍、とも言われている。もちろん慣れてくると、どんな長さのものでも上手に扱えるようになる。 |
| 2月7日 | 環境保全 |
|---|
| 滋賀県のびわ湖沿岸21市町が連携して、「琵琶湖ラムサール条約連絡協議会」の
設立総会が開かれた。「ラムサール条約」は、1971年の国際会議で採択され、特に国境を越えて移動する水鳥を中心に、
湿地の環境を保護する目的で、日本は80年に加盟し、琵琶湖は93年、国内9番目の湿地として登録されているとのこと。
近年は、各地で環境保全について、やかましく議論されるようになってきた。特に滋賀県は琵琶湖という大きな水資源を
抱える地域だけに、その使命と責任は重要である。
先日も私宛に滋賀県土木部河港課河川環境係から「琵琶湖の湖岸に関するアンケート調査」につての依頼があって、
県民の意識調査が行われている。県としてもあらゆる角度から、環境問題につては調査、研究されている実体はうかがわれる。
行政として、しなければならないこと、行政でなければできないこと、いやもっと国や地球規模で考え、やらねばならないことも
たくさんあると思いますが、我々個人では何が出来、何をしなければならないかを、よく考え即実行に移すべき状況にまで、
事態は深刻になってきていると思う。
全世界的規模で、危険度の高い原子力発電からもっと安全な風力、地熱、太陽熱を利用するクリーンエネルギーの開発、
大量生産、大量消費、大量廃棄を改め、循環型消費に・・・。そのためのリサイクル産業の育成、省エネ企業に対する減税処置など、
大きな問題は、我々個人では及ばないが、私たちも日常生活でのちょっとした心がけで、環境保全を実践する事が出来る。
|
| 1月23日 | こどものしつけ |
|---|
| 「しつけ」とは何なのか? どうあるべきなのか? 自分がしつけられたのは、
どうだったのか? 自問自答しても、明確に判らないことが多い。そもそも「しつけ」の「つけ」は、かかりつけの医者,
行きつけの床屋、つけで物を買う、しつけ糸、などのつけと同意語で「~を習慣にしている」という意味である。
従って、生活の全ての言動が、同じパターンで繰り返されていることが、習慣であり「しつけ」である。
こどもは、親の背中を見て育つと言われる。なのに自分が習慣にしていなくて、身に付いていないことを、こどもに習慣づけようとしても、
それは無理である。しかも特に2~3歳までにしつけておかないと、加齢してからは難しいとよく言われている。
脳の発達量について、大脳生理学者は、ゼロ歳から2歳までと、2歳から20歳までは同じ。しかも2歳ごろまでは、
母親が一日4時間はこどもに接していないと脳は正常に発達しないと忠告している。
それを裏付ける著書に、ソニーの創業者の故 井深 大氏の「幼稚園では遅すぎる」の中に「2~3歳までは甘やかし、自我の芽生える4歳以降に
しつければいいというのが、日本の母親の考え方のようです。しかし2~3歳までに厳しくしつけておかないと、後でどんなに厳しくしつけても、
まず効果はないと言っていいでしょう。その結果、大学生になっても、あるいは社会人になっても、自分の要求が通らないと駄々をこねる
大人が後を絶たないのです」と言っている。 ところが、日本の母親の育児に対する姿勢は「過保護溺愛型33%、消極型32%、適切型13%、矛盾型12%、拒否命令型10%」だと 分析されていることを聞いたことがある。ここでいう適切型13%が、本来あるべき乳幼児期に厳しくしつける方針の%とするならば、 全般的には日本の母親の育て方は、決してほめられるものではないと言えるのではないだろうか。母親自らが厳しく律っせられて、子供に対する真の愛情が、 厳しく育てることを認識していれば、「三つ子の魂百まで」のことわざの意味も分かろうというものだ。しかし現実的には、まだ2歳にもならない乳幼児に 母親の厳しいしつけや、生活態度が解っているのだろうか?と思うのは当然のことである。でもこどもが解らないから、可愛さ余って溺愛し過保護に育てることが、 習慣になると、「慈母に敗子あり」になることを解ってほしい。それだけに、これから迎える21世紀を担う子供達のしつけについて、 世界に誇れる子育てで、我々を安心させ、たくましい有望な青少年を育てて欲しいものだ。お母さん達!大変でしょうが、頑張って下さいね! 当然お父さん達も理解し協力しなくてはならないことは言うに及ばない。 |
| 1月18日 | いやしとペット |
|---|
| 六千数百人もの人達が亡くなったあの阪神大震災から、丸5年がたった今でも、
その被災者のほとんどの人達は、街は復旧したが生活や心は復興していないと訴え、心の傷を癒すのに苦慮しておられる。
人の心は、ハード的なものでは満たされず、如何にソフト面が大きなウエイトを占めているかがうかがわれる。誰でも
生活のストレスは溜まるもの、それを癒すのにいろいろな趣味や楽しみを求めて、明日への活力を養っているものだ。
その一つの方法にペットがある。世は正にペットブームである。アニマルテラピー(動物介在療法)という言葉も
あるほど、ペット達は私たち人間の心を癒してくれる存在であり、家族の一員のような存在でもあるのです。
それほど人の心を癒し、なついてくれる犬や猫であるにも拘わらず、彼らのフンの後始末をおろそかにし、近所に
迷惑をかけたり、中には飽きたら、すぐ捨てたり殺してしまったりする人もいる。何とも情けないことである。
私の町のロータリークラブの社会奉仕委員会が、犬のフンの後始末についての注意書きの看板を、数百枚各地域に立てて、
街の美化運動を推進したところ、地域の住民からたくさんのお礼状が、ロータリークラブに届けられた。
誰でもみんなが解っているモラルでありながら、他人の迷惑を省みず、自分の癒しのために節度を守らない不心得者は許せない
と思っている人は多いだろう。何処の犬のフンかわからないから、注意のしようもない。仮に判ったとしても、
顔見知りの人なら言いにくい。その代弁をロータリークラブの看板がしてくれたら、こんな有り難い奉仕活動はない。
その気持ちが一枚のはがきに託されている思いがする。 犬のフンにとどまらず、犬や猫を捨ててしまったり、訳なく殺してしまったりする人達もいる。愛知県のブリーダー(家畜を繁殖させる人) が捕まりましたが、彼らを裁くしっかりした法律が整備されていない現状では、各自の自覚に任せるしか仕方がないのです。 幼児期に動物を虐待している人は、成人してから殺人を犯しやすい傾向があると言われている。何とか「動物保護法」とか 「動物愛護法」とかの法整備を願っている。推計で年間 犬が40数万匹、猫が30万匹程処分されていると言われている。 動物は、物ではない。生きものなのです。弱いものへの思いやり、慈しみの心を育てることこそ、人間として大切なことではないでしょうか。 そしてペットとして可愛がるだけでなく、最後まで責任ある飼育と管理をしてこそ、自分の癒しの恩を返す仁義ではなかろうか。 |
| 1月13日 | 新着日本語 |
|---|
| ガングロのジモティ会話 では 私流に翻訳してみると・・・
日焼けサロンで焼いた黒い顔の同郷女子友達の会話 |
| 1月8日 | ミレニアム |
|---|
| 昨年一年間を印象付ける漢字に「末」という字が選ばれた。
確かに世紀末でもあるからなのかも知れないが、経済、金融、労働環境を含めて世の中は、真っ暗闇でもう
「世も末」という感があった。倒産や借金苦の生活苦から犯罪や自殺者も増え、夢も希望もなくし深刻な苦悩の
続く毎日なのに、それに追い打ちをかけるかのように、Y2K(2000年問題)というコンピューター誤作動
不安を追いかぶせて来た。何とか新世紀には、現況を脱して明るい見通しがつくことを、祈っていた人が
ほとんどではなかっただろうか。全国の行政区で20万人、民間でも数10万人という人達を総動員して、万が一
の緊急事態に備えての、大晦日の徹夜の管理体制も無駄になったとはいえ、何とか大きな事故もなく無事に
新世紀のスタートを迎えられたのは、一抹の不安解消の一助になったことは確かである。
ミレニアムとは千年紀のことで、「世紀」は100年単位の暦を指すが、1000年単位の暦を千年紀という。
ミレニアムには、終末にあたってキリストが再臨し、1000年間を統治するという「千年王国」という意味も
あるという。西暦2000年のスタートで、Y2K問題がスムースに解決されたことにより、何となく希望や
夢が明るく持てるよな気分になったように思う。千年王国の第一歩がキリストのお陰であれ、お釈迦様のお陰であれ、
誰でも良い、結果が良ければ、人間は気分が変わる。気分がよくなったところで、新世紀の壮大な夢を描いて
その実現に向かって行動しょうではないか。 あの心理学者のフロイトは、夢の分析から始めた。キング牧師は、「私には夢がある」といってアメリカの 公民権運動を起こした。世の科学技術の進歩は、夢の実現を目指して研究に取り組んで今日の技術革新を 成し遂げた。来るべき21世紀の革新は、20世紀を大きく上回る考えられないような大変化が期待出来ると思う。 我々を含む全世界の人間が、その大きな夢の実現に向かって、努力し行動を起こさねばならない。ミレニアムの 原点は、夢を持つことから始めよう!21世紀は明るいぞ!希望を抱いて頑張ろう! |

〔 2004.1.17~12.5まで分 〕
〔 2003.1.7~12.27まで分 〕
〔 2002.1.6~12.30まで分 〕
〔 2001.1.7~12.21まで分 〕
〔 1999.1.7~12.28まで分 〕
〔 1998.8.3~12.31まで分 〕
