


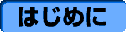
最近 特に見直されている植物油。身近な食品ですが、何故 健康食品なのでしょうか?
その疑問にお答えする「なるほど」をまとめてみました。おいしくてヘルシーな食生活にお役立て下さい。
- INDEX
- ・油の歴史
- ・植物油の種類
- ・植物油の製法
- ・植物油の主成分は脂肪酸
- ・植物油の脂肪酸含有率
- ・ビタミンと仲良しの植物油
- ・油料理のテクニック
- ・植物油の種類
 油の歴史
油の歴史
古代の人々は主に狩猟によって捕らえた哺乳動物から、身体の脂肪分をとっていたようです。貝塚の痕跡から
鹿、熊、狐、狸、うさぎ等の動物類やクルミ、栗、かや、とち、つばきの実等の植物性油脂も重要な脂肪源の様でした。
日本では日本書紀の記述から、3~4世紀神功皇后の時代に、大陸から搾油の技術が伝わり、摂津の国遠里(おり)
小野(現在の大阪。住吉区)の住吉明神にハシバミの実から搾った油を献灯した灯明油が、その始まりだったようです。
奈良時代に入ると、仏教の伝来と共にごまとその搾油技術が広まり大化改新(645年)の頃には、
荏胡麻(えごま)油が現物税として朝廷に献上されていたことが「賦役令」にのっています。
平安時代にはいると貞観元年(859年)、京都の大山崎離宮八幡宮でてこの原理を利用した搾油機が発明され、
荏胡麻油等の灯明油が大量に作られるように、離宮八幡宮の杜氏は朝廷から「主油司」(あぶらのつかさ)の位を賜り、
公課を免除される特権を得たと言われています。鎌倉時代にはいると、いろいろな”油屋”でその独占権を一手に握っていたのも、
いたのは、この大山崎の杜氏のようでした。こうして油が広く使われるようになってきましたが、明治の文明開化以降
急速に大衆に浸透し大正時代には家庭でも洋食が広まり植物油の需要は飛躍的に増えてきました。
 植物油の種類
植物油の種類
| 種 類 | 油 分 | 特 徴 | 用 途 | 主 産 地 |
|---|---|---|---|---|
| 大 豆 油 | 16~22 | 最もポピュラーな油で油ぎれのよい特有の旨味を持っている | 天ぷら油、サラダ油、マーガリン | アメリカ、ブラジル |
| ゴ マ 油 | 45~55 | リグナンという天然の酸化防止効果のある成分を含んでいる | 中華料理、天ぷら | 中国、ミャンマー |
| オリーブ油 | 40~60 | 薄黄色で特有の香りとうまみがあり、最高級の油との評価 | マリネ、シーフードサラダ、化粧品、医療品 | イタリア、スペイン |
| や し 油 | 65~75 | ココやしの果実を乾燥したコプラが原料。ココナッツオイルとも呼ぶ | マーガリン、ショートニング、製菓用、シャンプー | フィリピン、南太平洋諸島 |
| パーム油 | 44~53 | カロチンを多く含んでいるので赤橙色だが精製すると淡色 | フライ、マーガリン、ショートニング | マレーシア、インドネシア |
| こ め 油 | 12~21 | サラッとした風味が特徴で耐熱性にすぐれている | マヨネーズ、製菓用 | 日本 |
| 綿 実 油 | 15~25 | 風味とまろやかなうまみが特徴で、風味の安定性がよい | サラダ油、マヨネーズ | アメリカ |
| ひまわり油 | 28~47 | クセのない淡泊な風味が特徴で、生食用に使われる | マリネ、ドレッシング | アメリカ |
| コーン油 | 40~55 | 酸化安定性がよく、加熱すると香ばしい独特の香りがする | 揚げ物 | アメリカ |
| べに花油 | 25~40 | リノール酸の多いハイリノール原料とオレイン酸の多いハイオレイン原料がある | 生食用、(成人病予防に効果) | アメリカ |
| なたね油 | 38~45 | あぶらなの種子で、風味は淡泊で酸化しにくく熱に強い | 天ぷら油、サラダ油 | カナダ |
 植物油の製法
植物油の製法
- (1)荷揚げ
- 海外から輸入された原料は、アンダーローで直接サイロに運ばれ、貯蔵されます。
- (2)精選する
- サイロから工場に運ばれた原料は、金属やクギ、サヤなどを取り除き精選されます。
- (3)圧搾する
- 精選された原料は、圧搾機で圧力をかけて2/3ほど油分を採油した後、抽出機に送られる。
(大豆は油分が低いので、熱を加えて潰してから直接抽出される)
- (4)抽出する
- 圧搾された原料は、連続油脂抽出機で残りの油分を抽出され、油と脱脂粕に分けられます。
抽出された原油は次の精製工程へ。脱脂粕は飼料や肥料などに利用されます。
- (5)脱ガム・脱酸
- 抽出された原油には、水分、ガム質、脂肪酸、色素、有臭成分などの不純物が含まれていますので、
遠心分離器でガム質、脂肪酸などを取り除きます。
- (6)脱色
- 活性白土を使い脱色行程で、色素を取り除きます。さらに濾過機を通して色のきれいな油になります。
- (7)脱ロウ
- 10℃~0℃まで冷却して、油の中のロウ分を固体にして連続濾過機で取り除きます。
- (8)脱臭
- 高温・高真空状態の脱臭塔で、水蒸気を加えて油に含まれている臭いの成分を、完全に取り除きます。
- (9)製品充填
- 精製を終え、品質検査の後に、容器に充填され出荷されます。
 植物油の主成分は脂肪酸
植物油の主成分は脂肪酸
油の主成分である脂肪酸はエネルギー源としての役割と、身体の組織を正常に機能させる働きがあります。
脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に大別されますが、植物油の主成分はほとんどが不飽和脂肪酸で、
リノール酸、リノレン酸、オレイン酸などが代表、この内リノール酸とリノレン酸は、人間の体内では作られず、
食物から取らなければならないので「必須脂肪酸」と呼ばれています。
①飽和脂肪酸
- 一般的に固形で、乳製品や肉などの動物性脂肪に多く含まれています。主としてエネルギー源の役を果します。
②不飽和脂肪酸
- 常温では液状で、植物油に多く含まれています。身体の各種細胞膜の構成物質です。
- (1)リノール酸
- 身体の組織が正常に機能する上で欠かせません。不足すると、成長阻害や皮膚障害が生じたりすることがあります。
- (2)リノレン酸
- 発ガンの抑制やアレルギー症状に効果があります。脳細胞の活動を支えるDHA(ドコサヘキサエン酸)も、この系列の脂肪酸です。
- (3)オレイン酸
- 悪玉のコレステロールだけを下げる効果があります。体内作り出すことができ、又酸化しにくい特質を持っています。
 ビタミンと仲良しの植物油
ビタミンと仲良しの植物油

日本人はビタミンEを約半分は植物油から取っているといわれている位、豊富に含んだビタミンEは、 血液の流れをよくしたり、不妊症を予防するほか、老化の元凶といわれている活性酸素の働きを抑え、 ”過酸化脂質”の生成を抑える働きがあります”過酸化脂質”は、脳や心臓、肝臓、皮膚などの細胞に付着して 老化現象を引き起こす物質ですが、ビタミンEは、この物質が体内で作られるのを抑え、老化の防止に役立っているのです。 又ビタミンEは、ガンの予防にも効果があると、国立ガンセンターが発表した「がんを防ぐための12ヶ条」にも記されています。

ニンジン、ピーマンなどの緑黄色野菜に含まれているビタミンAは脂溶性ビタミンと呼ばれ、脂質が十分ないと 体内に吸収できません。たとえば、ニンジンを生で食べた場合のビタミンAの吸収率は10%。煮て食べると30%。 油と一緒に食べると50~60%の吸収率にあがります。

植物油は短時間で加熱調理できるので、パセリ、ピーマン、ほうれん草等ビタミンCをたくさん含んでいる 野菜の調理にはビタミンCの破壊が少なく、植物油が表面を覆って熱や空気からビタミンCを守ります。

でんぷん質の食べ物の消化には、大量のビタミンB1が必要になります。不足すると脚気や食欲不振、 疲労しやすい症状が現れます。植物油には、このビタミンB1の消費を節約する働きがありますから、油調理は、 ビタミンB1の確保にも効果がある調理法です。
 油料理のテクニック
油料理のテクニック

- (1)材料の水気をよく切る
- ふきんやペーパータオルで材料の水分を吸い取って揚げれば油ははねません。
- (2)油の温度を知る
- ◆おいしく揚げるには油の温度。温度計を使わなくても、衣を落としてみると油の温度が解ります。
①衣を落としてなかなか浮き上がってこない→ 140℃以下
②鍋の底に沈んで浮き上がる → 150~160℃
③途中まで沈んで浮き上がる → 180℃
④すぐ浮かんでくる → 190~200℃
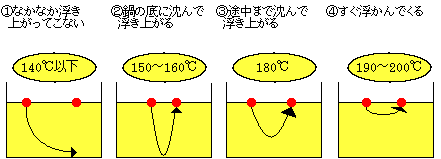
- ◆揚げ温度の目安
揚げ温度の目安 料 理 温 度 野菜の天ぷら 160~180℃ 魚の天ぷら 180~185℃ かき揚げ 180~185℃ コロッケ 170~180℃ ドーナツ 160~170℃ 魚のフリッター 160~170℃ とんかつ 160~185℃
- ◆揚げ温度の目安
- (3)油は適量で少しづつ揚げる
- 油は鍋底から3~3.5cmは入れるように、又材料を入れすぎると油の温度が急に下がってしまうので、
油の表面積の1/3程度を目安に少しずつ揚げ、又揚げかすをこまめに取り除くことも大切です。
- (4)揚げ油の上手な使い方
- 精進揚げや天ぷら等、他の材料の匂いが移ると風味が損なわれる調理の場合は、あたらしい油が適しています。
その次にコロッケやフライ類、最後に下味をつけた肉や魚を揚げるようにすれば、上手に使えます。
- (5)冷凍食品の揚げ方
- 油の温度を一定に保ち、冷凍食品を入れてから1分間は箸などでさわらないようにするのが、くずさないコツ。
又、一度溶けて再冷凍したものは、食品の周囲に氷の結晶が付着してしまい、揚げている最中にパンクする原因になります。

- (1)フライパンに油をなじませる
- 材料を入れるまでに、鍋やフライパンをよく熱してから油を入れ、全体になじませる。この下準備をしておけば、
焦げ付いたり油っぽくなりません。
- (2)同じ大きさに切る
- 一緒に炒めるものは、大きさを同じ大きさにそろえて切るようにすれば、全体に均等に炒めることが出来ます。
- (3)炒める順番がポイント
- ①香りを出す野菜、(長ねぎ、にんにく、唐辛子、生姜等)を油を温めながら十分に油につけることから始めよう。
- ②肉は、野菜を先に炒めると水分がでてしまうので、油が高温の状態で先に炒め、表面を固めることで、 旨みを逃さないようにします。
- ③ニンジンなど火が通りにくいものを先に炒め、葉もの等は後から入れるようにします。炒めすぎると、 野菜から水分がでて水っぽくなってしまうので、手早く火を通します。
- ④最後に卵を入れ、肉や野菜を包み込んで旨みが逃げないようにします。但しチャーハンの場合は 卵を先に入れ油を吸収させ、ご飯が焦げ付かないようにします。
- ②肉は、野菜を先に炒めると水分がでてしまうので、油が高温の状態で先に炒め、表面を固めることで、 旨みを逃さないようにします。
- (4)強火で手早く
- 低温で長く加熱していると、旨みや栄養分が流出してしまいます。又材料の歯ごたえや色が失われてしまう
原因にもなります。香ばしく口当たりよく仕上げるには、強火で手早く炒めるのがコツ。
- (5)油通しとボイル
- 肉や魚介類や固い野菜等は、油で一度揚げてから炒める「油通し」をする事で、おいしさを閉じこめる
方法があります。火の通りが悪い野菜は、あらかじめボイルしておく方法もあります。
- (6)調味料は手早く
- 炒めるときはスピードが大切。次々と調味料を手早く入れられるように、調味料は あらかじめ全部揃えておいて、
手元に置いておくようにします。

- (1)油を塗ってから焼く
- 表面が高温のため水分が蒸発するのを防ぐため、あらかじめ材料の切り口に油を塗っておくと、
色つやよく焼き上がり、しかも旨みが逃げるのを防ぎます。
- (2)焼き網にも油を塗る
- 魚や薄切りの肉等が網にこびりついたり、はがれたりするのを防ぐため、焼き網に薄く油を塗っておくと、
きれいに仕上がります。
- (3)バター焼きにも油を使う
- バター焼きをするとき、バターだけで調理すると、すぐに焦げ、バターの香りも消えてしまいます。まず、
油を熱しバターを入れ、溶けたら材料を焼きます。仕上げにバターを少しのせると、風味も増します。

- (1)サラダはしゃっきりと
- ドレッシングをかけて食べる野菜サラダは、みずみずしい歯ごたえが命、冷水に5分ほどさらした後、
乾いたふきんなどで軽く押さえて水気を切りましょう。
- (2)手でちぎった方がおいしい
- レタス、エンダイブ、クレソン、チコ等の葉野菜は、食べやすい大きさに手でちぎった方がしゃっきり感が残り、
ドレッシングもからみやすくなります。
| 【調 味 料】 | 【海 藻 類】 | |||||||
| みそ | 酢 | 醤油 | 植物油 | わかめ | ひじき | あらめ | 昆布 | のり |
| インスタント ラーメン | 小麦粉 | 食物せんい | 緑黄色野菜 | トマト | はちみつ | コーヒー |
