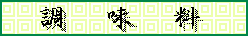

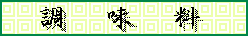
我々の食生活に欠かせない、日本古来からの調味料として、代表的な醤油について勉強してみましょう。
| 味 噌 | 酢 | 醤 油 |


◇小麦
でん粉を主成分とする小麦を炒り、酵素の作用を受けやすくする。次に小麦を砕いて微生物の
働く面積を増やします。粉になった小麦は、混ぜ合わせる大豆の表面を覆うことにより、
水分の調節や雑菌の繁殖を防ぐ役立ちをします。
小麦以外にも大麦、裸麦、ハト麦等も使われることもありますが、味が落ち色が黒ずむ問題点があります。特に香りの供給源は小麦のでん粉にあります。
◇食塩
食塩水は単に塩味のもとになるだけでなく、もろみを雑菌による腐敗から守り、しょうゆ造りには
欠かせない耐塩性や好塩性の有用菌の活動を助ける役目を担います。
◇種麹
しょうゆ造りの第一歩は、大豆と麦でしょうゆ菌を造ることから始まります。その為に必要なにが種麹です。
種麹には、プロテアーゼとアミラーゼという酵素をたくさん生産する菌を使いますが、
最近ではコウジカビAsper-gillus oryzaeとAsper-gillus Sojaeが広く使われます。
◇麹菌
麹菌とはおおくの酵素を造り出すカビの一種で、タンパク質をペプチドやアミノ酸に分解する「プロテアーゼ」
「ペプチターゼ」、でん粉をぶどう糖に分解する「アミラーゼ」等があります。
又麹菌は30種以上もの香りの成分を造り出す効果もあり、みそ、清酒、焼酎、みりん、米酢等醸造製品には必ず使われています。
◇うすくち醤油
米→蒸す→精麹→糖化→[甘酒]→【圧搾】
【圧搾】の行程で[甘酒]を添加する。それ以外の行程は〈こいくち〉と同じです。
◇うすくち醤油
うすくち醤油は、料理材料の魚や野菜などの持ち味や色合いを、天然のまま保ち、しかも
「だし味」を生かす目的のために、色がうすく、比較的塩味も多く、香りやうま味は少なくなっています。
製法は脱脂加工大豆を蒸す時に、色を付けないように圧力をかけず、小麦の炒り具合も浅く、
食塩の量もこいくちしょうゆの18%より2%程多く含まれている。
そして上記の「製法行程」の説明の通り、仕上げの時の調味加工用として、米麹の甘酒をもろみの中に
添加すること以外は、こいくちとほぼ同じです。
◇たまり醤油
たまり醤油は、黒っぽい、甘ったるい、濃厚な味をしたしょうゆで、主に愛知・三重・
岐阜・滋賀県下等中部地方でしか使われていない。全体の2%程度の生産量です。
原料も大部分が大豆で、あまり発酵されないので、香りはなく、味も引き締まっていない。
ブドウ糖も少なく大豆タンパクの窒素成分が多い為、濃く感じられる。
用途としては、さしみのつけ醤油の他、照り焼き、せんべいやおかきに使うとつやがでます。
◇白しょうゆ
白しょうゆの色合いは、うすくちよりもさらにうすく、黄金色に近い色をして、味が淡白な割に
特有の香気に富んでいる。
大豆の皮をむき、主原料の小麦を精白して、炒った大豆と共に
麹にし、水に仕込んだもので、色の進まないように短期間で熟成させるので、発酵が完了
していない為、半年もすると発酵して、色が濃くなり、甘ったるいような味に変わることもある。
主にたまりしょうゆと同じ中部地区でわずか生産されて、使用地域も愛知、三重県下に
限られている。
◇さいしこみ醤油
造り方はこいくちと同じですが、塩水の代わりに生しょうゆを使って仕込んだもので、
しょうゆを二度醸造するようになるため、別名「再生しょうゆ」とも呼ばれている。
味、色ともに濃厚で、白身の刺身や寿司のつけ醤油として、関西地区で使われ、
山口県の柳井市を中心に九州から山陰地方にかけての特産品として、わずかに生産されています。
◇生しょうゆ
普通のしょうゆは、モロミをしぼってできたものに、色、味、香りを整える目的と、微生物
を殺す目的で、火入れ(加熱)しますが、生しょうゆは、この加熱処理をしません。
その代わり特殊なフィルターで、微生物や不純物を取り除いて保存性を高め、同時に透明さを与えます。
新鮮な香りが特色で、色はこいくちの半分程ですが、こいくち同様のコクのある旨さをもっており、
タンパク質分解酵素等の酵素類を多量に含んでいますので、肉を漬け込んでおくと柔らかくなる、
という特徴を持っています。
◇減塩醤油
普通のしょうゆから特殊な方法で、塩分を半分の9%以下にし、うま味、香りなど他の成分は
そのまま残している。
減塩食を必要とする人を対象に造られた醤油で、昭和48年から
厚生省の「特殊栄養食品」として指定されている。
◇うす塩・あさ塩・あま塩醤油
塩分を普通の醤油の3/4にカット(13%台)になっています。防腐性を高めるため、アルコール分を1〜2%
おおくしてあります。そして減塩醤油と紛らわしくならないように、「低塩醤油」と言う表現を使わないようにしています。
◇粉末しょうゆ・固形しょうゆ
粉末しょうゆは、醤油から噴霧乾燥法、あるいは真空乾燥法によって、水分のほとんどを取り除いて乾燥
させ、粉末化した醤油。
インスタントラーメンのスープなど、即席スープに使われています。
固形しょうゆは、携帯用に作られたもので、粉末しょうゆを固めたものです。
◇魚しょうゆ
魚類・貝類・又はその内臓から造った醤油の総称です。魚しょうゆは、特有の匂いをもち、
動物性のタンパク質が原料なので、鍋物に使う場合は、ダシ汁をとる必要がない程です。
魚・貝類に食塩を加えて腐敗を防ぎながら、それ自身のもっている酵素を利用して、魚肉タンパク質を
分解し、アミノ酸などにしたもので、製造には1年以上、長いものは3年もかかります。
但し これは、JAS規格のしょうゆには入っていません。
 ◇味
◇味
★酸味成分
1〜2%含まれている乳酸が主で、リン酸(1%以上)、コハク酸、酢酸など15種類の
有機酸が含まれています。
酸味とおいしさは深い関係があり、最もおいしく感じられるのは、
pH4〜5のpH(酸性・アルカリ性の基準値)ですが、本醸造醤油のpHは、4.7〜4.8の弱酸性で最も
おいしく感じられる値になっていると同時に、醤油自身の香りや色の安定にも役立っているのです。
★塩味成分
仕込みの時に加える食塩が塩味成分で、こいくちしょうゆの濃度は17%前後で、海水の濃度の
5〜6倍にもなり、強い殺菌効果を発揮します。しかし、酸味やうま味等の他の成分によって
和らげられる為、それほど塩辛く感じないのです。
★苦味成分
ロイシン、イソロイシンなどの苦味アミノ酸やペプチド類などが、苦味の成分ですが、
直接苦味を感じることはなく、醤油にコクを与える隠し味的な存在で、味全体にしまりを
与えます。
★旨味成分
旨味を構成するのは、主として原料の大豆、小麦のタンパク質が麹菌のタンパク質分解酵素に
よって分解されて出来る約20種類のアミノ酸です。なかでも大きな働きをするのは、
グルタミン酸ですが、良質のこいくちしょうゆには、1.5%程含まれています。
これは食塩含有量のほぼ1/10で、最もおいしいと感じられる比率が10:1で、醤油の中の塩味と
旨味成分としてのグルタミン酸は、その比率に近いことがわかります。
その他にもアスパラギン酸、アルギニン、ヒスチジン、リジン、グリシン、アラニンなどがあります。よく醸造された
醤油にはまた、2〜3%のアルコール分が含まれており、調理のときに火や味の通りを
よくし、風味を引き立てる効果があります。
 ◇香り
◇香り
香りというのは、食べ物のおいしさに大きく影響します。又 香りによって味の感じ方も
全く変わります。醤油の香りは、非常に複雑で、原料の配合、麹菌、発酵に関与する酵母、
乳酸菌、発酵の強弱、精製管理、添加物の種類等によって微妙な違いを生じてきます。
現在、本醸造しょうゆに含まれている香りの成分は、250種類以上にもなっていますが、
全体として調和しているので、芳ばしい香りになっています。
その主なものは、しょうゆの醸造中に、アルコール類、エステル類、フェノール類、含流化合物、フラノン類
等が生成される。続いて、火入れのとき、加熱によって、アルデヒト類、アセタール類
等が、増加したり、生成したりします。
 ◇色
◇色
ほんとうに良いこいくちしょうゆは、透明感のある鮮やかな赤褐色をしており、ツヤがある。
しょうゆの着色は、熟成中メラノイジン(褐変物質)ができるためと考えられています。
メラノイジンは、酸化して色が濃くなる傾向があり、空気にふれると酸素によって酸化し、
色が濃くなっていきます。しかも、赤みより青みの方がより増色するので、濃くなるばかりでなく、
黒ずんだ感じになります。この酸化反応は、温度が高い程早く進み、直射日光によって
促進される。従って封を開けたら、フタを閉め冷暗所に保存することです。
しょうゆは加熱によって色が濃くなるが、常温の酸化と違って、この場合、青みよりも赤みの方が濃くつきます。
従って黒ずむというより、明るい色調になり、芳ばしい焦げた香りを伴うので、風味もよくなります。
◇色度
色度は、「日本醤油検査協会」が定めたしょうゆ標準色と比色して測定します。標準色の番号は大きくなるほど
色は淡くなる。18番未満がこいくち(一般的には8〜10番)18番以上がうすくち(一般的には20〜30番)
になっています。
◇全窒素分
しょうゆのうま味の指標で、しょうゆに含まれている各種アミノ酸やペプチドに必ず含まれている窒素の総量を測定しています。
◇無塩可容性固形分
しょうゆ中に溶けている塩以外の物質ということで、しょうゆから食塩と水を除いたもの。即ちしょうゆのエキス分。
主としてしょうゆの濃度を表します。
◇アルコール分
アルコール分は、香りの成分で、同時に発酵が十分に行われているかどうかの目安になります。
| 項 目 | 色度(標準色) | 全窒素分 | 無塩可容性固形分 | アルコール分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| こいくち醤油 | 特級 | 18番未満 | 1.50%(容量)以上 | 16%(容量)以上 | 0.8%(容量)以上 | 上級 | 同 上 | 1.35%(容量)以上 | 14%(容量)以上 | - | 標準 | 同 上 | 1.20%(容量)以上 | - | - |
| うすくち醤油 | 特級 | 22番未満 | 1.15%(容量)以上 | 14%(容量)以上 | 0.7%(容量)以上 | 上級 | 同 上 | 1.05%(容量)以上 | 12%(容量)以上 | - | 標準 | 18番以上 | 0.95%(容量)以上 | - | - |
| たまり醤油 | 特級 | 18番未満 | 1.60%(容量)以上 | 16%(容量)以上 | - | 上級 | 同 上 | 1.40%(容量)以上 | 13%(容量)以上 | - | 標準 | 同 上 | 1.20%(容量)以上 | - | - |
| さいしこみ醤油 | 特級 | 18番未満 | 1.65%(容量)以上 | 21%(容量)以上 | - | 上級 | 同 上 | 150%(容量)以上 | 18%(容量)以上 | - | 標準 | 同 上 | 1.40%(容量)以上 | - | - |
| 白しょうゆ | 特級 | 46番以上 | 0.40〜0.70%(容量)未満 | 15〜0.8%(容量)未満 | - | 上級 | 同 上 | 0.40〜0.80%(容量)未満 | 15%(容量)以上 | - | 標準 | 同 上 | 同 上 | 12%(容量)以上 | - |
◇特級・特選・超特選のちがい
主にうま味の指標となっている全窒素の含有量のちがいで、JASでは、特級の中で特にうま味の高いものとして
特選、超特選があります。
特選は、特級より全窒素が10%以上高いもの。超特選は、20%以上高いものに、この呼称が認められています。
こいくちしょうゆの全窒素分は、特級が1.5%以上、特選は1.65%以上、超特選は1.8%以上.。
うすくちしょうゆの全窒素分は、特級は1.15%以上、特選は、1.265%以上となっています。
| 【調 味 料】 | 【海 藻 類】 | |||||||
| みそ | 酢 | 醤油 | 植物油 | わかめ | ひじき | あらめ | 昆布 | のり |
| インスタント ラーメン | 小麦粉 | 食物せんい | 緑黄色野菜 | トマト | はちみつ | コーヒー |
