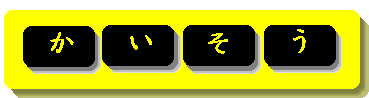
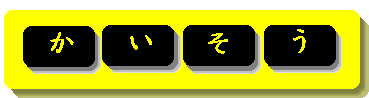
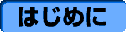
健康志向、食物繊維、ノンカロリー、アルカリ食品・ダイエット食品・・と言えば、即「海藻類」と答えざるを得ません。
その代表的な五種類を、特集してみました。関心のある海藻から勉強してみて下さい。
 |
 |
 |
 |
 |



| 品 質 | 原藻及び抄き方の優秀なもの | 優等・特等・1等 2等・3等・4等 5等・6等・7等 の9ランクに等級分けされる |
| 色 沢 | 黒褐色濃く、光沢の優秀なもの | |
| 香 味 | 優秀なもの、良好なもの | |
| 形 態 | 縦21cm、横19cm | |
| 重 量 | 300g前後 | |
| 乾 燥 度 | 水分量15%以下 | |
| 1束の枚数 | 100枚 |
| 区分 | 定 義 | |
|---|---|---|
| 上 | 同一等級のを二階級に細分する場合の上位のもので4等までとする | |
| 推 | 褐色濃く光沢あり、焼色、味共に良好と思われるもので3等まだとする | |
| 黒 | 普通等級と同程度又は、それ以上の風味を有するが、光沢が不足しているもので3等までとする | |
| B | 結束不良、選別不良、乾燥割れの軽微なものが混入しているもの(黄色結束紙) | |
| 重 | 重過ぎ、厚過ぎにより普通等級と同一格付け困難なもので、3等までとする(原則として350g以上) | |
| 軽 | 1束の重量が270g未満のもの | |
| ○ | 穴あきのものが混入しているもの | |
| ク | 水洗い不足、乾燥等によるくもりの軽微なもの | |
| 飛 | あおのり類が7%未満混入しているもの | |
| 混 | あおのり類が7%以上混入しているもの | |
| A | 赤芽のりで色浅く、普通等級と同一格付け困難なもの | |
| C | 珪藻が混入しているもの | |
| 縮 | 1束の中に縮みの混入しているもの(赤色結束紙) | |
| 破 | 1束の中に破れ、乾燥割れの混入しているもの(黄色結束紙) | |
| ⑦ | 破れ、横割れ、欠けが6cm以内のもの(⑦と明記する) | |
| 規格外 | 寸法不足(原則として縦21cm、横19cmに満たないもの) |
| 成 分 | 乾のり | 焼のり | 味付のり | わかめ | 大豆 | 鶏卵 | 乾椎茸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 分(g) | 11.1 | 6.2 | 4.6 | 13.0 | 12.5 | 74.7 | 10.3 | |
| たんぱく質(g) | 38.8 | 40.9 | 38.4 | 15.0 | 35.3 | 12.3 | 20.3 | |
| 脂 質(g) | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 3.2 | 19.0 | 11.2 | 3.4 | |
| 炭水化物 | 糖 質(g) | 39.5 | 41.7 | 39.7 | 35.3 | 23.7 | 0.9 | 52.9 | 繊 維(g) | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 0 | 8.9 |
| 灰 分(g) | 6.9 | 7.3 | 12.7 | 30.8 | 5.0 | 0.9 | 4.7 | |
| 無機質 | カルシュウム(mg) | 390 | 410 | 210 | 960 | 240 | 55 | 12 | リ ン(mg) | 580 | 610 | 600 | 400 | 580 | 200 | 270 | 鉄 分(mg) | 12.0 | 12.7 | 12.0 | 7.0 | 9.40 | 1.8 | 4.0 |
| ビタミン | A(IU) | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 1,800 | - | 640 | 0 | B1(mg) | 1.15 | 1.10 | 1.00 | 0.30 | 0.83 | 0.08 | 0.57 | B2(mg) | 3.40 | 3.20 | 2.90 | 1,015 | 0.30 | 0.48 | 1.70 | C(mg) | 100 | 95 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| たんぱく質 | 大豆に匹敵する位海藻のなかでは必須アミノ酸が一番多い。のり1枚で牛乳の1/5本、卵の1/5個分のたんぱく質を含む。 | |
|---|---|---|
| ミネラル | 骨や歯の生成に大切なカルシュウムはしらす干しより多い、貧血を防ぐ鉄分、甲状腺ホルモンに必要なヨウ素がバランスよく含まれている。 | |
| ビタミン A,B1,B2 | 皮膚の角質化を抑え、疲労回復に効果がある。Aはうなぎの3倍、ほうれん草の8倍程含まれている。 | |
| ビタミンC | シミ、ソバカスを防ぎ美容によい上、ガン予防に効果がある。野菜や果物並で長期保存が効く。 | |
| 食物繊維 | 30%もの食物せんいを含み老化を遅らせる。のりの食物せんいは柔軟で、胃腸の壁を傷つけることなく、有害物をつくるウエルシュ菌の繁殖を抑える。 | |
| 脂質 | 肥満と動脈硬化の敵の飽和脂肪酸やコレステロールの値を下げる。 | |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 血中コレステロール値を低下させ、動脈硬化を始めとした心臓疾患を防ぐ働きがある。 | |
| タウリン | コレステロールの増加を防ぎ、高血圧や胆石の予防に有効。 |
 ◆海苔の共販実績
◆海苔の共販実績| 年度 | 共販数量(単位:百万枚) | 共販金額(単位:百万円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本 | 瀬戸内 | 九州 | 全国合計 | 東日本 | 瀬戸内 | 九州 | 全国合計 | |
| 平成1年 | 2,633 | 3,676 | 3,700 | 10,260 | 27,508 | 27,551 | 48,628 | 115,881 |
| 2年 | 2,047 | 3,256 | 3,397 | 8,939 | 20,444 | 32,767 | 36,206 | 91,563 |
| 3年 | 2,103 | 3,404 | 3,876 | 9,632 | 22,924 | 34,460 | 48,034 | 107,731 |
| 4年 | 2,345 | 3,465 | 3,760 | 9,815 | 25,342 | 35,520 | 44,196 | 107,401 |
| 5年 | 2,545 | 3,838 | 4,070 | 10,657 | 28,113 | 38,554 | 52,763 | 121,473 |
| 6年 | 2,010 | 3,443 | 4,247 | 9,940 | 17,912 | 30,727 | 40,595 | 91,080 |
| 【調 味 料】 | 【海 藻 類】 | |||||||
| みそ | 酢 | 醤油 | 植物油 | わかめ | ひじき | あらめ | 昆布 | のり |
| インスタント ラーメン | 小麦粉 | 食物せんい | 緑黄色野菜 | トマト | はちみつ | コーヒー |
