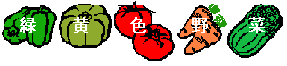

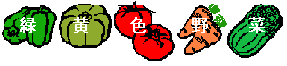
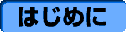
野菜を食べよう! 野菜は健康管理に不可欠なものだ!
最近 洋風化されつつある食生活で、野菜の必要性がが叫ばれています。
その体に良いと云われる野菜、特に緑黄色野菜について勉強してみましょう。
トマトについては[トマト]をクリックして下さい。

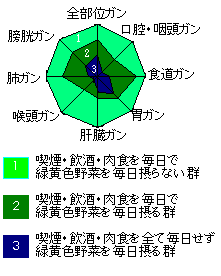 戦後の食糧不足の時代には、結核や脳卒中などの脳血管疾患が死亡率のトップでしたが、
その後医薬品、医療技術の進歩で激減し、それに代わって躍り出たのが、ガンと心疾患。
その原因として、食生活の欧米化による肉食の多用と野菜摂取不足や運動不足、喫煙、飲酒などが
挙げられる。その結果喫煙や飲酒によって、体内のカロチノイドはどんどん減っていきますが、
右のグラフのように、緑黄色野菜を摂ることによって、ベータカカロチンやリコピンを
補給し、ガンになるリスクを抑える効果があることが解ってきました。
戦後の食糧不足の時代には、結核や脳卒中などの脳血管疾患が死亡率のトップでしたが、
その後医薬品、医療技術の進歩で激減し、それに代わって躍り出たのが、ガンと心疾患。
その原因として、食生活の欧米化による肉食の多用と野菜摂取不足や運動不足、喫煙、飲酒などが
挙げられる。その結果喫煙や飲酒によって、体内のカロチノイドはどんどん減っていきますが、
右のグラフのように、緑黄色野菜を摂ることによって、ベータカカロチンやリコピンを
補給し、ガンになるリスクを抑える効果があることが解ってきました。
★たくさん含んでいる代表
| ビタミンB1 | カルシュウム | ビタミンC | ベータカロチン |
|---|---|---|---|
| ほうれん草 | かぶの葉 | 赤ピーマン | しその葉 |
| パセリ | こまつな | ブロッコリー | モロヘイヤ |
| 芽キャベツ | ほうれん草 | パセリ | にんじん |
★健康管理上効果のあるもの








| - | 野 菜 | 色 素 | 効 用 | 効果的な摂取方法 | 調理例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤色 | トマト、赤ピーマン 金時にんじん | カロチノイド系 ・リコピン ・カプサンチン | がん予防 動脈硬化予防 健胃、視覚 | 熱に強いので 炒めてもOK 脂肪分との同時摂取 により吸収が向上 | ミネストローネ,ラタトウイユ 魚介トマトシチュー | 黄色 | にんじん かぼちゃ | カロチノイド系 ・アルファカロチン ・ベータカロチン | がん予防 心臓病予防 免疫増強 | グラタン パウンドケーキ かぼちゃのソボロ あんかけホウトウ 天ぷらす揚げ |
| 緑色 | ほうれん草 緑ピーマン | ポルフィリン系 ・クロロフィル | がん予防 抗アレルギー 脱臭、増血機能 | 熱と酸の組合せに 弱いので注意 | おひたし,サラダ あえもの,マリネ | 褐色 | たまねぎ にんにく | フラボノイド系 ・ケルセチン | がん予防 心臓病予防 | オニオングラタンスープ ガーリックトースト ポタージュ |
| (赤)紫色 | 赤キャベツ しそ | アントシアニン系 ・ルブロブラシン | がん予防 血管の保護 | 熱に強く水溶性 なのでスープ などがよい | 梅干し,サラダ ミソ炒め,コールスロー しそジュース |


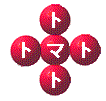
| エネルギー | 16kcal | カルシュウム | 0.9mg | カロチン | 390μg |
| たんぱく質 | 0.7g | リ ン | 18mg | ビタミンB1 | 0.05mg |
| 脂 質 | 0.1g | 鉄 分 | 0.3mg | ビタミンB2 | 0.03mg |
| 糖 質 | 3.3g | ナトリュウム | 2.0mg | ナイアシン | 0.5mg |
| 食物繊維 | 0.4g | カリュウム | 230mg | ビタミンC | 20mg |
| 年 度 | 主な研究者(地域) | 内 容 |
| 1989年 | モーリス(米) | 血中リコピン濃度の低レベルとすい臓ガン、膀胱ガンの発生に相関性のあることを報告 |
| 1990年 | キャンプベル(米) | 肺ガン患者は健常人に比べ血中リコピン濃度が有意に低いことを報告 |
| 1991年 | カサルグランディ(伊) | 肝硬変患者は血中リコピン濃度が低いことを報告 |
| 1991年 | ボーエン(米) | 血中リコピン濃度の低レベルと子宮頸ガンの発生に相関性のあることを報告 |
| 1994年 | ネグリ(伊) | トマトの摂取量と消化器系ガンの発生率が逆相関することを報告8リコピンの関与を示唆) |
| 1995年 | ウィレット(米) | トマト及びリコピンの摂取量と前立腺ガンの発生率が逆相関することを報告 |
| 1997年 | 秋田大・京都府立医大・カゴメ(日) | ラットにリコピン投与で大腸ガンの発生率が低下する研究結果を報告 |
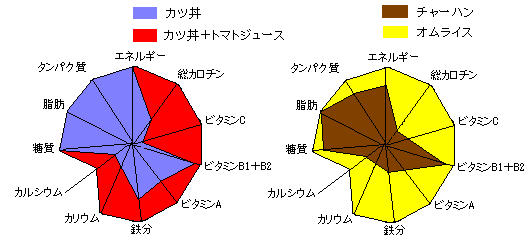
| 野菜名 | 最も好きな野菜 | 好きな野菜(複数回答) |
| トマト | 16.2% | 48.6% |
| じゃがいも | 11.5% | 39.2% |
| さつまいも | 11.5% | 36.9% |
| かぼちゃ | 9.5% | 36.9% |
| 野菜名 | 最も嫌いな野菜 | 嫌いな野菜(複数回答) | 嫌いだが必要な野菜 |
| カリフラワー | 13.1% | 30.6% | 11.0% |
| にんじん | 7.0% | 15.5% | 17.6% |
| ピーマン | 6.1% | 19.1% | 17.0% |
| かぶ | 4.5% | 21.6% | 7.0% |
| さやえんどう | 3.2% | 18.2% | 7.0% |
| 子供の好きな野菜 | 子供の嫌いな野菜 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | とうもろこし | 1. | セロリ |
| 2. | じゃがいも | 2. | パセリ |
| 3. | さつまいも | 3. | ふき |
| 4. | えだまめ | 4. | ピーマン |
| 5. | きゅうり | 5. | かいわれ |
| 6. | もやし | 6. | しゅんぎく |
| 7. | かぼちゃ | 7. | グリーンアスパラ |
| 8. | プチトマト | 8. | グリンピース |
| 9. | トマト | 9. | なす |
| 10. | さといも | 10. | しいたけ |
参考文献:石黒幸雄・ 稲熊隆博・坂本秀樹著「続・野菜の色には理由がある」(1999年 毎日新聞社 発行)
| 【調 味 料】 | 【海 藻 類】 | |||||||
| みそ | 酢 | 醤油 | 植物油 | わかめ | ひじき | あらめ | 昆布 | のり |
| インスタント ラーメン | 小麦粉 | 食物せんい | 緑黄色野菜 | トマト | はちみつ | コーヒー |
